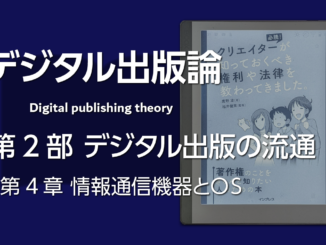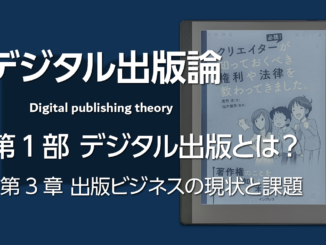鷹野凌がここ数年、大学の非常勤講師として講義している内容を、テキスト化して連載形式で公開。デジタル出版の歴史、現状、課題、生産・流通・利用といった過程について、解説を試みます。
【目次】
第1部 デジタル出版とは?
第1章 デジタル出版の定義
- 両手の指10本を使うと、いくつまで数えられるか?(同じ組み合わせは不可)
- 技術の進歩はコンテンツとメディアを分離した
- 本の複製は長年、手で書き写すことだった
- 広義の出版には、講演、音楽、映像、ブログ、Twitterのつぶやきも含まれる
- 表現と伝達のプロセスは、デジタル化とネットワーク化によって激変した
第2章 メディアとビジネスモデル
- リフロー形式のデジタル出版物はページ数がカウントできない
- 本を作るときはどのように頒布するか? まで考える必要がある(紙でも電子でも)
- 複雑なレイアウトには、文字と図版の配置そのものにも意味が込められている
- 多品種少量生産な本や雑誌には、流通合理化や保存利用のためのコードが存在する
- 梅棹忠夫「情報産業論」は60年経っても古びていない
- ユーザー生成コンテンツはいきなり世に出てユーザーから直接評価を受ける
- プラットフォームでマスコミ4媒体とウェブ発メディアは同じ土俵で競う
第3章 出版ビジネスの現状と課題
- 枕詞のように「出版不況」と言われるが、実態は「雑誌不況」である
- 電子出版物は有体物ではないため著作物再販適用除外制度の対象外
- デジタル出版は在庫を用意する必要がないため必然的に実売印税となる
- 新作の認知手段は基本無料のウェブやアプリに変化した
- 韓国型縦スクロールマンガと日本型ページめくりマンガは異なる表現メディア
- 電子書店は群雄割拠、競争市場で切磋琢磨
- デジタル出版のメリット
- デジタル出版のデメリット
- デジタル出版ビジネスの課題
第2部 デジタル出版の流通
第4章 情報通信機器とOS
第5章 インターネットと書店
- 準備中
第6章 検索技術と広告
- 準備中
第7章 ソーシャルメディア
- 準備中
第3部 デジタル出版の利用
第8章 ナレッジコミュニティ
- 準備中
第9章 情報の保存と活用(アーカイブ)
- 準備中
第10章 電子図書館
- 準備中
第4部 デジタル出版の生産
第11章 デジタル出版と著作権
- 準備中
第12章 デジタル出版と編集
- 準備中
第13章 デジタル出版の演習
- 準備中
第14章 誰でも出版できる時代に
- 準備中