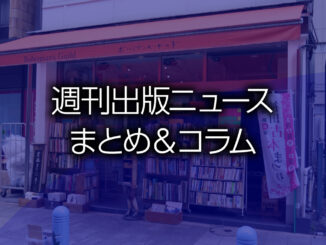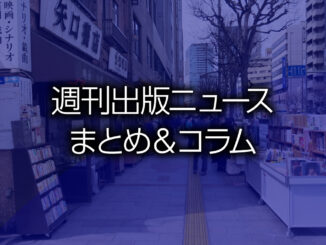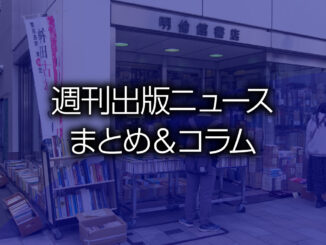《この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です(1分600字計算)》
本や雑誌の流通合理化のための工夫
本や雑誌は取次ルートを通じて、全国津々浦々へ大量に流通しています。冊数もさることながら、点数も多いため、管理や区別をするためのコード番号が存在しています。
国際標準図書番号 ISBN とは?
本は、出版科学研究所の集計対象だけで年間約7万点の新刊が発売されている、多品種少量生産なメディアです。この膨大な種類の商材を流通させるのにあたって、注文や在庫管理などをコンピュータで処理しやすくするため、業者間で用いる共通のコード番号が規格化されています。それが国際標準図書番号「ISBN(International Standard Book Number)」です1JPO 日本出版インフラセンター 日本図書コード管理センター『ISBNコード/日本図書コード/書籍JANコード 利用の手引き2010年版』(2019年1月改訂版)より。
https://jpo.or.jp/topics/2019/03/post-38.html。
ISBNは、1970年にISO規格として承認され、世界での普及が始まりました。日本では1960年代後半から国内限定の標準規格である「書籍コード」が運用されていましたが、1981年1月からISBNへ移行しています。以前は10桁のコード番号でしたが、2007年から13桁に変わりました。同じISBNコードを表記する本はないルールですが、残念ながら運用上のミスなどにより、違う本に同じ番号が振られてしまったケースもあるようです2たとえばJ-CAST ニュース「岩波文庫、新訳注文したら旧訳が届いた ISBN重複で起きる購入トラブル」(2016年12月4日)など。
https://www.j-cast.com/2016/12/04285125.html。
図書館関係の用語に「書誌同定」という言葉があります3FJJ 図書館ポータル 図書館用語集「書誌同定(ショシドウテイ)」
https://cloud-app-support.fjas.fujitsu.com/libwords/443.html。要するに「同じ本かどうか?」を特定することです。コード番号が無かったころの出版物は、タイトル、著者名、出版地、出版社(者)、出版年、版表示、ページ数などが一致しているかどうかをいちいち確認する必要がありました4国立情報学研究所 総合目録データベース実務研修 平成18年度 成果物 4班「目録初心者のための教育支援プログラム ~ひとり立ちを目指して~」添付資料4より。
https://contents.nii.ac.jp/hrd/db/2006/result。ISBNが付番されるようになったことで、販売流通だけでなく、保存や利用する上でも便利になっていったのです。
日本図書コードと書籍JANコードとは?
ISBNの付与対象は、紙の本や小冊子、雑誌扱いで配本されるコミックスやムック、点字出版物、マイクロフィルム出版物、電子書籍(eブック)および書籍をそのままデジタル化した出版物(狭義のデジタル出版)などです。詳しくは後述しますが、雑誌や新聞などの定期刊行物は、ISBNの付与対象となりません。

https://isbn.jpo.or.jp/index.php/fix__about/fix__about_2/。また、読書管理アプリなどユーザーが利用するものにも、このバーコードを読み取ると本が同定できる仕組みが導入されている場合があります。
本の内容が同じであっても、紙なら判型が違う場合、電子ならフォーマットが違う場合は、別の本として別のISBNを付番するルールになっています。また、紙で1冊の本を電子では分冊する場合も、それぞれ付番するルールになっています。ところが、電子の本は実務での必然性が低いためか、ISBNが付与されていないケースも多いようです。ただしデータ上では、紙の本のISBNを「底本ISBN」として持っている場合もあります6電子書店「BOOK☆WALKER」では配信されている書籍一覧をファイルで取得できる。2021年12月時点で約77万点のうち、底本ISBNが存在するのは約42万点だった。
https://help.bookwalker.jp/faq/301。
なお、発行されている紙版の本のうち、同じ内容の電子版がどれだけ出ているか? という電子化率は、この底本ISBNをキーにしてデータをマッチングすると算出できます。私と堀正岳さんの共同研究では、ISBNベースの電子化率は2020年1月時点で11.9%でした7「日本における 電子書籍化の現状 (2020年版)―― 国立国会図書館所蔵資料の電子化率調査」より。電子書店「BOOK☆WALKER」で配信されている書籍一覧とのマッチング調査。
https://wildhawkfield.com/2020/09/shuppan-gakkai.html。出版年別では、2017年が29.6%、2018年が31.2%、2019年が33.2%と、徐々に電子化率は高まっています。
また、ISBNとは別に、デジタルコミック協議会(当時)8文化通信デジタル「デジタルコミック協議会が解散 電書協に承継」(2021年8月27日)にあるように、デジタルコミック協議会は解散して、日本電子書籍出版社協会に継承されている。
https://www.bunkanews.jp/article/237907/
さらに、日本電子書籍出版社協会は2022年2月よりデジタル出版者連盟(通称:電書連)に社名変更している。
http://ebpaj.jp/informationが推奨していた「JDCN(Japan Digital Comic Number)」をベースに定められた「電子出版コード(JP-eコード)」という識別コードも存在しています。「電子書籍のIDナンバーとして、今後ISBNのような普及が期待されている」9沢辺均『電子書籍の制作と販売』(2018年・ポット出版)
https://www.pot.co.jp/books/isbn978-4-7808-0232-0.htmlそうです。
雑誌コードと定期刊行物コード(雑誌)とは?
前述のように定期刊行物はISBNの付与対象外なので、雑誌には「雑誌コード」という商品コードがあります。雑誌コード管理センターより雑誌の表題(誌名・タイトル)ごとに付与される5桁の数字と、2桁の月号数で印刷表示されます10雑誌コード管理センター「雑誌コードの概要」より。
https://jpo.or.jp/magcode/info/outline.html。
また、雑誌コードを含めた13桁のJANコード準拠コードに、価格を表現する5桁のアドオンコードを加えた「定期刊行物コード(雑誌)」をバーコードユニットとし、雑誌コードとともに表4(裏表紙)の下端に印刷表示するルールになっています。なお、雑誌コード系統で、電子版を別途識別するような業界標準の有無を調べてみたのですが、私にはわかりませんでした(情報求む)。

―― この続きは ――
《残り約1200文字》
〈前へ〉