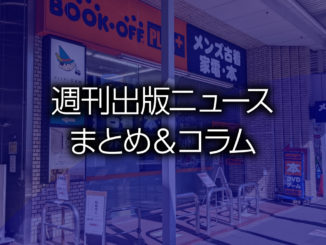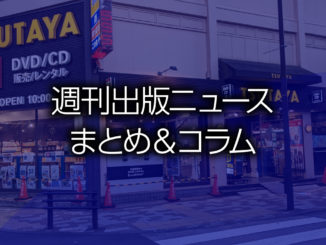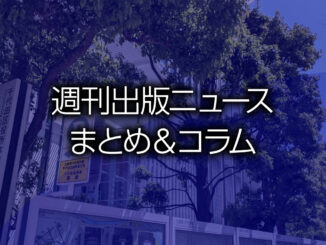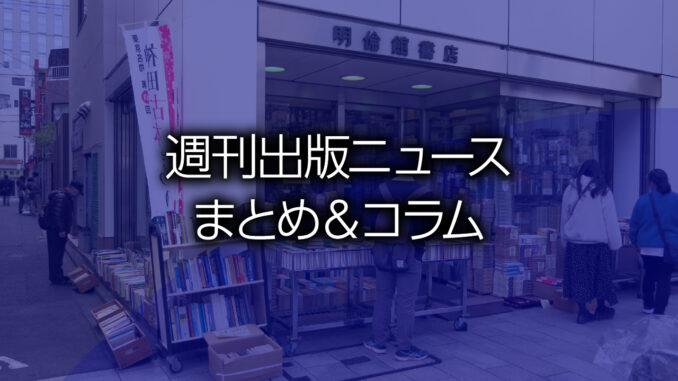
《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
2022年8月21日~27日は「韓国漫画が日本のお家芸を揺るがすってほんと?」「毎日新聞電子版、会員獲得の販売店に手数料」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
「本が読みづらい人」でも読みやすい電子書籍に アクセシビリティーを評価するJIS制定〈ITmedia NEWS(2022年8月22日)〉
電子書籍(EPUB出版物)のアクセシビリティを評価する国際規格(ISO/IEC 23761)が2021年2月に発行されたのを受け、日本標準規格(JIS X 23761)も制定されました。経済産業省からの発表ということで【政治】ジャンルとしましたが、今後を考えると【社会】とも【経済】とも【技術】とも言える、各方面への大きな影響が予想される動きです。
日本産業規格(JIS)を制定・改正しました(2022年8月分)〈METI/経済産業省(2022年8月22日)〉
日本産業標準調査会のウェブサイトでJIS規格を検索して本文を閲覧(要会員登録・閲覧は無料)してみましたが、とくに留意すべきなのは「ページナビゲーション(静的な改ページ位置へのナビゲーションを提供)」だと私は思いました。パッケージメタデータによる発見可能性の向上や、メディアオーバーレイズの構築も、もちろん重要なのですが。
紙の本であれば「p128参照」などと、ページ番号によって位置が示せます。ところがリフロー型EPUBは、文字サイズやディスプレイサイズによって見た目の改ページ位置が変わるため、ページ番号ではどこを示しているのかわからないという問題点があります。詳しくは「デジタル出版論」第2章第1節でも触れていますのでご参照ください。これは、視覚障害者に限った問題ではないのです。
で、今回のJIS規格化を受け「今後はページナビゲーションを提供しましょう」となったとき、現状ではEPUB制作ツールにページナビゲーションを入れる機能が無い場合が多いので、困ってしまう可能性が高いように思うのです。私が知る限り、たとえば「でんでんコンバーター」のマークダウンにはページナビゲーションがあります(さすが)が、他のEPUB制作ツールでは見かけません。やりたくてもできない、ということになりそう。早期実装を求む。
あと、コンテンツ側が対応しても、ビューア側が対応していないかも? という問題もあります。私の知ってる範囲では、BPS「超縦書」や「Apple Books」はページナビゲーションに対応しているようですが、他の電子書店で使われているビューアはどうなのか。サイドロード非対応だと、検証もできません。まあ、こうやって規格化されたことによって、実装が促進されていくのかもしれませんが。
「鳥取での販売がもはやリスク」──県の有害図書指定でAmazonから排除 三才ブックスが抗議のPDF公開〈ITmedia NEWS(2022年8月27日)〉
火の玉ストレートの表現規制。鳥取県が有害図書指定した理由も不透明だし、議事録もろくに残っていないというありさま。条例改正案が出た2020年当時から懸念されていた事態が、実際に起きてしまいました。鳥取県で規制されたら全国に影響を及ぼせるわけで、今後、悪用する輩が出てくることも予想できます。
鳥取県、有害図書・玩具の販売規制に「ECサイトも含む」と明記へ Twitterで物議〈ITmedia NEWS(2020年8月14日)〉
販売事業者には罰金30万円という罰則規程があるため、「悪法もまた法なり」で、Amazonが販売停止とするのは致し方ない部分もあります。ただ、アダルトジャンルに変更してもダメ、という杓子定規な対応はなんとかならんのか、とも思いますが。
また、三才ブックスの側も、これまで「売上の9割はAmazon」という極度に依存した状態だったようです。流通チャネル戦略の失敗と言えるでしょう。ただ、これを期に自社のオンラインショップへ誘導し、直販比率を高めるのが吉ではないかと。実際、本件を告発する記事の上部には「三才ブックス オンラインショップ」の告知バナーがでかでかと表示されています。「STORES」を使ってるようですね。
ちょうど、後述する「デジタル出版論」第3章第9節で「パブリッシャーはユーザーとの直接取引を増やしていくべき」という提言をしたばかりだったので、タイムリーでした。
社会
審査員の77%が男性 文化9分野のジェンダー比〈共同通信(2022年8月24日)〉
ジェンダー比、うちも「気がついたら男性ばかり」ということがちょくちょくあるので、身につまされます。毎週やっていた「HON.jp News Casting」は、ゲストに次のゲストを依頼する「笑っていいとも」方式を採っていましたが、ゲストには「ジェンダーバランスになるべく御配慮ください」というお願いをしていました。それでも、男性の出演ばかりが連続するときがありました。無配慮だったら、恐らくもっと偏っていたことでしょう。いろんな場面で無意識に圧がかかり、自然と偏ってしまうこともある、という前提で気を配る必要がありそうです。
デジタル出版ビジネスの課題 ―― デジタル出版論 第3章 第9節〈HON.jp News Blog(2022年8月25日)〉
デジタル出版論の連載で、過去最長となりました。本文が9400字を超え、注釈を入れると1万2000字近くになっています。第1部を「課題」で締めるにあたって、少し気合いを入れすぎました。ここまでの3章は「概要」という位置づけだったのですが、ところどころちょっと掘り過ぎたかも? 感が。第1章が1万5000字、第2章が2万字、第3章が3万4000字(いずれも本文のみ)と、だんだん長くなっています。
今後は、第2部「流通」、第3部「利用」、第4部「生産」と続く予定です。この大分類は箕輪成男氏『出版学序説』に示された「出版の過程」に準拠しています。ただ、全体の構成を考えると、第1部「概要」でいささか掘りすぎた部分を、もう少し後ろの部へ移行したほうがいいかも。完結したら、再構成しましょう。
経済
韓国漫画界、日本のお家芸揺るがす スマホ対応の縦読み〈日本経済新聞(2022年8月21日)〉
この記事、いささか以上にツッコミどころが多いため、菊池健さんが「マンガ業界Newsまとめ」で山盛りの指摘を入れています。詳細はそちらをご参照いただくとして、私は一般論として「なぜこういう誤解の多い記事が出てしまうのか?」の背景について少し。
【マンガ業界Newsまとめ】 Twitterが公式レポート「漫画ファンはどんな人々か?」など|8/21-065〈菊池健|note(2022年8月21日)〉
これはあくまで一般論ですが、株式市場で資本を調達する企業が、投資家向けのIRで語る内容に起因している部分があるように感じています。嘘を言ったら「風説の流布」になってしまうわけですが、嘘とまでは言えないけど、事実を一部だけ語ることで結果的に誤解を与えることは可能なわけです。もちろん不勉強な記者も悪いのですが、うまく誤解させるよう誘導している部分もあるのかな、と。あくまで一般論ですが。
よくあるのが、グラフの縦軸に数字が無いとか。単月でのイレギュラー現象なのに、説明を省くことにより、そういう傾向がずっと続いているかのように思わせてしまうとか。「××の調査で1位!」と広報しているけど、実はその××の調査は市場の一部に過ぎないとか。利用率の高さをアピールしているけど、実は無料利用の占める比率が非常に高く、有料利用率はたいして高くないとか。そういう大事な前提が、IR資料で省かれていたり、小さい字で目立たないように書かれていたり。繰り返しますが、あくまで一般論です。
また、逆に、投資家向けの詳細な説明を必要としない非上場企業は、公開されている情報が少なすぎるため、結果的に過小評価されている部分もあるように感じています。講談社、小学館、集英社がまさにそう。結果、たとえば「日本漫画の世界市場規模は?」といった他国と比較したい数字が、なかなか出てこなかったり、古い情報しかなかったりするわけです。
漫画アプリ「ピッコマ」が日本上場へ、時価総額8000億円超も-関係者〈Bloomberg(2022年8月23日)〉
といったことを踏まえた上で、こちらの記事。3段落目に『「ピッコマ」は、販売金額でLINEマンガと国内トップを争っている』という記述があります。確かに、data.ai(旧アップアニー)の調査によると、2021年のグローバルマンガアプリ部門では1位「ピッコマ」2位「LINEマンガ」です。
でも、本欄で何度も指摘してきた(#417、#450、#456)ように、data.ai(旧アップアニー)の調査は「Google Play」と「App Store」の合計なのですよね。アプリ内決済限定ランキングなんです。だから必然的に、ウェブから直接決済できてアプリは閲覧機能のみ(※iOSは以前から、Androidは今年から)である「Kindle」や「楽天Kobo」などは、ランキングに入ってこないのです。
という、限られた市場でのランキングである前提を知らない人も多いでしょう。そういう前提が記述されていない状態で「国内トップを争っている」なんて書いたら、まあ、誤解されかねないわけですよね。怖い、怖い。
韓国発デジタル漫画「ウェブトゥーン」が世界的成功、日本に欠けている視点とは | News&Analysis〈ダイヤモンド・オンライン(2022年8月26日)〉
こちらは、当初「ウェブトゥーン(コミック)は3420億円」「ウェブトゥーンの勢いは当面続き」と書かれていました。これは、「さすがにそれは語弊がある」と私から担当編集者に指摘したところ、「電子コミック(ウェブトゥーン含む)は3420億円」「電子コミックの勢いは当面続き」と訂正されました(記事末尾に記述あり)。知らない人が当初の記述を読んだら、あらぬ誤解をするわけです。怖い、怖い。
リテールメディアが急成長 アマゾンとウォルマートの金鉱脈に〈日経クロストレンド(2022年8月23日)〉
Amazon広告、Googleの検索連動型広告よりもっと直接的に売上へ繫がる可能性があるわけで、そりゃ伸びるよねと思う反面、今後いろいろ問題が出てきそうな予感もあります。記事の後半でも「頻繁に通う小売店が自分の買い物習慣を追跡してマネタイズ(収益化)するのが望ましいか否か」「ECサイトの検索結果で「スポンサー」商品を優遇する慣行が、最終的に消費者とオンラインショップとの関係を損なうかどうか」という疑問が投げかけられています。
端的に言えば、ユーザーにとっては「広告だらけでうざい」プラットフォームになっていく可能性が、そしてベンダーにとっては「広告を出さないと売れない」プラットフォームになっていく可能性があるわけです。当然、広告費のぶん売値も高くなるでしょうし。これ、負のスパイラルが生まれかねない気がするんですが、大丈夫なのかな?
「毎日新聞デジタル」 会員獲得の販売店に手数料 「第3の収入」で経営支援〈文化通信デジタル(2022年8月26日)〉
このニュース、「え? 販売店が電子版の会員を獲得したら手数料を払うような施策を、いままでやってこなかったの?」という意味で驚きました。毎日新聞の販売店網は読売・朝日に比べたら格段に弱いとはいえ、「新聞以外のメディア」と比べたら、全国戸別に営業できる部隊を持っていることが強みだと私は認識していました(同時に弱みでもある)。電子版を本気で拡販するなら「新聞販売店に手数料を払う」という施策が有効だというのは、わりとすぐ思いつくアイデアだと思うのですよね。
だからむしろ、なぜいままでやってこなかったのか? が不思議でした。Facebookでその旨を投稿したら、多くの方からコメントをいただいたのですが、いちばん納得できたのは「新聞販売店は折込広告の収入がなくなると困る」という意見でした。文化通信の見出しにある「第3の収入」は今回の電子版販売手数料ですが、第2の収入は「折込チラシ」なのですよね。紙版から電子版に乗り換えられたら、第2の収入も連動して減ってしまうわけです。それは確かに困る。
ただ、第1の収入「紙の定期購読」は今後ますます減っていくことが予想されているわけで、その戸別配達のインフラに依存している「折込チラシ」が共倒れすることも恐らく間違いないわけです。つまり、新聞販売店という業態は、否応なしに変わらざるを得ない状況へ追い込まれていると言っていいでしょう。
では、この第3の収入はどうか? 文化通信の有料会員限定部分を確認したら、電子版1契約あたり毎月1000円が販売店に支払われる形になっているとのこと。「dマガジン」などサブスク契約のアフィリエイトは、一般的に入会時のみ報酬なのであまりやる気が起きないのですが、毎日新聞電子版は一度契約してもらえば毎月報酬が貰える形になっているわけです。
これなら、目先の「折込チラシ」売上は減るかもしれないけど、長期的にはおトクくらいのインセンティブ設計になっているかも? 仮に販売店から販売員個人への手数料を20%、担当が300件とすると、すべてを電子版契約に切り替えたら契約が維持される限りなにもしなくても毎月6万円の収入になるわけです。年金みたいなもんですね。それに加えて、端末の販売や回線の契約、サポートなどが主業務、みたいな方向になっていくのでは。
同じようなタイミングで、朝日新聞デジタルが全記事有料化という動きもあるので、合わせてピックアップしておきます。
「朝日新聞」電子版、全記事有料に 課金路線に舵、「不動産が本業」払拭なるか:一部の速報は無料継続〈ITmedia ビジネスオンライン(2022年8月22日)〉
技術
画像生成AI「Stable Diffusion」がオープンソース化 商用利用もOK〈ITmedia NEWS(2022年8月23日)〉
AI創作系、急激に進化して新しい動きもどんどん出てますが、これは非常に影響が大きそう。オープンソース化されたことにより、既存のツールに組み込んで提供する事例が早くも出始めています。私が見た中でインパクトが強かったのは、デザインツール「Figma」のプラグイン。こういうのがあると、一気に広がる可能性が大きいように思います。
やばいやばいやばい#stablediffusion を導入したFigmaプラグイン登場した。パスとプロンプトを入力したらそれに合わせた画像を生成する。素晴らしすぎる。こういう革命が色んなデザインツールで起こりそうだな..
pic.twitter.com/Ni6MhfoqZE
— やまかず (@Yamkaz) August 24, 2022
商用利用もOKということで、フリー素材の配布や有料素材の販売をしている既存のサービスが窮地に陥る可能性も? また、ワンポイントのイメージイラストは、AIに描かせるのがスタンダードになるかも。テイストが異なる出力も可能なので、「いらすとや」の比ではない脅威となりそうです。
そうやってクリエイターの仕事が奪われる事態が起きたとき、著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)のただし書き「当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」と判断される可能性もあるでしょう。次の争点は恐らくそこ。
性教育本を購入→アダルト商品推奨される hontoメルマガに客困惑…運営は関連否定も改善検討〈J-CAST ニュース(2022年8月24日)〉
レコメンドエンジンとパーソナライズの問題。大日本印刷側は関連性を否定しているそうですが、じゃあなぜそんな露骨な性描写を含むようなメルマガが送られてしまったのか? というと、記事には「購買実績以外の諸条件にもとづき配信」という回答があるのみで、よくわからないのが正直なところ。
ちなみに、そういえば私にはそういうメルマガ来てないな? と思ったら、hontoのメルマガは大半が未購読に設定してありました。ONになっていたのは、お気に入り著者等の「新刊お知らせメール」くらい。これは本を買うときチェックがデフォルトで入っているので、外すのを忘れて、どんどん増えてる感じ。設定を見たら、100件以上になってました。わはは。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
8月ももうすぐ終わり。だんだん涼しくなってきました。なんだか7月のほうが暑かったような気がします。とはいえ、エアコンに頼りっぱなしでしたが。電気代怖い(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。