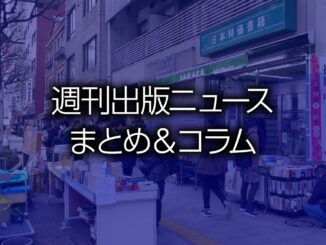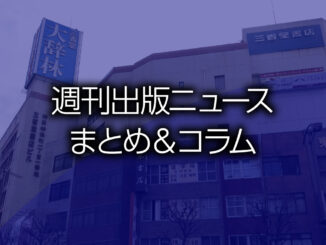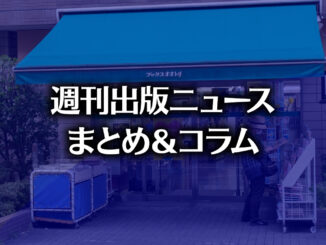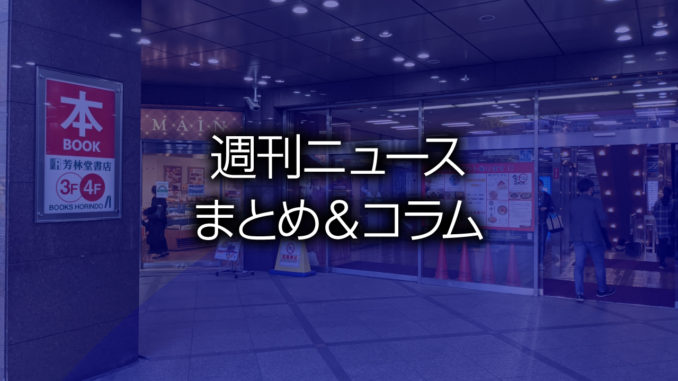
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2020年11月22日~28日は「書協・雑協が総額表示義務化の免除継続を要望」「鬼滅の刃特需で書店市場4年ぶりに拡大か」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。
【目次】
- 国内
- 新型コロナは同人誌活動にも暗い影…約半数が「創作意欲が減退」 コミケなど即売会中止が影響〈東京新聞(2020年11月22日)〉★
- 著作権の補償金受け取り、手数料を引くと…〈ニュースイッチ by 日刊工業新聞社(2020年11月23日)〉
- ハイブリッド型総合書店「honto」が会員数 600万人を突破 コロナが追い風に〈J-CAST 会社ウォッチ(2020年11月23日)〉★
- 書籍の価格表示 出版社から現状維持求める声相次ぐ〈NHKニュース(2020年11月24日)〉
- 本の総額表示義務化、苦慮する出版社 業界団体がアンケ〈朝日新聞デジタル(2020年11月24日)〉
- 出版不況が加速? 波紋呼ぶ図書館本「ネット送信」案の行方〈産経ニュース(2020年11月24日)〉
- 電子出版アワード2020 投票を開始!〈JEPA|日本電子出版協会(2020年11月24日)〉
- 漫画原作者に1年6月求刑、東京 強制わいせつ罪認める〈徳島新聞(2020年11月24日)〉
- 韓国発「ピッコマ」が漫画アプリで首位に、その背景とは? 日本企業の課題は?〈Media Innovation(2020年11月24日)〉★
- 「鬼滅の刃」特需で書店市場が4年ぶりに拡大か 帝国データバンク調べ〈ITmedia ビジネスオンライン(2020年11月24日)〉★
- 「鬼滅の刃」最終巻は395万部〈時事ドットコム(2020年11月25日)〉★
- くら寿司、コロナ禍でも平日の売上が過去最高に 『鬼滅の刃』コラボの底力〈AdverTimes(2020年11月25日)〉★
- リアル書店とインターネット経由の出版物の売上動向をさぐる(2020年公開版)(不破雷蔵)〈Yahoo!ニュース個人(2020年11月25日)〉
- 小説版ドラクエ著者、新たにスクエニ・東宝などを提訴 「主人公の名前を盗用された」〈ITmedia NEWS(2020年11月26日)〉
- 漫画ネタバレサイトは違法?適法? -ネット上における漫画ネタバレと著作権法の関係-|弁護士 田島佑規〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2020年11月26日)〉
- これってOK!? コンテンツにおける建築物の画像利用 岡本健太郎|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2020年11月27日)〉
- 著作権法第37条を使わない視覚障害者等向け読書支援サービス「YourEyes(ユアアイズ)」の衝撃〈HON.jp News Blog(2020年11月27日)〉
- 海賊版に誘導「リーチサイト」の運営者、初摘発…一定の効果期待も「巧妙化」する手口〈弁護士ドットコムニュース(2020年11月27日)〉
- なぜいま“異世界漫画”が売れるのか? 普通の漫画と違う「決定的な理由」とは〈文春オンライン(2020年11月27日)〉★
- 海外
- 香港民主派の周庭、黄之鋒両氏ら収監〈共同通信(2020年11月23日)〉
- 米グーグルを追加提訴か 7州が来月、独禁法違反〈共同通信(2020年11月24日)〉
- ロシア当局、対グーグルで行政手続き開始 禁止コンテンツ未削除で | ロイター〈(2020年11月24日)〉
- 英競争当局、グーグルを予備調査 デジタル広告など巡り〈ロイター(2020年11月24日)〉
- 全米図書賞の翻訳部門を受賞した柳美里『JR上野駅公園口』の功労者は誰か〈HON.jp News Blog(2020年11月25日)〉
- ロックダウンで苦境の小型書店、アマゾンにどう立ち向かうか フランス〈BBC NEWS JAPAN(2020年11月25日)〉
- ペンギン、米出版シェア3割超に 同業のサイモン買収〈共同通信(2020年11月26日)〉
- Bertelsmann to Buy S&S for $2.2 Billion〈Publishers Weekly(2020年11月25日)〉
- 武漢を書いたら「売国奴」 作家が直面した冷たい暴力〈朝日新聞デジタル(2020年11月28日)〉
- ブロードキャスティング
- メルマガについて
国内
新型コロナは同人誌活動にも暗い影…約半数が「創作意欲が減退」 コミケなど即売会中止が影響〈東京新聞(2020年11月22日)〉★
東京都府中市の同人誌印刷会社 緑陽社が、8月25日から9月末にかけてTwitterで回答を呼びかけたアンケート。約4000件のリツイートで回答数は約2800。あくまでその周囲の声であり統計的な代表性はありませんが、約7割が新刊発行ペースが落ちていること、約半数が創作意欲も減退していることなど「この状況下じゃ、そりゃそうだよね……」という結果が出ています。「締め切り」がないと、なかなか動けないんですよね。緑陽社の結果発表ページはこちら(↓)。
著作権の補償金受け取り、手数料を引くと…〈ニュースイッチ by 日刊工業新聞社(2020年11月23日)〉
著作権法第35条の授業目的公衆送信補償金制度で、支払いを受け取る側についても準備を進めておいたほうがいいですよ、という記事。補償金額はおそらく微々たるものなので、個人へ分配するより学会収入とするなど規定内に明文化しておいたほうがいい、と。なるほど。
ハイブリッド型総合書店「honto」が会員数 600万人を突破 コロナが追い風に〈J-CAST 会社ウォッチ(2020年11月23日)〉★
コロナ禍を受け、会員数が急増しているそうです。出版月報11月号特集にも、アマゾンが生活必需品や衛生用品の発送を優先させるため3月から4月にかけて出版物など入荷制限を行ったことから、他のネット書店に注文が殺到するような状況が起きていた、という記述がありました。そんな中、紙も電子も扱っていて、丸善ジュンク堂・文教堂ともガッツリ連携している「honto」が選ばれることも多いということなのでしょう。
書籍の価格表示 出版社から現状維持求める声相次ぐ〈NHKニュース(2020年11月24日)〉
本の総額表示義務化、苦慮する出版社 業界団体がアンケ〈朝日新聞デジタル(2020年11月24日)〉
日本書籍出版協会加盟社へのアンケート。400社のうち178社が回答。スリップ廃止済みが64社、徐々に廃止が16社。スリップでの総額表示対応には、後ろ向きな回答が多かったそうです。このことから、改めて財務省主税局に総額表示義務化の免除継続を要望した、と。
であれば、騒ぎになった9月の時点で「現在並んでいる本の回収などは必要なく、大きな混乱はないという認識だ」と言ってしまった(↓)のは、書協の大失態だったのではないでしょうか。
当時、騒ぎを受け、山田太郎参議院議員が動こうとしていたのに、ヒアリングに対し「現時点では、特段の心配はしていない」と回答(↓)して動きを止めてしまったことを覚えています。その後にアンケートをして、その結果を受けやっぱり問題があるので要望しますというのは、実にチグハグな動きではないでしょうか。
出版不況が加速? 波紋呼ぶ図書館本「ネット送信」案の行方〈産経ニュース(2020年11月24日)〉
他紙の先行報道に比べ、より具体的な声が挙がっています。遠隔複写サービスを実際に利用する場面を考えてみると、その本に載っている情報が「いますぐ欲しい」あるいは「ストックしておいて常時参照できるようにしたい」という状況で、その本が電子書店で売っているなら買ったほうがいいわけです。電子版なら買った次の瞬間には読めるわけですし。次点の選択肢として電子図書館サービスがありますが、同時アクセス制限がある場合はすぐに使えない可能性があります。リアル書店に紙本の在庫があるなら、行って買えばすぐ読めます。通販なら購入から届くまで早くても半日、という順でしょうか。それに対し、国立国会図書館の複写サービスは、申込みから発送まで5営業日ほどかかります(↓)。
この日数には郵送・宅配にかかる時間が含まれていないので、メールやFAXで対応可能になったとしても、やはり5営業日ほどかかるわけです。この「遅延」をどこまで許容できるか? ということになるでしょう。もちろんケースバイケースとは思いますが、その資料がすぐ買える状態にあるかどうかが、やはり大きいのではないでしょうか。複写サービス利用実態のデータが欲しいところ。実際のところ、市場で入手するのが困難だからこそ、図書館にアーカイブされている資料を利用する、という使い方が多いのではないかと想像します。
電子出版アワード2020 投票を開始!〈JEPA|日本電子出版協会(2020年11月24日)〉
選考委員としてお手伝いしました。投票受付は12月7日(月)23時まで。だれでも投票できます。なお、今年はHON.jp関連のノミネートはありません(苦笑)。
漫画原作者に1年6月求刑、東京 強制わいせつ罪認める〈徳島新聞(2020年11月24日)〉
『アクタージュ』原作者 松木達哉被告の初公判。逮捕されるに至った1回だけでなく「他にも同様のわいせつ行為をしたことがある」とのこと。あえて言いましょう。ほんと、バカだなあ。
韓国発「ピッコマ」が漫画アプリで首位に、その背景とは? 日本企業の課題は?〈Media Innovation(2020年11月24日)〉★
ピッコマの2020年の伸びがすごい、のは確かなんですが、記事タイトル「首位」の根拠であるAppAnnieのセールスランキングは「App StoreとGoogle Playの収益合計」であることに留意する必要があります(↓)。
App StoreやGoogle Playでは決済手数料30%とられるわけで、利益率を考えたら経営的にはなるべくそれ以外の決済手段の割合を増やしたほうがいいわけです。実際のところ、アマゾンや楽天など、ウェブ重視&自社決済中心のサービスは、このランキングの上位には存在していません。
このランキングでは、ピッコマの前はLINEマンガが首位だったわけですが、2020年5月から「LINEポイントクラブ」が開始(↓)され、LINE Payなら最大20%のマンガコインが還元されるなど、特典による利用者の誘導を図っています。LINEマンガが首位陥落した要因は、この要素も大きいのでは? と思うのです。
「鬼滅の刃」特需で書店市場が4年ぶりに拡大か 帝国データバンク調べ〈ITmedia ビジネスオンライン(2020年11月24日)〉★
「鬼滅の刃」最終巻は395万部〈時事ドットコム(2020年11月25日)〉★
くら寿司、コロナ禍でも平日の売上が過去最高に 『鬼滅の刃』コラボの底力〈AdverTimes(2020年11月25日)〉★
鬼滅フィーバーから3連発。出版月報10月号によると、コミックスは鬼滅を除いても前年を上回っているそうです。最終巻の初版395万部って、もう想像を絶する凄さ。あと5万部くらい誤差ではないかと思ってしまうほど。コラボはくら寿司以外でも、ダイドーや銀だこなどで売上が飛躍的に伸びているというニュースを見かけます。すげぇ。「妖怪ウォッチ」フィーバーを思い出します。
リアル書店とインターネット経由の出版物の売上動向をさぐる(2020年公開版)(不破雷蔵)〈Yahoo!ニュース個人(2020年11月25日)〉
不破雷蔵氏によるおなじみの「グラフ化してみる」シリーズから、日販「出版物販売額の実態」2020年版。書店やコンビニなどリアル店舗合計と、電子出版含むネット書店合計の比較です。2019年には3分の1以上がネット経由になっており、このままの傾向なら10年以内に逆転しそう、とのこと。この流れを止めるのはどう考えても難しいので、e-honの「My書店」のように宅配で自宅受け取りでも収益が還元されるとか、アメリカの「Bookshop」のような仕組みでリアル店舗を支えていくしかないのかな、という気がします。
小説版ドラクエ著者、新たにスクエニ・東宝などを提訴 「主人公の名前を盗用された」〈ITmedia NEWS(2020年11月26日)〉
当初は「製作委員会を相手方とした」「非金銭」の「本人訴訟」だったのを、クラウドファンディングで訴訟資金を集め、スクエニや東宝などを相手とした訴訟に切り替えたとのこと。事前に一言筋を通せば済むはずだったものを、なぜこじらせてしまったのか。スクエニといえば、『ハイスコアガール』でSNKプレイモアを怒らせてしまった(のちに和解)事件を思い出します。あのときも今回も、どうも手際が悪い。
漫画ネタバレサイトは違法?適法? -ネット上における漫画ネタバレと著作権法の関係-|弁護士 田島佑規〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2020年11月26日)〉
いわゆる「ネタバレサイト」の違法性について、類型ごとにわかりやすく解説しているコラム。画像の掲載がない文字だけの場合でも「ストーリー展開を詳述するような文字バレサイトについては、(もちろん具体的な記述次第ではあるものの)著作権侵害と評価される可能性は高い」とのこと。まあ、そりゃそうですよね。実態を知るためいくつか試しに閲覧してみましたが、感想が書かれていても1行とか、とても引用要件を満たしているとは思えない場合も多いです。
これってOK!? コンテンツにおける建築物の画像利用 岡本健太郎|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2020年11月27日)〉
こちらは建築物の画像利用について。著作権のみならず、商標権や意匠権など、さまざまな観点から解説しているコラムです。先日、蔦屋書店が内装の意匠登録1号を取得しましたが、仮にそれをイラストで表現しても、意匠権侵害にはなり難い、と。他にもパブリシティ権や施設管理権などにも触れられていて、非常に有益なコラムです。
著作権法第37条を使わない視覚障害者等向け読書支援サービス「YourEyes(ユアアイズ)」の衝撃〈HON.jp News Blog(2020年11月27日)〉
いままでとは異なる新しいアプローチの読書支援サービス。記者発表会がちょうど授業の時間に重なっていて、ライブでは取材できなかったのですが、遠隔対応で映像もアーカイブされていたので助かりました。ただ、著作権法第37条ではなく、第30条の4および第47条の5第1項第2号の「情報解析」に該当する、という見解で進めている点については、追加取材が必要でした。これ、わりと重要なところなので、もう少し丁寧な説明が欲しかったな、と思います。そういう意味で、急いで出した記事です。
ただ、反響を見ていると、それでもまだ踏み越えている部分があるかも? という見解が散見されます。第47条の5第1項→施行令は、「学識経験者に対する相談その他の必要な取組」を要件としている(↓参考記事)ので、ロジックはきっちり固めているとは思うのですが。Facebookで関係者から聞いた話では、元新潮社で弁護士の村瀬拓男氏など複数の専門家にアドバイスをもらっているそうです。それでもやはり、どういうロジックなのかは、当事者からも改めてきっちり説明して欲しいところです。
海賊版に誘導「リーチサイト」の運営者、初摘発…一定の効果期待も「巧妙化」する手口〈弁護士ドットコムニュース(2020年11月27日)〉
リーチサイトの初摘発事例に関連して、そもそもどういう規制なのか? その影響は? など、おなじみ福井健策弁護士による解説です。海賊版サイトの閉鎖や摘発も続いているけど、より巧妙になっていて、アクセス増加傾向もまだ続いているそうです。むむむ。
なぜいま“異世界漫画”が売れるのか? 普通の漫画と違う「決定的な理由」とは〈文春オンライン(2020年11月27日)〉★
出版関係者の匿名談話。異世界ものは2018年ごろに一時下火になったけど、『転生したらスライムだった件』のアニメ化で人気が再燃、読者層の中心は30~40代で、嫌な現実を忘れたいからではないか、とのこと。という記事の内容より、あいだに挟み込まれた『その門番、最強につき』がなんか気になるんですが。1話まるごと掲載されてるけど、PRではない?
海外
香港民主派の周庭、黄之鋒両氏ら収監〈共同通信(2020年11月23日)〉
8月に逮捕されたのは香港国家安全維持法ですが、今回は無許可集会扇動等の罪とのこと。周庭氏は11月22日にTwitterへ「去年香港の警察本部であったデモの件で、明日の日本時間朝10時半から裁判があります。裁判所から出られない可能性もありますが、無事に外に出られますように。」と投稿(↓)、そのまま即時収監されてしまいました。その後、Admin(管理者)を名乗る人物が、近況を伝えています。
米グーグルを追加提訴か 7州が来月、独禁法違反〈共同通信(2020年11月24日)〉
ロシア当局、対グーグルで行政手続き開始 禁止コンテンツ未削除で | ロイター〈(2020年11月24日)〉
英競争当局、グーグルを予備調査 デジタル広告など巡り〈ロイター(2020年11月24日)〉
アメリカ、ロシア、イギリスで続けざまに、行政による対グーグルの動きが、同じ日に報じられています。なんかもう、狙い撃ちされている感。
全米図書賞の翻訳部門を受賞した柳美里『JR上野駅公園口』の功労者は誰か〈HON.jp News Blog(2020年11月25日)〉
おなじみ、大原ケイ氏のコラム。文化庁が2002年に立ち上げたJLPPについて確認してみたら、今年から復活していることを知ってびっくり。かつての失敗は活かされているんでしょうか?翻訳出版するプロジェクトは事業仕分けで終了しましたが、翻訳コンクールとシンポジウムは続いているんですね。[なにか勘違いしていたようなので削除・追記]
ところで、2018年に多和田葉子氏が『献灯使』で同じく全米図書賞の翻訳部門を受賞したときのコラム(↓)もそうですが、最後を関係者への祝福で締めるのは良いですね。ステキ。
ロックダウンで苦境の小型書店、アマゾンにどう立ち向かうか フランス〈BBC NEWS JAPAN(2020年11月25日)〉
フランス政府がアマゾンに圧力をかけ、「ブラック・フライデー」のセールを延期させたそうです。さすがフランス、自国の文化を守るためには相当強引な手も使ってきます。
ペンギン、米出版シェア3割超に 同業のサイモン買収〈共同通信(2020年11月26日)〉
Bertelsmann to Buy S&S for $2.2 Billion〈Publishers Weekly(2020年11月25日)〉
ドイツ・ベルテルスマン傘下のペンギン・ランダムハウスが、バイアコムCBS傘下のサイモン&シュスターを21億7500万ドル(約2270億円)で買収すると発表。手続きはこれからですが、当局の承認が必要(恐らく独占禁止法関連)なので、難航も予想されるとのこと。統合すると、アメリカでのシェアは3割を超えるそうです。大原ケイ氏が今年1月のコラム(↓)で「大きくなって交渉力をつける」とおっしゃっていた動きそのものと言えるでしょう。
武漢を書いたら「売国奴」 作家が直面した冷たい暴力〈朝日新聞デジタル(2020年11月28日)〉
4月に馬場公彦氏がレポート(↓)してくれた『武漢日記』の方方氏が、朝日新聞の取材に応じています。最初は共感を呼び称賛された『武漢日記』が、海外版の翻訳出版で一転、批判と中傷に晒されているとのことでしたが、その後、中国国内での他の作品まで出版見送りの憂き目にあっているそうです。「極左分子」の活動がより激しくなっているのでしょうか? 朝日新聞の有料部分は読めていないので、気になります。
ブロードキャスティング
11月29日のゲストは東京ネームタンク代表のごとう隼平さんでした。上記のタイトル後ろに★が付いている5本+αについて掘り下げました。番組アーカイブはこちら。
次回のゲストは作家・ゲームデザイナー・漫画原作者の架神恭介さんです。ZoomではYouTubeへのライブ配信終了後、オンライン交流会を開催します。詳細や申込みは、Peatixのイベントページから。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジンに掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガに登録してください。無料です。なお、タイトルのナンバーは、鷹野凌個人ブログ時代からの通算です。