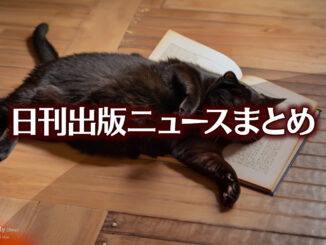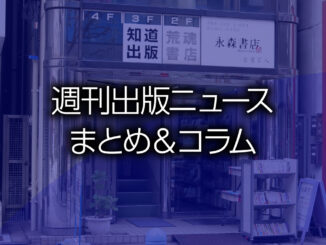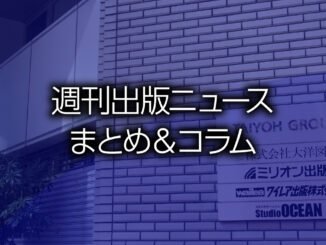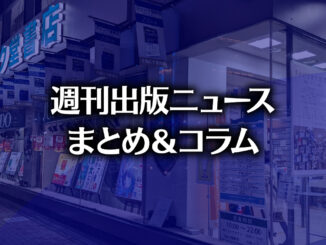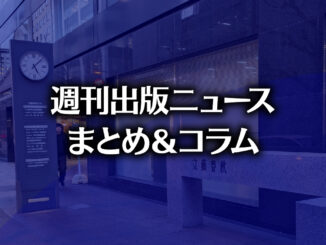《この記事を読むのに必要な時間は約 8 分です(1分600字計算)》
2025年11月16日~22日は「著作権侵害幇助でCloudflareに賠償命令」「AdobeやCloudflareで障害」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
AIの歌詞学習、ドイツ地裁が初の違法判決 OpenAIの著作権侵害認定〈日本経済新聞(2025年11月18日)〉
判決が画期的だったのは、AI学習モデルに歌詞を利用したことを「著作物の複製」と初めて認定した点にある。
アレ? 栗原潔氏の解説と微妙に違う。学習段階が完了しても複製を保存していたことが類推された、という判断なのですか。Anthropicの「中央図書館」と同じようなことをやっていたとみなされたのかと思いきや、福井健策氏(11/19追記)によると「現に簡単な指示で出力においてそっくりの歌詞が出力される以上、とりもなおさずAIのパラメーターは学習されたデータのコピーである」という判断だったとのこと。
インボイス負担軽減策、延長検討 小規模事業者向け―政府・与党〈時事ドットコム(2025年11月19日)〉
いわゆる「2割特例」は来年9月末までなのですが、ここに来て延長に向けた動きが。インボイス制度に特例措置という話が上がっていたころ「これであとは特例期間を延長し続けて実質恒久的なものにすればいい」みたいな話をどこかで目にした記憶があるのですが、掘り出せませんでした。
米クラウドフレアに5億円賠償命令 漫画海賊版の著作権侵害をほう助〈毎日新聞(2025年11月19日)〉
おおお! これは素晴らしい。Cloudflareと大手出版4社は2019年にいちど和解してるんですが、結局その後もCloudflareは、悪質な海賊版サイトのキャッシュ削除やサービス停止等を要求すると「措置を講じる」と返答しつつキャッシュを続けるという舌先三寸っぷりを発揮していたのですよね。
当時すでに政府の審議会で、著作権法47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)但し書き「著権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するのでは、という指摘もありました。私はすごーく妥当な判決だと思います。
海賊版サイトめぐり米・クラウドフレアに総額約5億円賠償命令 東京地裁 「ONE PIECE」や「進撃の巨人」も被害〈弁護士ドットコム(2025年11月19日)〉
こちらの記事には福井健策氏(集英社顧問弁護士)のコメントが載っています。1社1作品だけでの提訴って、賠償金目当てではなく、Cloudflareの行動変容を促す狙いだったわけですね。
海賊版サイト配信めぐり、米IT企業に約5億円の賠償命令 東京地裁〈朝日新聞(2025年11月19日)〉
Cloudflareは控訴するとのこと。まあ、予想通りではありますが、往生際が悪い。
「AI生成画は著作物」、無断複製の疑いで男を書類送検へ…千葉県警が全国初の摘発〈読売新聞(2025年11月20日)〉
このタイトルを見ると一般論として「AI生成画は著作物」であるかのように読めますが、そうではありません。AI生成物が著作物として認められるかどうかは、文化庁「AIと著作権(令和5年度)」のころからすでに解説されています(以下、PDF資料p57より引用)。
AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。
(例)人が何ら指示※を与えず(又は簡単な指示を与えるにとどまり) 「生成」のボタンを押すだけでAIが生成したもの
※プロンプト等
つまり、記事にある「プロンプトは2万回以上だった」というのが、単にボタンを押しただけの試行回数であるならば、それは著作物ではないということです。回数がどれだけ多くても、額に汗(Sweat of the brow)法理で否定されます。
これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
今回のケースは、こちらということなのでしょう。
経済
(社説)ファクトチェック 公権力が判定する怖さ〈朝日新聞(2025年11月16日)〉
三権(立法・行政・司法)が「ファクトチェック」って言うのは確かになんか変ですよね。しかし第四の権力(マスメディア)は第五の権力(一般ユーザー)に監視されたり振り回されてたりしているのも現状だからなあ。
技術
Cloudflareで障害 Xも不調〈ITmedia NEWS(2025年11月18日)〉
「Illustrator」「Premiere」「InDesign」などが起動できない、複数のアドビアプリに問題が発生〈窓の杜(2025年11月18日)〉
この日はあちこちで障害が起きていましたが、Adobeの障害はCloudflareの障害とは関係なかったようです。周囲で「入稿日なのに!」等の悲鳴や怒号が散見されました。いつのまにかインターネット接続が前提になってしまっているという。計算をクラウド側で処理しているのでしょうか。ローカルで動く業務用アプリなのに。怖い怖い。(計算能力
凄すぎてもはや意味不明!画像生成AIの到達点「Nano Banana Pro」ついに公開〈ASCII.jp(2025年11月21日)〉
画像キャプションの「Nano Banana Proで作成」に目をむいた。すさまじい。しかし、看板の文字がよく見たら「BANANA」ではなく「NANANA」ですね。
生成AI経由の流入、「note」強し ゼロクリック問題に一つの解〈日本経済新聞(2025年11月22日)〉
Google検索におけるゼロクリック率はすでに63.5%と、ほぼ3回に2回は遷移しないところまで進んでいた。
この引用箇所の前に検索ボリュームの推移データは出している(横ばい)のに、肝心のゼロクリック率は直近の値だけという。昔の値と比較しないと「進んで」るかどうかわからないでしょ。Gemini 3 Proに調べてもらったら、どうも同じデータソース(調査会社・収集方法)で計測され続けている一般公開データは存在しないっぽいです。
お知らせ
新刊について
『ぽっとら Podcast Transcription vol.1 ~ 詐欺広告や不快広告・金融検閲・生成AIと著作権・巨大IT依存問題など、激変する出版界の広範な論点を深掘りしてみた。』を上梓しました。ポッドキャストファースト、つまり音声コンテンツの書籍化という試みです。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
文学フリマ東京41のHON.jp Booksブースにお立ち寄り&お買い上げいただいたみなさま、まことにありがとうございました。館内放送で出店は3800ブース、来場は出店者含め1万8000人と聞こえてきました。過去最高だそうです。一般入場は大行列だったという声や、南1・2ホールは大混雑だったという声も耳にしました。次回文学フリマ東京42は、大型連休ど真ん中の2026年5月4日(月)です。申込済み。(鷹野)