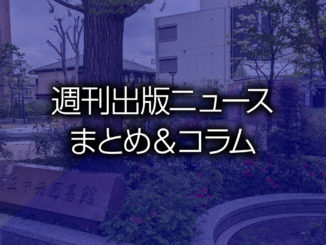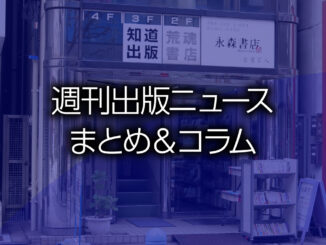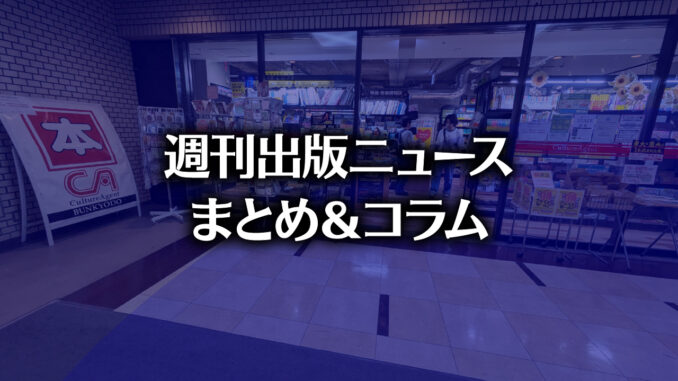
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年2月16日~22日は「RFID装着だけで返品は減る?」「地域書店振興を地方創生で?」「インターネット白書ARCHIVESで2024年版が無料公開」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- Can a Nonprofit Model Work for Bookstores?(非営利モデルは書店に有効か?)〈Publishers Weekly(2025年2月7日)〉
- 編集者の小林えみ氏・よはく舎代表「重い課題と心理的負担」 深井智朗氏めぐり講談社学術文庫に公開質問状 2025年2月18日〈キリスト新聞社ホームページ(2025年2月18日)〉
- 「全国民が知るべき」 国立国会図書館のサービスが話題に〈withnews(2025年2月20日)〉
- 国立国会図書館(NDL)、遠隔複写サービスの複写物をPDFファイルで提供する「遠隔複写(PDFダウンロード)」を開始〈カレントアウェアネス・ポータル(2025年2月20日)〉
- インターネット白書ARCHIVESで2024年版が無料公開に ~ 最新版『インターネット白書2025』発行に合わせ〈HON.jp News Blog(2025年2月21日)〉
- (パブリックエディターから 新聞と読者のあいだで)記事の先へ導くコメント、保存急務 佐藤信〈朝日新聞(2025年2月21日)〉
- 経済
- 第5回 書店人の覚書帳〈草彅主税(2025年2月18日)〉
- Google Play Books purchases on iOS now skirt the App Store’s commission | TechCrunch(iOSでのGoogle Playブックス購入はApp Storeの手数料を回避できるようになりました)〈TechCrunch(2025年2月18日)〉
- Amazon Makes It Clear That Kindle Books Are Licensed And Not Owned(アマゾンは、キンドル本はライセンスであり、所有物ではないことを明らかにした)〈Good E-Reader(2025年2月19日)〉
- 講談社と読売新聞社による「書店振興のための共同提言」の背景にあるものと「実現への大きな課題」(飯田 一史)〈現代ビジネス | 講談社(2025年2月22日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会 デジタル広告ワーキンググループ(第6回)配付資料〈総務省(2025年2月17日)〉
傍聴はしていませんが、資料6-2「広告主等向けガイドライン等の構成について」がちょっと気になりました。このガイドラインの対象範囲は「配信媒体:偽・誤情報、違法アップロードコンテンツ等を含む」かつ「広告主:違法・不当な内容を含まない」場合に限定されています。つまり要するにこれは「広告主」に限ったブランドセーフティーなどです。
対角線上にある「配信媒体:偽・誤情報、違法アップロードコンテンツ等を含まない」かつ「広告主:違法・不当な内容を含む」はどうするつもりなんだろう? そこに書かれている「広告仲介プラットフォームにおける利用規約等に基づく対応」だけでは現状足りていないから、たとえばFacebookで詐欺広告が蔓延していた(る)りするわけですよね? 広告仲介プラットフォームへの対策は必要不可欠だと思うのですが。次回以降でやるのかしら?
「SNS事業者の表現の自由と民主主義」|発信記事〈法学館憲法研究所(2025年2月17日)〉
Facebookがファクトチェックをやめてコミュニティノート形式へ移行することについて、アメリカの憲法修正第1条(表現の自由)の観点から検討したうえで肯定している論考です。他では否定する意見が多かったので、非常に興味深い。ちなみに私も、コミュニティノート形式には肯定的です。ちゃんと多数派工作への対応がなされていれば、ですが。
AI利用、4000件弱投稿か エネ基本計画の意見公募〈東京新聞デジタル(2025年2月19日)〉
本件、直接「出版」とは関係ありませんが、AIの悪用で何にでも応用できてしまう事例なので、注意喚起の意味も込め取り上げておきます。こういう「多数派を装う工作」が容易にできてしまうのですよね。多数派工作そのものはべつにAI利用に限った話ではありませんが、単なるコピペ意見ではなく「多様な意見が寄せられているように見せかけることが容易」である点に問題があります。こういうことがあるから、パブコメって意見の多寡では判断が大きく変わらないようにしているはずなんですよね。
減少が深刻な街の書店、国がデジタル化推進で経営支援…「地域の書店振興は地方創生の観点でも重要」〈読売新聞(2025年2月20日)〉
あー、なるほど。「地方創生」に該当するなら内閣府系でも書店支援が可能になるわけですね。「デジタル田園都市」とか「買物支援」あたりでしょうか?
社会
Can a Nonprofit Model Work for Bookstores?(非営利モデルは書店に有効か?)〈Publishers Weekly(2025年2月7日)〉
こちらの記事、公開日は2週間ほど前ですが、今週届いたPublishers Weeklyのニュースレターで紹介されていて気づきました。なかなか興味深い。確かに、儲けることが主目的の一般大衆向け(あるいはマーケットイン型)の本が「重出版」では求められているのに対し、そうじゃない本は非営利型組織で制作・販売するほうが事業の持続可能性は高いかもしれません。実際、学会誌なんかはすでにそういう形になっているところも多いわけですよね。
編集者の小林えみ氏・よはく舎代表「重い課題と心理的負担」 深井智朗氏めぐり講談社学術文庫に公開質問状 2025年2月18日〈キリスト新聞社ホームページ(2025年2月18日)〉
こちら、2月7日に松井健人氏(東洋大学助教)が公開質問状を発表したことが今回の発端なのですが、さらにその前提として、深井智朗氏が2019年に著書などの内容に極めて悪質な捏造や盗用があるとして東洋英和女学院から懲戒解雇されているという経緯があります。なんと、実在しない神学者カール・レーフラーの論文を引用(つまり創作)するという凄まじいことをやらかしています。
当時、捏造が指摘された著書は、岩波書店が絶版・回収対応をしています。当時私は、さすがにこれは契約書ヒナ型にある「甲(著者)は、その責任と費用負担においてこれを処理する」に該当するのでは、とコメントしていました。
で、小林氏はその「深井氏が様々な追及をうけて実質的に仕事を停止される直前、おそらく最後の公刊の仕事」に編集担当として関わっていたそうです。それはなんというか……お気の毒に。今回問題になっているのは、深井氏がその後、きちんと不正の経緯説明や公への謝罪をしないまま、今回の新刊翻訳で学術の世界へ戻ってくることになった点です。本人はもちろんですが、講談社の姿勢も問われています。
実は一昨年から昨年にかけて、類似する案件が私の身の回りでも発生していて、他人事ではないなと感じました。非常勤講師をやっている二松学舎大学での、前学長・中山政義氏の論文に不正行為(盗用)が認定された事件です。調査報告書・調査委員会意見書には、盗用が認定された1点以外に「そもそも論文の存否が確認できない」事例が複数あるなど、中山氏が自らの潔白を証明できていない点が指摘されています。
そしてこちらも問題は、盗用が認定されたあとに中山氏が公に経緯の説明や謝罪をした形跡が確認できない点なんですよね。少なくとも私は確認できていませんし、いま探しても見つけられません。繰り返し説明会が開かれていましたが、学生や卒業生からも強い不信の声が寄せられていました。現時点でも研究室紹介のページが公式サイトに残っていますが、どうなっているんだろう?
「全国民が知るべき」 国立国会図書館のサービスが話題に〈withnews(2025年2月20日)〉
東京や大阪に立ち寄る機会があったら利用登録をすれば、そのサービスが使えることを知らせています。
いや、利用者登録に「立ち寄る」ことは必須じゃありませんよ。本人確認書類画像のアップロードなど手続きはすべてオンラインでできます。ただ、いま申込みが殺到しているようで「確認が完了するまで1か月程度かかる場合がございます」とあるので、急いでいるなら訪館すべきかもしれませんが。ちなみにその「SNSで話題」になったという投稿を探してみたんですが、見つけられませんでした。リンクくらい貼っておいてくれればいいのに。
国立国会図書館(NDL)、遠隔複写サービスの複写物をPDFファイルで提供する「遠隔複写(PDFダウンロード)」を開始〈カレントアウェアネス・ポータル(2025年2月20日)〉
まず国立国会図書館での対応が始まりました。山田奨治氏がさっそく試しています。画面上でちゃんと見積が出るんですね。本体価格3200円の本を15ページPDFダウンロードで複写してもらうと、推定金額が2700〜3509円と出るそうです。郵送受取の額も同時に出て、その場で切り替えることも可能。親切設計ですね。
スキャナで読み取る紙資料(図書)とすると、NDLの「複写物の作成に要する費用」が画像1枚あたり83.6円(税込)。それとは別に、補償金が本体価格3200円÷300ページ×10で106.6円。つまりページ単価が約190円なので、15ページなら2854円になるはず。上振れはマイクロフィルム(116.6円)、下振れはデジタルコレクション収録資料(62.7円)かしら?
リリース予告の時点で「補償金額の高さに気づいたら怨嗟の声に変わるんじゃなかろうか」と心配していたのですが、山田奨治氏のブログへの反響を見るとすでに……。まあ、ふつうの人は郵送受取で充分でしょうね。海外からの利用は、郵送だとかなり時間がかかるのと、送料も実費がかかるので、PDFのニーズは高いかもしれません。
インターネット白書ARCHIVESで2024年版が無料公開に ~ 最新版『インターネット白書2025』発行に合わせ〈HON.jp News Blog(2025年2月21日)〉
毎年恒例の……ですが、今回ばかりは、昨年亡くなられた井芹昌信氏の名前をどうしても入れておきたかった。あらためて、ご冥福をお祈りいたします。
(パブリックエディターから 新聞と読者のあいだで)記事の先へ導くコメント、保存急務 佐藤信〈朝日新聞(2025年2月21日)〉
え、朝日新聞ウェブ版っていま、5年で必ず消えちゃうんだ……知らなかった。コメントが消えてしまうのも残念ですが、記事のアーカイブが使えなくなってしまうのが困ります。年鑑のURLはすべてWayback Machineにしなきゃダメでしょうか? まあ、別の手段(有料データベースなど)があれば、最低限、URLとタイトルさえ記録に残しておけば調べ直すことは可能ですけど。その場ですぐ検証できないのは面倒ですね。うーん、困った。
経済
第5回 書店人の覚書帳〈草彅主税(2025年2月18日)〉
講談社と読売新聞社の共同提言について、とくに「ICタグで書店のDX化を」の説明にある「購買傾向把握し返本削減」というのはちょっと違うんじゃないの? という趣旨の疑問です。ICタグ(RFID)を装着することで、棚卸がラクになるとか、盗難防止ができるというのは想像しやすいんですが、購買傾向はPOSデータで把握できるのでは? 感が。
そこで、ちょっと過去の資料を掘り出してみました。JPOが以前やっていた実証実験の報告(2007年)を見るに、返品を減らすにはICタグと同時に、部分的にでも「責任販売制(買い切り)」を導入する必要があるように思います。「販売条件、仕入先、取引条件、返品可・不可などの条件管理」がしやすくなるわけですから。あとは「時限再販」も?
Google Play Books purchases on iOS now skirt the App Store’s commission | TechCrunch(iOSでのGoogle Playブックス購入はApp Storeの手数料を回避できるようになりました)〈TechCrunch(2025年2月18日)〉
この英語記事を読んで「日本はどうなっているだろう?」と思い、iOS版Google Playブックスアプリを開いてみたら、もうすでに使える状態になっていました。記事内でも説明されていますが、アプリから外部へのリンクは「日本の公正取引委員会と和解した結果として導入されたもの」なのですよね。いやあ、ここまで長かった。
ただ、実際の使い勝手は、正直まだイマイチ。アプリの「探す」メニューで本の詳細ページを開いた状態から実際に購入できるまでに必要なステップ数がちょっと多すぎ。アプリから離脱するときにOSからの警告が出たりするんですよね。Appleが微妙な嫌がらせをしています。ともあれ、他のストアも早く対応して欲しいところです。
Amazon Makes It Clear That Kindle Books Are Licensed And Not Owned(アマゾンは、キンドル本はライセンスであり、所有物ではないことを明らかにした)〈Good E-Reader(2025年2月19日)〉
いわゆる「購入ボタン」の下に表示される文言が、アメリカのユーザーのみ以下のように変更されたそうです。
By placing your order, you’re purchasing a license to the content and agree to the Kindle Store Terms of Use.
Good E-Readerのマイケル・コズロウスキー氏はこれを、カリフォルニア州で昨年、デジタルでの「購入」はライセンスにすぎないことを開示する必要がある新法が成立したことを受けた対応ではないか? と推測しています。そういえば日本でも、以前は購入ボタンの文言は「1-Clickで今すぐ買う」だったはずですが、いまは「注文を確定する」になってますね。地味に変わってます。
講談社と読売新聞社による「書店振興のための共同提言」の背景にあるものと「実現への大きな課題」(飯田 一史)〈現代ビジネス | 講談社(2025年2月22日)〉
これは私も以前から何度か言っていることですが、そもそも本は粗利が薄すぎるんですよね。「返品できる」とか「腐らない」といったメリットももちろんあるわけですが、それでももう新刊本だけを販売するのでは商売として成り立たないのが現実です。
だからもっと利幅の大きい文具や手帳などを扱うスペースがどんどん拡大し、結果、ますます本が売れなくなるという悪循環。確かに、それを抜本的に解消する方策が、今回の共同提言には見当たらない。正味が高すぎるなんていうのは取引条件の話ですから、政府が口を挟めるようなことではないですもんね。
ところで、記事内で紹介されている『書籍正味問題のすべて』(1972年・新文化通信社)を国立国会図書館デジタルコレクションで読んでみましたが、書店・出版社ともにいまと言い分があまり変わってないことに苦笑い。しかし結局当時は、書店側が12日間の不買ストを行うという力技で、要望を出版社側に呑ませたんですね。知らなかった。私もまだ生まれてないころの出来事です。
技術
Google検索のコンテンツ品質における4本の柱とは?〈海外SEO情報ブログ(2025年2月21日)〉
コンテンツ評価基準の「E-E-A-T」かと思いきや、それとは別に「4つの柱」というのが品質評価ガイドラインに出てきたそうです。E-E-A-Tは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の略です。それに対し今回の「4つの柱」はメインコンテンツの品質についてで、Effort(労力)、Originality(独自性)、Talent or Skill(才能や技術)、Accuracy(正確性)とのこと。微妙に違います。こっちはE-O-T-Aって呼ばれるようになるのかしら?
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
日数の短い2月に祝日が追加され、さらに稼働日が少なくなって忙しない感じがします。いや、私自身はあんまり稼働に影響しないんですけど、世間一般的に。