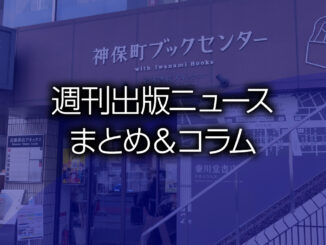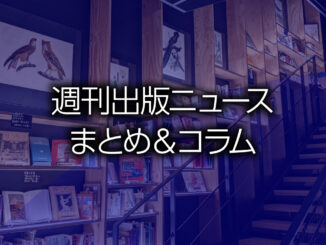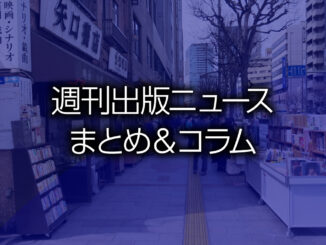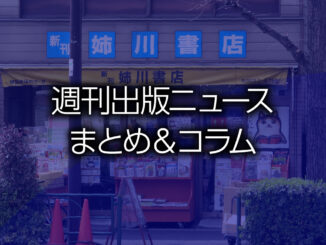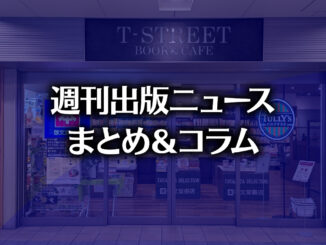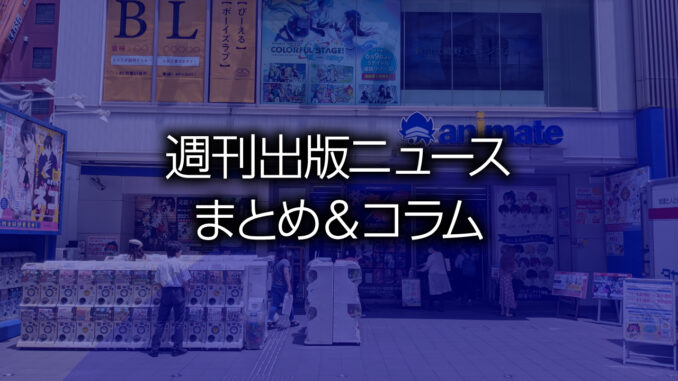
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2021年12月5日~11日は「サイト・ブロッキングは通信の秘密を侵害しない?」「コンピュータサイエンス誌bitが電子復刻」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 「街の書店が消えてゆく」…書店をめぐる状況は今、とても深刻だ(篠田博之)〈Yahoo!ニュース個人(2021年12月4日)〉
- コンピュータサイエンス誌「bit」、1969年の創刊号から全386巻が電子復刻版としてAmazon Kindleで販売開始。1冊わずか198円〈Publickey(2021年12月7日)〉
- 月間6億PV「まだ天井ではない」 文春オンライン、飛躍の裏に隠された施策とは〈Media × Tech(2021年12月8日)〉
- KADOKAWA、世界でコンテンツ発掘 テンセントと連携〈日本経済新聞(2021年12月9日)〉
- 電子コミック:LINEマンガ、ebookjapan 国内流通総額800億円見込み〈MANTANWEB(まんたんウェブ)(2021年12月9日)〉
- 漫画アプリ利用、2年で2倍超に〈日本経済新聞(2021年12月10日)〉
- 出版社とIT企業の思惑 | スペシャルリポート〈週刊東洋経済プラス(2021年12月10日)〉
- 技術
- イベント
- メルマガについて
- 雑記
政治
海賊版サイト、半年で閲覧20億件 被害額は正規市場超え〈日本経済新聞(2021年12月5日)〉
11月29日開催の総務省「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会」関係団体ヒアリングに関連した記事。本件は先週もピックアップしてますが、アメリカでの海賊版被害額が年間1兆円を超えていることや、摘発の難しさについての弁護士談話、そして、熊本大の大日方信春教授がサイト・ブロッキングについて「通信の秘密の侵害にはあたらず、抑止効果も高い」と主張している件について触れられているため、改めてピックアップしました。
大日方教授(専攻は憲法学)の主張について調べてみたところ、日本国際映画著作権協会のサイト(jimca.co.jp)にセミナー資料のPDFがアップロードされているのが確認できました。が、本稿執筆時点ではセキュリティ証明書の期限が切れているため(おいおい)本稿へ直接リンクを貼るのは避けておきます。代わりに、大日方教授の researchmap へリンクしておきます。サイト・ブロッキングについての論考は「日本知財学会誌」「法律時報」「コピライト」にも寄稿しているようです。
[以下2022年1月7日更新]
JIMCAのセキュリティ証明書が更新されたので、PDFへのリンクを貼っておきます。
「海賊版サイト・ブロッキングの憲法適合性」(2020年11月4日)
「サイト・ブロッキング法制化におけるプライバシー権と通信の秘密」(2021年11月4日)
[更新ここまで]
セミナー資料PDFにざっと目を通しましたが、2018年に問題視された刑法の緊急避難でのサイト・ブロッキングではなく、あくまで「法律を制定したうえで」という前提になっています。その上で、「海賊版サイト運営者と閲覧者の表現の自由を侵害するものとは考えられない」「サイト・ブロッキングのための法律に『合理的な期待』を守るための仕組みが規定されていれば、閲覧者の通信の秘密を侵害するとは言えない」という主張です。
緊急避難でのサイト・ブロッキングについては2018年当時、ちばてつやさんが公式サイトで表現の自由の制約につながる「諸刃の剣になりかねない」と懸念を示すなど、著作者側からも懸念が示されていました。それはもちろん「海賊版サイト運営者の表現の自由」を守るためなどではなく、当時、決定の経緯が不明瞭かつ拙速だったことが最大の懸念点だったという認識です。児童虐待記録物の流布を防ぐため開けられた刑法の緊急避難によるサイト・ブロッキングという穴を、経済犯にまで適用して良いのか?(良くない)という意見が当時は大勢を占めていたように思います。
当時と今とで大きく状況が異なるのは、正規版を示すABJマークを用意し「ホワイトリスト」化していること、そして同時に、海賊版サイトであることの証拠が保全されている「ブラックリスト」もABJによって作られている、という点でしょうか。総務省「インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会」の今後の議論で、サイト・ブロッキング法制化というところまで話が進むのかどうか、注視しておきたいと思います。
社会
仙台市図書館が電子書籍貸し出しサービス 文学中心に郷土・震災関連資料も〈仙台経済新聞(2021年12月10日)〉
開始から1カ月経った状況について詳細な数字が公開されています。サービス開始時のタイトル数は2580で、郷土資料や震災関連資料も用意しているとのこと。1カ月間でログイン数は1万8951回、貸出数は4245回、予約数は3540回。利用者は40~50代が最も多く、4割を占めるとのこと。なかなか良い滑り出しでは。
経済
「街の書店が消えてゆく」…書店をめぐる状況は今、とても深刻だ(篠田博之)〈Yahoo!ニュース個人(2021年12月4日)〉
書店の苦境を伝えたあと、末尾に「※そのほか月刊「創」12月号はお早めにアマゾンなどで入手可能です。」と書かれていて、どういう顔していいかわからなくなりました。電子版はYONDEMILLで配信しています。ヤフーニュースに載っているのはダイジェストなので、購入して読んでみました。
本誌では、元書店員の田口久美子さんへのインタビューで「ドイツだと、ネットでアクセスして本を注文すると、注文者の希望する書店に送ってくれ、その書店から注文者に入荷連絡があるというシステムを作っているそうです」というコメントがありました。それって、トーハン「e-hon」や日販「Honya Club」に近しいような。ネット注文での取り置きなら、紀伊國屋書店ウェブストアや丸善ジュンク堂系の「honto with」でも可能です。
もっとも、「e-hon」や「Honya Club」は近所に対応店がなければ利用できない点が大きなネック。ネットで注文してもリアル書店へ収益還元できる仕組み、なのはいいんですが、店頭受取可能な近所の書店が消滅している地域では、使いたくても使えないという。私の場合、最寄りの書店は非対応……。
コンピュータサイエンス誌「bit」、1969年の創刊号から全386巻が電子復刻版としてAmazon Kindleで販売開始。1冊わずか198円〈Publickey(2021年12月7日)〉
イースト「電子復刻」による、休眠資産の掘り起こし。懐かしのコンピュータサイエンス誌ということもあり、はてなブックマークでホットエントリー入りするなど大きな話題になっていました。HON.jp News Blogでは昨年、出版ジャーナリストの成相裕幸さんに取材・レポートいただいてます。単純な電子化作業ではなく、権利処理代行から売上管理請負まで、至れり尽くせりのサービスです([情報開示]イーストはHON.jpの法人会員として賛助いただいてる関係ですが、それを理由に褒めているわけではありません)。
今年成立した改正著作権法で、国立国会図書館による入手困難資料の家庭配信(要IDパス)が来年5月末までに始まる予定になっています。すると、新刊市場(電子含む)では入手困難な資料のほうが、断然アクセスしやすくなるという急激な反転が起きます。楽しみな反面、制度をよく分かってない人による妙な反発が若干怖いなと思っています。このイースト「電子復刻」は、国立国会図書館に「入手困難資料」として扱われないようにする、有効な手段の一つです。
私は正月に、今年の予想の1つとして「既刊の電子化が急がれる(というか急げ!)」と、珍しく命令形の言い回しまで使い、「入手困難資料として扱われたくないなら、早く電子化(POD含む)して市場で入手できる状態にしておきましょう」と書きました。その後も、関連する話題に触れるたび何度も発信し続けてますが、どこまで届いたことやら。
月間6億PV「まだ天井ではない」 文春オンライン、飛躍の裏に隠された施策とは〈Media × Tech(2021年12月8日)〉
SmartNews Awards 2021大賞受賞記念のインタビュー。「文春オンライン」は2年前に3億PVを達成していますが、今年の8月にはさらに倍の6億PVにまで成長しています。私は今年の予想の1つに「出版社系ウェブメディアの飛躍」を挙げていますが、想像を遥かに超える勢いです。コンテンツを提供している各編集部にしっかり収益分配(按分)していることや、編集体制の強化など、かなり細かな内実まで語ってくれています。
同じタイミングで、SlowNewでは「週刊文春」編集長へのインタビュー記事が公開されています。文春砲の内幕や、文春のDX、週刊誌の未来などについて語られており、こちらもかなり読み応えがあります。「『週刊文春』は日本で最後の雑誌になる」という宣言は、なかなかしびれる。
KADOKAWA、世界でコンテンツ発掘 テンセントと連携〈日本経済新聞(2021年12月9日)〉
日本から海外、海外から日本、だけでなく、海外から海外へ、という展開まで行っているKADOKAWA。拠点を現地に広げているので、「現地の法律や言語への対応が円滑に」なっているそうです。文化の違いを把握しローカライズを行わないと、思わぬことで炎上する可能性があります。
2013年には、榎宮祐さんの『ノーゲーム・ノーライフ』が中国で出版中止という事件がありました。恐らく、こういう事例をいろいろ積み重ね、試行錯誤しながら経験値を溜めているのではないかと。
電子コミック:LINEマンガ、ebookjapan 国内流通総額800億円見込み〈MANTANWEB(まんたんウェブ)(2021年12月9日)〉
両店合せた2021年の国内流通総額が800億円見込みとのこと。「LINEマンガ」は最近のリリースで月間流通額100億円超と記述するようになっており、単純計算するとそれだけで1200億円になるよな……とちょっと首を傾げてしまいました。
イーブックイニシアティブジャパンの第2四半期決算(2021年4月~9月)を確認したところ、こちらは「電子書籍事業」セグメントで累計約126億円。期の違いや伸びを考慮すると、年間250億円くらいはありそう。

すると残り550億円が「LINEマンガ」ということになるわけですが、月間流通額100億円超とのつじつまが……ちょっとよくわからなくなってしまいました。売上ではなく「流通額」と記述しているあたりにポイントがある?
漫画アプリ利用、2年で2倍超に〈日本経済新聞(2021年12月10日)〉
フラー「AppApe」による月間利用者数(MAU)での分析を元にした記事。上位6アプリは首位から順に「LINEマンガ」「ピッコマ」「マガジンポケット」「少年ジャンプ+」「マンガBANG」「ゼブラック」とのこと。上位2つが特に伸びているようですが、2019年12月スタートと超後発の「ゼブラック」がこの位置に食い込んでいるのもなにげにすごい。
出版社とIT企業の思惑 | スペシャルリポート〈週刊東洋経済プラス(2021年12月10日)〉
ちょっと「あれ?」と思った点があった記事。「1話売り」について、「当初はピッコマ独自の販売方式だった」「その成功によって他社でも多く展開され、スタンダードになりつつある」と記述されているのですが、話売ってケータイコミック時代からありますよね。
いつからだろう? と「TIMEMAP」で確認してみたところ、2004年6月にケータイWatchで、900iシリーズ向けコミック配信サイト「まんが稲妻大革命」について、「基本的に1話単位の購入となる」と書かれた記事を見つけました。2004年6月はパケット定額制が始まったタイミングで、ケータイコミック配信の大きな転換期です。
それより前だと、インターネット白書2001で「閲覧期間制限付き1回分50~70円で配信」という記述は見つけましたが、まだそのころには「話読み」「話売り」という言葉は出現していないようです。
その後のスマホシフトで途絶えた――わけではなく、例えばアムタス「めちゃコミック」が2015年2月に月間売上高100億円突破というプレスリリースの中で、「1話30円から購入できる~」という特徴を説明しています。「ピッコマ」が登場したのが2016年4月なので、それより前です。
まあ、そういう細かいツッコミはさておき、「漫画アプリの多くはサービス内容が均質化してきており、アプリそのものに根本的な違いがあるとはいえない」というのは、おっしゃる通りだと思います。だから、編集部機能を持っている出版社系が「独自コンテンツ」という意味ではやはり強いし、IT企業系が出版社と同じような編集部を抱え独自のヒット作を生み出せるようになるまで耐えられるかどうか。株式市場で資金調達すると、株主から短期での成果を求められちゃいますから。
技術
7型E Ink採用で170gのAndroidタブレット「BOOX Leaf」〈PC Watch(2021年12月10日)〉
Google Playが利用できるE INK端末の「BOOX」シリーズ、これまで購入を迷っては手が止まったり、買おうと思ったら売り切れだったりしていたんですが、7型170gという軽量の新型が出た報を見て、とうとう買っちゃいました。ペン入力機能は不要で、シンプル・コンパクトなのが欲しかったんですよね。これで「Kindle」「Kobo」以外でも、目に優しいE INKで読書できることに。わーい。
イベント
12月26日の HON.jp News Casting は2時間の年末特番! ITジャーナリストの西田宗千佳さんをゲストに迎え、2021年の出版関連ニュースをとくにテクノロジー的な観点で振り返り&掘り下げます。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
コロナ禍の2年間ですっかり出無精になり、体重がちょっとヤバイ水域に入っていました(デブ症とか言わない)。なるべく毎日散歩するよう習慣づけているにもかかわらず、あまり体重には影響がありません。そこで12月から、しばらく飲酒を断つことにしました。ここ10年ほど毎日飲酒していた習慣の見直しです。まあ、帰省時には多少飲んじゃうと思いますが(鷹野)