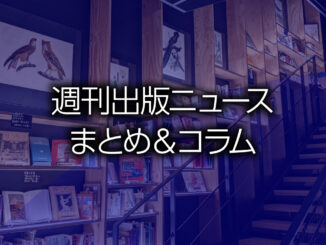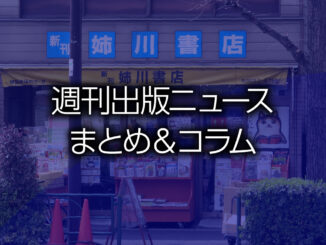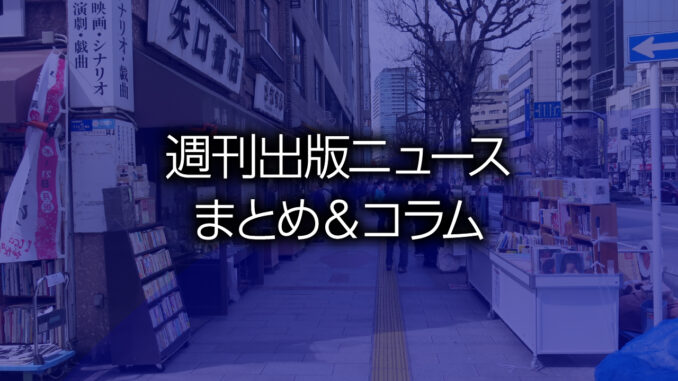
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2022年6月5日~11日は「週刊SPA!全部数にNFTデジタル特典が付与」「デジタル社会実現への重点計画閣議決定」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
政府 デジタル社会実現へ重点計画を改定 有識者会議新設へ〈NHK | IT・ネット(2022年6月7日)〉
記事にある経済財政運営の指針「骨太の方針」はこちら。内閣府で公開されています。「概要」のPDFを開いてみて、思わず「ぐえっ」と声が出ました。目が死ぬ。吐きそう。

また、あわせて閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」はこちら。デジタル庁で公開されています。こちらは要約がHTMLになっていて、比較的読みやすいです。概要(簡易版)PDFは、色づかいは内閣府よりマシですが、情報の詰め込み具合はいい勝負……。
ところが、この概要に目を通しても、記事の見出しにある「有識者会議新設へ」を示す内容が見つかりません。そこで「本文」のPDFを調べたら、54ページの「7. Web3.0の推進」のところにようやく「関係府省庁は連携して、デジタル資産に関する有識者会議を設置」という記述を発見しました。
有識者会議では「デジタル資産の国内外における利用実態、各国の会計基準・課税ルール・制度整備、国際的な事業創造と産業育成のエコシステム、国際標準や多国間のルール整備、研究開発動向と国際競争力への影響、利活用の推進へ向けて必要な人材のスキル、漏洩えい事故・詐欺事案に対応した国際協調体制など、今後の政策立案に資する調査研究を行う」とのことです。
アメリカでは「OpenSea」の元従業員がNFTのインサイダー取引容疑で起訴され、検事が「株もNFTも同じだ」と述べたというニュースもありました。こういった情勢を踏まえつつ、日本ではどういう法の網をかけるかがこれから決まっていくことになるのでしょう。
SNS事業者の情報開示、法制化も検討 ネット中傷などの対策巡り〈朝日新聞デジタル(2022年6月9日)〉
こちらは総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」の、違法・有害情報(誹謗中傷、偽情報)への対策に関する主な論点(案)を踏まえた記事です。資料はこちら。
この研究会は何回か傍聴していますが、TwitterやFacebook(Meta社)といった海外の事業者は、日本におけるユーザーからの通報数や削除件数といった情報開示に消極的なのです(Twitterは後から追加で出したようですが)。それに対し構成員が「責任のある数字を公表したいから、何も公表できないということ(Meta社の言い分)は納得できない」など、かなり強めの批判をしていたのが印象的でした。
まあ、法的強制力を伴っていない「要請」で、国内事業者は動かせても、海外事業者は動かない。それが通用するのは国内だけ、ということなのでしょう。それで「法制化」という話が挙がっている、と。コロナ禍でも「休業要請」とか「時短要請」とか、いろいろありましたね。
視覚障害者等の読書環境の整備の推進に係る関係者協議会(第8回)【WEB会議】配布資料〈文部科学省(2022年6月10日)〉
傍聴したのでピックアップ。まだどこも記事にしていないようですが、出席者に国立国会図書館関係者がいましたから、恐らく週明けくらいにはカレントアウェアネス・ポータルに記事が出てくることでしょう。
これは、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)第18条に基づき設けられた「関係者による協議の場」です。関係省庁が、文科省、文化庁、厚労省、総務省、経産省、国立国会図書館。日本図書館協会、全国学校図書館協議会、日本点字図書館。業界側から、書協、電書連、電流協、日本オーディオブック協議会。大学教授など研究者。そして利用者側として、障害者団体、障害者支援団体などなど。ウェブ会議の画面上で確認したら、44人が参加していました。
参加者が多すぎて、資料の説明だけでかなりの時間を食ってしまうという、これまで傍聴した中でもわりとキツめな会議でした。Cisco Webexの音質が悪くて聞き取りづらい……と思ったのですが、これは事務局だけ会議室に集まって集音マイク1本で運用しているからだと思われます。部屋の反響でエコーがかかってしまうんですよね。声は遠隔のほうがクリアでした。まあ、これは余談ですが。
いろんな話があった中で、とくに経済産業省の発表は「本のつくり手」に直接関わることだと思うので、「読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査報告書」を合わせてピックアップしておきます。印刷用データからテキストデータを作成するのにあたってどのようなハードルがあるのかを実証実験したり、視覚障害者等の読者側の利用環境にどのようなハードルがあるかをヒアリングしたり、といった内容がまとまっています。
また、準備会が設立されたアクセシブル・ブックス・サポートセンター(ABSC)が、今後どのような役割を果たす予定なのかも記されています。読書バリアフリー法第12条(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等)に基づく電子データの提供スキームは、視覚障害者等の受け皿機関がまだ「※要検討」ですが、窓口を一本化するという方向性は見えるのではないかと。
社会
新作の認知手段は基本無料のウェブやアプリに変化した ―― デジタル出版論 第3章 第4節〈HON.jp News Blog(2022年6月8日)〉
連載、今回はマンガの話。紙は、雑誌連載は赤字で作品認知を広げ、単行本で収益回収するモデルで回っていました。これが、雑誌の縮小とデジタル化によりどう変わったのかを整理してみました。インプレス「電子書籍ビジネス調査報告書」の「メディア」と「ストア」という表現は言い得て妙。細かく分類すればいろいろあるけど、大まかに言えばこの2つに集約・整理できると思います。次回は利用率の現状についての予定です。
出版業界事情:個人向けデジタル化資料送信サービスとは?=永江 朗〈週刊エコノミスト Online(2022年6月10日)〉
永江朗さんによる「いくつか誤解もあるようなので、その点に絞って記しておきたい」という解説。永江さんの書かれている内容は正確で良いのですが、もし当事者である出版社の方がいまだにこのレベルで「誤解」しているとしたら、それはちょっとあまりにアンテナが低すぎやしないか? と感じてしまいました。そりゃ「売れゆきへの影響が心配」などと言い始めるわけだ、と。
経済
広告を見ると収益の一部が作者の元に 「少年ジャンプ+」アプリでキャンペーン〈ITmedia NEWS(2022年6月7日)〉
面白い仕掛け。少しだけ「アドセンスクリックお願いします!」を思い出してしまいました(Google AdSenseを使っている場合、規約違反です)。リワード広告に近い形ですが、報酬が作品の著作者へ還元される点が大きな違い。ベクトルが変わると、印象が全然違います。それによって、読者も著作者も広告主も喜ぶのなら、パブリッシャーとしても嬉しいわけです。
これ、広告プラットフォームを他社に依存していたらできない技ではないでしょうか。集英社(&小学館)は独自の広告プラットフォームを持っています。自分たちでルールメイクできるのは強いです。実によい。
Kindle中国撤退、無料慣れした消費者に見切り。動画メディアの成長も逆風に〈Business Insider Japan(2022年6月7日)〉
先週(#524)お伝えしたKindleの中国撤退の「理由」についての報道がいくつか出ていました。いちばん詳しい(ように感じた)Business Insider Japanの記事をピックアップしておきます。
とはいえ「スマホ向け無料アプリ」や「スマホ向け有料閲読アプリ」との競争に負けたというのは、ちょっと釈然としないものがあります。Kindle中国版って、確かに電子書籍リーダー端末がよく売れてたかもしれませんけど、専用端末だけを展開していたわけではないはずなんですよね。他国と同様、アプリも提供しています。ヘルプには、アプリは2024年6月までダウンロード可能と書いてありました。それなのに、記事ではまるで専用端末だけを展開していたかのような記述になっていて。うーむ。なにか他にも理由がありそうな気が。
NFTデジタル特典が「週刊SPA!」全部数に付与〈新文化(2022年6月9日)〉
ちょっと驚きました。このメディアドゥ×トーハンの「NFTデジタル特典」は、従来はトーハン取引帳合先だけに限定されていました。それが今回は、全部数に付与されることに。トーハンのリリースではその理由を「当該商材の価値を読者に広く訴求し、マーケットの拡大を急ぐことが出版業界全体の活性化に資すると考え」と説明しています。出版社側(=今回は扶桑社)の強い意向があったのかな、とも思いますが。
なお、メディアドゥ「FanTop」が後述のNFTマーケットと大きく異なる点は、「誰でも出品できるわけではない」ことです。出版社など、一定の社会的信頼があるIPホルダーに限定しているので、偽物が出てくる心配はありません。完全に「別物」と言っていい。同一視したら可哀想です。
技術
「NFTの8割が偽物」に対策加速 JCBIなどシステム本運用へ〈日経クロストレンド(2022年6月7日)〉
誰でも売買可能なマーケットに有象無象が集まった結果、見事に偽物だらけのレモン市場に成り果てました。10年前、「Gumroad」が登場したとき私が危惧したことが、オープン型のNFTマーケットでは悪い意味で見事に実現してしまいました。それを解決するには、結局、中央集権型の契約管理システムが必要になるという。皮肉な話です。
ちなみに、アマゾンが2021年に250万件以上の偽アカウント開設を阻止したり、40億件以上の悪質出品を事前に阻止したというレポートを出していますが、中央集権型でここまでやってそれでもなおあの有様だということは頭に入れておいたほうがよいでしょう。ヤフオクやメルカリも似たような状態かな。
出品のハードルを上げると出品数が減ってしまい、購入者したい人も集まらない。出品のハードルを下げると偽物出品が増えてしまい、購入者したい人が逃げてしまう。ジレンマですね。なんでもアリの闇市みたいな状態を、ユーザーも許容しているうちはまだよいのでしょうけども。
スケブが表現の自由のための「スケブコイン」を発行 9月にZaifでの取引開始を目指す〈ねとらぼ(2022年6月11日)〉
改めて自分の過去記事を調べたのですが、このニュースの根幹にあるクレジットカード会社が表現規制を行っている問題について、本欄で取り上げたことがなかったことに気づきました。Twitterにはときどき書いていたんですが。
私の知る限り、始まりは2006年。クレジットカード会社を含む金融業界とインターネット業界から18社が集まり、児童性虐待記録物の撲滅を目指す団体「Financial Coalition Against Child Pornography(FCACP)」が結成されます。決済手段を封じることで、性的虐待コンテンツを購入できないようにする。そのための国際協力を行う団体です。
このFCACPが実際の運用にどの程度まで関わっているかは不明ですが、クレジットカード会社の言う児童性虐待記録物の示す範囲は、アニメやマンガといった日本では合法な「非実在青少年」の性描写まで及んでいます。このため以前からときどき、ネット通販(電子含む)の事業者に対し、クレジットカード会社から作品名指しで取り扱いを停止するよう連絡がある、という噂を耳にしていました。2015年には「エロゲー」に対しそういった動きがある、というニュースもありました。
そして最近、クレジットカード会社からの要求範囲はさらに広がっています。スケブのリリースに “2021年2月に大手クレジット会社から複数の出版社に対して、商品の表題に「○○殺人事件」等の特定の表現がある商品では、クレジット決済が取り扱えなくなる旨の通知があった事実が発覚し、表現の規制について参議院議員により問題提起が行われました” とあるように、性表現以外にも及んでいるのが現状です。
まあ、以前から Apple App Store や Google Play でも、程度の差はあれど似たような話はありました。こうなると、プラットフォームに依存しない別の決済手段を用意するしかない、という話になるわけです。そこでスケブは、既存の暗号通貨だけでなく、暗号通貨の新規発行(IEO)で資金調達したうえで決済に利用してもらう予定、というのがこのリリースの内容となります。引き続き「NFTはやらない」と明言していることもポイントでしょう。
なお、FCACPから出ている最後のレポートは、2017年の「Cryptocurrency and the BlockChain: Technical Overview and Potential Impact on Commercial Child Sexual Exploitation(暗号資産とブロックチェーン:技術的な概要と商業的な児童性的搾取への影響の可能性)」です。迂回手段として、当時からすでに想定されていたことになります。実際、暗号資産はマネーロンダリング(資金洗浄)に使われるなどの問題点も指摘されています。
関連してちょっと気になっているのが、DMMみたいに暗号通貨取引所を自社でもっているところの動き。現状では、自社のコンテンツストアで暗号通貨を決済手段として提供していないんですよね。LINEや楽天も同様。これ、なぜなんでしょうね?
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
関東甲信地方は、6月6日に梅雨入りしたようです。雨降りの中、散歩に出かけるのが少しおっくうになっています。ただ、気分が晴れないのは、雨模様だけが理由ではありません。戦争反対!(鷹野)