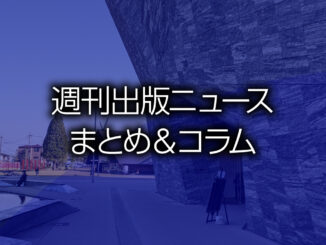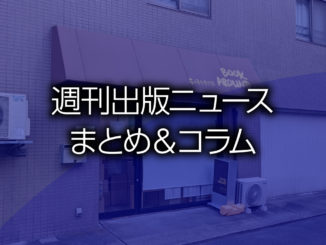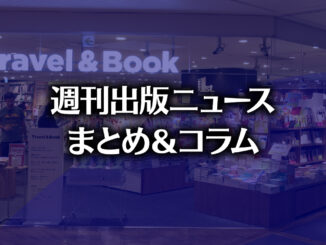《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年7月24日~30日は「漫画村提訴で賠償19億3000万円の請求」「上半期出版市場8334億円、電子は2373億円」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
Googleなどが日本で法人登記、裁判手続きは迅速化される? 今後の影響を聞いた〈弁護士ドットコム(2022年7月28日)〉
海外事業者の日本法人登記によってどのような効果が期待できるか? について、弁護士・清水陽平さんが解説しています。端的に言えば「さまざまな手続きを日本国内で完結できる」点がメリットですが、開示請求の迅速化は10月1日施行の改正プロバイダ責任制限法のほうが影響は大きいようです。なるほど。
ちなみに7月25日の日経報道によると、法務省が登記を要請した海外事業者48社のうち、13社が登記を申請し、うち6社の登記が完了したとのこと。7月1日時点で「登記の意思を示しているのは31社」だった(#528)ので、意思だけ示して実行していない事業者が18社あることに。法務省、舐められてる?
「本格的デジタルアーカイブ」は実現可能か?〈ITmedia NEWS(2022年7月28日)〉
ITジャーナリスト・西田宗千佳さんによる「消えるウェブサイト問題」などへの対策についての論考です。「残す努力をすれば」デジタル化以前より「残しやすい」のは確かで、問題はその「残す努力」=維持コストをどこが負担するか。おっしゃるとおり「国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)」の範囲を広げる、つまり国の予算で公共財産として残すのが現実解と思われます。
具体的には、国立国会図書館法第25条の4で民間は「オンライン資料(電子書籍・電子雑誌)」だけが対象になっているのを、国、地方公共団体、独立行政法人等(第25条の3)と同様、「インターネット資料」全体を対象とすることでしょう。来年からやっと「オンライン資料」の納本義務が有償またはDRM有まで広がりますので、次のステップとして納本制度審議会で議論を進めて欲しいところです。
もちろん、細部はいろいろ詰める必要があります。「日本国内で」の範囲をどう区切るか(海外から日本向けに配信されているものをどうするか)、著作権侵害・名誉毀損・侮辱行為・個人情報など犯罪行為あるいはそれに近いグレーゾーンの情報発信をどうするか、削除申請にどう対応するか、どこまで公開するか(国立国会図書館内閲覧のみ、あるいは図書館送信&個人送信までなど、段階的措置も可能でしょう)などなど。あれ? 結構大変かも?
社会
コミックアプリ利用率は「LINEマンガ」がトップ、46.2%が課金経験あり MMDの調査〈ITmedia Mobile(2022年7月25日)〉
2月のニールセンデジタルの調査(#519)では1位 ピッコマ、2位 LINEマンガでしたが、今回のMMD研究所の調査では1位 LINEマンガ、2位 ピッコマと逆になっています。調査手法が異なるので、参考程度に。
なお、ニールセンと同様、MMD研究所も「Kindleストア」や「楽天Kobo」など総合型電子書店は対象外にしているようです。つまりこれは、仮にリアル書店で言うならば、アニメイト、らしんばん、メロンブックス、K-BOOKS、とらのあな、COMIC ZIN、わんだ〜らんどなどのマンガ専門店だけを対象とし、マンガもたくさん売っているはずのAmazonや紀伊國屋書店や丸善ジュンク堂などはあえて除外している調査、ということです。それが「ダメ」という話ではなく、除外されている部分があることを念頭に入れておくべきだ、という話です。
個人的に興味深いのは「コミックアプリ/サービス別の課金経験」について。ストア型で長年やってる「めちゃコミック」「コミックシーモア」「ebookjapan」「Renta!」の4事業者が突出して高く、メディア型(無料閲覧)を基本とする他のサービスとは一線を画していることもわかります。
ただ、設問を確認したら「あなたはコミックアプリ・サービス内で課金したことがありますか?課金したことがあるコミックアプリ・サービスをすべて教えてください」と期限を切っていないので、最近は使っていないケースも含まれちゃってるようです。ちょっと残念。こういう調査はやはり、インプレス「電子書籍ビジネス調査報告書」のほうが良いかな。
デジタル出版のメリット ―― デジタル出版論 第3章 第7節〈HON.jp News Blog(2022年7月29日)〉
連載20回目。なんか妙に手こずるなと思ったら、文量が普段の倍くらいになっていました。授業でも「メリット」を違う立ち位置から見るとデメリットになることについては触れているのですが、ちょっと盛り込みすぎたかも? とはいえ、次回の「デメリット」は今回触れたこと以外にも結構あるんですよね。ただしその要因は……という構成になる予定。
スクエニ漫画アプリが黒塗りだらけ 海外版に苦言相次ぐ…運営が釈明「修正避けられなかった」〈J-CAST ニュース(2022年7月29日)〉
プラットフォームによる表現規制問題。「iBookstore(現Apple Books)」が始まってすぐのころ、『To LOVEる ダークネス』や『GANTZ』が配信停止になったのを思い出しました。もう9年以上前の話か……。当時はわりとすぐに復活しましたが、その後もプラットフォーマーが表現の内容にまでイチャモン付けてくる傾向はずっと続いているようです。
海外の報道を見るに、スクエニのアプリで黒塗りされているのは「水着」とか「胸の谷間」レベルのちょっとえっちな箇所だけでなく、「普通に描かれたズボンの股」とか「膝」のような意味不明な部分にまで及んでいます。審査する人がなにを考えているのか理解不能。こうやって騒ぎになることも見越したうえで、あまりに理不尽なプラットフォーマーへの抗議の意味を込めた黒塗りなのかもしれません。
経済
インプレス、「いちばんやさしいWeb3の教本」の販売終了と回収を発表〈INTERNET Watch(2022年7月25日)〉
発売に先駆けて7月19日から無料公開が行われ、その直後から騒ぎになっていました。直後にインプレスから「今後の方針発表は7月25日月曜日を予定」とあったので、先週の段階ではピックアップするのを止めていました。結局、「ご意見いただいた誤りやわかりづらい表現箇所を修正・反映しての本書の販売継続は難しい」という判断で、販売終了、返品・返金対応ということに。
これは「インターネットマガジン」や「インターネット白書」などを手掛けてきた、インターネットの歴史をよく知っているはずのインプレスだからこそ燃えた事例だと思います。「Web1の時代は1970年代から80年代にかけて整備され」といった記述は、インターネットの歴史をないがしろにしているようにも感じられるわけで。「Web3」が最先端のよくわからないものだったとしても、これまでの歴史についての記述をチェックすることは可能です。その歴史をちゃんとアーカイブし、公開までしているインプレスらしからぬ事件だと感じました。
◇ インターネットマガジン アーカイブ
◇ インターネット白書 アーカイブ
ちなみに私は、こういう事実があった記録を手元に残しておく意味で、騒ぎが起きた直後に1冊確保しておきました。なんだかメルカリ等で高騰しているようですが、手放すつもりはありません。内容はさておき、結果的に「世間の声による焚書」事例になってしまったのは残念です。
2022年上半期出版市場(紙+電子)は8334億円で前年同期比3.5%減、電子は2373億円で8.5%増 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2022年7月25日)〉
紙は店頭が落ち込んでいるので予想通りの減。ただ、この数字は取次ルートだけなので、ここに含まれていない出版社直販や書店直取引にどれだけ流れているかも気になるところです。コミックスが大幅減(約26%減)ですが、それでも2019年比では約10%増というのはすごい。
電子コミックはギリギリ2桁成長。そして、文字モノはまさかのマイナス成長。昨年の「DMMブックス」キャンペーンの反動が大きいとのことですが、うーん……ここまで市場が成長した段階で、1ストアの動向が全体の数字にそこまで影響するものなのでしょうか。解せぬ。
出版大手3社が「漫画村」提訴 賠償金「19億3000万円」請求〈弁護士ドットコム(2022年7月28日)〉
刑事は地裁での実刑判決が確定していますが、こんどは民事訴訟です。「巨額の損害賠償」が待ち受けていると言われていた通り。ただ、出版社側のコメントには「現実的な回収可能性を措いても避けることのできない責務」とあり、「巨額の損害賠償が認められた」ことによる犯罪抑止の効果を狙っているのでしょう。
ちょっと「おや?」と思ったのは、今回の提訴がKADOKAWA、集英社、小学館の3社である点。講談社が抜けています。なぜだろう? 別途、単独で提訴するのかしら?
Facebook、米国でニュース配信元との契約解消へ–動画やクリエイターを優先〈CNET Japan(2022年7月29日)〉
日本では未展開だった「Facebook News」が、日本へ来ることなく終了へ。2019年に開始されたこのサービスは、Facebookに承認されたパブリッシャー限定で収益分配するというものでした。Googleの同様な取り組み「Google News Showcase」は展開地域を広げましたが、Facebookは畳む方へ動いたことになります。とほほ。
動画やクリエイターを優先するなんて言ってるようですけど……実際、どうなんでしょうねぇ。眉に唾つけておきたい。私が管理しているFacebookページでは「HON.jp News Blog」のみ、複数ある収益化ツールのうち「インスタント記事(Instant Articles)」だけ申し込み基準を満たしている状態のようですが、設定してみる気になれないのが正直なところです。
技術
日経新聞がオンライン決済のStripe導入を発表・・・ボトルネックの決済手段を改善〈Media Innovation(2022年7月30日)〉
クレジットカード決済だけであることが「新規参入を阻害していたことに同社は気付きました」とありますが、これは「Stripe」のプレスリリースの言い分です。決済手段の少なさがボトルネックになると、日経がいままで気づいていなかった……なんてこと、ないと思うんですよね。日経IDって日経BPパスポートとの統合を行っていて、けっこうたくさんのサービスに絡んでいるので、なにか技術的なハードルがあったのかも?
ちなみに「令和3年版情報通信白書」によると、クレジットカード・デビットカードの利用率は全体で66.9%です(図表1-1-1-12)。つまり、クレジットカード決済だけだと、ユーザーの3分の1には逃げられることになります。普通に考えたら、結構痛い。
これが、インターネットが普及しはじめたころはどうだったか? というと、「平成10年版情報通信白書」で51.1%と約半分です(1997年調査・ユーザー利用と事業者採用のギャップがまだかなり大きい)。そこから20年以上かけてじわじわ増えて、ようやく3分の2にまで至った、ということになります。
ちょうど10年前、私は個人ブログで「電子書籍ストアレビュー」を始めました。そのとき、どういう観点で評価するかを考え、5項目挙げた中に「簡単に買えること」がありました。「クレジットカードの審査が通らない方や、未成年の場合が問題になります」と当時の私でも気づいてましたし、実際当時から、多くの電子書店ではさまざまな決済手段を用意するのが当たり前のような状態になっていました。だから、日経がいまさら気づくなんてことはないと思うのですけどね。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
公私ともどもお世話になっていた方が急逝しました。私よりほんの少しだけ年上で、ライターとしては大先輩。インディペンデントな電子雑誌という取り組みも、私よりずいぶん前にやっていた、人望の厚いすごい人です。いつかぼくがそっちへ行ったら、また一緒に飲んで食べて語り合いましょう。いまはゆっくりお休みください(鷹野)