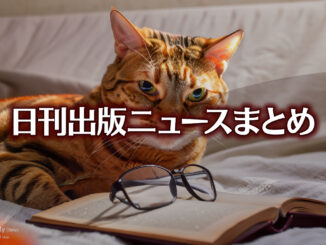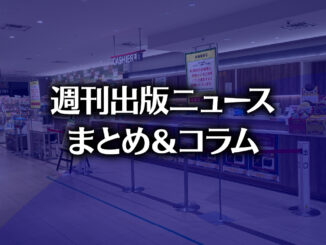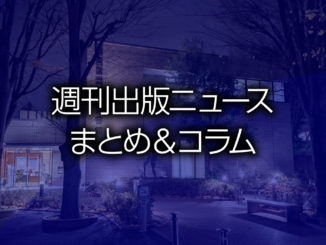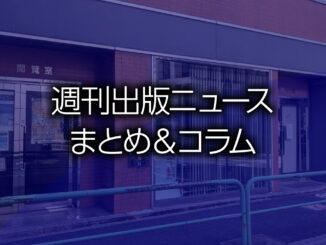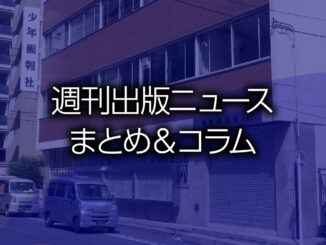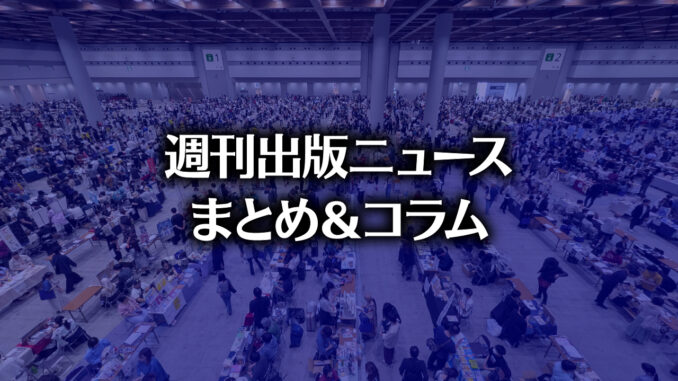
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2025年11月9日~15日は「ドイツ音楽著作権協会がOpenAIに勝訴」「新聞協会がNHKに記事を1週間で消すよう求めている」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 「カエル写真」最優秀賞を取消し、受賞者が「自作でない」と申告…SNSで「AI画像と似ている」と指摘も〈弁護士ドットコム(2025年11月10日)〉
- 第13回 書店人の覚書帳〈草彅主税(2025年11月11日)〉
- FANZA同人、AI作品の投稿を「月3本まで」制限 作品急増で「審査業務の負荷増大」〈オタク総研(2025年11月12日)〉
- 「10年で1万5000店舗が…」“閉店ラッシュ”が止まらない書店業界、深刻な事態を打破するための“生き残り策”とは〈日刊SPA!(2025年11月13日)〉
- 「Sora 2」が踏んだ虎の尾 国内から怒りの声明続出も、立ちはだかる著作権法の“属地主義”:小寺信良のIT大作戦〈ITmedia NEWS(2025年11月14日)〉
- オールドメディアはつぶしあって共倒れする〜NHK ONEのニュース1週間消滅問題〈境治@MediaBorder(2025年11月14日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
OpenAI、ChatGPTなどで歌詞無断利用 著作権法違反とドイツ地裁判断〈日本経済新聞(2025年11月12日)〉
勝訴したのはドイツの音楽著作権協会(GEMA)で、賠償額は明らかにされていないそうです。もう少し詳しく知りたいと思い調べてみましたが、The Guardianの記事が比較的詳細でした。OpenAI側は「使ったユーザーの責任だ」と主張していたようです。うへぇ。
OpenAI、ドイツでの著作権侵害訴訟で敗訴(理由は「無断学習」ではない)(栗原潔) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年11月13日)〉
もう少し詳しい解説は出てこないかな? と思っていたら、栗原潔氏が書いてくれました。ありがたや。どうやら「学習」段階ではなく、シンプルに「出力」段階の類似性で違法だと判断されたようです。
図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議(第8回)配付資料〈文部科学省(2025年11月14日)〉
報告書骨子案まで進んでいますね。電子書籍関連の項目が多い。ただ、p3にこんなことが書いてありました。
【今後の方向性】
広域連携による費用負担の解決:「デジとしょ信州」(長野県)等を例に
うーん……やっぱりそうなっちゃうんですね。これによりどこへしわ寄せが行くって、電子図書館サービス事業者、出版社、そして、著者なんですよ。買い手(自治体)の費用負担が軽減されるということは、売り手の売上が減少するのと同義ですから。
GIGAスクールで端末や通信環境といったハードウェアに予算がかかっているのは承知しています。でも、コンテンツを含むソフトウェアがなければただの箱なんですから。コンテンツにもしっかり予算つけて欲しいなあ。
社会
「カエル写真」最優秀賞を取消し、受賞者が「自作でない」と申告…SNSで「AI画像と似ている」と指摘も〈弁護士ドットコム(2025年11月10日)〉
これはもうパッと見てすぐAI出力を疑うレベルなので、審査する側に見る目がない。というか、どうやらこの取り消しになった方は、これまでも何度もストックフォトで見つけた良さげな画像をコンテストに応募することを繰り返していた常習犯だったようです。全日本写真連盟埼玉県本部公式サイトから過去の受賞作が消されているのを見つけてしまいました。痕跡はこちら。とほほ。
2022年に発生したMidjourneyの出力でファインアートコンテスト1位になった事件がこういう事例の嚆矢でしょうか。あれから3年経って、生成AIのレベルは当時より飛躍的に向上しています。でも人間のほうがまだ順応できていません。「子ガメをくわえるタヌキ」の写真事件のときも指摘しましたが、画像を受け取った側は最低限、画像検索とメタデータのチェックくらいは必須にしたほうがいいでしょう。
というか、私も決して他人事じゃないんですよね。出版演習の授業で学生の提出物を念のためチェックすると、わりと少なくない確率でどこかから盗んできたものが混入してますから。まったく油断できませんし、手も抜けません。
妖怪川柳コンテストが今年で終了 「AI作品との見分けが困難」〈テレ朝NEWS(2025年11月9日)〉
写真やイラストと違って、テキストは人間作品とAI作品を見分けるのが極めて困難です。プレーンテキストにメタデータなんか埋め込めませんし。ただ、こういうコンテストにとってより大きな問題は、AI出力の投稿が桁違いに届くようになってしまい、選出の手間に運営が押しつぶされてしまうことでしょう。SF誌「Clarkesworld Magazine」が投稿システムを一時閉鎖したニュースを思い出します。
第13回 書店人の覚書帳〈草彅主税(2025年11月11日)〉
松丸本舗と松岡正剛氏について。私は、松丸本舗がどういう店だったか知りません。あまりいい評判は聞かなかったのですが、こちらを読んで得心しました。棚を編集するといっても、書店だと売れたぶんを補充しなければならないわけです。でもその編集が凝りすぎていると、発注が間に合わない。だから必然的に「永遠に再現されない編集」になってしまう、と。逆に、角川武蔵野ミュージアムの棚はとくにおかしな印象は受けなかったので、入れ替え頻度が低い棚なら良かったのかも。
【書店員の目 図書館員の目】95 図書館現場の除籍と選書問題(菊池壮一)〈The Bunka News デジタル(2025年11月11日)〉
こちらも棚の編集に関する話。図書館の棚も、メンテナンスが必要だぞと。草彅氏のnoteと同じ日に公開されたのは偶然でしょうけど、興味深い。
FANZA同人、AI作品の投稿を「月3本まで」制限 作品急増で「審査業務の負荷増大」〈オタク総研(2025年11月12日)〉
FANZA同人は使っていないのでどういう状況になっているのかわかりませんが、こういう規制が入るということは、恐らくもう膨大なAI作品が投稿されているのでしょうね。しかし「月3本まで」という規制は、複数のアカウントを駆使して毎月上限いっぱいまで投稿するハックにやられちゃうのでは。イタチごっこになるだろうなあ。
過度な頻度で作品やエピソードを投稿する行為はお控えください〈カクヨムからのお知らせ(2025年11月13日)〉
カクヨムでも最近、ランキング1位にAI作品が入ってしまう現象が起きているのは把握していました。しかし、こちらのお知らせではAI作品については触れられていません。あえて曖昧な言い方をしているのかな? と感じました。
この本、AIではなく人間が書きました。「文学のオーガニック認証」が英国で始動〈IDEAS FOR GOOD(2025年11月13日)〉
こういう動きも。しかしこれ、意味あるのかな……?
「10年で1万5000店舗が…」“閉店ラッシュ”が止まらない書店業界、深刻な事態を打破するための“生き残り策”とは〈日刊SPA!(2025年11月13日)〉
SPA!の記事に真面目にツッコミ入れるのも我ながらどうかと思うのですが、もう冒頭からいきなりこれですから続きを読む気がしなくなります。
書店はここ10年ほどで約3割、およそ1万5000店舗が姿を消しました。読書離れが進んでおり、雑誌の売れ行きも低迷。書籍市場をけん引するコミックスは電子書籍化が進んでいるため、書店に足を運ぶ人が少なくなっているのです。
えっと、まず「読書離れ」はこういう記事の導入における常套句というか定型文みたいな状態になっちゃってますが、何度でも言います。こういう導入は止めましょうよ。
そして、コミックスは8割以上が“雑誌”扱いです。2024年実績で、紙のコミックス(単行本)市場は1472億円で、うち“書籍”扱いのコミックスは259億円、占有率17.6%です。つまり「書籍市場をけん引するコミックス」は間違い。
「Sora 2」が踏んだ虎の尾 国内から怒りの声明続出も、立ちはだかる著作権法の“属地主義”:小寺信良のIT大作戦〈ITmedia NEWS(2025年11月14日)〉
うーん……ちょっと解せない。著作権法が「属地主義」なのは間違いないのですが、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞、日経はすでに、Perplexityが日本で権利侵害しているからと東京地裁で提訴してますよね。この文脈でその動きに触れないのはなぜだろう? 不思議。
あと、2023年に読売が「政府が法改正当時、AIによる著作権侵害の可能性を権利者側に十分説明していなかった」と書いていたことを引用してますが、私は当時すでに激しくツッコミを入れています。改めて書くと、2016年時点の知的財産戦略推進事務局資料にはすでに「コンピューターから、人間の創作物と見分けのつかない情報が生成される状況になりつつある」と書いてあります。
つまり、想定しているどころか、もう当時からそういう状況だったことが示されているのです。そして、それを踏まえたうえで2018年改正は行われます。その改正について議論する審議会に、日本新聞協会はちゃんと委員を送り込んでいます。つまり、政府の説明が足らなかったのではなく、日本新聞協会の委員がちゃんと聞いてなかっただけなのでは?
オールドメディアはつぶしあって共倒れする〜NHK ONEのニュース1週間消滅問題〈境治@MediaBorder(2025年11月14日)〉
境氏が傍聴した11月10日開催の総務省有識者会議で、日本新聞協会の委員がこんな発言をしていたそうです。
「配信期間について、1週間が基本なのに実際の運用を見るとかけ離れた事例が散見される。ルールの例外を作ってなし崩し的に拡大することを危惧する。」との指摘があった。
うへぇ……現時点ではまだ総務省の検証会議のページに議事要旨が出ていないので確認できませんが、そんなこと言ってたのですか。「ちゃんと1週間で消せよ!」とNHKの足を引っ張ってるんですね。ユーザーの利便性とかまるで気にしてないわけですか。ゲスいな。
NHK ONE、簡単には「閉じられないメッセージ」表示へ 目的は“NHK受信料”の徴収 なぜ強引な仕様に?〈ITmedia Mobile(2025年11月12日)〉
そういう状況下でこういうことをされると腹が立つだけなので、私はChrome拡張機能を使って、news.web.nhkドメインへの自分のアクセスをブロックすることにしました。間違えてアクセスしても、ページが開けない状態に。だって、短期間で消されてしまうことがわかっている記事を拾いたくありませんし。あーあ、日本新聞協会の思惑通りになってしまった。
経済
モンストやウマ娘、Appleの聖域「決済」に挑む 12月スマホ新法追い風〈日本経済新聞(2025年11月12日)〉
電子書籍アプリでもiPhone向けで「リンク誘導決済」が広がっている。米アマゾン・ドット・コムの「キンドル」では書籍ページに「getbook」というURL付きのリンクが登場した。アマゾンのサイトに遷移して電子書籍を買える。
おっと、気づいてなかった。日本のKindleアプリ(iOS版)でも「getbook」のボタンが確認できました。タップするとAppleの嫌がらせのような警告が出ますが、無視して進むとウェブの商品ページが開きます。ついにこの仕様がAppStoreの審査を通るようになったのか!
「書く」で生きるは続けられるのか? 現役ライターが語る本音と実情〈朝日新聞(2025年11月15日)〉
無料イベントの告知だからそんなに目くじらを立てるようなことじゃないかもしれませんけど、あえて苦言を。「記事」として配信している以上は「theLetterを運営しているOutNowは朝日新聞社の100%子会社です」と関係性を開示したほうが誠実だと思いますよ。せっかく面白そうなイベントなんですから。私は申込済みです。
技術
老舗コンピューター雑誌のバックナンバー23年分、1枚の画像に変換され無料公開中【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2025年11月13日)〉
1枚の画像!? と思ったら、はてなブックマークにそれは違うという指摘がありました。OpenSeadragonというオープンソースの仕組みで、1024×1024pxの画像をたくさん並べて描画しているそうです。Googleマップみたいに、すっごい滑らかに拡大縮小スクロールできます。
グーグル「NotebookLM」が進化、「Deep Research」でソース集めが強力に–Wordにも対応〈CNET Japan(2025年11月14日)〉
こういう方向の進化はどうなんだろう……ゴミを拾ってくる可能性もあるから「信頼できる情報ソース」を判断できる人じゃないと使いこなすのは難しいかも。未管理著作物裁定制度の解説でも触れましたが、Deep Researchを使って旧制度と新制度の違いを調査したら、新旧制度がごちゃ混ぜになってキメラみたいなレポートが出力されましたから。
お知らせ
文学フリマ東京41出店について
HON.jp Booksは11月23日(日)開催の文学フリマ東京41に出店します。東京ビッグサイト南3-4ホール|あ-15〜16です。出版創作イベント「NovelJam 2025」で誕生した作品や、ウェブメディア「HON.jp News Blog」の記事をまとめた本などを販売いたします。ぜひお立ち寄りください。
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
11月23日開催の文学フリマ東京41に、予定通り新刊をもう1点用意できました。ポッドキャストの書き起こし本『ぽっとら Podcast Transcription vol.1 ~ 詐欺広告や不快広告・金融検閲・生成AIと著作権・巨大IT依存問題など、激変する出版界の広範な論点を深掘りしてみた。』です。通称は短く。でもサブタイトルは内容が分かりやすいように、ちょっと(だいぶ?)長めにしてみました。約10万字で160ページ。2500円で販売します。あ、ウェブカタログに載せないと……(鷹野)