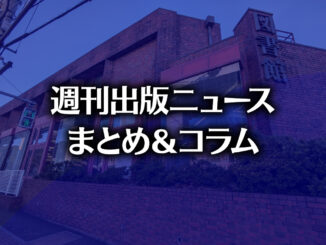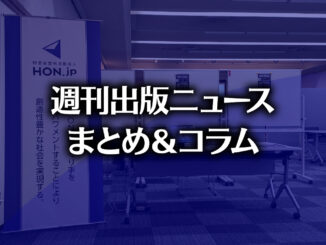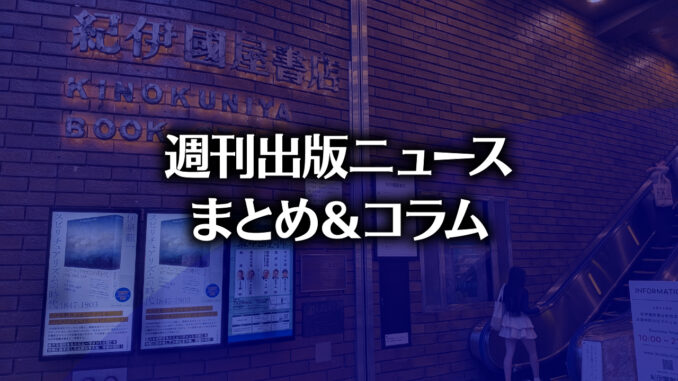
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2025年11月2日~8日は「Meta、詐欺広告で推定160億ドルの収益」「Getty対Stability AI訴訟で英裁判所は学習の是非を判断せず」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 「現代版トキワ荘」始動…若手クリエイター10人切磋琢磨、都が将来の起業に向け支援〈読売新聞(2025年11月3日)〉
- 生成AIと著作権の狭間で揺れる業界 集英社と漫画家協会の声明に見える「決定的なズレ」〈coki (公器)(2025年11月4日)〉
- 書店数激減のなか図書館蔵書数は20年で倍増。「書籍リユース」は出版業界を殺すか〈Forbes JAPAN(2025年11月6日)〉
- メタ、2024年売上高の1割が不正広告か ロイター報道〈日本経済新聞(2025年11月7日)〉
- 宇多田ヒカルさんの問題提起で、日本の「コタツ記事ロンダリング」問題は改善するか(徳力基彦) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年11月8日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
経産省、アニメ・エンタメ支援で「作品に口出ししない」など5原則を提案 国民の声や反省活かし新方針〈オタク総研(2025年11月3日)〉
作品の中身に口を出さない
作品の中身に影響を与えず、クリエイターの表現の自由を保障する
確かに、事務局資料の5ページ目に書いてありました。まだ「指針(案)」の段階ではありますが、感心してしまいました。ほんとうにそれが実現できるのなら。でも「エロ表現や暴力表現は除外」みたいな話が出てくることも容易に想像できてしまうのですが、どこまで徹底できるでしょうか? 民間の賞でも「この賞はクリーンなものにしたい。こんな漫画は受賞させられない」と除外された事例が話題になっていました。
ゲッティ社、画像生成AI企業に敗訴 「学習」の是非は判断示されず〈朝日新聞(2025年11月4日)〉
イギリスの司法判断です。なぜ「学習」の是非を判断しなかったんだろう? と思ったら、学習行為をイギリスでは行っていなかったから、とのこと。証人尋問終了時点でGettyがその争点を取り下げたため、学習行為の是非は判断されなかったそうです。アメリカでも同じ顔ぶれでの訴訟が行われていますが、そちらはどうなるか。ちなみに日本と同様、イギリスの著作権法ではAI学習が合法(PDF)であることが明文化されています(ただし非営利目的に限る)。
読売新聞と毎日新聞、愛知県蒲郡市を提訴 著作権侵害で〈日本経済新聞(2025年11月6日)〉
愛知県蒲郡市は以前、日経の記事を無断共有していたことを日経に報じられていたのを思い出しました。今回の記事ではそのことには触れられていません。なぜだろう? それはさておき、デジタル化した新聞記事を社内で共有していたのがバレて事件化する問題は、たとえばつくばエクスプレス著作権侵害事件など、以前から何度も起きています。社内で共有する場合はちゃんと日本複製権センター(JRRC)と契約しましょう。
社会
「現代版トキワ荘」始動…若手クリエイター10人切磋琢磨、都が将来の起業に向け支援〈読売新聞(2025年11月3日)〉
こちらは、東京都のプロジェクトなのですね。把握できていませんでした。つい最近日経で、サイバーエージェントが「現代版トキワ荘」を始めたという記事があったのが記憶に残っていたので、「都が」の見出しに「なんぞ?」と脳が混乱しました。
調べてみたら、サイバーエージェントのほうは「MANGA APARTMENT VUY」という漫画編集者・林士平氏が関わっているプロジェクトでした。公式サイト内を調べてみても「トキワ荘」という単語が使われている箇所はなかったので、日経の記者が勝手にそう呼称していただけみたいですね。
さらに調べてみたら、東京都のほうは8月の時点で「第1期生 募集開始!」というお知らせが出ていました。漫画家支援育成事業では2006年からある「トキワ荘プロジェクト」が先駆者ですが、こちらの運営はNPO法人LEGIKA(旧NEWVERY)です。少し気になって調べてみたら、「トキワ荘」の商標は豊島区が持っています。ただし、「トキワ荘プロジェクト」の商標はLEGIKAが持っていて、区分が違います。
生成AIと著作権の狭間で揺れる業界 集英社と漫画家協会の声明に見える「決定的なズレ」〈coki (公器)(2025年11月4日)〉
事実誤認のあるコラムなので指摘しておきます。冒頭の囲みに書かれている著作権法第30条の4についての解釈が間違っています。「AIが漫画や映像を“読む”こと自体は問題にならない」とありますが、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的」とした学習や「著作権者の利益を不当に害することとなる」ような学習はアウトです。
このコラムでは集英社だけ単独声明になった理由を、あたかも「日本漫画家協会との対立がある」かのように推測しています。そう考えてしまうのは「AIの学習段階からアウトになり得る」という前提がないからでしょう。
ちなみに、10月28日に公開されたCODAの声明には、法第30条の4が適用されないケースだという主張が明記されています。以下の箇所です。私はこの、学習過程から違法になり得るのだという踏み込んだ主張を高く評価しています。
Sora 2のように特定の著作物が出力として再現・類似生成されている状況においては、学習過程での複製行為そのものが、著作権侵害に該当し得ると考えます。
ところが、日本漫画家協会と大手出版社17社の共同声明は、法第30条の4があることを飛ばして「学習に使う場合は許諾を」と主張しているように読めてしまいます。これは必ず「法第30条の4は?」と突っ込まれるよな……と感じていました。だったら集英社みたいに余計なことは言わず、怒りを明確に表現したほうが分かりやすい。
集英社だけ単独声明になった理由を菊池健氏はnoteのまとめで「より強い調子の内容にするために単独になった」と推測していましたが、私もその意見に賛成です。方針の対立などではないでしょう。まあ、真相はわかりませんが。
書店数激減のなか図書館蔵書数は20年で倍増。「書籍リユース」は出版業界を殺すか〈Forbes JAPAN(2025年11月6日)〉
えーっとねぇ……そういう対立を煽る前に、大場博幸氏(日本大学教授)の研究発表「公共図書館の所蔵・貸出と新刊書籍市場との関係(PDF)」や著書『日本の公立図書館の所蔵 価値・中立性・書籍市場との関係』あたりをしっかり参照してみたほうがいいですよ。2024年に行われた「書店・図書館等関係者における対話の場」がきわめて穏当なところへ着地したのは、この研究成果のおかげなのですから。
メタ、2024年売上高の1割が不正広告か ロイター報道〈日本経済新聞(2025年11月7日)〉
ロイターがMeta社の内部文書をすっぱ抜きました。ロイター報道の原文(英語)はこちら。2024年は推定160億ドル(約2兆4000億円)の売上が詐欺広告によるものと見られているそうです。1日150億件の詐欺広告がユーザーに表示されているとの報告も。さにあらん。
さらに、詐欺広告の売上に占める割合が大きいため、業績に影響が出ないよう「疑わしい広告主の審査を担当するチームは、Metaの総収益の0.15%を超える損失をもたらすような行動を取ることを許可されていなかった」そうです。邪悪過ぎる。
まあ、Metaが邪悪なのは前からわかっていたことですから、矛先を変えます。デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)はそういう邪悪な企業(Facebook Japan)を認証し続けているわけですが、そんな認証制度に意味はありますか? 金さえ払えばいい認証になっていませんか?
宇多田ヒカルさんの問題提起で、日本の「コタツ記事ロンダリング」問題は改善するか(徳力基彦) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年11月8日)〉
Yahoo!ニュースが、いわゆる「釣り見出し」に近い紛らわしい記事の多い媒体に対し「タイムラインでの掲出量を一定期間減らす措置」をとるというリリースを出したことを受けて、徳力基彦氏がコラムを書いています。まあ、ページビュー数が収益に比例するような状態のままでは、残念ながらニュースの生態系は変わらないでしょう。
だからこそ「読者から高く評価された記事を多数配信しているメディアの広告単価を上げるような広告モデルの改革」という提言がなされているのだと思うのですが、それはYahoo!ニュースがすでに2021年からやっている施策です。当時、「記事リアクションボタン」のクリック率データを支払い指標のひとつとして活用という報道がありました(これはすでに徳力氏に伝えてあります)。
この施策は「Yahoo!ニュース 個人(現:エキスパート)」が対象外なので、徳力氏が知らなかったとしても無理はありません。ただ、徳力氏と話す中で私も気づいたのですが、結局これは、ベースはページビュー数のまま「追加で上乗せ」する施策です。だから、徳力氏の言う「レイジベイティング」を抑制するほどの影響力は無いし、それを狙った施策でもないのかもしれません。
いまここで問題になっているメディアって、女性週刊誌系とかスポーツ紙系ですよね。はっきり言って、インターネット普及以前から釣り見出しが常態化していたような媒体です。その記事が、他の比較的真面目な媒体の記事と同じフォーマットで同じ場所に乗っているプラットフォームなわけですよ、Yahoo!ニュースって。
経済
PRと広告はどう違う?重要性が高まるPRの役割を解説〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2025年11月5日)〉
仰ってることは至極正しいのですが、広告業界が「広告の略称として【PR】をいつまでも使い続けている」のも現実なのですよね。まあはっきり言えば、すごーく小さい字で目立たない位置に【PR】って表記し続けているメディアやプラットフォームが悪いのですけど。
ちなみに「HON.jp News Blog」の記事広告は、titleタグに日本語で〈記事広告〉と明記する方針にしています。titleタグに「広告」表記がないと、第三者がSNSへシェアしたときに、ページを開くまで記事広告だとわからない状態になる可能性が高いですから。それって読者を欺く行為ですよね。2016年くらいからすでに「それってステマでは?」という議論があったのを覚えています。
また1つ、電子書籍販売サイトがサービス終了。購入済みの本に対するケアは一切なし【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2025年11月6日)〉
このニュースを受け、また「これだから電子書籍は信用できない」論が噴出しています。ただ、これってほんとうに「購入済みの本に対するケアは一切なし」なのか疑わしいのですよね。大和リビング公式のフォームから問い合わせてみたのですが、残念ながら本稿執筆時点ではまだ回答がありません。HeartOne BooKsのお知らせは、以下のような表現になっています。
有料でご購入いただいたポイントにつきましては、返金対応をいたします。
これは確かに、有料購入のポイント“だけ”が返金対象であるように読めます。しかし、大和リビング公式サイトに出ているPDFの説明には、以下のように書かれています。こちらの表現だと、有料ポイントで購入した“商品の代金”が返金されるように読めます。どっちだ?
有料のポイントご購入分について返金いたします。
・対象となる方:有料ポイントにて商品を購入されたユーザー様
もうちょっと踏み込むと「有料のポイント」というのがなにを指すのかが、どちらのお知らせも明確ではありません。というのは、ベースに「月額コース」があって、毎月自動加算されるポイントがあるからです。
自動加算されるとはいえ、ユーザーからすると毎月対価を払って取得しているポイントです。それが「“有料ポイント”ではないから対象外」とされるのは、私なら納得できない。この点も含め問い合わせ中です。
Amazon、KDP著者向けAI翻訳サービス「Kindle Translate」提供開始〈ITmedia NEWS(2025年11月7日)〉
いまのところ英語とスペイン語、英語とドイツ語のみで、日本語から他言語への翻訳は未対応です。KDPの新サービスは日本になかなか来ないのが通例ですが、これはどうなるかな?
技術
共同通信、生成AIで加工の「子ガメをくわえるタヌキ」の写真を配信取り消し…加盟社の指摘で判明〈読売新聞(2025年11月2日)〉
監視カメラの画質を向上するよう「ChatGPT」に指示した結果の出力とのこと。それを信じる限り、画像を提供した団体に悪意はなさそう。でも、タヌキの顔の向きが変わってしまったことには、できれば気づいて欲しいところです。
メディアの立場としては、今後は悪意ある写真提供者が出てくることも想定しなければならないでしょう。いやあ、怖い。編集者して背筋が寒くなります。これぞまさに「エディターシップ(編集能力)」の問題です。自分が撮った写真以外は、最低でも「生成AI画像チェッカー」などでメタデータにC2PAやSynthIDが含まれていないことを事前にチェックするフローが必要でしょう。
「見えない壁」を築くOpenAIのAIブラウザ「Atlas」:訴訟相手を避け、競合へ誘導する巧妙な迂回戦略の全貌〈XenoSpectrum(2025年11月5日)〉
これって、人間を装う挙動などについてはさておき、オーバーレイ型ペイウォールについては私が以前から言ってる「なんちゃってペイウォール」の実装ですよね。人間の見た目だけは文章が隠れているけど、HTMLソースには全文そのまま書かれているというパターン。他の“迂回戦略”はともかく、これについてはAIブラウザかどうかは関係ないです。HTMLソースは人間でも読めますから。読めちゃうような実装をしているほうが悪い。
お知らせ
文学フリマ東京41出店について
HON.jp Booksは11月23日(日)開催の文学フリマ東京41に出店します。東京ビッグサイト南3-4ホール|あ-15〜16です。出版創作イベント「NovelJam 2025」で誕生した作品や、ウェブメディア「HON.jp News Blog」の記事をまとめた本などを販売いたします。ぜひお立ち寄りください。
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
11月23日の文学フリマ東京41に向け、新刊を準備中です。年鑑『出版ニュースまとめ&コラム2020』はすでに完成し、物が届くのを待つのみ。ただしこれは本来、現時点だと2024年版まで出ていなきゃいけない計画でした。とほほ。早く追いつかねば。あと、ポッドキャストの書き起こし本『ぽっとら vol.1』を準備中です。原稿はもうある(公開もしている)のですが、あと1週間で編集が間に合うかな……。(鷹野)