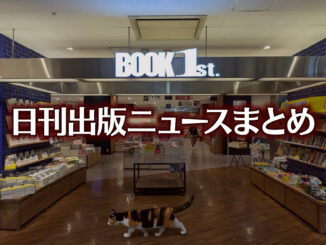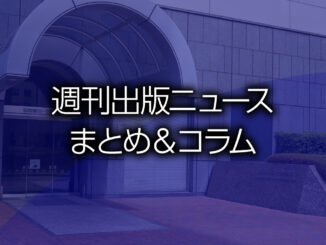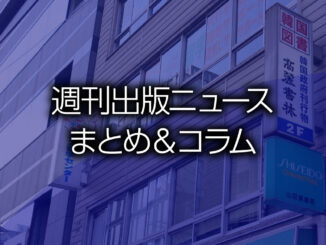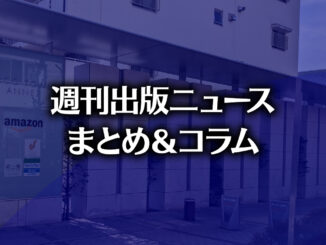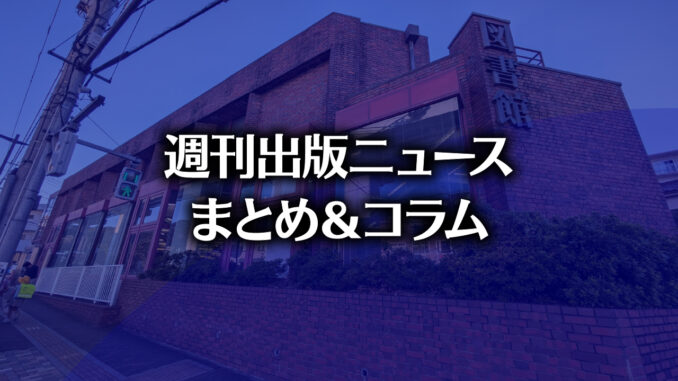
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2025年2月2日~8日は「講談社と読売新聞が書店振興共同提言」「国立国会図書館遠隔複写がPDF送信に対応(ただし要補償金)」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- (取材考記)文学フリマにヒント 出版界、理想描くことから 真田香菜子〈朝日新聞(2025年2月3日)〉
- 本の街・神保町 パネルディスカッションで課題と展望を共有 「街の品格は本屋があること」〈The Bunka News デジタル(2025年2月3日)〉
- 「縦読み漫画全盛」の戦国時代、漫画家たちは闘う。『モーニング』新人賞作家の場合〈Forbes JAPAN(2025年2月4日)〉
- 「高い金払って買ってるんだからこれやめろ」 大学の過去問集を解こうとしたら…… 目を疑う“とんでもないページ”が1090万表示〈ねとらぼ(2025年2月5日)〉
- 国立国会図書館、遠隔複写サービスがついにPDF対応 20日から〈ITmedia NEWS(2025年2月6日)〉
- 「は」の直後に「、」は必要か? 論文60本を分析、使い分けの基準を提示 筑波大と琉球大が発表:Innovative Tech〈ITmedia NEWS(2025年2月7日)〉
- ところで、そろそろSNSにも飽きてきてませんか?〈日経ビジネス電子版(2025年2月7日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
GoogleやCloudflareに要請して著作権侵害サイトへのアクセスを禁止するアメリカの新法案をDisneyやソニーが所属する業界団体が支援〈GIGAZINE(2025年2月4日)〉
これが成立すると、日本でも再び「海賊版サイトをブロッキングすべし」論が出てきそう。日本では2018年に「漫画村」問題を端緒として海賊版サイトのブロッキング法制化が有識者会議で議論され、猛反対により報告書がまとまらなかったという異例の事態で見送りとなっています。私も当時、反対していました。
アメリカではそれ以前の2011年に、SOPA(Stop Online Piracy Act)とPIPA(PROTECT IP Act)という2つの法案が討議され、日本と同じように猛反対により廃案になっています。順番的には「日本がアメリカと同じように」と言うべきかも。その結果、「米国の権利者たちは主に他国にブロッキングを導入させることに力を注いできた」経緯があるそうです。
ところが、いまアメリカで提案されている新法案FADPA(Foreign Anti-Digital Piracy Act)は、SOPA / PIPAのときには猛反対していた議員が、今回は「必要不可欠な代替案」と評価しているとのこと。なにがその差を生んだのか、ちょっと調べただけではわからず。まあ、まだ法案の段階なので成立するかどうかはわかりませんが、日本への波及も含め注目しておいたほうがよさそうです。
CDCサイトで主要な情報やデータ閲覧できず-HIVに関する資料も〈Bloomberg(2025年2月3日)〉
トランプ政権から知識を守れ、科学者は徹夜でデータの引っ越し急ぐ〈Bloomberg(2025年2月7日)〉
トランプ氏が署名したDEI(多様性・公平性・包括性)推進プログラムの廃止と、性別は男女二つだけという大統領令に基づき、連邦政府の人事管理局(OPM)が政府機関に「ジェンダー・イデオロギーを教え込んだり、促進したりするような対外メディアを全て削除する」よう求めた結果、疾病対策センター(CDC)で重要なデータが閲覧できなくなったりする影響が出ているそうです。現代の焚書だこれ。
[スキャナー]消える書店、出版界に打撃[読売新聞社・講談社提言]〈読売新聞(2025年2月7日)〉
書店振興のための共同提言〈講談社(2025年2月7日)〉
政府だけに向けた提言というわけではないのですが、政府がいま策定している「書店活性化プラン」に関連する内容が多いので「政治」カテゴリとしました。講談社と読売新聞社から共同提案されているのは以下の5項目です。
- キャッシュレス負担軽減
- ICタグで書店のDX化
- 書店と図書館の連携
- 新規書店が出やすい環境
- 絵本専門士など活用
現状、経産省からはすでにアクションプラン案(PDF)が出ており、ICタグ(RFID)関連の環境整備は進みそうです。キャッシュレス負担軽減は、決済事業者に対する補助が必要でしょうから、これもやるとしたら経産省でしょうか。現在のアクションプラン案にはありません。書店と図書館の連携は、いままさに文科省「図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議」で議論が行われています。
こういった動きに繋がった要因である2023年の書店議連提言(PDF)では他に、不公正な競争環境等の是正(公正取引委員会)とか、出版物への消費税・軽減税率の適用(財務省)などの要望もありましたが、今回のこの読売新聞社・講談社提言にはありません。まあ、新聞にはすでに軽減税率が適用されてますからね。やぶへびになるのを避けたのでしょうか。
社会
(取材考記)文学フリマにヒント 出版界、理想描くことから 真田香菜子〈朝日新聞(2025年2月3日)〉
文フリ(とくに東京)が大きくなって盛り上がっているのは確かですが、そういう年に何回もない「ハレの日」に大勢集まってお祭りみたいに売買している状況と、特別なことがない「ケの日」も常時展示で粛々と売り続ける必要がある状況とでは、単純比較はできないし、“業界”が参考にするのも難しいのでは。
本の街・神保町 パネルディスカッションで課題と展望を共有 「街の品格は本屋があること」〈The Bunka News デジタル(2025年2月3日)〉
ちょっと言葉尻に噛みついてしまいますが、その「街の品格」って都心在住者だけの感覚では? と思いました。平成の市町村合併でやたらと広くなった自治体もあるわけで、「街」というのがどれくらいの範囲までを示すものなのか? という疑問もあります。ちなみに発言者は林真理子氏です。
たとえば、私の実家がある自治体にはまだ書店が残っていて、市の中心街からは近いのですが、実家からは4キロメートルほどあります。歩くと1時間。自動車でも10分かかります。「同じ市」ではあるけど、「同じ街」という感覚にはならない距離なんですよね。
「縦読み漫画全盛」の戦国時代、漫画家たちは闘う。『モーニング』新人賞作家の場合〈Forbes JAPAN(2025年2月4日)〉
本題に入る手前の、編集部による前説部分でいろいろ引っかかってしまいました。まずタイトルにもある「全盛」という言葉。それって「一番盛んな時期にあること」という意味ですから。いまが「全盛」なら、今後は下がっちゃうの? と思えてしまいます。
韓国から始まったスマートフォンでの縦スクロール・フルカラー漫画のウェブコミック「webtoon(ウェブトゥーン)」の勢いは、国家からの支援も受ける一大産業に成長し、ナンバーナイン社が手掛けるオリジナルWEBTOON(略)
あと、ここに書かれた「国家からの支援も受ける一大産業」について。記事全体もこの段落も、基本的には日本国内の話をしているはずですが、縦スクマンガは日本政府からの支援を受けているのでしょうか? 縦スクに限らずコミック全体という話であれば「クールジャパン」系の話かなと思えますが、縦スクだけ支援してるなんて話は聞いたことがありません。
「高い金払って買ってるんだからこれやめろ」 大学の過去問集を解こうとしたら…… 目を疑う“とんでもないページ”が1090万表示〈ねとらぼ(2025年2月5日)〉
入試問題のような事前に情報が漏れては困るケースには、著作権者に無断で利用できる例外規定があります(著作権法第36条)。無断で利用はできるけど、あとから補償金を支払う形です。しかし、その問題を「過去問集」へ掲載する場合にはその例外規定が適用できないため、掲載する前に著作権者の利用許諾が必要となります。ところが、連絡がつかない・拒絶されたなどの理由で、掲載できないことが起こり得ます。そういう過去問集を買った人には気の毒ですが、これはいかんともしがたい。
国立国会図書館、遠隔複写サービスがついにPDF対応 20日から〈ITmedia NEWS(2025年2月6日)〉
遠隔複写サービスの複写物がPDFファイルで入手できるようになります(令和7年2月20日予定)〈国立国会図書館―National Diet Library(2025年2月6日)〉
紆余曲折ありましたが、ひとまずようやく、国立国会図書館で開始されます。SNSの反響を見ていたら、地方在住の方や英語話者も喜んでいる様子が観測できました。「個人送信」と同じく日本国内在住者だけが対象だと思い込んでいたのですが、これは日本国外に在住している方でも利用できるんですね。それはけっこうニーズがありそうだ。
ところがどうも、補償金が別途かかることに気づいてない(見落としている?)方が多いように見えます。国立国会図書館の案内は、補償金の額はSARLIBの規程を参照とだけ書いてあるので無理もないのですが、ITmedia NEWSの記事はちゃんと補償金の額を明記しているのに、それでもなお複写料金だけを参照して「安い!」なんて反応もありました。
SARLIBの補償金規程では、1ページあたり最低で500円かかるんですよね。公衆送信だけが対象の制度なので、紙で送ってもらって自分でスキャンすれば補償金はかかりません。補償金額の高さに気づいたら怨嗟の声に変わるんじゃなかろうか。ちょっと心配。
「は」の直後に「、」は必要か? 論文60本を分析、使い分けの基準を提示 筑波大と琉球大が発表:Innovative Tech〈ITmedia NEWS(2025年2月7日)〉
専門日本語教育学会誌掲載の「人文系論文における係助詞『は』直後の読点使用の傾向と指導指針」という論文です。目を通してまず「読点の必要性って確率で決めていいものか?」と疑問を感じました。そしてその確率を判断するのに、60本の分析じゃ少なすぎるのでは。
あと、例文がなぜ「この先生きのこる」なのか。「は」の後ろに読点を打つべきか否かを論じるなら、例文も「は」を使うべきでしょう。「ここではきものをぬいでください」とか。このような、着物なのか履物なのか区別できないような場合は、漢字にするか読点を1つ入れることにより、誤読を防げます。
つまり読点は、必然性がある箇所と、あってもなくてもいい箇所、さらには、入れるべきではない箇所もあります。それを単に確率で要否判断することには強い抵抗感があります。そんなの個々の文章に依って異なるでしょ。
係り受けが遠くてわかりづらい問題は、読点の有無云々より、句点で区切って一文を短くするよう指導したほうが良いように思います。学生のレポートを見てると、延々と読点で区切って文が終わらないケースがわりと頻出するんですよね。まあ、人に依りますが。
ところで、そろそろSNSにも飽きてきてませんか?〈日経ビジネス電子版(2025年2月7日)〉
不特定多数に対する拡声器としての利用ではなく、本来の意味での社会的な繋がり(ソーシャル・ネットワーキング)を持つ手段としては、私はまだ飽きていません。もしそれに「飽きる」としたら、人間関係が嫌になったなど、ちょっとベクトルが違った意味合いになりそう。恐らくここでは、前者の「拡声器」的利用への飽きが論じられていると思います。
そういう意味で言うと、以前、確か堀正岳氏が「アテンションで稼げる仕組みを普及させてしまったGoogle AdSenseの罪深さ」みたいなことをおっしゃっていたのを思い出しました。ただ、たとえばDeNA「Welq」とか「NAVERまとめ」みたいな事例にあるように、以前は広告プラットフォームを利用する側の問題が大きかったように私は思うのです。
広告プラットフォームを提供する側のGoogleは、ある時期まではそれなりに抑制的でした。しかし、Googleが「自動広告」の自動適用を始めたことが、いまのウェブ空間の惨状を招く分岐点だったように思います。Googleから届いた過去メールをあらためて確認してみたら、自動広告の初出は2018年3月でした。当初は「自動広告を試す」を自分でオンにしないと有効になりませんでした。
ところが、2020年4月に「広告設定が自動的に最適化されます」という連絡が届きました。それはつまり、それまでとは逆に、わざわざ自分で無効にする操作をしないと、自動的に自動広告が表示されるように仕様が変わったのです。私はこの時点で即座に無効化したのですが、非常に嫌な予感がしたのを覚えています。そして残念ながら、その予感は正しかったのです。
その後しばらくして、ページ分割された記事の「次へ」を押すと全画面広告が表示されるなど、記事を読んでいてイライラするサイトが激増しました。これは、一般的にはメディア側の問題と捉えられていると思いますが、Googleが自動広告を自動適用したことのほうが要因としては大きいように思います。武器商人が、とんでもない武器を提供しやがった、みたいな。
Google AdSenseについては他にもいくつか「こりゃダメだ」と感じることがあり、HON.jp News Blogでは2020年10月時点で完全オフに切り替えました。もうそれから4年以上経ったのですね。
経済
BookCellar出版社利用の有料化について〈BookCellar事務局(2025年2月3日)〉
あれま。うーん……まあ、うちはこれまで書店向けに本格的な販促活動は行っていないのもあり、BookCellar経由での書店からのオーダーは1回もなかったのですよね。ランディングページには載せてますが、気づかれていないのかも。でも、無料でランニングコストがかからないから、利用させてもらってました。
そういう状態だから、仮にいちばん安いエントリープラン月額3300円に切り替えたとしても、確実に赤字垂れ流し状態になってしまいます。正直、ユーザー向けの販促が優先で、まだ書店向けは優先度が低い。残念ながら退会せざるを得ません。まあ、経営的にはサービスの存続が第一ですからね。いままでお世話になりました。
第4回 書店人の覚書帳〈草彅主税(2025年2月6日)〉
中ほどからの「特約店制度」に対する問題意識が重要だと感じました。ジェームズ・ドーント氏がバーンズ&ノーブルのCEOに就任してすぐのころ、大原ケイ氏に解説記事を書いていただいたことがあります。最近あまり触れられなくなりましたが、当時は「コアップ」と呼ばれる宣伝費を廃止した、というのがポイントに挙げられていました。草彅氏のおっしゃる「特約店制度&報奨金を止める」話は、バーンズ&ノーブルが本部一括仕入れを止めたことと「コアップ」を廃止したこととの両輪という気がします。
技術
全米作家協会が「この小説は人間が書きました」マークを導入へ〈ギズモード・ジャパン(2025年2月4日)〉
うーん……これは評価が難しい。Authors Guildのリリースを読む限り、あくまで作家自身の自己申告に基づく認証みたいなんですよね。つまりそれは「人間が書きました」マークが付いていたとしても、AIを使っていない証明にはならないことを意味します。悲しいけど「人間は嘘を付く」ので。性善説のシステムは、成り立ちづらいように思います。
更新されたGoogle検索品質ガイドラインではAI生成コンテンツはどう評価されているのか?〈海外SEO情報ブログ(2025年2月5日)〉
おおむね想定通りですが、プレスリリースをAIに要約させただけみたいな記事は、低品質または最低品質として評価されることになりそうです。正直、プレスリリースをAIが要約した記事だとあらかじめわかっているなら、私は読まないです。それなら元のプレスリリースを読んだほうが良い。
たとえば、そのリリースに至る背景にはなにがあるのか、競合他社との関係ではどういう意味を持つのか、今後どのような影響が考えられるか、そう考える根拠はなにか……そういう附帯情報は、プロンプトを工夫すれば出力できるんでしょうか? そこまで手をかけてないケースのほうがまだ多そう。
Meta trained their AI on Pirate Shadow Libraries(メタは海賊版シャドウライブラリでAIをトレーニングしていた)〈Good e-Reader(2025年2月7日)〉
以前からそういう話はありましたが、新証拠(メール)が出てきたとのこと。社内弁護士が、著作権保護された作品をライセンスする努力を止め、代わりに海賊版を利用するよう助言したという記述があって、力一杯吹きました。海賊版を利用してもフェアユースで通るという見込みだったのでしょうか?
お知らせ
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
日本海側はとんでもない大雪のようです。お気を付けください。愛知の実家でも積雪があったと連絡がありました。若狭湾とのあいだにある伊吹山がそんなに高くないから、わりと越えて来るんですよね。そんなに頻繁ではないけど、意外と降るんです。(鷹野)