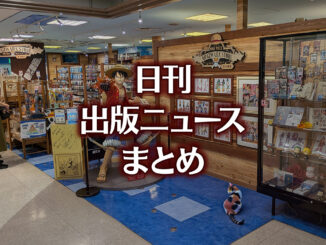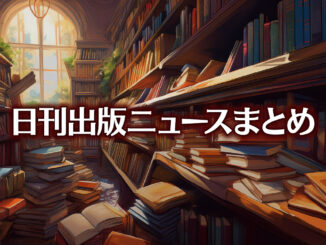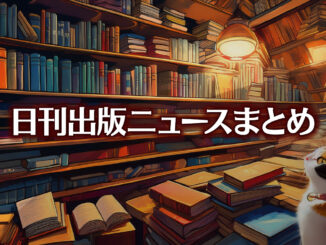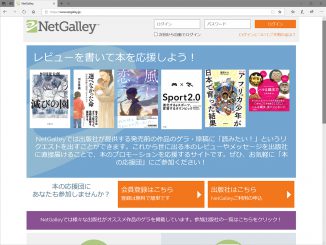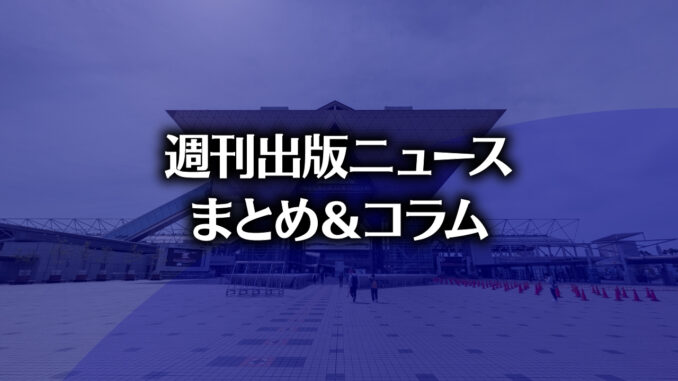
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年8月31日~9月6日は「Anthropic訴訟の和解案が判明、2200億円の支払い」「正確性を保証しないヤフーのSNSバズまとめ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- GoogleにChrome売却求めず 米連邦地裁、データ外部提供で独占是正〈日本経済新聞(2025年9月3日)〉
- 日米で裁判ラッシュ、生成AIと「著作権」めぐる攻防広がる…福井健策弁護士が「視点」解説〈弁護士ドットコム(2025年9月4日)〉
- EUで2025年末から段階的に施行されるEUDRという規制が世界中の書籍業界にとってかなりの問題になりそうだという話〈Togetter(2025年9月4日)〉
- デジタル教科書を正式な教科書に…中教審素案、使用学年など指針作成へ〈読売新聞(2025年9月5日)〉
- 米アンソロピック、作家らに2200億円支払い AI著作権訴訟で和解〈日本経済新聞(2025年9月6日)〉
- 社会
- ネット閲覧やSNS投稿で「著作権意識せず」6割超、関心低いこと浮き彫りに…文化庁調査〈読売新聞(2025年8月31日)〉
- 講義を記録しない学生は1割、本・新聞など読まない学生は2割…いずれも国語問題の正答率低く〈読売新聞(2025年9月1日)〉
- 「スタートアップより高い存続率」 非営利メディア最大のカンファレンスから学ぶ「報道の生き残り方」 現地ルポ前篇〈SlowNews | スローニュース(2025年9月2日)〉
- 「差別的表現を助長」と書籍紹介を削除 「書店にはさまざまな意見が並ぶべき」と批判も〈産経ニュース(2025年9月2日)〉
- 首相「辞める」明言、読売「退陣」報道を検証…石破氏が翻意の可能性〈読売新聞(2025年9月3日)〉
- 若手が生成AI任せで仕事して、レビュー地獄で逆に生産性が落ちた話〈片山良平@paiza代表(2025年9月4日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
ご支援のお願い
チームで行う創作と出版のワークショップ「NovelJam 2025」東京・札幌・沖縄の三拠点同時開催に向けクラウドファンディングを実施中! ゼロから作品を生み出すクリエイターの発掘育成活動をぜひご支援ください。
政治
GoogleにChrome売却求めず 米連邦地裁、データ外部提供で独占是正〈日本経済新聞(2025年9月3日)〉
これで、Chromeブラウザが不便になることは回避されそう? ただ、Googleは独占禁止法違反という判断そのものに反発して控訴する方針を示しているので、決着にはまだ時間がかかりそうです。もっとも、ChatGPTの登場以来、AIで調べ物をする行動もだんだん一般化していて、司法省の「Googleが検索市場を独占している」という主張が実態とは離れ始めているのも事実です。そういう意味で、データの独占を認めない方向性の司法判断は、なかなか「やるな」という感じがします。
日米で裁判ラッシュ、生成AIと「著作権」めぐる攻防広がる…福井健策弁護士が「視点」解説〈弁護士ドットコム(2025年9月4日)〉
栗原潔氏の解説と同様、やはり争点に軽微利用(著作権法第47条の5)がありません。訴えた新聞社は、「軽微利用の範疇を超えている」という点は争点にしなかった? 私はそここそが勝負所だと思っていたんですけどね。まあ、恐らくPerplexityが反論の材料として使ってくるとは思いますが、「ぜんぜん軽微じゃないよね?」と蹴散らされると予想しておきます。
EUで2025年末から段階的に施行されるEUDRという規制が世界中の書籍業界にとってかなりの問題になりそうだという話〈Togetter(2025年9月4日)〉
EUDRって知りませんでした。農林水産省によると、印刷用紙を含む特定品目の生産において「森林減少を引き起こしていないことの確認(森林デューデリジェンス)等を義務化する規則」とのこと。つまり、紙の本をEUへ輸出する場合に引っかかってくる規制ということになるでしょう。古紙100%なら対象外になるようです。
しかし欧米の出版社って、自国言語の書籍でも中国のメーカーで製造して輸入しているケースがけっこう多かったはず。規制対象は原材料のパルプなので、書籍そのものの生産地はそれほど問題にはならないかもしれませんが。ただ、いままでは安く製造できていたのが、仕入れ先の変更で製造原価の高騰に繋がる可能性はありそう。サプライチェーンに大変動が起きるかも。
それにしても、EUはこういう「ルールを変える政策」が好きですねぇ。それで自爆してるケースもわりとあるような気がしますが。
デジタル教科書を正式な教科書に…中教審素案、使用学年など指針作成へ〈読売新聞(2025年9月5日)〉
やっと。とはいえ、紙、デジタル、ハイブリッドの3種類から各地域の教育委員会などが「選択」するわけですから、いきなりすべてが置き換わるという話ではありません。たぶん、非常にゆっくりとしたペースでしかデジタルへの移行は進まないでしょう。教育分野は保守的ですから。それにしても読売新聞は、相変わらず批判的な論調ですね。メリットは無視し、デメリットしか見ていない感じ。
米アンソロピック、作家らに2200億円支払い AI著作権訴訟で和解〈日本経済新聞(2025年9月6日)〉
予定通り、和解案が明らかになりました。弁護士が「著作権訴訟の支払額で史上最高額」と自慢しているそうです。AAPも誇らしげな声明を公表しています。あとはこれを裁判所が承認するかどうか。支払額は巨額ですが、仮にこのまま訴訟を続けてAnthropicの著作権法違反が認められた場合「制裁金は数十億ドルから最大で1兆ドル(約147兆円)超に達する可能性」とも言われていたので、これでもかなり抑制されたと評価できるでしょう。
とはいえ、この支払額に耐えられる企業も、ごく僅かだと思います。Anthropicは1.9兆円を調達したばかりですが、いきなり和解金で1割強をもっていかれることになったわけです。同じようなことをやっていたAIスタートアップはいまごろ戦々恐々でしょう。大手でも、Metaは海賊版データを使っていたことがバレてますから、同じような賠償を迫られることになります。Appleもさっそく訴えられたというニュースが。
あと、AnthropicはLibGenやTorrentなどからダウンロードした海賊版データを破棄することになるそうです。このデータはAnthropicの社内サーバー(中央ライブラリ:Central Libraryと呼ばれている)に保管されていて「学習目的以外にも使う」ことが企図されていたとのこと。それってつまり、検索拡張生成(RAG:Retrieval-Augmented Generation)に使っていたのでしょうか?
だとすると、私がポッドキャスト「#29 生成AIは新刊の要約を出力できるか?(2025年4月29日版)」で挙げた「考えられるパターン」の5番目「Claudeは権利者に無断で、新刊の全文データが参照できる状態にしている」がおおむね正解だったことに。これはまずあり得ないと思っていたんですが。ただ、もし4月のポッドキャスト収録時点で「中央ライブラリ」の存在を知っていたら、この可能性が高いという判断をしていたかも。
言い訳をすると、この「中央ライブラリ」の存在は、訴訟になるまで公表されていませんでした。報道されるようになったのは、6月の判決以降だったはずです。4月時点では、さすがにそこまでやっているとは思いませんでした。想像が及んでいなかった。申し訳ありません。そのうえ、正規版を買ってAIのために使うのはフェアユースだと認定されちゃってますし。この#29はちょうど「ぽっとら」で次に公開する予定の回なのですが、追記が必要ですね。とほほ。
社会
ネット閲覧やSNS投稿で「著作権意識せず」6割超、関心低いこと浮き彫りに…文化庁調査〈読売新聞(2025年8月31日)〉
この「文化に関する世論調査」って、令和に入ってからは毎年やってる調査なんですね。知らなかった。記事では言及されていませんが、30代以下では「SNS等に投稿する際は、著作権を侵害していないか注意しながら発信を行っている」が高くなっているそうです。若い世代のほうが「情報」の授業などでITリテラシー教育をしっかり受けてますもんね。
講義を記録しない学生は1割、本・新聞など読まない学生は2割…いずれも国語問題の正答率低く〈読売新聞(2025年9月1日)〉
東京大学のリリースはこちら。若いころよく「メモをとれ」と指導されたのを思い出しました。恐らく「読む」「聞く」といった受け身の情報摂取だけでなく、「書く」というアウトプットを行うことが「反復学習」になっているのでしょう。いちど聞いただけで忘れないような記憶力の持ち主なら話は別なんでしょうけど、ふつうの人はメモをとったほうがいいです。記憶はアテにならない。記録に残しましょう。
「スタートアップより高い存続率」 非営利メディア最大のカンファレンスから学ぶ「報道の生き残り方」 現地ルポ前篇〈SlowNews | スローニュース(2025年9月2日)〉
チャリティマネーがジャーナリズムに流入 米非営利メディアの最前線レポート<後編>〈SlowNews | スローニュース(2025年9月3日)〉
うちも非営利メディアなので興味津々です。そもそも非営利メディアに特化したカンファレンスで480人も集められるのがすごい。そして、非営利のメディアでも事業が成り立つくらい寄付文化が根付いていることがうらやましい。
「差別的表現を助長」と書籍紹介を削除 「書店にはさまざまな意見が並ぶべき」と批判も〈産経ニュース(2025年9月2日)〉
大型書店は「言論のアリーナ(by 福嶋聡氏)」ですから、並べて売るところまでは構わないと思うのですよ。図書館で書架に並べるのも同様です。しかし、単に書棚や書架へ並べていることと、公式アカウントがPOPやSNSでその本を紹介・推薦する行為とのあいだには、大きな違いがあるはずです。でも、そこを混同した意見がけっこう散見されるんですよね。
特定の本だけを推したら、それは「肩入れしている」とみなされますよ。思想的に反対側の陣営から批判されるのは当然のことです。逆に、信念を持って肩入れしたなら、ちょっと批判を受けたくらいで投稿を削除するようなヤワな真似をしちゃ、それもやっぱりダメでしょ。弱すぎる。批判される覚悟もなかったのか、と。
首相「辞める」明言、読売「退陣」報道を検証…石破氏が翻意の可能性〈読売新聞(2025年9月3日)〉
本文には「結果として誤報となったことを読者の皆様に深くおわびします」とあるのですが、このタイトルからは誤報の謝罪だと読み取れません。また、本文に書かれていることも「周囲に明言した」「周辺に明かしていた」「周辺に伝えていた」「周辺に語った」「周囲に語り」と、読売新聞記者が石破氏本人から直接辞意を聞いた様子がありません。さらに、ほぼ同時に出ているもう一本の記事では「石破氏が虚偽説明」と断定しています。その「周囲」だか「周辺」とやらが嘘を付いている可能性は考えないのでしょうか。だいぶひどくないですかこれ。だんまりの毎日新聞よりマシかもしれませんが。
若手が生成AI任せで仕事して、レビュー地獄で逆に生産性が落ちた話〈片山良平@paiza代表(2025年9月4日)〉
これはコードレビューに限った話ではないのでピックアップしました。単に「ベテランの生産性が落ちる」という問題でもないでしょう。より深刻なのは、生成AI任せにすると「若手が育成できない」ことだと思います。いままでなら「若手を育成するため、ベテランの生産性は多少犠牲になる」というのが、むしろ健全な在り方だったはず。でも論点がそういうベクトルになっていないあたりに根の深い問題がありそうです。仮にきっちりレビューして戻したところで、若手がそれを理解できるか? という問題もあるのでしょうけど。あるいは、もう少しAIのレベルが上がれば「AIが教育係」になる……のかなあ? まあ、人間の教育係も間違えることがあるから、それはAIじゃなくても同じことか。
経済
‘Existential crisis’: how Google’s shift to AI has upended the online news model | Newspapers & magazines(「存在の危機」:グーグルのAIへの移行がオンラインニュースモデルをいかに覆したか)〈The Guardian(2025年9月6日)〉
何度でも指摘します。この記事で事例として挙げられているDaily Mailは、Googleから「サイトの評判の不正使用(Site reputation abuse)」(=通称「寄生サイト」)でペナルティを食らったはずのメディアです。改めて調べて、AI Overviewsが開始された2024年5月15日より前の記事でペナルティを食らったメディアとして名前が挙がっているのを見つけました。
それなのに、Daily Mailのオーナーは“AI Overviews have fuelled a drop in click-through traffic to its sites by as much as 89%(AI Overviewsのせいで自社サイトへのクリックスルートラフィックが89%も減少した)”などと主張しているわけです。いやそれ、大半はペナルティのせいですよね?
技術
EPUBリーダー表示テスト正解集 次世代パブリッシング研究会(著) – ポット出版プラス〈版元ドットコム(2025年9月1日)〉
次世代パブリッシング研究会が、EPUBのサイドロードができない(あるいはサイドロードと販売時の表示が異なる)電子書店のビューアを検証するため、表示テスト用のEPUBを実際に電子取次経由で売ってみるテストを行っています。こちらは正しい(意図している)表示はこうですという「正解集」なので固定レイアウトです。青い表紙がリフロー型の検証用。もちろん両方買いましたヨ。
ペイウォールをJavaScriptで実装する構成の注意点をGoogleがドキュメントに追加〈海外SEO情報ブログ(2025年9月1日)〉
私がよく「なんちゃってペイウォール」と呼んでいる実装について、Googleが注意喚起しています。人間の見た目では隠れているけど、HTMLソースでは丸見えだったりするんですよね。だから、そういう実装をしているメディアによる「AIボットがペイウォールの向こう側を読み取っている」などという主張は、実は成り立たないという。だってHTMLソースを開けば人間でも読めちゃうじゃん。
Xのバズ+生成AI=全自動ニュースサイト? ヤフー「SNSのバズまとめ」開始 ただ「正確性は保証しない」〈ITmedia AI+(2025年9月2日)〉
いやあ……さすがにこれは「正確性は保証しない」と言っておけば免責されるような次元を幾重にも飛び越しちゃってませんか。ひどい。ひどすぎる。記事内容とまったく異なるサムネイルが設定されているあたり、技術的にも致命的な問題があるとしか思えません。
あと、SNSへの無断転載を第三者的に二次利用することで、あたかも著作権の問題がないかのように振る舞う「著作権ロンダリング」ができちゃうのも問題です。「NAVERまとめ」などのキュレーションサイト問題を思い出します。まあ、その仕組みを提供していた会社(LINEのほう)だったりするわけですが。悪影響しか思いつかない……頼むからやめて欲しい。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
今年からとある賞の審査委員を拝命し、大量の資料に埋もれています(データですが)。公式サイトには実行委員長しか名前が出ていないので、恐らく私の名前が公開されることはなさそうです。JEPA電子出版アワードは選考委員で、候補を挙げて理由を説明するだけだったので、気はラクでした。しかし、こちらの賞はけっこう細かく審査基準が定められていて、責任の重さと緊張感があります。私でいいのかな? と思いつつ。(鷹野)