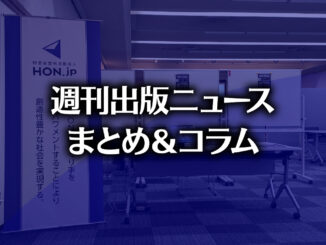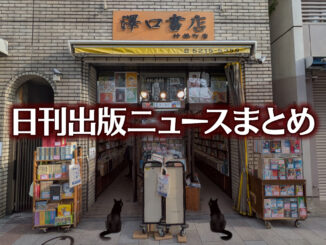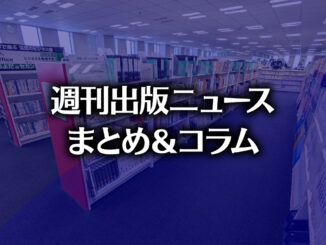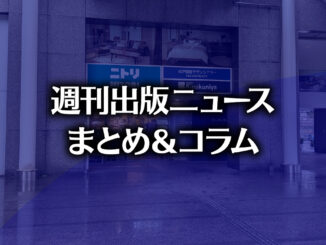《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
新コーナー「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。5年ぶりの再開である第18回では、なぜ更新を止めてしまったのか? なぜいま再開したのか? などの“言い訳”から、今後どういう方針でやっていくかなどについて語っています。
【目次】
#18 リスタート
HON.jpの鷹野です。ポッドキャストでは大変ご無沙汰しております。
実は、ブック・コーディネーターの内沼晋太郎さんが最近、「本の惑星」というポッドキャストを始められました。それを聞いて、大いに刺激を受けました。そこで、5年ぶりに再開してみることにした、というわけです。
以前は2020年の1月から4月までの4カ月間、17回で一旦終了していますので、このリスタートで通算18回目ということになります。2020年といえば、コロナ禍が始まった年です。といっても、ポッドキャストを始めたときは、日本ではまだ流行してない時期でした。
2月にクルーズ船で集団感染が発生して、あっという間に日本でも広がり始めて、政府から臨時休校の要請が出て、緊急事態宣言が出て……という、とんでもないタイミングでポッドキャストをやってたんですね。
そういう大きな変動があったんで、ウェブメディア「HON.jp News Blog」の運営体制を見直しましょうと。どこにリソースを分配すべきかというようなことを検討した結果、反響の見えづらいポッドキャストは止めましょう、ということになったわけです。
あのときは「三密」を避けましょうなんて言われていたから、定期的に開催していたリアルイベントができなくなってしまうっていう問題のほうが大きかったんです。結局、ポッドキャストみたいな「声」だけでなく、「映像」もある番組に集約しましょう、という判断でした。両方やるのはちょっと厳しかったですね。
それで、ZoomとYouTubeを使って、毎週ゲストを招く、ライブの映像番組をやりました。「笑っていいとも」のテレフォンショッキング方式……って、そろそろ通じない人も多くなってきてますかね? タモリさんがホスト役で、ゲストが次のゲストを紹介する方式で繋いでいくというやり方です。「笑っていいとも」は、いま話題のフジテレビ系列で2014年まで30年以上やっていた番組です。
平日のお昼に毎日生放送で、キャッチフレーズが「友だちの友だちはみんな友だち、世界に広げよう友だちの輪!」という(番組)ですね。もう終わってから10年以上経つんですね! いやー、もう懐かしい感じがします。で、そのゲストが次のゲストを紹介するという方式なら、次のゲスト誰にしよう? と考えなくても済む、という、いま思えばけっこう安直な考えでその方式を導入したんですね。
まあ、確かに最初のころは知ってる人が中心だったから、わりとラクができました。けど、「初めまして」のゲストが増えてきてから「実はこれってかなり大変だぞ?」と気づいたんです。タモリさんすごいな、と。
基本は1週間の(出版)ニュースを振り返る番組だったんですけど、もちろんゲストをほったらかしにはできませんから、あらかじめゲストのことを知っておく必要があるわけですね。著書がある、本を書いてる方なら。その本を読んでおく必要もあります。
それを1週間のインターバルでやる、となると、意外と大変なんですね。というのもあって、1年くらい続けたところで、毎週やるのはやめました。映像番組の方です。最初は四半期に1回くらい振り返る形にしましょう、と。最近は年に1回、年末にその年を振り返る、という形で細々と続けている感じになっています。
「なぜポッドキャストなのか?」を真剣に考えていなかった
まあ、ポッドキャストにせよ、ZoomやYouTubeの映像番組にせよ、ウェブメディア「HON.jp News Blog」での、文章での記事配信とは違う手段、違うメディアを使うことで、違う層に届けられるんじゃないだろうか、という狙いがあったのも確かなんです。
で、最初にお話した内沼晋太郎さんのポッドキャスト「本の惑星」を聞いて、「なぜポッドキャストなのか?」というところから最初始まるわけです。で、ここまで真剣に考えて考えて考えたうえで始めたのか、と。まあ、いたく感心させられました。
たとえば、インプレッションは「わかりやすい」に集まる。「わかりやすい」だけならYouTubeのほうがいいよね、と。でも、世の中わかりやすく説明できることばかりじゃないわけですよね。わからないままのこともたくさんある。そういうわからないままのことは、声だけのメディアのほうが向いてるんじゃないか、というようなことをおっしゃっていました。
なるほどなあ、と。そういうメディアの特性というところが、5年前の私にはよくわかってなかったんですね。というか、そこまで考えてなかったんですよ。当時、「これからポッドキャスト来るかもね」みたいなムーブメントを感じていて、まあ、やってみないとわからないし、いっぺんトライしてみるかあ! くらいの軽いノリでした。だから、練り込みも足らないし、メルマガに書いてることを原稿にして、そのまま読んでるのに近い状態になってしまったんです。
当時、やってて痛感したのが、音だけのメディアって、すごく不便なんですよ。高校生ぐらいの時にラジオとか聴いてたんで、なんとなく分かってるつもりでいたんですけど、全然分かってなかったんですね。音だけのメディアがどういうものなのか。
映像なら、1枚写真とか図とかを見せれば済んじゃう。それだけのことが、声だと伝わらないんです。説明が要るんですよ。その点、私はアドリブってすっごい苦手なんで、話すにはちゃんと台本を用意しておく必要があるんですね。今日も、ちゃんと台本用意してます。
ところが5年前は、メルマガに書いたことをそのまま原稿(台本)にしてました。「説明が要る」というのは、文章でももちろん同じことが言えますけど、声の番組をやってみて思ったのが、文章と声とでは、説明が必要なポイントがちょっと違うんですよ。
私は10年くらい毎週メルマガを書いてますけど、これには、いろんなメディアの記事がベースにあるわけなんですね。毎週たくさんのニュースがあって、その中から、私が「これはコメントしておきたい」と思った記事をピックアップしているわけです。
で、その記事のタイトルだけでそれなりに情報量があって、ある程度の説明になっている場合は、タイトルを読み上げるだけで充分かもしれません。でも往々にして、タイトルだけだとなにがなんだかわけわからんみたいな記事も、往々にしてあるわけです。往々にしてね。
あるいは、単に記事を紹介するんじゃなくて、記事の内容を前提として「私はこう思った」「これは良い」「これは違うと思う」「これは次にこうなるんじゃないか」みたいなことを書いているわけです。つまり、取り上げた記事を読者が読むこと、読んだことを期待して、読んだことを前提として、説明をわりと端折ってる部分もあるんです。
ところが声だけで伝えようと思うと、読んだことを前提にできないわけですよ。記事だとリンク1個クリックすれば開けるって行為が、声だとできない。説明が端折れないんです。タイトルだけじゃ足らないって場合に、ある程度説明を足す必要がある。となると、メルマガの原稿をそのまま台本には、できないわけです。まあ、いま思うとね。
声のニュアンスと、相方問題
逆に、文章と違って、声の場合、トーンとか、ハリとか、話す速さを変えたりとか、繰り返す、繰り返す、繰り返す、ということをしたりとか……間を取ったり……みたいなことによって「ここが重要なんだよ!」みたいなニュアンスを、伝えることもできるわけです。
文章だと太字にしたりとか、「かぎかっこ使ったり」とか、
段落を変えたり、
みたいなテクニックになるんでしょうけど。
あるいは、「えー」とか「あー」みたいな、いわゆる「フィラー」ってやつですね。文章なら削っちゃうやつです。でも、声だと、「あ、なんか言葉選んでるな」とか、「なんかちょっと考えまとめてるのかな?」みたいな、言ってみれば、私の人となりとか思考みたいなものも伝えられる、というか、意図しなくても伝わってしまうみたいなところもあるように思います。
あと、これは内沼晋太郎さんも言ってたんですが、相方ですね。パートナー。ひとりでずっと喋ってると、聞いてるほうも喋ってるほうも、だんだん辛くなってくると思うんです。5年前にポッドキャストやったときも、相方欲しいなーって思ってました。
それで、映像番組ではゲストを毎回呼ぶ形にしたんですけど、それはそれでね、さっきも言ったような、相手のことを知るために本を読んだりとか、あるいは、スケジュールを調整したりとか、そういう番組の外側で、やらなきゃいけないことってのがね、すごく多くなる。それも事実なんですね。
そこで! そこでです。今回から、AIナレーターのモリアキさんにお手伝いいただくことにしました。モリアキさん、自己紹介をお願いします。
はい、モリアキさん、ありがとうございます。というわけで、今後は取り上げるニュースの説明部分についてはモリアキさんにお願いして、解説とか感想とか、そういうコメント部分は、わたくし鷹野が担当する、という役割分担で行こうと思います。よろしくお願いいたします。
今後このポッドキャストで扱う内容は?
で、今後このポッドキャストで話す内容なんですが、まあ当然、HON.jpがやってるメディア事業の中でやることなんで、やっぱりHON.jpのビジョンである「本(HON)のつくり手をエンパワーメントする」、これが目的となります。主軸は「本のつくり手」なので、出版、それももちろん紙の出版だけでなく、電子出版も対象です。
書籍とか雑誌みたいなパッケージの流通販売から、ウェブメディアとかメルマガ・ニュースレターなんかも守備範囲です。情報流通の担い手には取次、書店、図書館といったプレイヤーが存在しますが、これらはリアルはもちろん、頭に「電子」が付く、電子取次、電子書店、電子図書館も対象です。
あと、情報流通の基盤、つまり、プラットフォームですね。これを提供している、Google、Amazon、Apple、Microsoft、日本だとLINEヤフーなんかも含まれるでしょう。そういうビッグテックですね。この動向からも目が離せません。
あるいは、そういった情報流通に大きな影響を及ぼす法律とか行政、裁判、つまり政治的な動きも、国内だけでなく海外の状況も知っておく必要があるでしょう。まず著作権法。改正の動きはもちろん、ソフトローのガイドライン制定とか、法解釈の変更とか。
国が主催する審議会とかワーキンググループでの議論や、従来とは違った判例なんかも重要な政治動向です。あるいは、表現の自由を脅かすような動きであったりとか。逆に、海賊版サイトみたいな明確な犯罪行為から、グレーゾーンギリギリを攻めた事例なんかも取り上げる必要があるでしょう。
もちろん、「情報」に関連するテクノロジーの動向もスコープに入ってきます。最近は生成AIがホットトピックスですが、少し前にはブロックチェーンとかNFTも大きな話題になりました。先端技術としてはARとかVR・XRなんかも関係してくるでしょう。電子ペーパーとかヘッドマウントディスプレイみたいなハードウェア方面にも気配りが必要だと思います。
あるいはセキュリティ関連であったりとか。あとは、いまこうやってお話しているような、視覚ではなく聴覚に情報を伝える表現。オーディオブックとかポッドキャスト、音声読み上げ、それに関連してくるアクセシビリティなんかもそうですね。隣接する分野で言うと、映像表現も無視はできないでしょう。
ま、要は紙も含めたメディアに関することすべて。というですね、わりと広い範囲が対象となります。私自身ですね、情報を追いかけるのがけっこう大変だったりしますが。記事のタイトルを見ただけで捨ててる情報のほうが圧倒的に多いのが現状です。
佐々木俊尚『キュレーションの時代』
いま私は毎日、日曜日を除く毎日、たくさん流れてくるニュースの中から、広い意味での出版に関連するものというのをメディアを問わずにキュレーションする、という活動をしています。キュレーションというのは要するに、X(旧Twitter)とかFacebookとかBluesky、Threads、MastodonみたいなSNSに、気になる記事を随時投稿する、ということです。
これは、ジャーナリストの佐々木俊尚さんが2011年に筑摩書房から出版した『キュレーションの時代』という本に刺激を受けて始めた活動です。これからはマスメディアだけじゃなくて、人の繋がりで情報を共有していく時代だ、といった趣旨の内容です。
もう14年前の本ということになるわけですけど。まだSNSがいまみたいな惨状になる前の、いろいろ希望に満ちた未来が想像されてたころに出た本だったりしますけど、まあそれは置いておいてですね。
キュレーション、情報を選んで、意味づけをして、共有する、という行為ですね。それを日曜以外の毎日やってます。随時やってます。土曜日とか祝日はニュースが少なくなるので、1日に10本くらいですね。記事10本くらい。平日だとで20本くらいになります。多い日だと40本超えたときもありますけど、まあだいたい1日20本前後かなという感じです。
でもその20本を選ぶ前には、タイトルだけ見て捨ててる記事が軽く100倍くらいあります。100倍です。プレスリリースだけで1日300件とか400件届きますから、まあ、大半は捨ててる感じですね。まさに「情報洪水」の時代というのを、日々、私自身が実感しているわけです。
で、その1日20本くらい取り上げたニュースの中から、週に1回、10本から15本くらいをピックアップしてコメントするというのがメルマガ「週刊出版ニュースまとめ&コラム」というわけです。政治・社会・経済・技術の4分野に分類して、コメントを付けて、というスタイルですね。
最初は、個人ブログで書いてました。2012年、『キュレーションの時代』を読んだあとからですね。2012年8月からずっと毎週、正月とかそういう大型連休を除いて、ずっと出し続けてます。いまこれを録音しているのが2月10日の月曜日なんですけど、今日配信したメルマガ「週刊出版ニュースまとめ&コラム」が通算652号です。メルマガはHON.jpになってからなんでもうちょっと数は少ないんですけど、個人ブログからの通算で652号ってことで、まあ、そこそこ長いことやってるコーナーです。
「情報洪水」時代の川上から川下まで
そこにどういうトピックスを取り上げるか? というのは、まあ最終的には私の感性、感覚なんですけど、分野、出版に関連する分野というところ以外で共通する点はなんだろう? ってのをちょっと考えてみたんですけど、キーワードとしては「変化」かなという感じですね。
個々のコンテンツの中身、本の内容とかそういうことよりも、世の中のさまざまな仕組みとかシステムといったところに興味があって、それがどう変わっているのか、あるいは、変わっていくのか。そういう観点で見ているということです。
本のつくり手がいま置かれている状況というのは、デジタル化、あるいはネットワーク化、さらには生成AIの出現もそうですけど、「情報洪水」と言われる時代である、というのがまずあるわけです。そういう状況の中で、なにを重視するか? というと、私自身が文章の書き手ということもありますけど、情報の流れとしてはいちばん上流にあたる、書き手、書き手がいかにして生き残っていくか、というところがまず、私の最大の関心事です。
そのためには、書き手としての価値をどうやったら高められるか、信頼される書き手になるにはどうすればいいのか、アウトプットの質を高めるにはどうすればいいか、情報収集や情報発信のありかたはどうあるべきか、あるいは、どう編集するか、どうデザインするか、どう見せるか、どうパッケージ化するか。で、それをどうやって流通に載せるか……ま、そんなような順番ですね。
単純化すると、まずは情報の流れのいちばん上流の書き手、そこが起点です。最終到達点は、読書、あ、読者ですね。書き手から読者に至るプロセスに、まあいろいろある、ということになりますね。単純化するとそういう感じです。
週に2つくらいのトピックスを深掘り
で、ポッドキャストの話に戻ります。このポッドキャストでなにを話すか。これは、まあ、やっぱり「週刊出版ニュースまとめ&コラム」がベースになります。なりますが、その週に1回、10本から15本くらいをピックアップしている中から、さらに厳選して、2つか3つを深掘りしていく、そんな感じでいこうかなというふうに考えてます。
「週刊出版ニュースまとめ&コラム」で書いてるのはニュース記事単位なんですけど、このポッドキャストではトピックス単位にしようかなと。まあ、深掘りなんで、速報ニュースではなく、スローなニュース解説、みたいな感じです。だから、その週の動きだけでなく、少し前から継続している事柄というのを、振り返る感じで取り上げるみたいな感じになるかなと思ってます。
基本、毎週、月曜日か火曜日に配信、という感じでしばらくいこうと思います。あ、あと、リスナーの方からの質問に答えるコーナーも、今後はやっていきたいなと思ってます。フォームを用意しましたので、気軽に質問をお寄せいただけたら幸いです。本に関する事だったら、何でもいいとは思ってます。取り上げるかどうかは、私の胸先三寸ですね。
というわけで再開一発目は、こんなところで締めくくります。パーソナリティーは、HON․jpの鷹野でした。また来週!