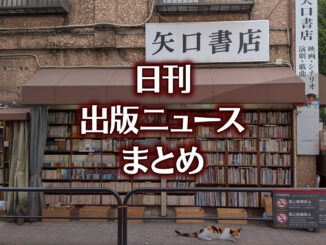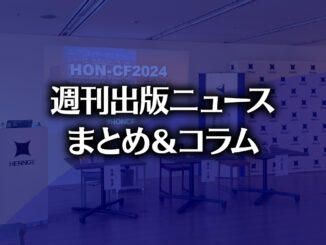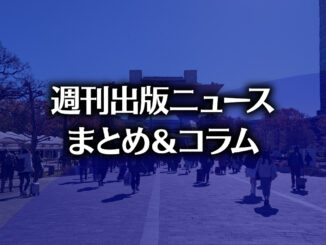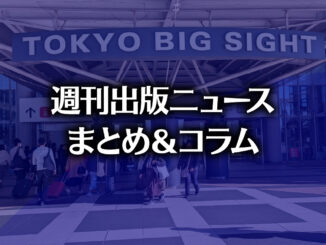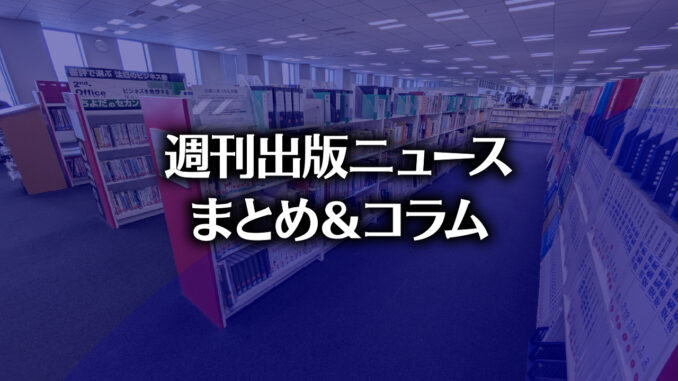
《この記事を読むのに必要な時間は約 17 分です(1分600字計算)》
2025年7月27日~8月2日は「“エロ広告”自主規制で苦情が団体非加盟事業者中心に」「情プラ法指定でX(旧Twitter)が対応窓口新設」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
お知らせ
#40 本と音声コンテンツ(2025年7月29日版)〈HON.jp Podcasting(2025年7月30日)〉
今回は「本と音声コンテンツ」をテーマに、新コーナー「ぽっとら」を始めた理由などについて語りました。ポッドキャストはマネタイズのことをまったく考えずに始めたのですが、調べてみたら音声コンテンツのままマネタイズするのはまだ難しそう。それなら、音声とテキストの両面作戦かな、と。とはいえ違う層に届けたいから、ポッドキャストも続けます。
新コーナー「ぽっとら」(Podcast Transcription)を更新しました
クレジットカード決済の表現規制、いわゆる“金融検閲”問題はなにが原因なのか?〈HON.jp News Blog(2025年7月28日)〉
この回は3月の収録・配信なのでその時点のまとめなのですが、ちょうどいま「Steam」などゲーム系でも問題が大きくなっているタイミングに偶然公開がぶつかってしまいました。タイミングが良かったのか悪かったのか。当時私が推測したこの「国内外の法律の違いが越境取引で問題になっている可能性」という観点は、現在に到るまで他でも見たことがありません。ゲーム系の動きを見てると的外れだったかも?
ともあれ、ゲームに火がついたことで、日本だけでなく世界的に「金融検閲」が問題視され始めました。そして、その働きかけをした団体は、公開書簡を出したことで特定されています。ただ、日本でこの問題が起きていた当時には表立った動きは観測されていないので、今回の公開書簡を出した団体とは要因が別ではないかという気もします。
不快な広告への事後対応が絶賛されているのを見て、事前対応しているメディアとしては正直うらやましかった〈HON.jp News Blog(2025年7月29日)〉
この回も収録・配信は3月なのですが、当時「これだけ気合い入れた内容ならそれなりに聴かれるだろう」と期待していたんですよね。でも正直、期待したほどは聴かれませんでした。それが、文字に起こししただけでバズっちゃいました。「ポッドキャストはバズらない」ことを強く実感しています。ただ、「聴かれたい」「読まれたい」とは思うけど、「バズって欲しい」とはあまり思わないんですよね。バズると変な反応が来ることが多いんで。今回は変な反応がほとんどないのが幸い。
しかし、ウェブメディアで1万字を超えている記事でも、リーダビリティが高ければ(広告に邪魔されなければ)いまでもふつうに読まれることが再確認できました。「読者に対し誠実であろうとするほど収入が減る」というフレーズが、メディア関係者を中心にぶっ刺さっているみたいです。まあ、「長い」って声も数件ありましたが。この内容は、圧縮しても8000字くらいかな。
ウェブメディアを広告まみれにしてユーザーを日々イラッとさせている戦犯はだれか?〈HON.jp News Blog(2025年7月30日)〉
だいたいGoogleが悪いという話です。Googleが「Better Ads Standardsに準拠してない広告はChromeで非表示にします」と宣言したときは「これでウェブ広告の世界が健全な方向へ変わるかも?」という期待があったんですが、直後に自ら「自動広告」でそれを破りにいきましたからねぇ……罪深い。
東京・札幌・沖縄で作家・編集者・デザイナーが3日間集まり“本”を創り上げていくパブリッシングイベント「NovelJam 2025」開催!
参加者一次募集で定員に達しなかったため、引き続き二次募集を行います。定員に達し次第終了する予定です。開催は10月11日から13日の3日間です。詳細は上記リンク先の開催概要をご確認ください。
政治
社説:AIの無断生成 声優や歌手の権利どう守るか〈読売新聞(2025年7月27日)〉
いつもの読売新聞しぐさですねぇ……いちおう反論しておきます。「声」に著作権はないので、仮に著作権法を「著作物をAIが学習する際には許諾を要する」形に改正しても「声」の問題は解決しません。権利を強化する方向の改正は、読売新聞にとって都合がいいからこういうことを言うんですよね。我田引水にもほどがある。
じゃあ現実的にどうすれば? というと、「声」がパブリシティ権に含まれるという判例を勝ち取った方が早いのではないか、と。パブリシティ権はもともと法律で明示されおらず裁判で確立した権利なので、こっちのほうがたぶん筋が良いです。声を聞いてパッと「あ、この歌手だ!」「あ、この声優だ!」と誤認できてしまうレベルの有名な声を真似たAIなら、元の声には顧客吸引力があると認められるのでは?
英国、ウェブサイトでの年齢認証を大幅強化—アダルトコンテンツから子どもを守る新制度が始動〈Media Innovation(2025年7月29日)〉
イギリスのこの動き、ちゃんと把握できていませんでした。2023年10月に成立した「オンライン安全法」とその後に発行されたガイドラインに基づき、2025年7月25日以降は子供がポルノや有害なコンテンツにアクセスできないよう、ポルノを許可するすべてのサイトとアプリに厳格な年齢確認を実施することが義務付けられたそうです。これは「日本にも導入を」という声が上がりそう……と思って調べてみたら、子ども家庭庁で調査レポートを発見しました。そりゃ調べますよね。
競合アプリストアの排除禁止 スマホ新法指針、Appleは安全懸念〈日本経済新聞(2025年7月29日)〉
スマホソフトウェア競争促進法の指針案に対し、パブコメでアップルが「安全性が保てなくなる」などといった意見を送っていましたが、原案から小幅の修正に留まったとのこと。脅しには屈しなかった! 確かに、アップルが言うように安全性は下がるかもしれませんが、競争を促進する意味では良いと思うのですよね。これでいよいよiOSにも、他のアプリストア――たとえばGoogle Playなどが入るようになる?
X、権利侵害投稿の「削除窓口」新設–7日以内に対応 日本語スタッフも配置〈CNET Japan(2025年8月1日)〉
こちらは、情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)への対応です。X(旧Twitter)が同法の指定を受け、法律で義務づけられた「対応の迅速化」と「運営状況の透明化」に対応するために窓口を新設したとのこと。情プラ法がしっかり効果を示した事例です。とくにこのX(旧Twitter)にちゃんと言うこと聞かせられたのは、大きいと思います。
社会
性的なネット広告 いわゆる“エロ広告” 対策は進んだ?線引きどこに 電子コミック業界は自主規制も|WEB特集|デジタル深掘り〈NHK(2025年7月29日)〉
ただ、苦情が寄せられている広告は、いずれの団体にも加盟していない海外のゲーム事業者のものが多かったということです。
あれまあ……私が「問題は、非加盟社がどう動くか」と懸念していた通りになってしまいました。結局、広告枠の奪い合いですからね。自主規制していない企業からすると、単に「競合が減った」という状態になってしまっているわけです。
成人向けゲーム規制問題について、クレジットカードMastercard社が「ゲームプラットフォームに制限を求めたことはない」と声明〈AUTOMATON(2025年8月2日)〉
クレジットカード国際ブランドが「ウチの指示じゃない」と言い出すのって、日本で「金融検閲」問題が騒がれるようになったときと同じ反応ですね。その言い分を信じるならこれも、アクワイアラか決済代行事業者の「過剰対応」って線が強いのでしょうか。
経済
$17 for a Kindle Book? So Much for the Paperless Bargain(キンドル本が17ドル? ペーパーレスのお買い得はこれで終わり)〈TeleRead(2025年7月29日)〉
At first, I assumed this was Amazon squeezing readers. But here’s the twist: it’s mainly the publishers driving the price increases.(最初は、アマゾンが読者から搾取しているのだと思った。しかし、ここで意外な事実がある:値上げを推進しているのは主に出版社なのだ。)
そうなんですよね。AmazonがKindle版を9.99ドルで売り出したことに対抗するため、大手出版社はAppleと共謀して価格をつり上げ、司法省に提訴されました。出版社は司法省とすぐに和解したんですが、その和解条件のひとつにエージェンシーモデルの2年間禁止がありました。その2年間が過ぎて出版社に値付けの主導権が戻ったら、また一斉に値上げしたんですよね。
私はこれが、アメリカで電子出版市場の拡大を止めた最大の要因だと思っています。紙の市場の縮小を恐れ、電子版の販売価格をつり上げることにより、電子版の購入メリットを損ねて購入意欲を削いだわけですよね。つまり、アメリカで電子出版市場の拡大は自然に止まったのではなく、出版社が意図的に止めたのではないか、と。
米アマゾン、AI利用でNYタイムズに年37億円支払い 米報道〈日本経済新聞(2025年7月31日)〉
金額が判明。用途は「AI訓練」と「要約の作成」の両方です。その条件で、NYTの年間売上高の1%程度ですか……うーん、だいぶ安いのでは?
電子コミック市場崩壊の危機|パピレス 天谷幹夫〈日本電子出版協会(2025年8月1日)〉
天谷氏のこの御意見、概要はJEPAの会合で何度か伺っていました。こうして文面でしっかり読むのは初めてです。懸念はわかるのですが、いくつか異論があります。
まず、音楽市場との比較について。音楽市場をパッケージ販売とストリーミング配信だけで捉えないほうがよいです。ぴあ総研の調査によると、ライブ・エンタテインメント市場はアフターコロナで急回復し2023年には過去最高額を記録しました。音楽だけで4757億円あります。
もう一点、「電子書籍ビジネス調査報告書」のユーザー調査を引用している箇所について。
この結果、有料の利用率は2017年の17.6%から2021年まで徐々に伸びて20.5%を達成しましたが、それ以降3年連続して低下し、2024年は18.7%になってしまいました。これに対して、無料の電子書籍のみを利用するユーザの利用率は、2017年の22.8%が徐々に増加し、2021年で24.8%になり、その後も増加し2024年には、28.8%になりました。
この「有料利用率が下がっている」理由については、2024年版のリリースでは以下のように理由が推測されていました。端的に言えば「高齢者のスマホ利用率が急激に伸びたから」です。
ただし、スマートフォンが高齢者にも広まってきていることから、スマートフォンユーザーに占める60歳以上の人口の割合が増加していることにも注意が必要です。有料・無料ともに電子書籍利用率が低い女性60歳以上のスマートフォン利用者が増えていることが、スマートフォンユーザー全体の電子書籍利用率を押し下げる方に作用しています。これらのことから、電子書籍利用人口自体は増加傾向を維持していると推測しています。
要するに、母数が増えたぶん、率が減ってしまった、と。実際、NTTドコモ モバイル社会研究所の調査でも、シニア世代にスマホが急に普及していることが見て取れます。この世代は人口が多いから、母数に与える影響も大きいはず。これ実は、2025年版のリリースには記述がありません。毎年書いたほうが良いかも?
ちなみにどういう調査でも、端っこは要注意です。つまりこれは、逆サイドの10代についても同じことが言えます。同じくNTTドコモ モバイル社会研究所の調査によると、スマホ所持率は10歳17%、11歳42%、12歳65%、13歳77%、14歳77%、15歳82%です(10歳が何年生かは誕生日のタイミング次第ですが、ここでは小学4年生と仮定しました)。
「電子書籍ビジネス調査報告書」のアンケート調査部分にも「10代の回答は少ないことに留意されたい」という記述がありますが、そりゃそうですよ。スマホを利用したアンケートに、スマホを持っていない人は回答できないわけですから。
もっと言うと、2020年以降はGIGAスクールによって、小学1年生以降の全員がICT端末を利用している世代に急変しています。授業でChromebookやiPadなどを使っているにも関わらず、スマホは持っていない児童生徒が相当数いることになります。
そして、同じく2020年以降に普及が急加速した電子図書館サービスを授業で使った児童生徒は、無料の電子書籍利用に含まれるはずです。このように、ちょっと考慮すべき要素が多くて私も整理が難しいのですが、以前とはいろいろ前提が変わっています。少なくとも、要因をひとつに決めつけないほうがいいと愚考します。
2つの電子書籍市場「推計」はどのくらい・なぜ違うのか 出版指標年報と電子書籍ビジネス調査報告書〈出版・読書・コミック・図書館・デジタルパブリッシング(2025年8月2日)〉
関連する話題なので合わせてピックアップ。
『出版指標年報』2025年版には「ライトノベルは電子書籍では売れ行きを伸ばしている。シリーズものが多く、割引などの施策も効果的で、電子との親和性は高い。デジタルシフトが進行していると思われる」とあるが、筆者が今年の春に国内電子書店事業者や電子取次にヒアリングした際に「ラノベが好調。伸びている」などと語った会社は一社もなかったので、ここを読んだときには「え?」と思ってしまった。
電子書籍(文字もの等)市場でライトノベルが売れ筋という話は、「出版指標年報」では少なくとも2019年版から毎年言われ続けていることです。2025年版で急に出てきた話ではありません。電子書籍(文字もの等)市場が微減傾向だった2022年(2023年版)、2023年(2024年版)でも、ライトノベルは「堅調」「比較的好調」と表現されています。だから私はこの記述について「2024年(2025年版)も同じような傾向だったんだな」程度にしか捉えませんでした。
もしやKADOKAWAの担当者が盛った話を鵜呑みにしただけなんじゃないかと邪推したくなるレベルである。
えーっと……この箇所は私でさえちょっと唖然としてしまったのですが、KADOKAWAの関係者が読んだらどう思うか。ちょっと心配です。ま、まあ、KADOKAWAはそろそろジャンル別の数字を、ざっくりとでもご公表いただいたほうがいいのかもしれません。
直近の2025年3月期 通期決算説明資料(PDF)でも、紙はライトノベル売上高を公表しているのに(p50)、電子書籍事業売上内訳は以前から「コミック77%、文字もの23%」くらいの粒度でしか公表してないのですよね(p52)。決算説明資料によると、KADOKAWAの電子書籍・電子雑誌売上高はFY2024で約644億円あります。市場全体に与える影響は大きいです。
ただし、拙著『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか?』でも記したように、この数字には「dマガジン」「読書メーター」と海外向けが含まれているのと、自社ストア「BOOK☆WALKER」(小売販売額)と他社ストア(卸売販売額)が混在しています。そのため、出版科学研究所の推計と単純比較はできません。
技術
情報コンテンツはもう作る意味ない? クリックされないAI時代にSEOでやるべきこと(前編) | Moz – SEOとインバウンドマーケティングの実践情報〈Web担当者Forum(2025年7月28日)〉
いやー、Googleボットに読ませるための、SEOを目的とした情報コンテンツは、過去もこれからも要らないですよ。というか、お前らがウェブにゴミをまき散らしていたのか。憎悪が先に立ちますわ。
Google、AI年齢推定でYouTubeや広告を自動制限 米国で開始〈ITmedia NEWS(2025年7月31日)〉
うーん……この「AI年齢推定」を全面的に否定するつもりはありませんが……たとえば、Google for Educationのアカウントには現状、Googleのコアサービスだけ広告が表示されない仕様になってますよね。そんな半端な真似をせず、教育向けにはGoogle AdSenseを一切表示しない仕様にすればいいのでは。これはやろうと思えばすぐにでもできるはず。まずそこからでしょう。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」で新たに誕生した16点の作品を合本にしました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
台風9号の直撃は免れましたが、ちょろっとだけ雨が降りましたね。カンカン照り続きで夕立すら来ない日が続いていたので、農作物への影響を少し心配していました。また米が値上がりしちゃう!(鷹野)