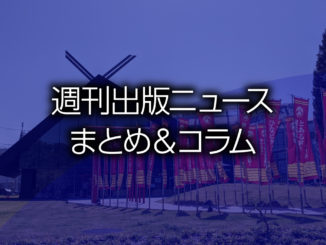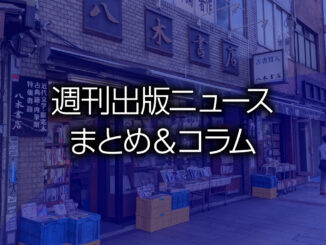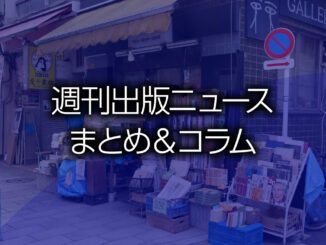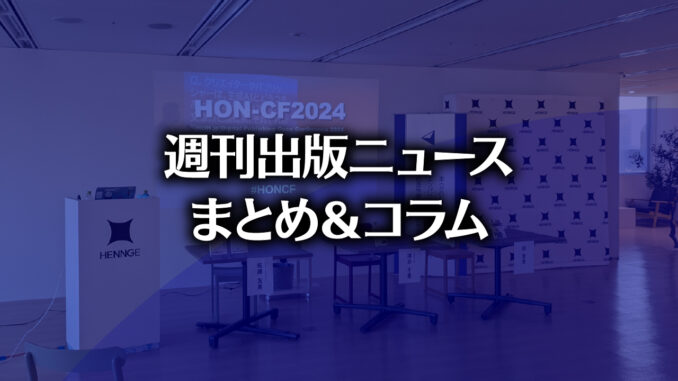
《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
2025年3月23日~29日は「エロ広告の規制はなぜ進まないのか?」「ジブリ風画像を生成AIで出力するのは著作権侵害?」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 社会
- SNS投稿、日本では初期の「ネットは匿名」定着…実名派「自分隠し言いたい放題はフェアじゃない」〈読売新聞(2025年3月22日)〉
- Xの「コミュニティノート」兵庫県知事選挙でほとんど機能せず 偽情報・誤情報対策 研究グループ分析|IT・ネット〈NHK(2025年3月24日)〉
- “AIのChatGPTが95% 芥川賞作家の九段理江さんが5%書いた小説” 雑誌「広告」に掲載|文芸〈NHK(2025年3月25日)〉
- 生成AIで“ジブリ風”画像生成しSNS投稿 疑問や懸念の声も|生成AI・人工知能〈NHK(2025年3月27日)〉
- 「ストレートニュースの価値はゼロになる」AI時代にメディアはどう戦う?【Media Innovation Conference 2025】〈Media Innovation(2025年3月28日)〉
- 経済
- Facebook(Meta社)の広告枠があまりにもクソすぎる件 / ひさびさにここまでひどい詐欺広告を見た気がする〈ロケットニュース24(2025年3月25日)〉
- SNSの時代にメール? 欧米メディアが取り組む「ニュースレター」の知られざる成功例(飯田一史) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年3月27日)〉
- デジタル製造による書籍が3000万部を突破、売上高は業界トップに KADOKAWAが進める「出版製造流通DX」の最前線〈Japan Innovation Review powered by JBpress(2025年3月27日)〉
- デジタル広告詐欺、世界の被害約13兆円 生成AI悪用〈日本経済新聞(2025年3月29日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
HON.jp Podcasting「#24 報酬を獲得できる広告(2025年3月25日版)」を配信しました
今回もまた広告の話ですが、#21は「詐欺広告」、#23は「下品な広告」と、少しずつベクトルの違う話です。とはいえ、今回は初めてお便りをいただいたこともあって、後半のお便りコーナーのほうが長いです。やはり、お便りが届くとテンションが上がりますね。
「こんなトピックスを取り上げて欲しい」とか「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。お便りはこちらのページからフォームで送付できます。あなたのお便りをお待ちしています!
政治
野放しになる「エロ広告」 学校のタブレットにも…規制なぜ進まず?〈毎日新聞(2025年3月27日)〉
GIGAスクールの端末に「エロ広告」が出てしまうというのは、フィルタリングがちゃんとできていない自治体なのでは? と疑いの目を向けてしまいました。調べてみたところ、デジタルアーツ株式会社が昨年12月に発表した調査結果では、有償フィルタリングの導入率が79.7%(昨対比約5ポイント増)、未導入はようやく2.1%(同7.4ポイント減)まで減ったという状況のようです。端末更新のタイミングでやっと導入するところが増えてきたみたい。
で、「規制」がなぜ進まないか? という話なのですが、そりゃもう記事後半にもあるように、政府による規制はストレートに表現の自由を脅かすからです。新聞や雑誌は倫理規程を設けて自主規制してますよね。
そもそも倫理観のない広告主・広告代理店がきわどい広告を入れてくることが発端ではあるんですけど(それなのにアドフラウドとかブランドセーフティーなどと言って自分たちが被害者側であることばかり対策を進めているのがおかしいという話でもありますが)、根本的な問題はプラットフォームがザル審査なところにあると私は思います。
HON.jp Podcasting「#23 下品な広告(2025年3月18日版)」でも触れましたが、プラットフォームがメディアに広告審査のコストを丸投げしているような状況でもありますから。そして、メディアが広告審査にコストをかけると、短期的には収入が減る可能性が高いわけです。
だから、もし法規制するとしたら、詐欺対策と絡めてプラットフォーム事業者をターゲットにすべきだと思います。さすがに詐欺広告以外で、ユーザーに「プラットフォームが不明」な広告は少ないと思いますが、「広告主が不明」だったり「フィードバックの仕組みが貧弱」だったりするものは、珍しくない印象ですから。
国会でも話題の性的広告 担当者が語る「アダルト業者も金を無駄使いしたくない。見せたくない人には見せないのが普通」〈テレ朝news(2025年3月23日)〉
この観点も重要です。当然のことながら、広告主もなるべく無駄な広告費は払いたくないわけですよ。子供が使っている端末にアダルトな広告を表示したところで商品は売れません。ところが、プラットフォームの提供しているシステムが貧弱で、広告主やメディアがうまくフィルタリングできない仕組みだと、ミスマッチが起きてしまうわけです。
私たちは「エロ広告」に困っている 国民民主・伊藤孝恵議員の「許すまじ!」に敬意を示したい 北原みのり〈AERA dot.(2025年3月26日)〉
伊藤孝恵議員が参議院予算委員会で「エロ広告」を問題視する質問をしていたことは知っていたのですが、発言すべては把握していませんでした。こんなことをおっしゃっていたのですね。
「性的同意のない性行為、性的児童虐待コンテンツを広告にするなど許すまじ!」
うーん、これはど直球の表現規制ですねぇ……そりゃ玉木雄一郎代表が慌てて火消しに走るわけです。被害者のいる性虐待記録物(絶対ダメ!)と、被害者のいない創作物(合法!)は、大違い。そこはちゃんと区別しましょうよ。青少年の保護育成という観点なら、ゾーニングの問題でしょう。
社会
SNS投稿、日本では初期の「ネットは匿名」定着…実名派「自分隠し言いたい放題はフェアじゃない」〈読売新聞(2025年3月22日)〉
これ、私は20年くらい前から言い続けてますが、「匿名」か「実名」かの二元論ではありません。「匿名性が高いか低いか」のグラデーションです。本名ではない芸名や筆名は「匿名」ですが、ずっと同じ芸名や筆名で活動していたら匿名性は低いわけですよ。
ちなみに、この記事には珍しく署名がありますが(あまりに小さくて最初気づかなかった)、署名記事の少ない読売新聞がなにを言うか、と思いましたよ。「読売新聞」という看板に隠れた匿名性の高さをいいことに、言いたい放題してませんか? 無署名記事も、フェアじゃありませんよ。
Xの「コミュニティノート」兵庫県知事選挙でほとんど機能せず 偽情報・誤情報対策 研究グループ分析|IT・ネット〈NHK(2025年3月24日)〉
公開されていたはずのコミュニティノートが、あとで見たら消えていたりする場合もあるのですよね。単純な多数決ではないにせよ、やはり多数派工作に対する若干の脆弱性があるのでは。つまり、元投稿へのカウンターでコミュニティノートが付くと、元投稿への賛同者が大量の低評価で対抗する、みたいな合戦が起きてしまっているように感じます。
“AIのChatGPTが95% 芥川賞作家の九段理江さんが5%書いた小説” 雑誌「広告」に掲載|文芸〈NHK(2025年3月25日)〉
おお……芥川賞を受賞した『東京都同情塔』は「5%」のAI使用という発言があり、そのことを批判する声も若干見かけましたが、こんどは数値を真逆にしましたか。ずいぶん思い切ったことを。逆張りというか、炎上上等というか。ロックだなあ。まあ、話題性はあるので、問題は「面白いかどうか」でしょう。私はどうも、AI出力だとわかっている文は、よほど気合いを入れない限り目が滑ってしまうんですよね。先入観で脳が勝手に「読む価値がない」と判断しちゃう、というか。
生成AIで“ジブリ風”画像生成しSNS投稿 疑問や懸念の声も|生成AI・人工知能〈NHK(2025年3月27日)〉
著作権的な観点から。まず、例示されているトランプとゼレンスキーの口論写真には、撮影者に著作権があります。それをi2i(Image to Image)でジブリ風にすると、撮影者の著作権を侵害している可能性が高いです。しかし、絵柄はアイデアの範疇ですから、ジブリ風であってもジブリの著作権は侵害していない可能性のほうが高いです。そのあたりの切り分けが難しいからか、いろいろ誤解も流布されていました。
ちなみに、某所で“文化庁も「絵柄」は生成AIへの学習に限り著作権侵害となると言っています”などという意見も見ましたが、それはチェリーピッキングです。文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について(PDF)」に“当該作品群の創作的表現が直接感得できる場合、当該生成物の生成及び利用は著作権侵害”(p21)と書かれているのがその根拠のようですが、その手前にある検討の前提を飛ばしていますね。同じPDFのp5には以下のように書かれています。
このように、著作権法は、著作物に該当する創作的表現を保護し、思想、学説、作風等のアイデアは保護しない(いわゆる「表現・アイデア二分論」)
つまり、作風・絵柄などのアイデアは「創作的表現」に含まれないのが前提です。だから仮にAI出力の作風・絵柄がなにかに似ていても「創作的表現が直接感得できる場合」に当たらない可能性が高くなります。ただし「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当する可能性は、完全には否定できません。
ChatGPT「トトロそっくり」画像も生成 著作権にリスク〈日本経済新聞(2025年3月27日)〉
逆に、この記事の1枚目に例示されている“ChatGPTに「トトロのようにして」と指示した画像”が本当にプロンプトだけで出力されたなら、これは「創作的表現が直接感得できる場合」として認定される可能性が高いでしょう。だって、まんまトトロだもん。複製権、もしくは、翻案権の侵害(ただし親告罪)。
ChatGPTで「ジブリ風」イラスト作って問題ないの?福井健策弁護士が「著作権のポイント」解説〈弁護士ドットコム(2025年3月29日)〉
専門家による解説がこれだけ素早く出てくるのは素晴らしい。さすが弁護士・福井健策氏と弁護士ドットコム。ただし、利用者視点での解説に特化しているようで、学習用データセットが原則無許諾で利用できる著作権法第30条の4については恐らく意図的に省いていますね。著作権以外で、i2i(Image to Image)で画像をアップロードすると、それが学習用に用いられてしまう可能性があるという指摘は、確かに。
海外のAIアプリ関係者が「ジブリから著作権侵害で正式に警告を受けた」と投稿→ついにジブリが動いたか!と思いきや、警告文の画像自体がフェイクというカオス〈Togetter(2025年3月28日)〉
地獄みが増しているわ……画像をよく見れば、トトロの顔が「へのへのもへじ」みたいになっているから、偽物だと怪しむこともできたんでしょうけど。「これは話題になる!」と飛びついて煽った人の負け。
「ストレートニュースの価値はゼロになる」AI時代にメディアはどう戦う?【Media Innovation Conference 2025】〈Media Innovation(2025年3月28日)〉
こちらのイベント、行ってきました。「ストレートニュースの価値はゼロになる」あたりの話は、実際にはもっと不安を煽っていて「500万倍にコンテンツが増えた世界でメディアは何をしなければいけないのか」とか「AIが記事を0.1秒で書けるんだったら(中略)最初にストレートニュースを出す価値って0.1秒リードするだけだよね」みたいなことをおっしゃっていました。
私は、以前から「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側にある状態になる」と言っています。だから、メディアが記事を今後もいままでと同じように無料で誰でも読める状態で発信することを前提とした「ストレートニュースの価値はゼロになる」というこの考え方に、けっこう疑問を感じました。
実際、少し前に大手新聞社のウェブサイトでrobots.txtを調べたら、いずれもすでにAIボットを許可しない設定になっていたんですよね。AI企業へ記事を提供する代わりに対価をもらう共同通信社のようなメディアは、少数派になる気がします。もっと言えば、恐らくYahoo!ニュースやSmartNewsなどのニュースアグリゲーターにも、ニュースを提供しない方向へシフトするのでは。
そうなると、いくらAIが高性能になったところで、無料で誰でも読める状態の記事が少なくなって、あるとしても信頼性の低いものか、無断転載かみたいな状態では、その能力が発揮できなくなります。さすがに「EPIC 2014」で予想された、ニューヨーク・タイムズがインターネットから撤退して紙だけに回帰するみたいな状況にはならないと思いますが、ペイウォールを築いてIT企業がコンテンツを利用できないようにすることは可能なわけで。
そんなことを考えながら、質疑応答の時間で私は真っ先に手を挙げ、以下の質問をぶつけてみたのです。
―――AIで記事作成の速度が飛躍的に上がり、ストリートニュースの価値がゼロに近づいていくという話だが、AIによるニュースがファクトであるかどうかは誰がどのように担保するのか。
つまり、無料で誰でも読める状態の記事が信頼性の低いものばかりになったとしたら、そこからAIで生成される記事も信頼性の低いものとなってしまうわけだから、むしろファクトが担保された信頼性の高いストレートニュースは、価値が上がるのではないか? と。これに対する深津氏の答えがこちら。
深津 とても鋭い質問です。それは大きなビジネスチャンスだと考えています。たとえば。新聞社がAIの発信するニュースに対してファクトであるという保証の認定制度を展開したら、大きなお金が動くかもしれません。
うーん、それが「大きなビジネスチャンス」だと本当に考えていたのなら「ストレートニュースの価値はゼロになる」と連呼して不安を煽ったりするだけでなく、私から質問される前に可能性についても述べるのでは? と思いました。
「それって『ファクトの担保』を考慮すると、ストレートニュースの価値はゼロにならないってことでよろしいでしょうか?」と重ね問いしようかと思ったんですが、喧嘩を売りにいったわけではないし、さすがに意地悪過ぎるかと止めておきました。昔の私だったら、その場で聞いていたかも。丸くなったなあ。
経済
Facebook(Meta社)の広告枠があまりにもクソすぎる件 / ひさびさにここまでひどい詐欺広告を見た気がする〈ロケットニュース24(2025年3月25日)〉
通知を装ったバナー広告について。「ひさびさに」とありますが、私は以前からよく見かけます。目撃回数は少なくとも2桁には届いているはず。そして見かけるたびにFacebookへ通報してますが、毎回「問題ない」と回答が返ってきます。
何度でも言いますが、そういう企業がJICDAQ認証されたままでいいんですか? 「状況が改善されない場合、認証を取り消します」といった警告を一般公開で発するくらいのことをしてもいいのでは。JICDAQ認証の信頼性向上と、認知向上を図ることもできると思いますよ。
SNSの時代にメール? 欧米メディアが取り組む「ニュースレター」の知られざる成功例(飯田一史) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年3月27日)〉
日本における「ニュース」という言葉の響きにつられてNewsletterをニュースのヘッドラインをまとめたものや、「○○ニュースまとめ」を配信するものだと誤解している人もたくさん見ますが、別にNewsletterはそういうものに限らないこともなかなか伝わっていません。
その誤解、私は初耳でした。たくさんいるのか……後半の“letter”すなわち「購読者への手紙」だと捉えるのが良いんでしょうね。ちなみにうちは「ニュースレター」を名乗っていません。始めるとき少し迷ったんですが、すでに日本ではわりと浸透している「メールマガジン」の呼称でいいだろうという判断でした。
デジタル製造による書籍が3000万部を突破、売上高は業界トップに KADOKAWAが進める「出版製造流通DX」の最前線〈Japan Innovation Review powered by JBpress(2025年3月27日)〉
中でも、KADOKAWAは2024年度に売上高が2581億円に達し、集英社(2043億円)や講談社(1710億円)を抜いてトップとなり、飛躍的に業績を伸ばすことに成功している。
本筋ではないのですが、この記述が気になってしまいました。これって、全部門合計の数字ですよね。出版・IP創出部門は1420億円です(2024年3月期 通期決算資料参照)。それ以外の売上は、アニメ・ゲーム・ウェブ・教育などです。
この記述が2ページ目にあったので、3ページ目では部門別の説明があるのかと思ったのですが、本筋のBECプロジェクトの話にいきなり飛んでました。全部門合計売上で比較して「集英社や講談社を抜いてトップ」は、さすがに若干ミスリード気味なのでは。ちなみにリクルートやベネッセのほうが売上高は大きいです。
まあ、いちおう最後のページで「KADOKAWAにとって、出版・IP(知的財産)事業は売上高の半分を占める重要な中核事業である」という説明はありますが。
デジタル広告詐欺、世界の被害約13兆円 生成AI悪用〈日本経済新聞(2025年3月29日)〉
クリック偽装などのアドフラウドと、MFA(made for advertising)メディアを、同じ運営主体がやっているケースがあるわけですね。詐欺師視点で考えたら、むしろ当然か。こちらも、プラットフォームがそういうメディアをちゃんと排除できていない点こそが問題だと思うのですが。
技術
生成AIの検索エンジンは60%以上も間違った情報を引用。有料版は無料版より自信を持って間違えやすい(生成AIクローズアップ)〈テクノエッジ TechnoEdge(2025年3月24日)〉
ウェブ情報の信頼性判断は、どう考えてもGoogleに一日の長、というか20年以上のアドバンテージがあるはずなんですよね。相対的に。Google以外のディープサーチが、どうやってウェブ情報の信頼性を判断しているのか、正直、強い疑問があります。一見、キレイに調理済みのものが出力されているように「見える」ぶん、タチが悪い。「これからはSEOではなくLLMO(大規模言語モデル最適化)」みたいな言説も見かけますが、ブラックハットSEOの再来になりそうな悪寒。
無料で使えて超高品質、画像生成AIの最新事情〈ASCII.jp(2025年3月24日)〉
記事内にも書かれている、画像系生成AIの学習用データに使われてしまっているという「Danbooru」を改めて調べてみました。運営者情報はパッとわかる箇所に記述されていないようですが、プライバシーポリシーのところに以下のような記述を見つけました。
We are based in the United States and we process and store information on servers located in the United States.(当社はアメリカに拠点を置いており、アメリカにあるサーバーで情報を処理および保存しています)
であれば、広告もありませんし、アメリカの法律に基づいて「フェアユース」を主張するでしょうね。無断転載サイトと忌み嫌われていますけど、Internet Archiveとなにが違うのか? という話になるでしょう。法制度が日本とは違うから、難しいなあ。
GPT-4oとGemini-2.0の画像生成能力はいかにして作られているのか〈Zenn(2025年3月27日)〉
OpenAIのGPT-4oやGoogle Gemini-2.0の画像生成が従来の拡散モデル(Diffusion Model)ベースではなく、自己回帰型のAny-to-Anyモデルであるという解説です。これを読んで、Adobe Fireflyの進化が最近(相対的に)止まっているように感じられる理由がわかった気がしました。
Adobe Fireflyは拡散モデルのままなんですよね。「猫」と指示してるのに、おかしなクリーチャーが生成される場合がいまでもけっこうな頻度であるのですが、そのクリーチャーが、私がStable Diffusionを触っていた2年前といまだに同じような感じなんですよ。
いちおうAdobe Fireflyのモデルは昨年4月にImage 2から3に進化してるんですが、根本的なところが直っていない印象です。商業デザインに安心して使えるモデルという差別化は良いとして、もうちょっと技術的なところを頑張って欲しい。
ところで、この記事の以下の箇所について。
ここ1年半ほど画像生成AIいじりを仕事にしてきた者としては、これまで積み上げてきた成果や進捗がすべて無に帰すレベルでの進化が突然起き、巨人にすべてを蹴散らされたという感じです。
私は、Stable Diffusionをしばらく使ってみて「こういうプロンプトを入れるといいぞ」みたいな小手先のノウハウ(プロンプトエンジニアリング)は、いずれ無意味なものになる運命だろうなと思っていました。だから、そろそろ、いよいよ、そういう段階なのだろうな、という印象です。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
エアコンの電源を入れるかどうか迷う、5月くらいの陽気になったと思ったら、この週末はまた寒さが戻っています。桜も咲き始めていますし、いわゆる花冷えというやつでしょうか。(鷹野)