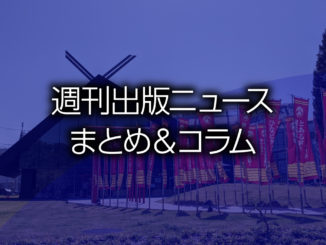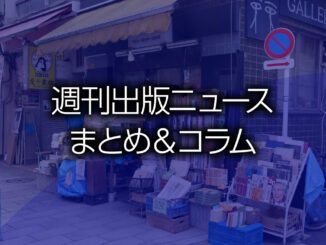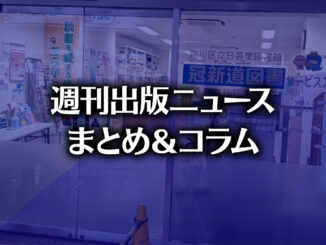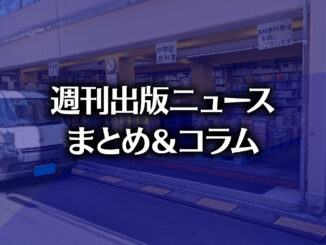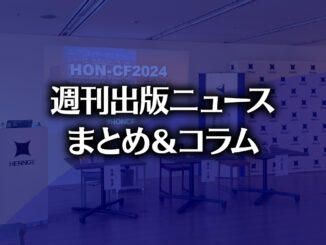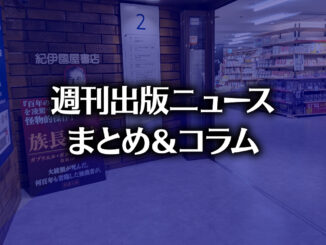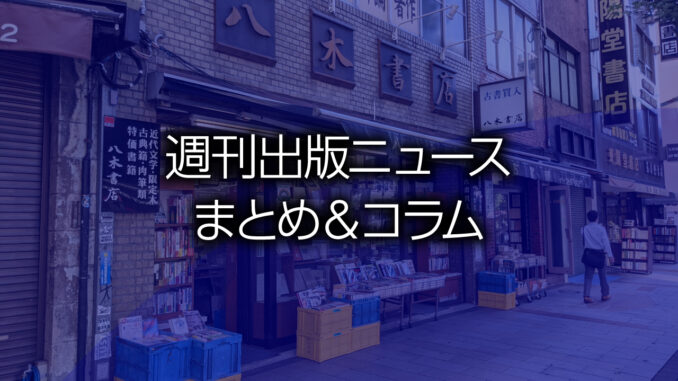
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2022年1月23日~29日は「出版大手4社、海賊版サイト問題でCloudflareを提訴の方針」「アフィリエイトで広告主にも責任」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 2021年紙+電子出版市場は1兆6742億円で3年連続プラス成長 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2022年1月25日)〉
- 休刊の映画誌『ロードショー』14年ぶりに復活 集英社3月創刊のWEBサイト内レーベル〈ORICON NEWS(2022年1月25日)〉
- ネット炎上、情報流出、フェイクニュース…広報におけるウェブリスク再考〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年1月26日)〉
- オトバンク、オーディオブック配信「audiobook.jp」に法人向け聴き放題プラン〈CNET Japan(2022年1月26日)〉
- Amazonのオーディブル、月額1,500円で12万作品が聴き放題に〈PC Watch(2022年1月27日)〉
- インプレスホールディングスとメディアドゥがPOD出版サービスで国内最大シェアとなる合弁会社PUBFUN(パブファン)を設立〈株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース(2022年1月27日)〉
- 出版社向けHPシステム「HONDANA+」でJPRO連携機能を提供開始~リリース後 初の大型機能追加~〈株式会社とうこう・あいのプレスリリース(2022年1月27日)〉
- 技術
政治
小中高の図書館に複数の新聞を 文科省5カ年計画〈日本経済新聞(2022年1月24日)〉
5年間で190億円の地方財政措置。紙の新聞は情報の一覧性が高く、見出しの付け方や情報分類方法なども勉強になるから、悪くはないと思うのです。ですが、せっかくGIGAスクール構想が前倒し施行され児童生徒1人1台端末が実現されたというのに、活用するためのコンテンツ提供、すなわち電子図書館導入に向けた動きへの言及が皆無なのはガックリ。発表された5カ年計画ははこちら。
第6次「学校図書館図書整備等5か年計画」〈文部科学省(2022年1月24日)〉
「アフィリエイト広告」広告主の責任を明確に 消費者庁検討会 | IT・ネット〈NHKニュース(2022年1月28日)〉
昨年6月に始まった「アフィリエイト広告等に関する検討会」で、報告書案がおおむね了承されたというニュース。検討会の資料はこちらです。
第6回 アフィリエイト広告等に関する検討会(2022年1月28日)〈消費者庁(2022年1月27日)〉
本件、私も何回か(#476、#499、#503、検証、予想)取り上げてきましたが、法改正ではなく、指針で対応する方向に着地しました。とはいえ既報通り、アフィリエイト広告の表示内容はまず広告主が責任を負うべき主体であること、また、広告であることを消費者が理解できるような表示を行うことなどが求められています。
また、アフィリエイト広告掲載前後に広告主やASPが表示内容を確認すること、消費者相談窓口を設置し通報に迅速な対応ができる体制をつくることなども、要求されるようになっていくようです。
メディア側としては、今後はアフィリエイトでも広告であることを明示する必要があることを頭に入れ、過去記事の修正対応なども早めに進めておくべきでしょう。ウチも多少はお世話になってますので、他人事ではありません。
報告書案の最後には「Ⅳ 今後の対応」として、「消費者庁は、ステルスマーケティングの実態を把握するとともに、その実態を踏まえ、消費者の誤認を排除する方策を検討すべきである」と示されている点も注目です。今後はステマ対策が検討されることになるのでしょう。
【独自】TikTok運営会社が一般投稿装い動画宣伝…協力者に歩合制報酬、年500万円も : 社会 : ニュース〈読売新聞オンライン(2022年1月24日)〉
口コミ装う「ステマ」後絶たず…法整備求める声も : 社会 : ニュース〈読売新聞オンライン(2022年1月24日)〉
というわけで、非常にタイムリーなネタだったので、「TikTok」運営のバイトダンスがやらかしていたニュースもついでにピックアップ。「サービスを宣伝するものではなく、広告表記は不要との認識だった」と謝罪してますが、「違法じゃないからやる」というなら「じゃあ法律で規制するのもやむなしだね」となるのは必然ですよね。
講談社など、米ITを提訴へ 漫画サイト海賊版のデータ配信〈朝日新聞デジタル(2022年1月30日)〉
CDN大手のCloudflareを、出版大手4社が提訴する方針を固めたというニュース。本稿を書き始めたタイミングで目に飛び込んできたので、迷いましたがピックアップすることに。
2019年6月に、Cloudflareが管理する日本国内のサーバーで著作権侵害が行われていると裁判所が判断したら、データの複製を中止するという条件で出版大手4社との和解が成立しています。
これで少なくとも国内向けの海賊版は沈静化するのでは……と思っていたのですが、どうやらそうではなかった様子。先週、総務省と文化庁で相次いで海賊版対策の有識者会議が開かれ、両方傍聴したのですが、そこで関係者から明かされた実態は、なかなか凄まじいものがありました。
インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第6回)配布資料〈総務省(2022年1月24日)〉
第21期文化審議会著作権分科会国際小委員会(第4回)〈文化庁(2022年1月25日)〉
まず、侵害が裁判所に認められ仮処分が下りキャッシュが削除されても、「ドメインホッピング」には無力なのですね。削除から10時間後に同じ海賊版サイトがドメインだけ変えて復活した、という事例もあったそうです。
また、出版社からCloudflareに対し、事前警告・裁判所決定の省略・ホッピング対策など削除スキームの改善を要求するも、現在に至るまで改善がなされていないといいます。裁判所の命令なら従うが、そうじゃない要請レベルなら動かないという強い意思を感じます。
驚いたのは、特に悪質な9サイト限定で、キャッシュ削除やサービス停止等を要求した件について。政府からも適切に対応するよう求めたそうですが、「措置を講じる」と返答しつつ、現時点でもキャッシュを続けているそうです。なんという舌先三寸っぷりか。
Cloudflareからよくある反論として、「当社はホスティングサービスではない」というものがあるそうです。以前、日経xTECHのインタビューでも「米国の裁判所は一般に、そうした命令は我々のようなCDN事業者には出さない。命令はWebホスティング事業者に出す」と述べており、いまでもそういう姿勢は変わっていないということなのでしょう。
ただ、総務省の検討会議で有識者から、日本の著作権法ではCDN事業者とホスティング事業者は区別されないため、著作権法47条の4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)ただし「著権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するのでは、という指摘がありました。なるほど確かに。
朝日新聞の取材に対しCloudflareは「著作権侵害に直接的に関与していない。当社が問題の根源ではない」などとコメントしているそうですが、国内にサーバーを置いて事業を行っている以上、日本の法律に従う必要があります。法廷できっちり決着付けて欲しいですね。
なお、広告を止める兵糧攻めに関しては、JIAAなどにブラックリストを提供することで「いわゆるまっとうなクライアントの広告」は海賊版サイトでまったく表示されなくなった、という報告がありました。素晴らしい。ただ、こんどは海外のプラットフォーム&海外の広告主が利用されるようになってきたそうです。イタチごっこ。
社会
電子出版制作・流通協議会(電流協)、「電子図書館(電子書籍貸出サービス)実施図書館(2022年01月01日)」を公表〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年1月24日)〉
定点観測。昨年10月1日時点から14増の272自治体265館とのこと。昨年7月1日時点から3カ月間では29増だったので、ペースが若干落ちています。自治体の決裁タイミングなど、季節要因もありそう?
「MacはもともとWindowsだし」にならなかった理由:CloseBox〈ITmedia NEWS(2022年1月27日)〉
20世紀の終わりごろ、Macの次世代OSに候補にはWindows NTカーネルも挙がっていた、という思い出話。当時のCEOギル・アメリオの著書『アップル薄氷の500日』(ソフトバンク出版事業部・1998年)に詳細が語られているそうですが、内容的にはちょっと出版関連とは縁が遠そうな話。
ではなぜピックアップしたかというと、「残念ながらこの書籍は絶版となっており、翻訳本なので電子書籍も難しいだろう。」という一文があったから。国立国会図書館資料デジタル化の範囲は、従来は「1968年までに受け入れたもの」でしたが、「2000年までに刊行されたもの」に拡大されました。つまりこの本、デジタル化の対象となるはずなんです。
電子含む新刊市場で入手が困難な資料なら「図書館送信」と、今年の5月から始まる「個人送信」の対象になり、遠隔でも閲覧可能となります。つまり、1998年に出版されいまは新刊市場で入手困難になったこの資料が、急にアクセスしやすくなるという典型例なのです。身近で分かりやすい事例なので、取り上げてみました。
関連して、2月2日にJEPAで国立国会図書館ビジョン2021-2025の取り組みについてのオンラインセミナーがあります。誰でも無料、YouTube Liveは人数制限なしです。参考まで。
経済
2021年紙+電子出版市場は1兆6742億円で3年連続プラス成長 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2022年1月25日)〉
昨年末の見込みどおり、紙の書籍が15年ぶりの増加となりました。値上げや返品率の改善などが寄与しているとのこと。ただし下半期は数字が落ち込んでいるので、今年はどうなるか。また、電子出版市場は年始の予想で、上半期と同じ成長なら4889億円の見込みと試算しましたが、着地は4662億円でした。つまりこちらも、下半期は伸びが鈍化しています。海賊版の影響もあるのでしょうか?
昨年9月初頭から12月いっぱいまでは、新規感染が沈静化していました。それ以前は「巣ごもり需要」と言われていたくらいですから、少なくとも家で消費するコンテンツには好影響が出ていたわけです。つまり、コロナ禍が落ち着くのは喜ばしいことですが、コンテンツ市場にはマイナスの影響が出そう。
休刊の映画誌『ロードショー』14年ぶりに復活 集英社3月創刊のWEBサイト内レーベル〈ORICON NEWS(2022年1月25日)〉
休刊誌がウェブで復活、というのが主になっているニュースですが、むしろ「新しいスマートフォン向けWEBニュースサイト『集英社オンライン』を3月31日に創刊」という部分に着目したい。名称から推察するに映画だけではなく、「文春オンライン」のような総合型ニュースサイトになる模様。女性誌ファッション系は「HAPPY PLUS(ハピプラ)」ネットワークがありますが、統合するのか、別でやるのか。バラバラで戦うより束ねたほうが良いような気がしますが、果たしてどうなるか。
ネット炎上、情報流出、フェイクニュース…広報におけるウェブリスク再考〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年1月26日)〉
こういう企業広報のリスク回避という観点は、経営上どうしても必要になると思います。以前、著書にも書いたのですが、「クレームに対応する時間はコストでもあるので、そうした負担をなるべく避けようとすると予防措置としての自主規制が強く」なるのですよね。それは創作表現に限った話ではありません。
問題は、「それによって表現できる幅もどんどん狭くなってしまったり、実際の問題状況が隠ぺいされやすくなったりする」こと。創作表現より企業広報のほうが、その傾向は強く出るでしょう。最近の「自主規制を“求める”動き」を見ていると、この懸念は著書を書いた当時より大きくなっているかもしれません。
オトバンク、オーディオブック配信「audiobook.jp」に法人向け聴き放題プラン〈CNET Japan(2022年1月26日)〉
Amazonのオーディブル、月額1,500円で12万作品が聴き放題に〈PC Watch(2022年1月27日)〉
2本まとめてピックアップ。オトバンク「audiobook.jp」法人向け聴き放題プランの発表とほぼ同時に、Audibleから定額聴き放題プランへの変更が発表されました。前者は販路を追加する話ですが、後者は2018年に導入したコイン制の廃止というビジネスモデルの転換です。Audibleはこれで2回目のプラン変更となります。試行錯誤なのか、予定通りの段階的な変更なのか。
インプレスホールディングスとメディアドゥがPOD出版サービスで国内最大シェアとなる合弁会社PUBFUN(パブファン)を設立〈株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース(2022年1月27日)〉
メディアドゥから同じリリース(順番だけ違う)が出ていますが、合弁会社への出資額はインプレスが51%であること、代表取締役社長へ就任するのがインプレスR&Dの福浦一広さんであることから、インプレス側をピックアップ。主に個人向けのインプレスR&D「ネクパブ・オーサーズプレス」と、中小出版社向けのメディアドゥ「PUBRID」を統合。各グループの出版社だけでなく、「エブリスタ」とのシナジー効果も狙うというあたりに注目です。
出版社向けHPシステム「HONDANA+」でJPRO連携機能を提供開始~リリース後 初の大型機能追加~〈株式会社とうこう・あいのプレスリリース(2022年1月27日)〉
出版社公式サイト向けに書誌情報を登録すると、連携して「JPRO」にも登録される仕組み。ようやく中小出版社向けに、こういうシステムが展開されるようになったか……という感慨があります。これぞ出版DX。次の課題は、メタデータの“厚み”ということになるでしょう。
[追記:同様な仕組みを2011年から中小出版社自身がやっている「版元ドットコム」のことが頭からすっかり抜けていました……大変失礼いたしました。]
ちなみに私は、2013年にマガジン航へ「情報誌が歩んだ道を一般書籍も歩むのか?」を寄稿し、古巣がやってる「クライアント自身が直接オンライン上で物件の情報を入力」するシステムを紹介しました。当時、転換が起きた年は明記しませんでしたが、おおよそ2005年前後だったと記憶しています。
要するに、情報をなるべく早く届けるにはどうしたらいいか? を突き詰めると、同じような形に辿り着くということなのでしょう。
技術
広告で個人特定を大幅に制限 グーグル、新技術を発表〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年1月26日)〉
Cookieの代替として開発されてきた「FLoC」を捨てて、個人を識別する情報を大幅に削減した「Topics API」を提供していくという発表です。ユーザーの閲覧履歴から推定したユーザーの興味・関心項目を「トピック」にまとめ、サイト側はその「トピック」に基づいた広告を表示する仕組みです。ユーザー側では「トピック」の確認や削除も可能とのこと。個人的には、パーソナライズよりコンテンツマッチを優先して欲しいなあ、と思うのですが。
Web3時代に情報発信はどう変わる? 次世代のブログプラットフォームやSNSが続々と登場〈DIAMOND SIGNAL(2022年1月28日)〉
次のバズワードとなりそうな「Web3」。要するに暗号資産やNFTと同様、ブロックチェーン技術の応用なんですが、どうもピンと来ないのが正直なところ。参考になるかな? と思い読み進めたら、3つ目の事例(全体の4分の3)で紹介されている和らしべ「HiÐΞ(ハイド)」について「編集部注:林氏が所属するHeadline Asiaは和らしべに出資している」という情報開示が出てきて、思わず大笑い。おもいっきりポジショントークじゃないか。いや、正直ではあるけど、遅いわ!
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
禁酒&ウォーキングによって、2カ月で約5kg減りました。スマホアプリ連動型の体組成計を買って毎日計測していますが、着実に右肩下がりなグラフを見ると、やる気が出てきますね。あと10kg減らしたい!(鷹野)