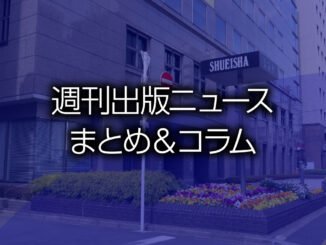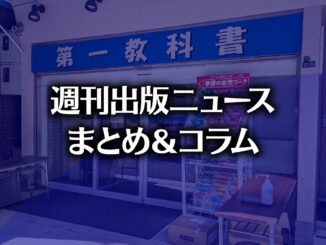《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2021年12月19日~25日は「広告代理店による海賊版サイトの著作権侵害幇助を認める判決」「紙の書籍販売15年ぶり増加へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 国立国会図書館、電子書籍の本格収集を23年開始へ〈新文化(2021年12月20日)〉
- CA2011 – 動向レビュー:電子書籍を中心とした公貸権制度の2005年以降の国際動向 / 稲垣行子〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年12月20日)〉
- 2021年 モバイルニュースアプリ市場動向調査〈ICT総研(2021年12月20日)〉
- TOPS OF 2021: DIGITAL IN JAPAN~ニールセン2021年日本のインターネットサービス利用者数/利用時間ランキングを発表~〈ニールセン デジタル株式会社のプレスリリース(2021年12月21日)〉
- 電子出版アワード2021(第15回)ジャンル賞決定、大賞は「ビジョン2021-2025」!〈JEPA|日本電子出版協会(2021年12月22日)〉
- 「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」の公表について〈国立国会図書館―National Diet Library(2021年12月22日)〉
- 公益財団法人文字・活字文化推進機構ら、「学校図書館図書等の整備・拡充に関する要望」を総務大臣と文部科学大臣に提出〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年12月23日)〉
- 子どもの読書に電子化の波 「学校向け電子書籍サブスク」次々〈朝日新聞デジタル(2021年12月24日)〉
- シリコンバレー101(905) 電子書籍誕生から50年、コロナ禍を経て公立図書館がデジタル図書館へ〈TECH+(2021年12月24日)〉
- 経済
- HON.jp News Casting
- メルマガについて
- 雑記
政治
アフィリエイト広告、誤認防ぐ 消費者庁が指針策定へ〈日本経済新聞(2021年12月18日)〉
#499 でピックアップした「アフィリエイト広告等に関する検討会」に関する報道が出ました。消費者庁が提示した取りまとめの方向性にほぼ沿っています。未然防止の取り組みとして、メディア側にも【広告】表示の明示が義務化されることになりそうです。過去記事の修正が大変そう。
また、アフィリエイターによる誇大表示は、今後は広告主や代理店にも責任が及ぶため「アフィリエイターが勝手にやったこと」といった言い訳が通用しなくなります。報告書は年明け1月の検討会でまとまる予定です。後述の、海賊版サイトへ広告を流し込んでいた代理店への賠償判決と合わせ、今後はネット広告の健全化が進みそうです。
「漫画村」を“ほう助”した広告代理店「エムエムラボ」「グローバルネット」に1100万円の賠償判決、『魔法先生ネギま!』の赤松健さんが提訴〈ねとらぼ(2021年12月21日)〉
海賊版サイト運営の「旨みなくなる」 漫画村に広告料はらった「代理店」に賠償命じた判決の意味〈弁護士ドットコム(2021年12月24日)〉
海賊版サイトの資金源となっていた悪質な広告代理店に対する鉄槌です。赤松健さんによる民事訴訟で、賠償請求は満額認められました。全面勝訴と言っていいでしょう。広告代理店に、著作権侵害の幇助が認められたのは初めてのことだそうです。
こういう前例ができたことで、当然、他の漫画家(被害者)も追随するでしょうから、総賠償額は大変なことになりそう。今後は代理店も、ヘタなところに広告を出せなくなるわけで、強い抑止効果が働きそうです。懸念点は、海外の代理店に逃避され追求が難しくなる可能性、でしょうか。
社会
国立国会図書館、電子書籍の本格収集を23年開始へ〈新文化(2021年12月20日)〉
3月に公表された納本制度審議会の答申(#466)を受け、有償・DRMありの電子書籍・電子雑誌の本格収集が「2023年1月から」始まるとのことです。あと1年。
以前から何度も指摘している(#412・#430・#464)リポジトリで電子納本義務を免れようとする動きは、その後どうなったのか。「広く一般に利用可能である(有償契約や会員登録が必要な場合を含む。)」という条件を満たすなら、ご随意にという感じではあるのですが。
あと、納本制度は「すべての出版物」が対象なので、もちろん同人誌など個人出版も対象です。ところが納本制度の存在や、納本が義務であることも、知らない人が多いのではないか? という懸念があります。どうやって周知すればいいんだろう?
また、デジタル出版物(EPUB)で厄介なのは、書誌を作成するために必要な情報(メタデータ)がEPUBそのものに埋め込まれていない可能性が高いこと。タイトルと著者名だけ、みたいなEPUBファイルが多そうです。
デジタル出版の場合、書誌情報の大部分は電子書店の商品紹介ページにあるのですよね。出版社が入力しているJPRO経由でNDLに入ってくるデータはそれなりに整っているはずですが、個人出版(電子書籍)の納本はどうなるか。
書誌情報の入力システムをNDL側で用意し、最低限必要な項目を必須化して、出版者(=著者)の納本(アップロード?)時に入力させる形にしないと、EPUBファイルだけ納本されても困ってしまいそう。
逆に、「どこで頒布しているのか?」という情報(電子書店の商品紹介ページURL)の入力を必須にすれば、精度の高い(そして有用性も高い)所在情報サービスとして活用されることになりそうです。
CA2011 – 動向レビュー:電子書籍を中心とした公貸権制度の2005年以降の国際動向 / 稲垣行子〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年12月20日)〉
諸外国の公共貸与権制度についての最新動向まとめ。イギリス、カナダ、デンマーク、ニュージーランドは、新たに電子書籍を公貸権の対象に導入、もしくは導入の検討をしているそうです。興味深いのは分配の対象について。フランスは出版者も対象なのですが、イギリス、カナダ、デンマークは出版者が対象外。もし日本で導入を検討するとしたら、どういう扱いになるんだろうか?
なお、日本の動向のところでは「権利者への経済的補償を行う動きが見られる」ということで、図書館資料メール送信等の補償金制度にも触れられています。私はちょうど一年前に、この補償金制度は「公共貸与権の導入への足がかりになるかもしれない」と書いたのですが、この動向レビューの著者も同じことを想起したのではないでしょうか。
2021年 モバイルニュースアプリ市場動向調査〈ICT総研(2021年12月20日)〉
ニュースアプリ・ニュースサイトの利用動向調査。利用者数は2021年度9371万人。うち、ニュースサイトが3497万人、モバイルニュースアプリが5874万人。モバイルが約1.7倍と差を広げています。まあ、端末の普及率に比例しますよね。
面白いのは、ニュースアプリごとの利用率だけでなく「掲載媒体数」や「掲載記事数」まで調べている点。間口の広い「スマートニュース」に対し、他社はぐっと絞っている感があります。「Googleニュース」が少ないのは意外。利用率では、ポータル系が圧倒的に強く、新聞系アプリは10%以下という状態。
ニュースデリバリーのインフラは、紙の時代は新聞販売店が戸別配達制度で支えてきたわけですが、モバイルの時代は完全にニュースアグリゲーターに持っていかれている感があります。読売新聞がいまだにオンライン単独の有料会員制度をやっていないのは、販売店網への配慮があるからだと想像しているのですが、そうこうしているうちに取り返しのつかない事態に至ってしまいそうな気も。
TOPS OF 2021: DIGITAL IN JAPAN~ニールセン2021年日本のインターネットサービス利用者数/利用時間ランキングを発表~〈ニールセン デジタル株式会社のプレスリリース(2021年12月21日)〉
毎年恒例、ニールセンによる日本のインターネットサービス利用者数と利用時間のランキングです。昨年までは「スマートフォンアプリ」と「トータル(PCとモバイルの重複を除く)」が別になっていたのですが、今年は「トータル」のみとなっています。
電子出版アワード2021(第15回)ジャンル賞決定、大賞は「ビジョン2021-2025」!〈JEPA|日本電子出版協会(2021年12月22日)〉
今年も選考委員としてお手伝いしました。2年連続で国立国会図書館が大賞受賞というのは驚きですが、JEPA会員社による投票の結果なので、忖度などではありません。けっこう接戦だったようですね。ジャンル賞は東洋経済新報社、カカオピッコマ、メディアドゥ、ボイジャーが受賞しています。おめでとうございます。
「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」の公表について〈国立国会図書館―National Diet Library(2021年12月22日)〉
2021年5月に成立した改正著作権法により入手困難資料の個人送信が行われることになりますが、それに先立ち、関係者協議会との合意文書が公表されました。サービス開始は2022年5月から。当面は閲覧のみで、印刷は2023年1月を目処に開始予定。
利用対象者は、日本国内に居住している「個人の登録利用者」です。「インターネット限定登録利用者」は利用できません。新規登録、アップグレードの手続きは、郵送でもできます。つまり、登録さえすれば日本全国どこからでも利用可能です。
個人的には、送信対象となる資料の範囲が、資料デジタル化及び利用に係る関係者協議会「国立国会図書館のデジタル化資料の図書館等への限定送信に関する合意事項(PDF)」(平成24年国図電1212041号)から変わらなくてホッとしています。この機に範囲を狭められてしまうことを危惧していました。この合意事項のままなら、マンガ、商業出版社の雑誌、出版済みの博論は、これまで通り除外(取り扱い留保)です。海外在住者への提供は次の課題ですね。
公益財団法人文字・活字文化推進機構ら、「学校図書館図書等の整備・拡充に関する要望」を総務大臣と文部科学大臣に提出〈カレントアウェアネス・ポータル(2021年12月23日)〉
公益財団法人文字・活字文化推進機構と全国学校図書館協議会(全国SLA)、日本新聞協会、学校図書館整備推進会議による連名の要望です。学校図書館蔵書の充実、新聞配備の拡充、学校司書配置の促進、あらゆる子どもが利用できる学校図書館の実現の4項目を要求しています。
「紙の」という記述は無いので、デジタルでも構わないということでしょうか。「あらゆる子どもが利用できる」という要望には「視覚障害者等が利用できる書籍の充実」とあり、アクセシブルな電子書籍が望まれているように読めます。JEPAが提言している「学校デジタル図書館」のような形なら、地域格差も是正できて良いと思うのですけどね。
子どもの読書に電子化の波 「学校向け電子書籍サブスク」次々〈朝日新聞デジタル(2021年12月24日)〉
そのいっぽうで、民間によるサービス展開はすでに一歩も二歩も先を行っている感。ポプラ社の読み放題サービス「Yomokka!(よもっか!)」や、エスペラントシステム「読書館」、「School e-Library」などの事例が紹介されています。
シリコンバレー101(905) 電子書籍誕生から50年、コロナ禍を経て公立図書館がデジタル図書館へ〈TECH+(2021年12月24日)〉
1971年に始まった「Project Gutenberg」を話のマクラに、普及した電子図書館(電子書籍貸出サービス)の費用負担が重荷になり始めているアメリカの現状について語られています。実はデジタル出版50周年のメモリアルイヤーなんですよね。
経済
出版業界2021重大ニュース 異例の大型提携相次ぐ〈文化通信デジタル(2021年12月23日)〉
業界の重大ニュース。トーハンとメディアドゥの資本業務提携と事業領域の拡大、過去最大となったコミック市場、大手取次の出版流通改革などが取り上げられています。今年もいろいろありましたね。来年はどんな年になるでしょうか。
書籍販売、15年ぶりに増加 出版科学研究所調査、児童書好調〈共同通信(2021年12月24日)〉
出版科学研究所から、2021年の着地見込みが公表。紙は前年比約1%減の1兆2100億円台になるとのこと。デジタルも合わせたら、3年連続のプラスになりそうですね。紙の書籍が2%増というのがちょっと意外。15年ぶりとのことです。
変わりゆく出版モデル 流通改革や動画発ヒット〈日本経済新聞(2021年12月25日)〉
上記の発表を受けた年間総括。書籍の増加については「大型書店の休業が相次いだ昨年4月の反動増があり単純な比較は難しい」という記述が。なるほど確かにと思い、コロナ禍前一昨年の2019年1~11月期を調べてみたら、6214億円でした。2021年1~11月期は6263億円ですから、一昨年との比較でも増加ですね。なるほど、なるほど?
HON.jp News Casting
12月26日の HON.jp News Casting は2時間の特番、ゲストはITジャーナリストの西田宗千佳さんでした。前半はこちらのアーカイブでどなたでもご覧いただけます。
後半の部を視聴したい方は、Peatixでチケットをお求めください(1月15日AM6時まで)
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
いよいよ2021年も大詰め。新年の準備はお済みでしょうか? 今年の本稿はこれが最後。年明けは1月10日からの配信です。その前に、毎年恒例の振り返りと年始の予想記事があります。まだ書けてないけど(鷹野)