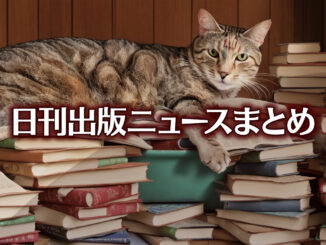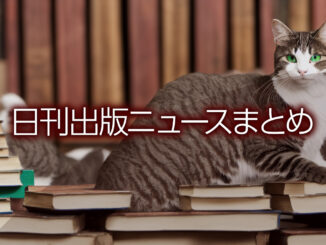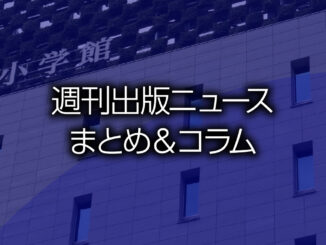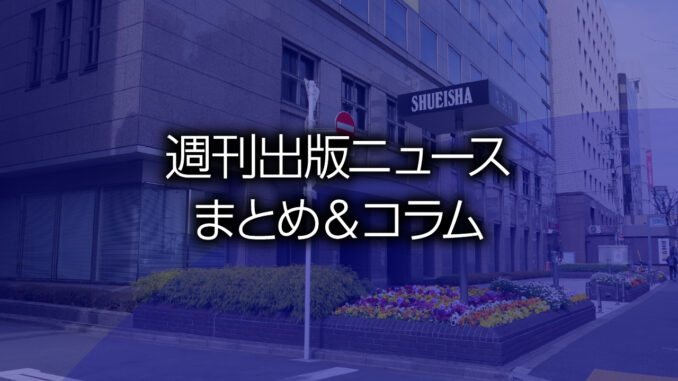
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2023年3月19日~25日は「自民党が和製ChatGPT構想?」「Internet Archiveが敗訴」「Adobe、Microsoftからも画像生成AI」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 「AIが描いた絵」は誰のもの?~テクノロジーと著作権の新たな関係を考える | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン〈imidas – イミダス(2023年3月13日)〉
- 「そんなメールがきたのは初めて」 東大院生も驚いたChatGPTの“効果” 池谷裕二教授の活用法〈AERA〉〈AERA dot.(2023年3月16日)〉
- CA2035 – 公共図書館における電子雑誌提供サービス / 間部 豊〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
- CA2038 – 動向レビュー:図書館の所蔵又は貸出が出版物の売上に与える影響に関する研究動向 / 貫名貴洋〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
- CA2037 – 図書館向けデジタル化資料送信サービスへの北米からの参加の現状と今後への期待 / マルラ俊江, 原田剛志〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
日本のAI政策、「和製ChatGPT」の開発にこだわるべきか否か–自民党が提言へ〈CNET Japan(2023年3月23日)〉
自由民主党のデジタル社会推進本部が、AI関連の政策提言をまとめる「AIホワイトペーパー」の骨子を公開したそうです。先日発表されたGPT-4でも、英語に比べると日本語はまだレベルが低いようなので、個人的には、もっと日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)があってもいいと思います。ただ、たとえば国立国会図書館がまだ一般公開していないOCRデータの利用には、政治的判断が必要になるだろうな……なんてことを考えていました。
ところが改めて調べてみたら、令和3年(2021年)度の時点ですでに、一般公開されていないデータでも国立国会図書館と協議すれば「著作権法上認められた範囲内での利用(著作権法第30条の4の規定による機械学習目的など)に限り」提供可能と書いてありました。なんだ、政治判断要らないのか。それなら、GPTやBardなどいま話題のAIの学習目的にも、もうすでに使われているかもしれません。
ところで、CNETの記事に「公開した」とある「AIホワイトペーパー」を探してみたのですが、残念ながらどこにあるのかわかりませんでした。完全一致で”AIホワイトペーパー”だと、この記事のほか、さまざまな企業が出している別モノや欧州委員会の規制案(もちろん別モノ)などが引っかかってくるばかりで、自民党をキーワードに入れるとこの記事だけになってしまうという。ぐぬぬ。
「ChatGPT」後の日本語AI開発、web3産業を支える環境整備など、自民党デジタル社会推進本部が活動を説明〈INTERNET Watch(2023年3月24日)〉
で、こちらの記事を見たら、「デジタルセキュリティ」「web3」「AIの進化と実装」「デジタル人材育成」「防災DX」の5つの課題についてプロジェクトチームが設置されたとあります。つまり、CNETが報じているのは、そのうち「AIの進化と実装」についてのみである、と。なるほど。こちらにはPDFからのスクリーンショットと思しき画像もあるので、説明会に参加したメディアには資料のデータが配布された(=公開)のかもしれません。
The Internet Archive has lost its first fight to scan and lend e-books like a library〈The Verge(2023年3月25日)〉
本欄でも何度かお伝えしてきた、Internet Archiveと大手出版社のControlled Digital Lending(CDL)を巡る訴訟の地裁判決が出ました。フェアユースには当たらないという判断で、Internet Archiveの敗訴に。以前私は、「CDLは合法だけどNEL(National Emergency Library)は違法、あたりが落としどころでしょうか?」と予想していたのですが、外してしまいました。
ただ、これは下級審。まだ決着はついていません。Internet Archiveからは「The Fight Continues(戦いは続く)」というブログ記事が出ており、上訴する予定との意思表明がなされています。長い戦いになりそうです。私は非常によくお世話になっている(とくにWayback Machine)身なので、毎月少しずつですが寄付することにしました。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
「AIが描いた絵」は誰のもの?~テクノロジーと著作権の新たな関係を考える | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン〈imidas – イミダス(2023年3月13日)〉
弁護士・福井健策氏による解説。AI生成物には著作権が「ない」という整理は、私の認識通りで安心しました。柿沼弁護士の言う「実は著作権が発生しないAI生成物の方が少数なのかもしれません」という見解は、かなり先鋭的なのかもしれません。ただ、実務を考えたとき問題になるのは、福井氏も指摘している「AIが生成したのか、人が創作したのかを見分けるのは困難」というところでしょう。
AI生成画像は、よく描けているように見えても、細かなところで不自然なところがあったりしますので、まだ現時点のレベルなら判別できないこともないようにも思えます。しかし、AI生成文章の判別は至難の業でしょう。検出ツールの信頼性は低く、100%人間の書いた文章が「疑わしい」とか言われる場合もあります。きっちり推敲した誤字脱字のない文章だと、整い過ぎてて逆に不自然とか言われかねないという。
もっとも、ちゃんと書けていて誤りもとくにないなら、AI生成でも人の創作でも構わない、という考え方も可能です。AIがしれっと嘘をつくハルシネーション(幻覚)問題については、人間の書いた文章でも嘘や誤りは存在するわけで。それを思えば、レポートや論文を受け取る先生や原稿を受け取る編集者も、いままでとやることは変わらないとも言えます。
ただ、たとえば学術出版倫理に関するサポートを行っている出版倫理委員会(COPE)からは「AIツールを論文の著者としては認められない」という見解が表明されていたりします。そのスタンスは理解できますが、じゃあ実際に編集者が論文を受け取ったとき、それがAI生成を一部でも使っているかどうかを見抜けるか? というと……おそらく無理じゃないかなあ。
「そんなメールがきたのは初めて」 東大院生も驚いたChatGPTの“効果” 池谷裕二教授の活用法〈AERA〉〈AERA dot.(2023年3月16日)〉
試験問題をChatGPTに作成させ、提案された中から4つ選んで出題したら単位を落とす学生が2倍に増え「例年と出題傾向が違いますが」というメールが届いたとのこと。単位救済措置のレポートで「ChatGPTの書いた解説文の間違いを説明せよ」というのは、私が以前考えた「AIのついた嘘を発見し、根拠とともにレポートしてください」とほぼ同じでニヤリ。やはり、「使うな」と言うほうが無理がありますよね。
CA2035 – 公共図書館における電子雑誌提供サービス / 間部 豊〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
CA2038 – 動向レビュー:図書館の所蔵又は貸出が出版物の売上に与える影響に関する研究動向 / 貫名貴洋〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
CA2037 – 図書館向けデジタル化資料送信サービスへの北米からの参加の現状と今後への期待 / マルラ俊江, 原田剛志〈カレントアウェアネス・ポータル(2023年3月20日)〉
今回のカレントアウェアネスは(私にとって)豊作でした。気になった3本をまとめて紹介しておきます。電子雑誌の法人向けプランは、まだ公共図書館にあまり入っていないんですね……dマガジン for Bizが7件というのはけっこう衝撃的でした。図書館貸出が出版物売上に与える影響は「研究動向」なので、なにか結論が出ているわけではありません(影響有/無の両方紹介されている)。念のため。海外向け図書館送信が広がらないのは、国内向けでも指摘されていた点に加え「複写サービスを提供できない」ことの影響が大きいようです。国内市場は人口減で小さくなる一方ですから、海外の方々に日本文化をたっぷり研究してもらって、良い顧客が世界で育ってくれることを期待したほうが良いと思うのですけどね。
経済
書籍「ゲームの歴史」にツッコミ相次ぐ 「内容が事実と異なる」との声 講談社は「確認中」〈ITmedia NEWS(2023年3月16日)〉
“事実誤認”指摘の「ゲームの歴史」がAmazonで購入不可に〈ケータイ Watch(2023年3月20日)〉
書籍「ゲームの歴史」、“事実誤認”の指摘を受け講談社がコメントを発表〈GAME Watch(2023年3月20日)〉
ああ……とうとう、という感じ。年末くらいからゲーム業界関係者が何人も事実誤認を指摘し続けていた『ゲームの歴史』(岩崎夏海・稲田豊史 著)が、3月16日にITmediaで「ツッコミ相次ぐ」と報じられました。翌日には版元の講談社青い鳥文庫から「現在、編集部と著者で全体の確認作業を行っております」というお知らせが出て、その後、ネット書店系では徐々に紙も電子も注文できない状態となっていきました。
私は、騒がれているのは少し前から把握していましたが、ネガティブな話題なので成り行きを見守っていました。しかし、ついにニュースとなり大きな動きもあったことから、ピックアップしました。アマゾンレビューで☆1つが80%超って、なかなか見ないように思います。

昨年、インプレス『いちばんやさしいWeb3の教本』(田上智裕 著)が発売からほどなくして販売終了、返品・返金対応となったことを思い出しました。インプレスの対応が迅速だったのに比べると、今回の講談社は少しのんびりしている印象を受けます。発売から4カ月経ってますし、けっこう図書館にも入ってるようです。全3巻でそこそこ値が張るので、私のコレクションを増やすのは止めました。
もう一つ思い出した事例は、幻冬舎『日本国紀』(百田尚樹 著・2018年)です。こちらも当時、相当な数のツッコミが入れられていました。ところが売れていたこともあってか販売は止まらず、結局、初版から9刷までに50カ所以上の修正が行われたという凄まじさ。ただ、『日本国紀』って実はC0095(文庫はC0195)「日本文学、評論、随筆、その他」なのですよね。版元自身が歴史書としては扱っていないという。
ちなみに『ゲームの歴史』はC0020(歴史総記)です。それもあってか、放っておくとここに書かれたことが後の世に「正史」とされてしまう恐れがあると、ゲーム業界関係者のツッコミが止むことなく続いていた感があります。典型的な「人間の書いた文章でも嘘や誤りは存在する」事例と言っていいでしょう。とほほ。
対話型AIの登場でグーグルら巨大ITとニュースメディアの関係はどう変わるか〈CNET Japan(2023年3月22日)〉
GoogleやFacebookがニュースメディアから利用料を要求され続けてきたのと同様、ジェネレーティブAIにも矛先が向けられることになりそうです。すでに、News Corpは戦う構えを見せているとのこと。GoogleやFacebookにはユーザーの流入効果があったわけですが(それでも批判されていた)、AIの学習利用は無断で利用されたうえ見返りがほぼないわけですからね。
Bing Chatには出典リンクが出ますが、前にも書いたように、あまりクリックされる気がしません。Google AnalyticsやBing Webmaster Toolsを見ても、流入量は以前とまったく変わってません。まあ、うちは運用型広告をやめたので、流入量はもうあまり気にしてないのですが。一般メディアはそういうわけにはいかないですもんね。
A new digital manga service called K Manga is launching soon〈Good e-Reader(2023年3月22日)〉
講談社直営のアメリカ向け新マンガアプリ。プレスリリースには「講談社のマンガ編集部が直接運営するサービス」とあり、集英社の「MANGA Plus by SHUEISHA」という先行事例を大いに参考にしたのだろうな、という印象を受けました。いまのところ日本のメディアで取り上げたところはないようですが、当事者であるアメリカのメディアは敏感な反応を見せています。サービス開始は5月10日です。
技術
Adobeから画像生成AI「Firefly」登場。権利関係もクリア〈PC Watch(2023年3月21日)〉
アドビもジェネレーティブAIの開発競争に参入。まだベータ版としての発表ですが、今後、クリエイター御用達ツールの「Photoshop」「Illustrator」「Premiere Pro」などにも組み込まれていく予定とのこと。MicrosoftやGoogleのオフィス系ソフトへの組み込みとは違った意味で大きな影響がありそうです。
「権利関係もクリア」という点には少し補足が必要でしょう。日本の著作権法(第30条の4)とは異なり、アメリカの著作権法では機械学習目的だからと無断利用が許されているわけではない、という前提があります。無断利用で訴えられた「Stable Diffusion」や「Midjourney」がフェアユースと判断されるかどうかは、今後の裁判次第なのですよね。
そのため、「Adobe Stock」にアップロードされた時点で規約に同意したことになるコンテンツだけを学習に使っている、というのが日本以外では差別化になる、と。とはいえ「Adobe Stock」もCGM(Consumer Generated Media)の一種ですから、権利関係やばそうなのがアップロードされてるぞ! クリアじゃないぞ! とツッコミを入れられているのを散見します。
しかし、少なくとも、生成画像にストックフォトのウォーターマークが出ちゃうようなAIとはわけが違う、とは言えそうです。さすがにアドビの立場でそれをやったら、製品ボイコットされちゃいそう。昨年、セルシスが「CLIP STUDIO PAINT(クリスタ)」に「Stable Diffusion」の試験実装を発表したら猛反発され、画像生成AI機能を搭載しない方針の発表を余儀なくされた事例にも学んでいるのでは。
Bingチャットに画像生成AIが実装。OpenAIのDALL-Eを活用〈PC Watch(2023年3月22日)〉
Adobeの発表直後に、Microsoft「Bing」に画像生成AIが「実装」されました。Bing Chatのプレビューに参加していれば、すぐに使える状態でリリースされています。私もすぐに試してみましたが、「Stable Diffusion」では苦戦している「へそ天(belly trap)猫」をあっさり出力できてしまいました。簡単に、安定した出力が得られる、という印象です。少々拍子抜けするくらい。そのぶん意外性や面白みに欠けるかも?

お知らせ
デジタル化の荒波を乗り越える道しるべに。年鑑「出版ニュースまとめ&コラム」の2019年版が直営ショップで予約可能になりました。3月31日刊行予定です。詳細はこちら。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
ソメイヨシノがずいぶん早く開花しました。日本気象株式会社によると、東京では3月22日に満開が観測されたそうです。平年より9日早いとのこと。ところがしばらく雨の日が続いていて、すでにけっこう散り始めています。はかない。(鷹野)