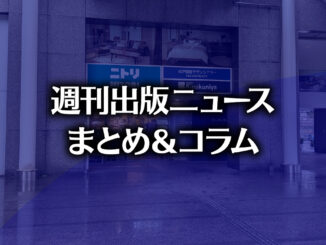《この記事を読むのに必要な時間は約 17 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年4月8日に配信した第26回では、講談社とYahoo!ニュースの契約解除の噂話と、Amazon「Kindle」のAI要約機能の話題について語っています。
【目次】
#26 パブリッシャーとプラットフォーマー
こんにちは、鷹野です。今回は「パブリッシャーとプラットフォーマー」をテーマにお話したいと思います。なんで「出版社」じゃなくて「パブリッシャー」か? というとですね。「出版社」を英語で言うと Publisher ですけど、私は「出版社」と Publisherってイコールでは結べないと思ってるんですね。
日本語で「出版社」というと、そのニュアンスってちょっと狭いんですよね。Publisher より。「出版社」といったら、まあ「新聞社」とか「通信社」とか「テレビ局」なんかは、含まれないじゃないですか。含まれないというか、含まないと考える人が多いんじゃないかなと思うんですね。
もっというと「ウェブメディア」もけっこう除外されがちじゃないかなと。まあこれは人によるかもしれませんけどね。紙媒体に馴染みが深い人なら、「出版社」がやってる「ウェブメディア」を思い浮かべるかもしれません。
でも、たとえばうちみたいに、「HON.jp News Blog」みたいに、紙媒体はやっていない。ボーンデジタルで記事を配信している。そういうところってけっこう多いですよね。多いんですけど、わりと存在を忘れられるんですよね。こういう分類のとき。というか、無視されてるのかな、とか思うようなところもあります。
紙媒体が休刊になって、ウェブだけ続けてるっていうメディアもけっこうありますけど。紙媒体が休刊になるとね、なんかもう存在してないのも同然みたいな扱いをする人もいたりして。もちろん、当事者とかメディア関係者ならそんなことないはずですけど。
一般の人から見たときに、という話です。一般の人からは、ウェブだけだとちょっと縁が遠くなってしまうのかな、という感じがします。
通信品位法230条やプロバイダ責任制限法での分類
で、今回のテーマ「パブリッシャーとプラットフォーマー」、その「プラットフォーマー」のほうでは、「新聞社」「通信社」「テレビ局」「出版社」「ウェブメディア」――このへんとか、あんまり区別なく扱ってるんですよね。「プラットフォーマー」はあんまり区別していない。
たとえば「Yahoo!ニュース」に記事を提供しているところは「ニュース提供社」という呼ばれ方をしています1ニュース提供社 – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/media。でも世の中には「ニュース提供社」、その「Yahoo!ニュース」にある「Yahoo!ニュース提供社」には含まれない「出版社」もたくさんあるわけですよ。雑誌ではなく書籍を中心とした「出版社」ってのもたくさんあります。
で、私が「パブリッシャー」ってなんで言ってるかというと、「パブリッシャー」には「新聞社」も「通信社」も「テレビ局」も「“雑誌の”出版社」も「“書籍の”出版社」も「ウェブメディア」も含まれる。そのへんがぜんぶ包摂するようなニュアンスを「パブリッシャー」に含めてるんですね。
これに対し「コンテンツプロバイダー」という言葉もありますね。ありますけど、これだと「パブリッシャー」だけでなく「プラットフォーマー」も含まれちゃうんですよ。両方含まれちゃう。ポータルサイトを運営しているようなところも「コンテンツプロバイダー」って言いますから。ちょっと広すぎちゃう。
要するに、自前でコンテンツを制作して配信しているところが「パブリッシャー」。それに対し、自前ではコンテンツをあまり制作してなくて、ほとんどがいろんな「パブリッシャー」からコンテンツ提供を受けてる、そういうところを「プラットフォーマー」と、そういうふうに呼び分けて区別するようにしています。
これね、私独自の区別ってわけでもなくて、もとはアメリカの通信品位法230条ってやつです。自前でコンテンツを制作配信してる「パブリッシャー」ってのは、その発信した情報に責任を負うわけですけど、そうじゃない「プラットフォーマー」は情報発信の場を提供してるだけなんで、なんかあったときすぐ削除すれば免責されるよ、っていうね。そういう法律があるわけですよ。
日本だとプロバイダ責任制限法ってやつです。最近法改正されて情報流通プラットフォーム対処法に名前が変わりましたけど。要は、「パブリッシャー」は情報の責任を負うけど、「プラットフォーマー」は場を提供してるだけだから免責される。自前でコンテンツを制作してるのが「パブリッシャー」。場を提供しているだけなのが「プラットフォーマー」。
で、ニュース系の「プラットフォーマー」って別の呼ばれ方もしてて、「ニュースアグリゲーター」と呼ばれたりもしてます。具体的には、たとえば「Yahoo!ニュース」「LINE NEWS」「Googleニュース」「Microsoft MSNニュース」「SmartNews」「Gunosy」「NTT docomo dメニューニュース」「au Webポータルニュース」とか、まあ、いろんなところがありますよね。
Yahoo!ニュースの記事をすべてヤフーの人が書いてるという誤解
ちょっと話を混ぜっ返すようですけど、ちょっとややこしい話ですけど、こういう「プラットフォーマー」の中には、自社でコンテンツ制作しているところもあります。「プラットフォーマー兼パブリッシャー」というね。
たとえば「Yahoo!ニュース」には「Yahoo!ニュース オリジナル」というコーナーがあって2オリジナル – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/original/。ヤフーが独自制作してる記事と、コンテンツパートナーと共同企画して配信しているコンテンツというのが、「Yahoo!ニュース オリジナル」という名前がついて配信されています。
でも、その「Yahoo!ニュース オリジナル」の記事、本数は少ないんですよ。「Yahoo!ニュース」全体の9割くらいは、ヤフーが制作には直接関わっていない記事と言われています。9割。9割は「ニュース提供社」つまり「パブリッシャー」が制作している記事。ほとんどがそういう「パブリッシャー」の記事ということですね。
私、大学の講義で毎年この話をしてるんですけど、講義のあとにコメントシートを見るとですね、「Yahoo!ニュースの記事はぜんぶヤフーの人が書いてると思ってました!」なんて書いてくる学生もね、少なからずいたりするんですよね。笑っちゃうんですけど……いや、笑えないか、むしろ。
「ニュース提供社」からの記事って、必ず冒頭にその「ニュース提供社」の名前とかロゴとかね、必ず入ってるんですよ。「Yahoo!ニュース」って。それがぜんぜん視界に入ってない、ということですよ。笑えないですよね。ぜんぜん視界に入ってない。
逆に言うと、「Yahoo!ニュース」なんかで配信されてる記事って、ぜんぶ同じフォーマットに落とし込まれちゃってますから、どこから提供されてる記事ってのを意識しづらい。そんな状態になっているってのも言えるんでしょうね。
もちろん「プラットフォーマー」も悪意があってそうしているわけではなくて、ユーザーが利用しやすいように、そう考えて仕組みを作った。そういうふうに、利用しやすいようにって考えて仕組みをつくると、こうなっちゃうということだと思うんですよね。
単純に考えると、記事ごとにフォーマット違ってたら、読みにくいですからね。レイアウトとかフォントもバラバラで配信されてる。あっちの記事とこっちの記事と全然見た目が違う。そんなの、読みにくくてしょうがないですよ。
だから必然的にその媒体独自の特徴みたいなものが削ぎ落とされちゃう。それが「プラットフォーマー」、「ニュースアグリゲーター」で配信されてる記事ということになるでしょうね。
パブリッシャーとプラットフォーマーには確執がある
で、今回のテーマは「パブリッシャーとプラットフォーマー」なんですけど、自前でコンテンツを制作している「パブリッシャー」と、その「パブリッシャー」のコンテンツを束ねて配信している「プラットフォーマー」って、基本的にはビジネスパートナーなんですよね。
パートナーなんですけど、そこには確執があるんですよ。確執が。争いと言ったほうがいいかな。要するに「パブリッシャー」って、自分のところで制作したコンテンツが「プラットフォーマー」に安く買い叩かれてる、という意識があるわけです。
以前、財界展望新社というところが出してる経済情報誌「ZAITEN(ザイテン)」で「ヤフー『ニュース支配』横暴の果て」という特集が組まれたことがあるんですね。2022年5月号の「ZAITEN」です。
その「ZAITEN」の特集によると、「Yahoo!ニュース」にコンテンツを提供すると、ページビューに応じた配信料が「パブリッシャー」に支払われると。「Yahoo!ニュース」は基本的に広告モデルですから、広告収入の一部が「パブリッシャー」に還元されるというわけです。
で、「ZAITEN」によると、その配信料が「パブリッシャー」によってけっこう格差があるそうなんですよ。1ページビューあたりで換算すると、新聞の全国紙クラスで0.21円。それに次ぐ有力紙だと0.1円。地方紙とか週刊誌系だと0.025円。けっこう差がありますね。
仮にめっちゃ読まれて100万ページビューいったとします。100万ページビュー換算すると、全国紙なら21万円ですね。それに次ぐ有力紙で10万円。これが地方紙とか週刊誌系だと2万5000円ですよ。うっひょーって感じですよね。
実は「ZAITEN」でこの特集が出る直前くらいに「Yahoo!ニュース」から、ページビューに応じた配信料とは別に、記事末尾に設置してある「記事リアクションボタン」が押された回数を加味しますってお知らせがあったんですね3ユーザーによる記事へのフィードバックを媒体各社へ還元──Yahoo!ニュースの「記事リアクションボタン」開発の舞台裏〈news HACK by Yahoo!ニュース(2022年2月15日)〉
https://news.yahoo.co.jp/newshack/inside/reaction.html。
だから、いまはもうちょっと違った形になってるはずです。当時ヤフーからはそのお知らせで「ページビューだけでは測れない質の高いコンテンツを支援します」なんていうコメントがありました。2022年です。
これで「パブリッシャー」の不満は多少は軽くなったのかと思ってたら、その後、2023年に日本新聞協会から「記事対価 算出基準説明を」なんて声明が出てるんですよ4記事対価 算出基準説明を IT大手に協議求める 公正取引委報告書巡り新聞協会見解〈日本新聞協会(2023年10月5日)〉
https://www.pressnet.or.jp/news/headline/231005_15170.html。まだまだ確執は残ってる感じがぷんぷん匂ってきますね。
―― この続きは ――
《残り約5000文字》