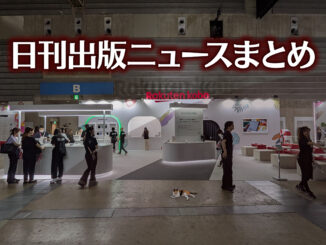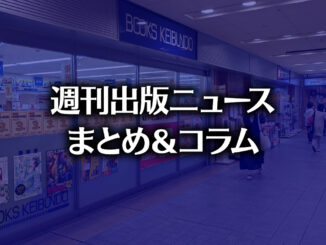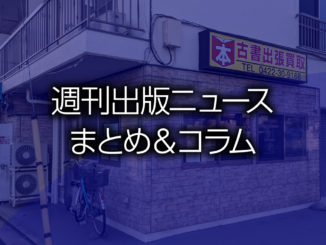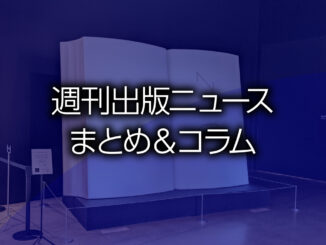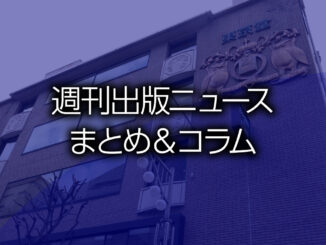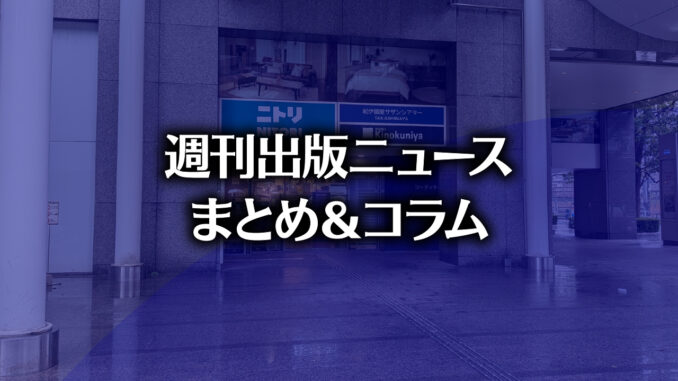
《この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です(1分600字計算)》
2025年8月10日~23日は「デンマーク、読書推進で書籍の消費税率を0%に」「円建てステーブルコインで金融検閲問題解消?」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
今回はお盆休みを挟んで2週間分の大増量版となります。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 生成AI無断学習は記事「ただ乗り」 言い回し同じ場合も 読売の米社提訴、国内大手で初〈産経ニュース(2025年8月14日)〉
- Publishers, Authors Win Ruling Against Florida Book-Banning Law(フロリダ州の書籍禁止法案「ハウスビル1069」に対し、出版社と著者が新たな判決を勝ち取る)〈Publishing Perspectives(2025年8月15日)〉
- 国内初の円建てステーブルコイン、金融庁承認へ JPYCが秋にも発行〈日本経済新聞(2025年8月17日)〉
- 広告ブロッカーはページを改変するから著作権侵害の疑い? ドイツ最高裁が衝撃的判決、高裁での再審理へ【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2025年8月18日)〉
- デンマーク、読書促進のため書籍税を廃止へ〈AFPBB News(2025年8月20日)〉
- 【提訴】日本でも大手メディアと生成AIの戦いが始まった〈NewsPicks(2025年8月22日)〉
- 社会
- タレントなりすまし情報窃取、X社がアカウント開示 「嵐」や「Snow Man」〈日本経済新聞(2025年8月14日)〉
- 週刊新潮のコラム巡り、新潮社が回答 「批判を受ける事態」謝罪〈朝日新聞(2025年8月15日)〉
- 閉鎖の続くブログはオワコンなのか 惜しむ声、でも保存議論は進まず〈朝日新聞(2025年8月16日)〉
- 生成AIの成果物に責任を持ってくれ〈qsona(2025年8月17日)〉
- 発行人が一堂に会して、自社本の魅力をアピールする、独立出版者エキスポ(IndependentPublishers EXPO)を開催します。〈株式会社QANDOのプレスリリース(2025年8月18日)〉
- 「信頼できる情報源はない」と感じる若者。これからのメディアはどうあるべきか?〈ウェブ電通報(2025年8月20日)〉
- Study Finds 20-Year Drop in Reading for Pleasure(研究によると、娯楽目的の読書は20年間で減少している)〈Publishers Weekly(2025年8月21日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
ご支援のお願い
チームで行う創作と出版のワークショップ「NovelJam 2025」東京・札幌・沖縄の三拠点同時開催に向けクラウドファンディングを実施中! ゼロから作品を生み出すクリエイターの発掘育成の活動をぜひご支援ください。
新コーナー「ぽっとら」(Podcast Transcription)を更新しました
生成AIの普及がウェブや本にもたらす影響について、わりと牧歌的な未来予想〈HON.jp News Blog(2025年8月11日)〉
私はこれまで繰り返し「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側になる」と言い続けてきましたが、実はそのことに悲観はしていません。むしろ「価値ある情報に適切な対価を払うのは当然」という世の中になって欲しいと考えています。だからこの回も「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側になる」と言いながら「楽観的」「牧歌的」な予想だとしています。
パブリッシャーは、そろそろプラットフォーマーに依存しない骨太なメディアになるべきだ〈HON.jp News Blog(2025年8月12日)〉
講談社がヤフーニュースに契約切られたという噂(あくまで噂)の件、結局、いま調べてみても報じたメディアは見つけられませんでした。有料記事だけでなく無料記事の配信も止まったのは確認できていますが「切られた」のか「切った」のかは判然としません。まあ正直、どっちでもいいんですけど。いずれにしても、巨大プラットフォームになるべく依存しないようにしたい、という結論は変わらないです。
自分の作品が勝手に利用される(かもしれない)けど利用停止もできちゃう制度〈HON.jp News Blog(2025年8月13日)〉
来年から始まる「未管理著作物裁定制度」について、4月の収録時点でわかっていることを整理・解説した回です。現時点でもあまり状況は変わっていません。あえて本編では言わなかった(書かなかった)のですが、連絡がつかないフリをして裁定後に名乗り出て利用停止を命じるみたいな地雷を仕掛ける人が出てくる可能性があると思ってます。利用する側としても怖い制度。
政治
生成AI無断学習は記事「ただ乗り」 言い回し同じ場合も 読売の米社提訴、国内大手で初〈産経ニュース(2025年8月14日)〉
後半に上野達弘氏(早稲田大教授)のコメントがあります。やはり、軽微利用(著作権法第47条の5)がどう判断されるか? ですよね。確かに、学習段階の30条の4も論点にはなり得るとは思うのですけど、そもそもAI企業側が新規記事を学習しているかどうかが不確かなので、それを立証することから始めなきゃいけない点が難だと思っています。立証義務は原告側にあるはずなので。
Publishers, Authors Win Ruling Against Florida Book-Banning Law(フロリダ州の書籍禁止法案「ハウスビル1069」に対し、出版社と著者が新たな判決を勝ち取る)〈Publishing Perspectives(2025年8月15日)〉
Freedom to Read Advocates Cheer Decision in ‘PRH v. Gibson’(読書の自由を擁護する人々が“PRH対ギブソン”の判決を歓迎)〈Publishers Weekly(2025年8月15日)〉
A federal judge on Wednesday (August 13) struck down provisions of a Florida law that’s been used to remove hundreds of books from public school libraries since it was enacted in 2023.(連邦判事は水曜日(8月13日)、2023年に施行されて以来、公立学校の図書館から数百冊の本を撤去するために使われてきたフロリダ州法の条項を無効とした)
ここ数年、学校図書館蔵書に対し行われてきた検閲の根拠法が、憲法違反で無効と判断されました。これは大きい。しかしまだ連邦地裁の判決であること、トランプ大統領から横やりが入ることが予想できることなどから、楽観はできません。いまのアメリカは、三権分立が機能するだろうか? という疑問が。
国内初の円建てステーブルコイン、金融庁承認へ JPYCが秋にも発行〈日本経済新聞(2025年8月17日)〉
この動きは要注目。ステーブルコインは相場が安定した(Stable)コインである点が特徴です。暗号資産が決済での利用に使われないのは、相場が不安定過ぎるからなのですよね。その問題点をステーブルコインはクリアしています。そして、この記事には書かれていませんが、現金と同じような匿名性も持っています。
ただし、暗号資産型ではなく、デジタルマネー類似型のステーブルコインが税務上どう扱われるかは、当局から具体的な指針がまだ出ていないようです。そこが明確になってくると、価格変動が大きくて使いづらい暗号資産を、ステーブルコインに替えるような動きも出てくるでしょう。
ステーブルコイン「JPYC」は金融検閲の突破口になり、経済活動の自由・表現の自由を守る!?〈あたらしい経済(2025年8月21日)〉
私は、ステーブルコインが普及すると「金融検閲」問題が解決できる可能性があると考えています。JPYC代表取締役の岡部典孝氏もX(旧Twitter)で「ステーブルコインが金融検閲を解決します!」と投稿していました。それがなぜか? を解説しているのがこの記事です。最大のポイントは、以下の引用箇所でしょう。
ステーブルコイン(電子決済手段)には、「加盟店」という概念はありません。クレジットカードやポイントのように、運営・発行している会社に承認を得る必要が無いのです。
現状、アクワイアラや決済代行事業者が過剰反応して加盟店を締め付けていることが「金融検閲」の原因であると推測されています。ステーブルコインならそういう中間事業者の存在をパスして、ストア側での実装だけで決済できるようになる、と私は認識しています。ただ、肝心のその実装が、そこそこハードルが高そうな気もしています。WooCommerceが対応したら、うちでもすぐ使いたい。
負の側面も予想しておきます。調子にのったストアが違法な取引をやってしまい、警察にいきなり踏み込まれて逮捕みたいな事件がいずれ起きることでしょう。現状は違法取引を行わないよう中間事業者がストアにブレーキをかけている(それが過剰になって検閲化している)わけですが、ステーブルコイン決済をストアが実装したらいきなり全責任をストアが負う形になります。
まあ、実店舗で扱ったらヤバイものはECでもヤバイし、決済手段も関係なくヤバイという話ではあります。大きな違いは越境取引。物理商品なら通関で止められますが、デジタルデータは簡単に国境を越えちゃいます。いけない事業者が違法なヤバイデータをこっそり取引する可能性があります。
それがバレて逮捕されちゃう事例が出てくる。すると、マスメディアが「ステーブルコインで闇取引」みたいな感じで殊更に負の側面を煽ってくる。そして、法規制が検討されることになる……という未来まで見えました。
広告ブロッカーはページを改変するから著作権侵害の疑い? ドイツ最高裁が衝撃的判決、高裁での再審理へ【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2025年8月18日)〉
仰天。まあ、差し戻し再審理ですから、まだ「著作権侵害が認められた」わけではありません。ただ、もし「広告ブロッカーはページを改変するから著作権侵害」というのが確定しちゃうと、むしろページ改変可能なブラウザの機能そのものが危ない、という話になりそうな気が。Safariの「気をそらす項目を非表示」とか、どうなるんだろう?
デンマーク、読書促進のため書籍税を廃止へ〈AFPBB News(2025年8月20日)〉
Denmark to abolish VAT on books in effort to get more people reading | Denmark(デンマーク、読書促進のため書籍へのVATを廃止へ)〈The Guardian(2025年8月20日)〉
“書籍税”というか“書籍への消費税”の話です。そしてまだ確定ではありません。The Guardianのほうが少しだけ詳しいです。このニュースを受け、恐らく日本でもまた、書籍・雑誌に軽減税率を適用しようみたいな話になりそう。ただ、検討が始まると必ずまた「有害図書をどうする?」という話になります。断言しておきます。要注意です。前回の反省を踏まえ、こんどはもっとアクロバティックなことをやってきそうな気がします。
ちなみに、フランスやイタリアの書籍軽減税率は、ポルノが除外されています。それは知っていたんですが、だれがどうやってポルノか否かを判定しているのか、少し調べた範囲ではよくわかりませんでした。どうやら税務当局っぽいのですが、表現の自由とは衝突しないのか。だれか詳細プリーズ。
【提訴】日本でも大手メディアと生成AIの戦いが始まった〈NewsPicks(2025年8月22日)〉
後半がペイウォールの向こう側だから読めていないのですが、フリーライドをメディアから批判され謝罪・補償することになったNewsPicksの編集部から、まるで他人事のように出てきた記事だと思うと大変味わい深い。ちゃんと「お前が言うか」とツッコミを入れておかねば。
社会
タレントなりすまし情報窃取、X社がアカウント開示 「嵐」や「Snow Man」〈日本経済新聞(2025年8月14日)〉
開示された発信者情報を分析したところ、約半数がバングラデシュに拠点があるとみられるものだった。
以前、Facebookで跋扈していた著名人なりすまし詐欺の犯人グループは大阪在住の日本人でしたが、こちらは半数が海外からの越境犯罪だったようです。2016年の米大統領選のとき、マケドニアの若者がFacebookを使ったフェイクニュース拡散で荒稼ぎしていたニュースを思い出しました。当時はまだ「日本語」が越境犯罪の障壁になっていましたが、いまなら機械翻訳で比較的容易に突破できちゃうでしょうからね。
週刊新潮のコラム巡り、新潮社が回答 「批判を受ける事態」謝罪〈朝日新聞(2025年8月15日)〉
新潮社は回答で「高山氏が言うところの真意が極めて伝わりづらいものとなっており、
あの反吐が出そうな文章の「真意」ねぇ……これでは収まらないでしょう。「新潮45」のときは文芸編集部が強く反発、社長が謝罪する事態になり、最終的には休刊(事実上の廃刊)に到ってしまったわけですが。
週刊新潮コラム「変見自在」終了へ 作家名指しし「日本名を使うな」〈朝日新聞(2025年8月19日)〉
と思っていたら、お盆明けの号で連載終了のお知らせ。「dマガジン」で確認してみましたが、本文で経緯や理由はとくに説明されておらず、欄外に「高山氏と編集部で協議の結果、本コラムは今回で終了することになりました。長年のご愛読ありがとうございました。(編集部)」とだけ記されていました。その最終回で高山氏はなぜか、朝日新聞をボロクソに叩いています。当の朝日新聞は、記事ではそのことに一言も触れていないあたりに矜持を感じました。
「コラムは新潮の思想の核心部分」 過去に批判呼んでも続いた連載〈朝日新聞(2025年8月20日)〉
別の社員は「このコラムは新潮の思想の核心部分でもある。うちの読者が望んでいるのはその部分だった」と語る。
新潮社社員のコメントとのこと。なんというか……言葉を失う。この箇所に引っかかっている(というか怒っている)方は、私以外にもけっこういることを確認しています。「新潮45」のときの経緯を思い返すと、新潮社って編集部の思想が雑誌と書籍でけっこう違うんでしょうね。雑誌側の思想とは、私は相容れないや。
閉鎖の続くブログはオワコンなのか 惜しむ声、でも保存議論は進まず〈朝日新聞(2025年8月16日)〉
これは「営利事業としてブログサービスを提供し続けること」の話なのでは。それに関しては、収益性が厳しくなっているのは間違いないでしょう。とくに広告収入に強く依存していた場合。元関係者が「オワコン」などと言いたくなるのもわかります。だけど、たとえばレンタルサーバーを借りてWordPressで運用してる勢とか、広告のない「note」が急成長しているあたりの話が、この記事では完全に無視されているのが気になります。
ちなみに、W3Techsのデータによると、日本語ウェブサイトのCMSはWordPressが83.1%を占めています。サービスとして上位のHatena Blogでも0.8%なので、WordPressの100分の1ということに……えっ? それはそれで違和感があるなと思い調べてみたら、このデータはドメイン単位の集計(We do not consider subdomains to be separate websites.)でした。サブドメインは集計していません。つまり、はてなブログ+独自ドメインのものだけカウントされています。これじゃ比較できないじゃんか!
生成AIの成果物に責任を持ってくれ〈qsona(2025年8月17日)〉
強く同意します。というか、私も以前からこういう行為は「文責を放棄している」と批判してました。AIにぶん投げて出てきた出力をコピペしてリプライって行動をよく見かけますが、これをやられるとけっこうカチンと来るんですよね。なんでだろう? と考えてみたら、それは要するに「内容に関する責任は負いません」という態度だから。「だって、ChatGPTがそう言ってるんだもーん」みたいな。いや、貼ったお前が責任持てよ、って。
発行人が一堂に会して、自社本の魅力をアピールする、独立出版者エキスポ(IndependentPublishers EXPO)を開催します。〈株式会社QANDOのプレスリリース(2025年8月18日)〉
プレスリリースを見てこれは興味深いと思ったのですが、出店募集の案内がありません。そこで「出店したい」とメールで問い合わせてみました。すると「会場スペースの関係上、今から新規出店枠を増やすのは難しい状況」とのことでした。残念。同じような問い合わせは私以外にもたくさん来ていたようです。ベータ版なのでまずは小規模メンバーでテストしてみるとのことなので、出店公募は次回以降に期待しましょう。
「信頼できる情報源はない」と感じる若者。これからのメディアはどうあるべきか?〈ウェブ電通報(2025年8月20日)〉
こういう調査結果を見ると、デジタルネイティブ世代のリテラシーは私の思っていた以上に高い、と感じます。まあ、ちょっと伝統的メディアに対し厳しすぎという気もしますが、鵜呑みにしない姿勢は大事。大学の授業でこれまでは「鵜呑みにするな、疑え」という話をしてきましたが、それはもうできている前提で、もう一歩先の話をすることにしようかな。
Study Finds 20-Year Drop in Reading for Pleasure(研究によると、娯楽目的の読書は20年間で減少している)〈Publishers Weekly(2025年8月21日)〉
n=236,270というかなり大規模な調査です。Reading for Pleasure(娯楽目的の読書)ってなんだろう? と思い元のレポートを参照してみました。“any kind of reading done for enjoyment or purposes other than work or school(仕事や学校以外の楽しみや目的のために行われるあらゆる種類の読書)”かつ“which can be accessed through multimodal forms of reading, from print text to e-books and audiobooks(印刷されたテキストから電子書籍、オーディオブックに至るまで、多様な形態の読書を通してアクセスできます)”で、“Reading for pleasure may include reading fiction, non-fiction, magazines, and newspapers, alongside other genres.(楽しみのための読書には、フィクション、ノンフィクション、雑誌、新聞、その他のジャンルの読書が含まれます)”とのことです。
仕事や学校での読書というのは、主に教科書などが想定されていると思いますが、いわゆる学参とか実用書・学術書なんかはどういう扱いになるんだろう? あと、雑誌、新聞が含まれるなら、ウェブ記事はどういう扱いなのか。“e-books(電子書籍)”だけならパッケージ化されている必要があるように思いますが、“multimodal forms(多様な形態)”と書いてあります。ざっと目を通しただけだと、このあたりが判断できませんでした。
経済
小学館の文芸誌「GOAT」創刊即1位 異例の特殊紙・安すぎ・ジャンルレス〈日本経済新聞(2025年8月12日)〉
出版社側が「いくら売れても赤字」なのは、他部署で利益が出て余裕のある企業なら、べつに良いと思うのですよ。好きにすればいい。雑誌は赤字だけど単行本でリクープするモデルというのは、マンガでもやってきた実績があるでしょうし。
むしろ、販売価格510円のうち取次や書店の取り分はどうなっているのか? が気になります。一般的な分配率のままだと取次や書店はあまり旨味がないのでは。そりゃ売れてない本に比べたら、売れてるほうが良いに決まってますが。別途、販売報奨金とか出たりしてるのかしら?
ヤバすぎ…AIでWebの「調べもの」が激変、フリーランサーの仕事がマジで消えた〈ビジネス+IT(2025年8月13日)〉
タイトルは煽りすぎ。どこかのまとめサイトじゃないんだから。「FiverrやUpworkといったフリーランスプラットフォーム」へのアクセスが急減しているそうですが、それってクラウドソーシングサイトですよね。つまり、消えてるのは「クラウドソーシングサイトで募集されてたような単価激安の」仕事と見て良さそうです。ああいうのはむしろフリーランスにとって害悪だったと思いますから、消えて良かったのでは。
「『クローム』分割なら買収」 米AI新興、相次ぎ名乗り パープレキシティ、5兆円案 実現性は不透明〈日本経済新聞(2025年8月14日)〉
仮にPerplexityがChromeを買収できたとしても、シェアが維持できるとは思えないのですよね。というのは、私がChromeを使っている理由は「Googleアカウントに連携して便利に使える」のが大きいから。そういう人、けっこう多いんじゃないかしら。
とくに私の場合、複数のGoogleアカウントを使う必要がある(個人、大学、NPO法人)ため、プロファイル機能を重宝しています。仮に他社へ事業譲渡されたら、Googleアカウント連携がなくなっちゃう可能性が高い。しかし、乗り替えたくても、恐らく代替手段がない。やめて欲しい。
今やブランド検索の「3分の1」がAIによるものと判明 SEO一辺倒はすでに終焉か〈CNET Japan(2025年8月18日)〉
AI検索対策を煽る記事。見出しの「ブランド検索の『3分の1』がAIによるものと判明」が、にわかには信じがたいのでいろいろ調べてみました。結論から言うと、私は「眉に唾しておいたほうが良さそうだ」と判断しています。
まず、CNETの日本語記事だと「デジタルマーケティング企業BrightEdgeが13日に発表した調査」へのリンクがありません。調べてみたら、BrightEdgeはAI検索対策のツールを販売している企業でした。つまり、自社にとって都合の良い「これからはAI検索対応だ!」という情報を広報的に発信している可能性があります。
また、英語版CNETの元記事を参照してみたら、こちらにはBrightEdgeの記事へのリンクがありました。ところが、その記事のどこにも「ブランド検索の3分の1がAIによるもの」とは書かれていません。というかむしろ“Google maintains overwhelming market dominance at 90% of search traffic(Googleは検索トラフィックの90%を占め、圧倒的な市場支配力を維持している)”などと書かれています。
念のためBrightEdgeのレポートフル版PDFまで確認しましたが、ウェブで公開されている内容とほぼ同じでした。CNETがリンクを間違えている可能性も考えたのですが、困ったことにBrightEdgeの記事には公開日付が表記されていません。HTMLソースにはそれらしい記述はありますが、公開日かどうかは判然としないため「8月13日に発表した調査」がどれか判別できませんでした。
AIが発見しやすいサイトとは プリファード系の事例に見る「AIO」〈日本経済新聞(2025年8月16日)〉
こちらもAI検索対策を煽る記事。まっとうなSEOをやっているのなら、AI対策で特別なことをやる必要はないと思いますよ。私がSEOの情報源としてわりと信頼している「海外SEO情報ブログ」の鈴木謙一氏も「生成AI専用のSEOは必要ない」と否定していました。
そもそも、ChatGPT searchの外部検索エンジンがBingからGoogleに切り替わったらしいって話もあるわけです。要するにそれは、ChatGPT searchがいずれかの外部検索エンジンに依存しているってことですよね。つまり、Search Engine(検索エンジン)へのOptimization(最適化)を行えば、AI対策にもなるって話なのでは?
OpenAIの最新LLMモデル、GPT-5によりSEOは必要不可欠な存在になる!?〈海外SEO情報ブログ(2025年8月19日)〉
まっとうな意見だとは思いますが、これはこれでポジショントークだということも指摘しておきましょう。まあ「SEOは“これまで通り”重要だ」くらいに思っておけば良い、と私は判断しています。
Google検索の「AIによる概要」でメディアは大打撃、クローラー課金は救世主となるか〈日経クロステック(2025年8月22日)〉
で、なぜAI検索対策が必要か? という話の根拠のひとつとして、このような「Google検索でAI Overviews(AIによる概要)やAI Modeが始まったことでメディアへの流入が減っている」という主張があるわけです。しかし、私はこれにも懐疑的なんですよね。こちらの記事も、メディア業界団体による主張が根拠です。
これは先日も指摘しましたが、Googleがいわゆる「寄生サイト」へのペナルティを実行したのが2024年5月5日からで、AI Overviewsが始まったのは同15日からです。ほぼ同時なんですよね。つまり、寄生サイトペナルティを食らったメディアがアクセス減少の原因をAI Overviewsに転嫁している可能性があると私は思っています。
少なくとも、そのことに一言も触れない分析に、どこまで意味があるのか甚だ疑問です。なお、寄生サイトペナルティを食らったと見られるメディアは、Forbes、CNN、The Wall Street Journal、USA Today、Los Angeles Times、Fortune、Daily Mailなどです。これら大手メディアが、アルゴリズムをハックするような、まっとうではないSEOで稼いでいた事実を棚上げしてAI Overviewsを批判しているのです。
Xは83%減、Facebookも60%減。こんなに変わったメディアのトラフィック源、では検索は……【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ〈Web担当者Forum(2025年8月22日)〉
で、こちらも鈴木謙一氏による記事です。メディア各社が「AI OverviewsやAI Modeで流入が減った」と主張しているのとはぜんぜん違う調査結果が、第三者から出てきました。リアルタイムアクセス解析ツール「Chartbeat」による、アメリカ・イギリスのパブリッシャー565社を対象とした分析です。Google検索の流入は、トータルでは6年間安定推移しているとのこと。
これ、AI Overviewsではなく、ほぼ同時に行われた寄生サイトペナルティの影響が大きいことの傍証になってますね。仮にAI OverviewsやAI Modeがなんらかの悪影響を及ぼしているなら、それはメディア全体に影響しますから、検索流入の総量が減少するはずです。しかしこの調査では、AI OverviewsやAI Modeが展開されたあとも、検索流入の総量はほとんど変化していません。
それに対し、ペナルティにより検索結果の表示順位を落とした(そして流入が減った)メディアがあると、そのいっぽうで、ペナルティを食らってないメディアはそのぶん表示順位が上がって流入が増えます。結果、Google検索からの流入総量に変化がなくても、まったく不思議ではないわけです。そしてそれは、Googleが主張しているとおりのことでもあります。
技術
「4oを返せ!」世界で大炎上、GPT-5のアプデがヤバすぎる〈すまほん!!(2025年8月10日)〉
すごい現象が起きてますね……まるでSFだ。以前、Googleのエンジニアが「AIに感情が芽生えた」と主張した(そして解雇された)ことがありましたが、同じようなことを世界規模でとんでもない人数に主張されているような感じでしょうか。なんというか、非常に興味深い。
グーグル検索に新機能「Preferred Sources」、トップニュースに好みのメディアを表示〈ケータイ Watch(2025年8月13日)〉
現時点ではアメリカとインドだけのリリースです。Google公式によると、Labsの時点ではユーザーの半数以上が4つ以上の情報源を選択していたそうです。ウェブサイトにも登録を促すバナーリンクが設置できるそうですが、どういう感じになるのかは不明。ポップアップ表示みたいなユーザーに負荷をかける手段をこれ以上増やすのはやめてほしい。
フェイクニュース対策の切り札? Google検索、ニュースサイトの優先順位を決める機能を海外で公開【やじうまWatch】〈INTERNET Watch(2025年8月14日)〉
この件を報じた海外メディア「The Register」は、「フェイクニュースはもう終わり」として、信頼性の低いニュースサイトの優先順位を下げる用途に使われるであろうことを予言している。
信頼性が低いと判定されて優先順位を下げられたニュースサイトは、大量のフェイクアカウントを使ったフェイクお気に入り工作をするでしょう。あるいは、それを商売にする事業者が出てくるかも。クリックファームみたいな。
Googleはそういった動きに対抗するため、お気に入りが「生きたアカウント」による挙動かどうかを検証したうえでデータを使う対策をします。アクティブな利用が他にあるかどうかをチェックすればいいわけです。するとこんどは「生きたアカウントを偽装するフェイク挙動」を行うように……というイタチごっこが起きますよ。たぶん。
「インターネットアーカイブ経由でクロール」AI企業の行動にRedditが怒り〈Media Innovation(2025年8月18日)〉
これは酷い……あまりにお行儀が悪くて反吐が出そう。どのAI企業なのか名前が明かされていない(Redditが6月にAnthropicを訴えたという話は記述されてますが、そのAnthropicがInternet Archive経由でクロールしているとは断定していないので注意)のですが、お行儀の悪い企業として記憶に刻みたいので、ぜひ名前を明かして欲しい。今後、法的措置みたいな動きがあれば、名前も出てくるかな。
Google「Pixel 10」のカメラが一線を超えた–捉えきれない細部を生成AIが描き足すように〈CNET Japan(2025年8月21日)〉
デジタルズーム30倍を超えると、生成AIによる画像補正がかかるそうです。以前、「AIによる画質改善」をうたう有料カメラアプリで、実際には画質改善ではなくAIが捏造していたことが判明。ありえない写真や存在しない鳥の写真が、利用者の意図とは関係なく量産されてしまっていたことが話題になっていたのを思い出しました。それに拍車がかかりそう。
ところでこの見出しの「一線を超えた」という表現、三省堂国語辞典(第7版)によると「ここまではなんとか許される、という範囲をはみ出して、絶対にしてはならないことをする」という意味です。ところが、本文からそういうニュアンスは読み取ません。私が上記で懸念したようなこともいちおう指摘はされてますが、「苦笑い」程度の触れ方です。
なんだろうこれは? と思い英語版の元記事を参照してみたら、元のタイトルは“I Roamed the Streets of Paris With the New Pixel 10 Pro XL and It Was Magnifique(新しいPixel 10 Pro XLでパリの街を歩き回ってみた。素晴らしかった)”でした。日本語版の編集者がなにかおかしな改変を行った? CNETさん、勘弁してください。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
帰省のため、JR東海道新幹線「スマートEX」で切符を予約。Suicaに登録してあるので、改札はすべてタッチアンドゴーでいけるはずでした。ところが、東京駅内での買い物にSuicaを使ったら、残高がギリギリ在来線の乗車料金に足らなくなってしまい、乗り替え改札であえなくストップ。クレジットカード機能付きSuicaなので、JR東日本管轄内の改札ならオートチャージされたのですが、JR東海道新幹線への乗り替え改札はオートチャージに非対応なのですよね。慌ててニューデイズの有人レジまで行ってチャージすることに。少し乗り換え時間に余裕もってて良かった。旅はトラブル。(鷹野)