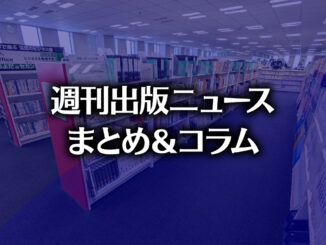《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年3月11日に配信した第22回では、決済サービスが表現規制を行うという、いわゆる「金融検閲」の話題について語っています。
【目次】
#22 決済サービスと表現規制
こんにちは、鷹野です。今回は「決済サービスと表現規制」をテーマにお話したいと思います。最近は「金融検閲」なんて呼ばれ方もしてますね。直接的な被害者は、インターネット経由でコンテンツを提供している事業者です。Electronic Commerce、ECサイトと言ったほうがわかりやすいでしょうか。出版関連だと電子書店が中心で、主に成人向けコンテンツが標的になっています。
「なーんだ、エロ本の話か」と思ったかもしれませんが、最近はエロ以外にも影響が出始めてるんですね。電子だけではなく、物理メディアの通信販売でも発生してますし、同人系とかクリエイター支援系なんかでも事例があります。有名なところだと動画共有プラットフォームの「ニコニコ動画」もやられていますね。モリアキさん、今日の話題に関連する記事を紹介してください。
はい、モリアキさんありがとうございます。この問題、最近までウェブメディアの報道くらいしか見当たらなかったんですが、ここへきてようやく大手メディアでも報道されるようになりました。
なにが規制されているのか?
ではまず、どんな表現が規制されているのかについて。決済代行事業者から加盟店、ECサイトですね。こちらにNGワードのリストが届くそうです。たとえば「レイプ」とか「拷問」とか。NGワード50個くらい。そのNGワードが作品タイトルや作品紹介文なんかに含まれてたり、NGワードそのものじゃなくても、連想させるものについても、削除しないと取引停止しますと。
つきましては、3日以内に対応しなさい、みたいな連絡が急に来るというような話です。NGワードのなかには、犯罪の「犯」1文字もあったそうです。そんな無茶なって話ですよね。犯罪の「犯」1文字がNGとなると、たとえば法務省が出してる「犯罪白書」とかね、これ引っかかりますよね。笑いごとじゃない。さっき国立国会図書館サーチで犯罪の「犯」1文字で検索してみたら、約15万件出てきたんですよ。図書だけに絞っても、8万件以上ありました。
「犯」1文字ではなく、2文字の「犯す」、これがNGワードになっているという情報もありました。「犯す」がNGになると、作品紹介文に「罪を犯す」とか「法を犯す」って書いてあるミステリー作品なんかかが、一般向けのミステリー作品なんかが軒並み引っかかっちゃうわけです。まさに言葉狩りですよ。
どうも内容は見ないで、タイトルや紹介文に含まれるキーワードだけで雑に判断しているみたいな、そんな話もあったりしてですね。まあ、だいぶ荒っぽいなという状況です。だからエロ以外にも影響が出てるっていう話なんですね。
決済が止まるとなにが困るのか?
で、このECサイトでの決済が、そもそもいまどんな状況なのか? と言うと、決済が止まるとなにが困るのか? という話ですね。ECサイトって基本的に現金が使えないわけですよ。対面取引だったら使えるんですけど――ECサイトでも現金がまったく使えないわけじゃなくて、物と引き換えに代金を払ってもらうっていう「代引き」だったらできますけど、デジタルコンテンツの配信だともうこれは100%キャッシュレス決済になりますね。
まあ最近だとリアル店舗でもキャッシュレス決済ってだんだん普及してきましたけど、現金って実はめちゃくちゃ強いんですよ。現金不可って明示されてて、事前にそれを客が承諾していない限り、代金として現金の受取は拒否できないんですね。これ法律で定められています。強制適用力っていいます。
あとは匿名性が高い。誰がいつなにに使ったのかって、現金には書いてないじゃないですか。書けない、書かないですよね。記録されない。現金とは別に、データベースとかに記録されてりゃ別ですけど、お金そのものに記録されるわけじゃないわけですね。匿名性が高い。
でもECサイトだと基本的に現金は使えませんよね。で、誰がいつなにに使ったのか、これすべて記録が残ってしまうわけです。リアル店舗とはそういう違いがあります。で、その決済はECサイトそのものが直接やってるわけじゃないんですね。あいだにいる決済事業者がやってます。クレジットカード決済なら、VisaとかMastercardとかJCBとかアメリカン・エクスプレスとか。
その決済事業者から、ECサイトで扱っている商品の表現内容を規制されてしまうという問題が今回のお話です。もう一回言いますけど、エロ以外にも影響出てますからね。エロやってないから関係ないっていう話じゃないですからね。
ECサイトの決済は半分以上がクレジットカード
ではそのECサイトでよく使われる決済手段ってどんなものがあるでしょう? これはモリアキさんに解説してもらいましょう。
はい、モリアキさんありがとうございます。要するに、ECサイトの決済は半分以上がクレジットカードということですね。ちなみにクレジットカードにもいろいろありますが、シェアってどんな感じなんでしょう? モリアキさん、教えてください。
はい、モリアキさんありがとうございます。VISAが半分以上、Mastercardと合わせると7割近くになるということですね。そのVisaやMastercardが使えなくなってしまったというECサイトが、2024年に急増しています。中にはサービス停止に追い込まれてしまった「マンガ図書館Z」のような事例もあります。
クレジットカード決済が半分、そのうちVisaとMastercardで7割だから、だいたい3分の1くらいってことですね。決済手段を提示してるのはECサイトですけど、どの決済を使うかを選ぶのはユーザーです。つまり、VisaとMastercardが使えなくなると、3分の1のユーザーに直接的な影響があるということになります。
クレジットカード決済だけの問題ではない
じゃあクレジットカード以外を使えばいいじゃんって話になるわけですよね。もちろんクレジットカード以外の決済手段もあるんですけど、ECサイトって多くの場合、いろんな決済手段をまとめて提供している決済代行事業者と契約してるわけですね。で、その決済代行事業者から提供された決済システムとシステム的に接続しているわけです。
で、その決済代行事業者から、ヘタをすると「ぜんぶまとめて止めます」って言われちゃうわけです。クレジットカード以外もね。さっき例に挙げた「マンガ図書館Z」の事例はまさにそれで、決済代行事業者にぜんぶまとめて止めますと言われちゃいました。
だから「マンガ図書館Z」が直接契約していたビットキャッシュだけが使える状態になっちゃったんですね。その状態になってから、私は初めてビットキャッシュを使ってみたんですけど、まあ正直、ちょっと面倒くさいです。
ビットキャッシュって、アカウントを作ったら、まずクレジットカードとかPayPayとかコンビニとか振込とかそういうのを使って「残高チャージ」ってのをしておくんですね。残高チャージ。で、ECサイトで買い物をするときビットキャッシュ決済を選択したら「ひらがなID」っていうプリペイド番号が、ビットキャッシュアカウントのところで発行されてるんで、それを入力すると決済できるっていう仕組みになってます。
面倒くさい。正直、どこでもだいたい使えるクレジットカード決済があるなら、そっち選びますよ。「マンガ図書館Z」もビットキャッシュ決済だけだとサービスの存続は難しいっていう判断で、サイトを停止しました。いまサイト再始動プロジェクトということで、クラウドファンディングをやってます。始めて速攻で、初日で目標達成して、いまストレッチゴールの段階ですけどね。3月末までクラウドファンディングやってます。興味がある人は支援してみてください(※本稿公開時点ではもう終了しています)。
お布施のつもりの月会費決済が止まった
ちなみに「マンガ図書館Z」は、主に絶版になったマンガを無料で閲覧できるっていう、広告モデルが基本です。広告モデルが基本なんですけど、プレミアム会員サービスというのと、高解像度PDFの有料販売もやってたんですね。その決済が止まっちゃったというわけです。プレミアム会員の特典は、広告なしで作品が読めるとか、PDFが月1冊ダウンロードできますとか、成人向け作品が閲覧できます、などでした。
私はプレミアム会員が始まったときから契約してますけど、最初のころはプレミアム限定のメルマガがあったんですよ。「はんぺん」って名前の。いまは参議院議員になったマンガ家の赤松健さんが書いてたやつで、「電子マンガ業界のヤバいニュース」みたいなコーナーがあってですね。
そういう読み物が面白くて、ほとんどメルマガ目当てでプレミアム会員になってたんですけど、途中から無くなっちゃったんですよね。メルマガ。だけど、絶版マンガから収益を作家に還元する! とか、海賊版に対抗する! みたいな試みを応援したくて、まあ、お布施とか寄付みたいなつもりで解約せずに続けてたんです。
いまやってるクラウドファンディングの集まり具合を見るに、お布施とか寄付みたいなつもりで払ってた方が私以外にもけっこういたんだと思うんですよ。そうやって毎月プレミアム会員の会費を払ってくれてた決済が止まっちゃったということなんですね。そりゃ致命的ですよ。
コンテンツを販売しているECサイトで決済ができなくなる。できなくなると、当然、コンテンツが販売できませんから、ユーザーにコンテンツが届けられなくなる。そうすると、そのコンテンツの著作者とか出版社にも収益が入ってこなくなるという、そういう結構範囲の広い問題なんですね。
なにが原因なのか? がはっきりしない
で、この問題の難しいところはですね、なにが原因なのかなかなかはっきりしない点なんですよ。いや、もちろんクレジットカード国際ブランドのVisaやMastercardと、実際に商品サービスをユーザーに提供しているECサイト、つまり加盟店とのあいだの話ってのははっきりしてるんですけど。
VisaやMastercardは「法的に保護された言論の自由や適法な表現を伴う取引を制限することはしない」とか「特定のウェブサイトについて、いかなる措置も決定も下していない」って否定しているんですよ。VisaとかMastercardが。
これ、初めは参議院議員の山田太郎さんがですね、アメリカのVisa本社まで行って言質を取ってきたんです。最近は、日本経済新聞や朝日新聞、さきほど紹介した記事でも書かれているように、日経も朝日も取材して、VisaとMastercardに取材して、同じ回答を得てるんですね。でも、VisaやMastercardは「うちがやってるわけじゃない」と否定しているわけですよ。
じゃあどこが規制しているのか? これがはっきりしないんですね。VisaとかMastercardと加盟店のあいだに入っている事業者のどこか。そのどこか? がよくわからない。あいだに入っているのは、加盟店獲得業務を行っている加盟店契約会社、英語で言うとアクワイアラ(acquirer)っていうやつですね。と、さきほども出てきた決済代行事業者です。
で、鈴木淳也さんというモバイル決済ジャーナリストの方がいて、どうやらこういう状況なのではないか? という推測記事をITmedia NEWSに書いています。さっきモリアキさんに紹介してもらった「クレカの表現規制、真犯人は誰か」って記事です。その中で、あくまで鈴木さんの推測なんですけど、各所にヒアリングを重ねた上での推測なので、それなりに確度は高そうだなあと思っていることがあります。
ざっくり言うと、国際ブランドの運用ルールというのは明確なんだけど、加盟店が違反したときのペナルティーが厳しい。だから、中間事業者のアクワイアラや決済代行事業者が過剰反応してるんじゃないか? と。ペナルティーって要は、即時取引停止とかですね、違反金が請求されるみたいな、そういう話ですね。
じつはこの記事が出る前日、3月6日に都内で「金融的検閲と表現の自由」というパネルが行われてました。そこでいろいろ話を聞いてきたんですけど、そこで聞いた話とも鈴木さんの記事は符合してるんですね。そのパネルのレポートが、さっきモリアキさんに紹介してもらった、うぐいすリボンのnoteです。興味がある人は是非読んでみてください。
なんでもね、加盟店から決済代行事業者に「なんでダメなのか?」って理由を質問するだけで「そんなうるさいこと言うんだったら全部止めます」「加盟店の規約違反は損害賠償請求できますからね」と脅される、という話があったんです。
これは会場に来ていた方の発言なんで、うぐいすリボンのnoteには書いてないんですけど。あまりに問答無用すぎるという。さすがにそれは優越的地位の濫用に当たるんじゃないか? みたいな、そんな話も出ていました。
―― この続きは ――
《残り約5000文字》