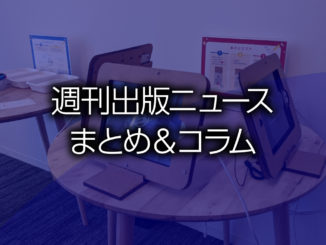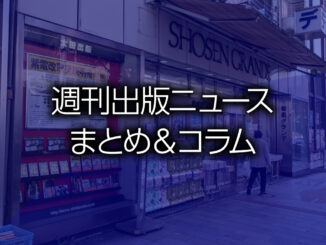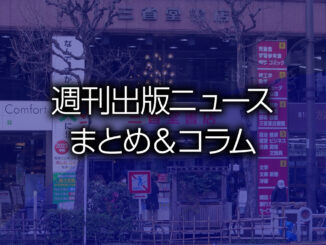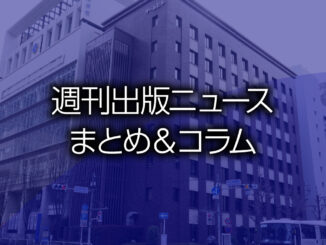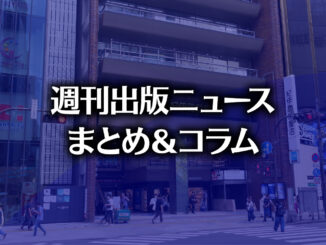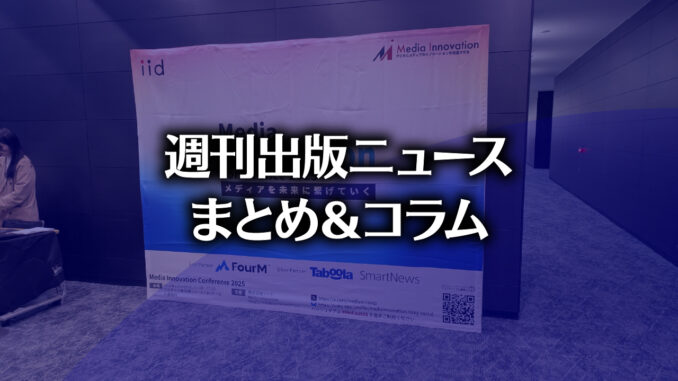
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年7月20日~26日は「2025年上半期出版市場」「Mediumが大赤字から復活」「AIガチャ」「ポッドキャストも本である」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 社会
- 経済
- KADOKAWA、イラストレーターがおうの不祥事を受け関連書籍を回収/絶版へ〈KAI-YOU(2025年7月23日)〉
- デジタルメディアの再生、大赤字から復活した「Medium」が取り組んだこと〈Media Innovation(2025年7月24日)〉
- 2025年上半期出版市場(紙+電子)は7737億円で前年同期比2.1%減、電子は2811億円で4.2%増 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2025年7月25日)〉
- 「本とPodcastは似ている」? 第一人者が語る“音声×出版”から生まれる新たなビジネスの手法とは(飯田一史) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年7月25日)〉
- 技術
- AIボットのWebデータタダ取り阻止。クリエイターが報われる時代が来るか?〈ギズモード・ジャパン(2025年7月20日)〉
- AIが書いた怪談小説が面白い 2分に1本のペースで出力されるのは驚異的〈ASCII.jp(2025年7月21日)〉
- Third-party AI scrapers stealing publisher content to order(第三者のスクレイパーがAI企業からの依頼を受けてパブリッシャーのコンテンツを不正に取得しています)〈Press Gazette(2025年7月24日)〉
- 時事通信社 AIで日本語に自動翻訳 AFP通信のニュース提供開始〈The Bunka News デジタル(2025年7月25日)〉
- Google検索にAI新機能「Web Guide」追加 まずは米国のSearch Labsで〈ITmedia NEWS(2025年7月25日)〉
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
HON.jp Podcasting「#39 中国BL作家の摘発と表現規制(2025年7月22日版)」を配信しました
「週刊まとめ」の時点ではあまり掘り下げられなかったのですが、少し調べてみたら周密 『BLと中国:耽美(Danmei)をめぐる社会情勢と魅力』(ひつじ書房・2024年)が見つけられました。電子版で読んで、YouTubeも観て、収録に臨みました。
新コーナー「ぽっとら」(Podcast Transcription)を更新しました
投資詐欺広告などへの対策で進む法整備/作家自身による出版と著作者名の詐称騒動〈HON.jp News Blog(2025年7月24日)〉
新聞報道が「SNS型投資詐欺」と呼ぶのは欺瞞じゃないか? と疑問を呈した回です。私には珍しく、口調が少し荒くなってます。だって私、読売新聞オンラインで「Microsoft Defender」を偽装した全画面表示の詐欺広告に当時、少なくとも5~6回は遭遇しましたから。広告出しっぱなしで注意喚起だけって、ふざけてるのかと思いましたよ、ほんと。
政治
そこが聞きたい:生成AIと「フェアユース」 ノンフィクション作家 下山進氏〈毎日新聞(2025年7月20日)〉
日本の場合、学習段階(著作権法30条の4)はさておき、RAGの出力が合法か否かの判断は著作権法47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)がどこまで適用されるか? 次第なんですよね。
そこで、日本新聞協会加盟社様におかれましては「著作権侵害に該当する可能性が高い」とか「権利者の許諾を得るのが筋」などといつまでもぐずぐず言ってないで、さっさと訴えて白黒はっきりしてください。著作権侵害に該当する可能性がほんとうに高いなら、法改正は要らないし、裁判でも勝てるでしょう。いずれにせよ、判例をつくって欲しいのですよね。
生成AIの学習と著作権:「市場の希釈化」がフェアユースを否定する可能性/Meta事件米国連邦地裁判決(関真也) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年7月21日)〉
Metaの裁判の「市場の希釈化」という文脈で、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AI と著作権に関する考え方について(PDF)」23頁(令和6年3月15日)の以下の箇所が引用されています。
著作権法が保護する利益でないアイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、特定のクリエイター又は著作物に対する需要が、AI生成物によって代替されてしまうような事態が生じることは想定しうるものの、当該生成物が学習元著作物の創作的表現と共通しない場合には、著作権法上の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。
これは従来通りの見解なので、私はむしろこの続きにある下記の箇所こそが重要だと思っています。
他方で、この点に関しては、本ただし書に規定する「著作権者の利益」と、著作権侵害が生じることによる損害とは必ずしも同一ではなく別個に検討し得るといった見解から、特定のクリエイター又は著作物に対する需要が、AI 生成物によって代替されてしまうような事態が生じる場合、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当し得ると考える余地があるとする意見が一定数みられた。
これは、アメリカの裁判で「市場の希釈化」が言及されるより1年以上前に、日本の文化審議会著作権分科会法制度小委員会ではすでにそれが「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当し得るという意見が複数出ていて、公式文書にもそれが明記されていたという証左なのです。
もちろんこの文書に法的な拘束力はなく、現時点で存在する特定の生成AIや関連技術について確定的な法的評価を行うものではないわけですが。
社会
相次ぐSteam成人向け削除は「クレジット決済代行業者や銀行の要請によるもの」Valve、弊誌らに回答〈Game*Spark(2025年7月19日)〉
ゲーム系の話題ですが、いわゆる「金融検閲」繋がりで取り上げておきます。Steam はアメリカ企業の Valve Corporation による運営ですから、正直、いままで無事だったのがむしろ不思議な気がしますね。「マンガ図書館Z」の事例みたいに、基本的には日本国内ユーザー向けだけに提供されてるサービスなら「おいおいちょっと待て」って話になりますけど、これはグローバルな話ですから。もちろん、私がこの規制を是とするわけではありません。念のため。
インディゲーム配信「itch.io」、成人向けコンテンツを全面非表示に 人権団体・決済業者に緊急対応〈ITmedia NEWS(2025年7月25日)〉
こちらの記事では、オーストラリアの女性権利団体「Collective Shout」の関与について言及されています。公開書簡があるのですね。日本で起きている「金融検閲」ではこういう表立った動きが観測されていないため、原因は異なるのでは? という気がします。
AIへの不信感が広告効果を低下させる【Media Innovation Weekly】7/22号〈Media Innovation(2025年7月22日)〉
Raptiveが米国成人3,000人を対象に実施した調査では、読者がAI生成と感じた記事への信頼度は、約50%も低下したということです。
半減! それも、実際に使っているかどうかではなく、これはAI生成だと「感じられた」かどうかの問題だというのですから驚きです。“AI stink”(AI臭)という概念も生まれているとのこと。なんかそれ、わかります。私の場合、信頼度の低下というより「読む気が失せる」感じですが。
Amazon電子書籍Kindleで同人小説ライトノベル(ラノベ)を個人出版したら、1年で数百万円稼いだ→本の不況で売上が減少した話【副業・兼業・プロ作家を目指す人にオススメ】〈白波 鷹(しらなみ たか)(2025年7月22日)〉
小説投稿サイトではあまり読まれていなかったのに、KDPで出版したら売れたという話です。1年で数百万円はすごい! ……のですが、急に売れるようになった理由がよくわからない。ユーザーの違いと、表紙の力も大きい気はします。あと、1年で急に売れなくなった理由もよくわからない。
著者は「エンタメコンテンツ不況」と分析していますが、2024年の下半期から急に電子書籍が売れなくなったというデータはない(出版科学研究所の調査ではむしろ下半期も伸びている)ので、なにか別の要因があるように思います。アマゾンのアルゴリズムに翻弄されている?
経済
KADOKAWA、イラストレーターがおうの不祥事を受け関連書籍を回収/絶版へ〈KAI-YOU(2025年7月23日)〉
未成年淫行ですから、同意の有無とは無関係に絶対ダメ。回収まで行う絶版というのはかなり厳めですが、私はこの対応を支持します。しかし、巻き添えを食らった形の著者は気の毒です。「ギルます」は「イラストレーターを変更し再発売予定」とのことですが、アニメ化されてる作品ですから、イメージが大きく変わるのは避けられないでしょうね。
デジタルメディアの再生、大赤字から復活した「Medium」が取り組んだこと〈Media Innovation(2025年7月24日)〉
興味深い。タイトルに「デジタルメディアの再生」とありますが、「Medium」は自社で記事を制作配信する「メディア」ではなく「プラットフォーム」という認識です。日本の「note」とけっこう似たモデルを採用していたはず。一時期は「金儲けのハウツー記事」だらけになっていたのを、推薦アルゴリズムの変更やインセンティブ構造の変更などの施策で、コンテンツの質が大幅に改善したそうです。
「note」もときどき外野から「金儲けのハウツー記事だらけ」とか「情報商材屋だらけ」みたいな批判をされているのを見かけますが、実際にはそれほど腐った場ではないと私は認識しています。おそらく「Medium」と同じような工夫をしているんでしょうね。
2025年上半期出版市場(紙+電子)は7737億円で前年同期比2.1%減、電子は2811億円で4.2%増 ~ 出版科学研究所調べ〈HON.jp News Blog(2025年7月25日)〉
記事内に書くのはやめたんですが、下半期の対前期比が上半期と同じになると仮定すると、通期で紙は9500億円の着地見込みです。つまり、ついに1兆円を割り込むことになります。通期の電子は5901億円で、年間の出版市場は計1兆5401億円となります。あくまで「このまま推移したら」という仮定ですが。
「本とPodcastは似ている」? 第一人者が語る“音声×出版”から生まれる新たなビジネスの手法とは(飯田一史) – エキスパート〈Yahoo!ニュース(2025年7月25日)〉
ポッドキャスト運営者として参考になります。ありがたい。内沼晋太郎氏の著書『本の逆襲』(朝日出版社・2013年)の「本の定義を拡張して考える」を思い出しました。当時からすでに「カレーも本である」とか「Ustreamの配信も本である」のような、固定概念を打ち破る発想をされていたんですよね。
技術
AIボットのWebデータタダ取り阻止。クリエイターが報われる時代が来るか?〈ギズモード・ジャパン(2025年7月20日)〉
CloudflareのAIボットブロックは、Googlebotが従来の検索機能にも使われているため、さすがにブロックできない、という問題に触れられています。CloudflareのCEOはそこで、AI OverviewsやAI Modeでの利用だけブロックできるようにしろとGoogleに対し働きかけていく、と発言しているそうです。
Googleがその意見に耳を貸すと良いのですけどねぇ……現状、Search ConsoleではAI OverviewsやAI Modeのデータが自然検索の中に含まれていて、個別に分析できません。いまの状況のままだと、あまり期待できないように思います。
AIが書いた怪談小説が面白い 2分に1本のペースで出力されるのは驚異的〈ASCII.jp(2025年7月21日)〉
これ、「2分に1本」というのはこの記事を書いた新清士氏が、同じプロンプトで実際に試した際の話です。そのプロンプトを公開した花笠氏の元記事には「平均30分」と書かれています。元記事では「ガチャ」と表現されているように、当たりを引くまでなんどもトライしています。つまり「2分に1本」は、捨てたゴミも含めたカウントです。それはフェアじゃないでしょう。
私は、花笠氏の元記事で最も重要なのは、以下の箇所だと思いました。
このプロセスにおいて、私の役割は「作家」ではなく「編集者」に近いと感じました。
つまり、やはりエディターシップが重要だということですよ。
Third-party AI scrapers stealing publisher content to order(第三者のスクレイパーがAI企業からの依頼を受けてパブリッシャーのコンテンツを不正に取得しています)〈Press Gazette(2025年7月24日)〉
なんか、有料ペイウォールの向こう側もスクレイピングできるなどと豪語してるスクレイパーがいるそうです。そりゃ、ターゲットと契約してログイン状態にしてプログラムを回せば可能でしょうけど、そこまでやりますか。
ちなみに、Anthropicへの連邦地裁判決で、「LibGen」の海賊版データ学習はフェアユースに該当しない(つまり違法)と判断されています。ほんとうに第三者へ依頼して取得させているとしたら、同様の判断になりそうな気がしますけどね。契約して取得するのは合法でも、第三者への譲渡は違法でしょう。
時事通信社 AIで日本語に自動翻訳 AFP通信のニュース提供開始〈The Bunka News デジタル(2025年7月25日)〉
うーん、あらかじめ自動翻訳された記事を読むのと、ユーザーがブラウザの自動翻訳機能を使って読むのと、正直、あまり大きな差はないと思うのですが。そのひと手間を乗り越えられない人も意外と多い、という判断なのでしょうか?
Google検索にAI新機能「Web Guide」追加 まずは米国のSearch Labsで〈ITmedia NEWS(2025年7月25日)〉
おー、これは面白い試み。検索結果のうち同じような内容のものを自動でグループ化してくれる機能とのことです。果物のAppleと企業のAppleのように、同じ言葉を使っている別のことがもしキレイにグループ化されるとしたら、それだけで効率が段違いになる気がします。個人的にはけっこう助かるかも。「そっちじゃない」って、×を押してパッと消せるようになっていると良いですね。
「SmartNews」でAI要約「スマニューAIまとめ」が提供開始、複数媒体の記事を個別に要約〈ケータイ Watch(2025年7月24日)〉
というGoogle「Web Guide」のニュースを見てから、こちらの「SmartNews」のAI要約についての記事を振り返ってみたら、やろうとしていることはかなり近いことに気づきました。しかし、1トピックスに1記事だけの掲載ではなくなるということは、そこでアクセスが分散しますよね。当然、いままで1記事だけが得られていた収益も分散します。複数記事が掲載されると、そこでのCTRもまた並び順に大きく左右されることになります。じゃあ、その並び順のアルゴリズムは? というループに。サイト運営者としては、けっこう悩ましいですね。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」で新たに誕生した16点の作品を合本にしました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
本気の夏が本気を出し過ぎてますね……猛暑日予報で、関東平野のほぼ全域が紫色のヤバイ感じになっています。みなさま熱中症にはくれぐれもお気を付けください。(鷹野)