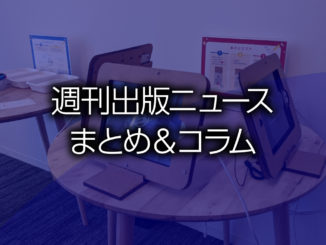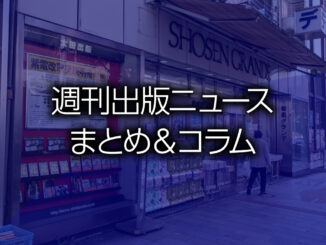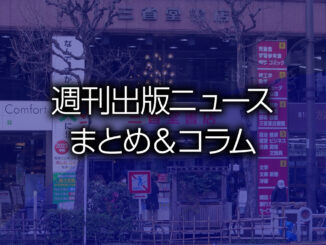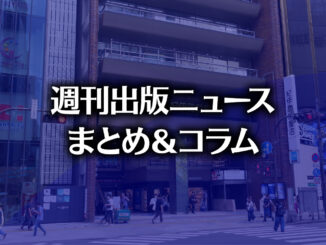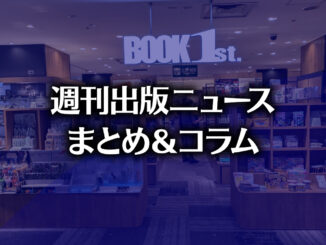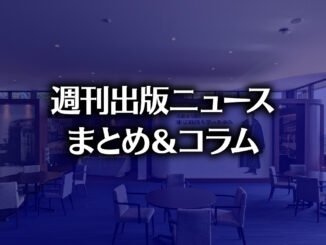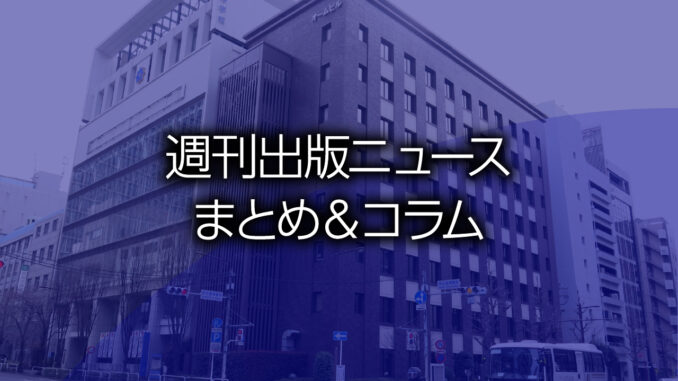
《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
2022年11月20日~26日は「インボイス制度にさらなる経過措置?」「警視庁がカード決済中止を要請」「AppleとAmazonの広告」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 値上がり続く文庫本 平均価格800円超 20年で25%値上がり 千円台も続々 ハードカバーより高価買い取りのケースも〈まいどなニュース(2022年11月21日)〉
- ピクスタ、漫画・アニメ・ゲームなどのキャラクターを広告などに使えるサービス「PIXTA IPコンテンツ」開始〈CreatorZine(2022年11月21日)〉
- ピクシブ、マンガなどのエンタメ商材に特化した運用型広告プラットフォーム「pixiv Ads」の正式版提供開始〈CreatorZine(2022年11月24日)〉
- 米アップルが広告事業で失態 まさかの“方向転換”の布石なのか〈日経クロストレンド(2022年11月21日)〉
- アマゾンの顧客満足度が低下、競合ECサイトを下回る〈JDIR(2022年11月23日)〉
- 【メディア企業徹底考察 #85】ダウンラウンド上場のnote、成長には法人事業が鍵?〈Media Innovation(2022年11月25日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
インボイス、フリーランス消費税軽減 売上税額の2割に〈日本経済新聞(2022年11月20日)〉
先週挙がっていた経過措置案は「小規模業者」ではなく「少額取引」を対象とするものでしたが(#547)、やっとまともに「小規模業者」を対象とした策が出てきました。「売上高500万円の場合、全商品が税率10%なら納税額は売上税額50万円の2割の10万円になる」とのことなので、従来の免税=ゼロではないものの、税負担はかなり減少する形になりそうです。ただし3年間の経過措置……釣られて課税事業者になると、3年後には100%負担が待っていることに。問題の先送り感。
請求書保存、紙印刷も容認〈日本経済新聞(2022年11月25日)〉
本欄で以前、インボイス制度と並んでもう一つヤバイのが「電子帳簿保存法」だと指摘しましたが(#546)、税務当局が「相当の理由」があると判断すれば紙での保存も容認する特例を設けるとのこと。「会計ソフトへの登録」という事務処理が毎月発生する(従来の確定申告なら年1回で済んだ)問題は、これで軽減できそう?
FC2のカード決済中止求める 警視庁、違法わいせつ動画横行で〈朝日新聞デジタル(2022年11月21日)〉
公権力が、FC2との取引中止を「クレジットカード会社に要請」していたことが発覚しました。カード会社から促された取次事業者(※割賦販売法で「立替払取次業者」と定義されているアクワイアラのことでしょうか)が実際に契約を解除し、動画の販売数が激減したとのこと。わいせつ動画横行への対策とのことですが、さすがにこれは警察の権力濫用ではないかと騒ぎになっています。
コロナ禍での自粛要請と同様「命令ではない」という建付けなのでしょうけど、このやり方がどんどん拡張していくのを許してしまうのは非常に危うい気がします。というか、このところDMM/FANZAやpixivで起きている表現規制の動きって、もしかして同じような圧力がかかっていたのでは? なお、山田太郎議員も早速動いています。
11月21日、本件警察庁に確認。警視庁がクレカ国際ブランド3社に対してFC2動画に関する情報提供をし措置を講じるよう要請した、というのは事実とのこと。違法わいせつ動画横行への対策とのことだが、過剰規制と恣意性の懸念あり。FC2そのものが違法でないとすれば、非常に問題https://t.co/ntTlIA663e
— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) November 21, 2022
米出版大手ペンギン、同業の買収破談に 違約金280億円〈日本経済新聞(2022年11月23日)〉
先日、アメリカ連邦地裁から、ペンギン・ランダムハウス(PRH)によるサイモン&シュスター(S&S)買収計画を阻止する判決が出ていましたが(#545)、控訴して争うのかと思いきや、結局破談に。PRHはS&Sの親会社パラマウント・グローバルに2億ドルの違約金を支払う必要があるとのことですが、これ、原因は司法省の訴えと裁判所の判決なのだから、国家賠償って話にならないのかしら?
なお、この記事は他の出版大手(ハーパー・コリンズやアシェット・リーブルなど)がS&Sの買収に関心を寄せているという一文で締められていますが、大手同業他社ならPRHと同じように独占禁止法で訴えられる可能性が高いわけですよね。そしてPRHの二の舞になる未来も見えてるわけで。よほどの確証がない限り、うかつに手を出せないのでは。
「NHKのネット活用業務」めぐり懸念示す。民放連、新聞協会〈AV Watch(2022年11月25日)〉
新聞協会から、“NHKが配信した記事が検索サービス上で上位に表示されるなど、ウェブ上にニュースを配信する以上、本質的には民間報道機関への影響は避けられないのではないか。”といった主張があったとのこと。本欄で以前、映像のネット配信ではなく、テキストで配信される「NHKニュース」への影響が気になると書いたのですが(#539)、やはりそうきましたか……。
実際のところ、NHKの記事って消えるのが新聞系より早い印象があります。1週間保たないことさえあるので、週1回の本欄で取り上げるのをためらうんですよね。まあ、新聞系もけっこう消しちゃうから、年単位で見ると同様に困るんですが。バックリンクを自ら踏みにじるスタイル。だから検索上位になれないのでは? という気もします。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
論文の無料公開促進で合意 10大学、国際的な学術出版社と〈共同通信(2022年11月21日)〉
図書館が出版社に払っている電子ジャーナル購読料を、オープンアクセス出版料に転換する契約。従来は、オープンアクセス出版するには著者が掲載料を支払う必要があったのを、大学側でまとめて負担することにより無料公開枠を得る形とのこと。海外のメディアでも取り上げられていて、ちょっと驚きました。この契約は、関与する大学が「各機関に適した速度での移行を可能にする」と評価されています。なるほど。
JEPA電子出版アワード 一般投票の受付開始〈文化通信デジタル(2022年11月24日)〉
今年も選考委員として、候補作品リスト作成のお手伝いをしました。部門がたくさんあるから、あまり偏らないようにするのが意外と手間だったり。ジャンル賞は誰でも投票できます。12月5日まで。
図書館の司書は「情報のプロ」、でも待遇は… 国に期待する役割とは〈朝日新聞デジタル(2022年11月25日)〉
朝日新聞で図書館司書の待遇についての特集が。何本か公開されてますが、長年司書育成に関わってきた都留文科大学の日向良和教授(図書館学)へのインタビューをピックアップしておきます。前半は非正規・低賃金で女性が多いことへの問題提起ですが、後半では自治体間格差の問題にも触れられています。なお、「扶養範囲の中に押し込めたり」という表現には、もちろん配偶者控除も含んでいると思われます(※扶養控除は配偶者以外が対象)。
経済
値上がり続く文庫本 平均価格800円超 20年で25%値上がり 千円台も続々 ハードカバーより高価買い取りのケースも〈まいどなニュース(2022年11月21日)〉
出版物の価格について、新刊書店と古書店に取材した記事。再販制度により新刊価格の決定権は出版社側にあるので、「原因」とか「理由」は出版社に聞かないとわからないんじゃないかな……まあ、一般向けの「やわらかニュースサイト」なので、そこまで深い掘り下げを求めるのは酷かもしれませんが。
なお、本文にある「出版科学研究所(東京都)の調査」以降の数字は、「出版月報 2022年3月号」の特集「文庫本市場レポート2021」が出典と思われます。ちなみに「出版月報 2022年10月号」の特集は「出版物の価格を考える」で、紙はもちろん、電子出版の価格設定にも触れられているなど、かなり興味深い内容でした。
とくに「再販制度と委託販売制度によって、かつて“出版物は物価の優等生”と言われた」けど、近年は消費者物価指数を上回る価格上昇になっていることを、データ付きで明確に指摘しているのが良いと思いました。私が「デジタル出版論」で指摘していることでもありますが、こういう業界向けに歴史と権威ある媒体で発信されるとより効果的でしょう。
要するに、日本書籍出版協会「再販制度」のページが2001年4月から更新されておらず、「読者のみなさまへ」と呼びかけている主張が古いデータを根拠にしていて、現状とまったく合っていない状態になっているのはマズいのでは? という話なのですが。
ピクスタ、漫画・アニメ・ゲームなどのキャラクターを広告などに使えるサービス「PIXTA IPコンテンツ」開始〈CreatorZine(2022年11月21日)〉
せっかくの自社IPを、自社で展開していく余力のない中小企業向けのプラットフォーム、と言っていいでしょう。集英社・講談社・小学館・KADOKAWAあたりは、すでに自社でやってて収益の大きな柱になってますもんね。面白いのは、これが一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)の会員企業繋がりで始まった話だという点。今後、ブロックチェーンの活用という展開も出てくることでしょう。
ピクシブ、マンガなどのエンタメ商材に特化した運用型広告プラットフォーム「pixiv Ads」の正式版提供開始〈CreatorZine(2022年11月24日)〉
マンガなどエンタメ系+広告の動きがもう一つ。こちらは「pixiv」や関連サービスへの運用型広告出稿を、セルフで簡単にできる仕組み。Google AdSenseやYahoo!広告といった、巨大IT企業の広告プラットフォームからの脱却を図る動きと言っていいでしょう。「pixivおよび関連サービスにおける広告表示面については、順次拡大をしていく予定」とありますが、恐らく「pixivおよび関連サービス」以外への展開も視野に入れているのでは。
米アップルが広告事業で失態 まさかの“方向転換”の布石なのか〈日経クロストレンド(2022年11月21日)〉
Apple「App Store」で、ギャンブル依存症の治療に役立つアプリを探していた人に、ギャンブルアプリを試すよう促す広告が表示されるといった「失態」が起きているというニュース。プライバシー保護強化によりGoogleやFacebookの収益に打撃を与えながら、自らも広告事業に身を投じていくのかと批判されています。
関連して、iOSの新ポリシーでSNSでのブースト広告が「アプリ内課金とみなす」とされ、Meta社などが批判しているというニュースもありました。こちらも、Appleの広告事業強化への動きの一つ。10月末ごろからの動きだったようですが、あまり話題になっておらず見落としていました。どちらもMeta社狙い撃ちっぽい。
アマゾンの顧客満足度が低下、競合ECサイトを下回る〈JDIR(2022年11月23日)〉
以前、本欄で「リテールメディアが急成長」という記事に対し、“ユーザーにとっては「広告だらけでうざい」プラットフォームになっていく可能性が、そしてベンダーにとっては「広告を出さないと売れない」プラットフォームになっていく可能性”と指摘しましたが(#535)、どうもその通りになりつつあるようです。これはアメリカでの調査ですが、マーケットプレイスの急拡大や検索精度の低下、偽評価や模倣品の横行などが原因と考えられているようで、日本でも同様の傾向が現れそう。
【メディア企業徹底考察 #85】ダウンラウンド上場のnote、成長には法人事業が鍵?〈Media Innovation(2022年11月25日)〉
noteの上場分析関連で、「cakes」が炎上してサービス終了した経緯にもしっかり触れてる記事としてピックアップ。新規上場申請のための有価証券報告書にも、他の分析記事でも、不自然なくらい「cakes」には触れられていないのが気になってました。つい最近(2022年8月)までサービスが続いていたわけですから、来期以降の収入・支出に影響が出ないはずがない、と思うのですよね。
法人事業(note pro)は、先行他社(「法人向けはてなブログ」とか)との競争になります。情報商材対策の負荷も重たいことでしょう。地方公共団体、学校、文化施設、中央省庁、独立行政法人向けには、すでに無償提供しています。「オウンドメディア」のクローズが相次ぐとも言われるなか、どう独自性を発揮していくか。私は、エクスポート機能が無い状態では、勧めづらいとずっと思っているのですが。
技術
Facebook、第3四半期は14億件のスパムに対処–前四半期から倍増〈CNET Japan(2022年11月24日)〉
Metaによると「8月にスパム攻撃が急増したことが原因」とのこと。こんな膨大な件数を人力で対処していたら、そのコストだけで大変なことになってしまいます。多くの場合、アルゴリズムで自動処理しているのでは――って、思いますよね? これ恐らく、FacebookページやFacebookグループの管理者が手動で対処した件数も含まれているのでは。
というのは、実は、私が管理しているHON.jpのFacebookグループでもこの8月、実際にスパム投稿が急増していたのです。毎日のように何件かスパムがきて、手作業での対処を強いられていました。管理権限のない人には承認前投稿が見えないので、一般の参加者はスパムが増えたことには気づかないはず。
HON.jpのFacebookグループは誰でも参加・投稿できますが、最初に参加・投稿するときは承認が必要な形に設定してあります。まあ、手作業での対処とはいえ、投稿しようとしている内容を確認して[承認しない]をクリックするだけの簡単な手順ではありますが。ちなみに、Amazon Sellerを名乗るスパムが圧倒的に多いです。
ただ、私が管理者ではない他のFacebookグループでは、一般参加者にスパムが見える状態になっているところもありました。恐らく、参加・投稿に事前承認が不要な設定になっていたのでしょう。この場合、グループ参加者は「グループ管理者」またはFacebookに対する報告が可能です。
つまり現状、FacebookページやFacebookグループへの投稿に関しては、グループ管理者にある程度の自治権を与える代わりに、コンテンツモデレーションの負荷も分担させる形になっています。しかもタダで。そのぶんFacebookは労力やコストをかけずに済んでいるわけです。
余談ですが、パソ通時代、NIFTY-Serveのフォーラム管理者(SYSOP)は、けっこう高額なロイヤリティを貰っていたそうです。最盛期には年収4000万円を超えていたという証言も残っています。いまならテクノロジーで解決するのがクールなんでしょうけど、往々にしてユーザーにタダでやらせる方向に進むんですよね。
お知らせ
イベント
11月28日開催の日本出版学会出版デジタル研究部会(HON.jp共催)は『パブリッシング・スタディーズ』第4章「書籍」第3節「デジタル化と今後の展開」の執筆を担当した林智彦会員(有斐閣)にご報告いただきます。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
サッカー日本代表がワールドカップ本戦でドイツ代表を破るという大波乱があったそうですね。以前の自分なら大騒ぎしていたと思うのですが、いまは自分でも不思議なくらい心が動きません。「ドーハの悲劇」のころから30代後半までは夢中で観ていたはずなのに。なぜだろう?(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。