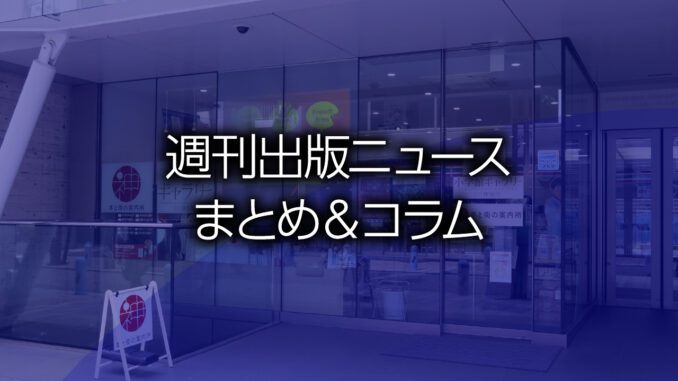
《この記事を読むのに必要な時間は約 18 分です(1分600字計算)》
2022年10月30日~11月5日は「Kindle Vella開始1年強で1000万ドル分配」「イーロン・マスク氏に買収されたTwitter社の今後」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- Kindle Vella Awards More than $10 million to Authors〈Good e-Reader(2022年10月29日)〉
- 2万件超すフェイク記事・サイトの6割で、Google広告が収益を支える 初の大規模国際調査〈新聞紙学的(2022年11月1日)〉
- 2023年のソーシャルメディアマーケティング市場は1兆899億円に拡大の見通し 2022年市場動向調査〈Media Innovation(2022年11月2日)〉
- ネイバー、米ウェブ小説プラットフォーム「ヨンダー」発売〈韓国経済新聞(2022年11月2日)〉
- “海賊版サイトの収入源を絶つ” 集英社が広告会社に停止要請 | エンタメ〈NHK(2022年11月4日)〉
- イーロン・マスクがTwitter買ってからやったことまとめ〈ギズモード・ジャパン(2022年11月2日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
米連邦地裁、出版大手2社の合併計画に差し止め命令〈ロイター(2022年11月1日)〉
ペンギン・ランダムハウスによるサイモン&シュスター買収計画が阻止される判決が出ました。合併によって作家の獲得競争が阻害され、アドバンスの減少に繫がるという主張が認められたとのことです。2年前の発表当時、合併の狙いや作家の反応などについて、大原ケイさんに解説いただいてます。ご参考まで。
なお、買収計画が発表されたタイミングはジョー・バイデン氏の大統領選勝利が確実になったころですが、いちおうまだトランプ政権下でした。司法省による提訴は2021年11月なので、バイデン政権に変わってからのこと(#496)。買収合意の発表から2年ががりで、結局ご破算に。
これは典型的な政治リスクと言っていいでしょう。お気の毒さま。他の買い手をまた探すのか、売却を諦めるのか。今後の動向にも注目です。なお、サイモン&シュスターの親会社は、当時は「ヴァイアコムCBS」という名称でしたが、2022年2月から「パラマウント・グローバル」に社名変更していました。
Z-Library domains are seized and pirate book site is dead〈Good e-Reader(2022年11月4日)〉
アメリカで学術系の海賊版サイト「Z-Library」のドメインが押収され閉鎖になったとのこと。ドメインって押収できるんですね……知らなかった。調べてみたら、アメリカではけっこう前からわりと頻繁に行われているようです。民事の差止命令なので負担が小さく、迅速・容易に実行できるとのこと。
ならば「日本でもこの制度を導入しよう」となってもおかしくないよな? と思い、さらに調べてみました。すると、知的財産戦略本部のサイトで「米国におけるドメイン・ネームの差押・没収制度について」という説明資料が発掘できました。2018年に開催された「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議(タスクフォース)」の参考資料です(資料3. 奥邨教授提出)。
この検討会議は海賊版サイト「漫画村」が問題になったあと、村井純さんと中村伊知哉さんが共同座長を務め、政府の緊急課題として対策が話し合われたもの。ブロッキングの是非などが侃々諤々の議論になり、結局「中間まとめ(案)」がまとまらなかったといういわくつき。これはその際に提出された参考資料ということになります。
当時、この資料がどのような扱いになったかまでは未確認ですが、その後に公開された総合的な対策メニューに「ドメインの差押・没収」といった内容は見当たりません。財産所有者に通知や反論の機会がない点や、制度濫用の問題(表現規制)なども指摘されているので、法制化のハードルも少し高そう。あと、ドメインホッピングにより、すぐに後継サイトが生まれてしまうという問題もあるようです。
社会
電子図書館(電子書籍貸出サービス)実施図書館〈電流協(2022年11月1日)〉
2022年10月1日現在の電子図書館(電子書籍サービス)実施数が公表されました。前回(7月1日)との比較で実施自治体数が+112と急増していますが、実施館数は+30と大きな差があります。なにが要因だろう? と思ったら、長野県「デジとしょ信州」が1館で1県19市22町35村の広域電子図書館だからでした。なるほど。
「第67回学校読書調査」の結果が公表される〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年11月2日)〉
先週の本欄で「全国SLAの公式サイトにはまだ情報が出てません」とお伝えしましたが、その翌日に公表されました。「第67回調査は、全国学校図書館協議会が実施しました」とあり、単純に毎日新聞社が抜けただけの実施体制になっています。調査結果のトピックスとしては、中学生の不読率が前年比で8.5ポイント増えている点が挙げられます。小学生・高校生はそれほど大きく変動していないので、中学生だけちょっと異様な感じ。なにが要因だろう?
デジタル出版物を閲覧できる情報通信機器の普及状況 ―― デジタル出版論 第4章 第1節〈HON.jp News Blog(2022年11月3日)〉
連載再開しました。このまま毎週続けたい。第2部ではデジタル出版の「流通」を深掘りしていきます。主に巨大IT企業=プラットフォーマーの果たしている役割についての話が中心になる予定です。今回は導入として、情報通信機器の特徴とその普及率についてまとめました。ディスプレイの大きさを出版物の判型と比較すると、マンガ以外の電子出版市場がなかなか広がらない理由の一つが理解できるかも。試験的に後半を「Readers」限定としました。登録は無料なので気軽にどうぞ。
経済
Kindle Vella Awards More than $10 million to Authors〈Good e-Reader(2022年10月29日)〉
2021年7月にアメリカのKDP限定で開始された新サービス「Kindle Vella」が、1年ちょっとで著者に1000万ドル(約14.6億円)以上を分配しているそうです。カナダの小説投稿サイト「Wattpad」に対抗するサービスで、短いエピソードを連載形式で公開していくスタイル。この記事では「過小評価されているプラットフォーム」と表現されていますが、分配額からすると著者にとってはけっこう魅力的な作品発表手段の一つになっているのでは。日本の「Kindleインディーズマンガ」みたい。
KDPコミュニティのお知らせをチェックしてみたら、分配額(Kindle Vella Bonus)は昨年10月時点では50万ドルでしたが、今年10月には100万ドルと倍増していました。ユーザーによるトークン購入額の50%が著者に還元される仕組みなので、トークンだけで月商3億円くらいの規模になっている計算に。Amazonには珍しく、数字が丸見えになっているビジネスです。
ちなみに、ちょうどこの記事と同じようなタイミングで、KADOKAWAの小説投稿サイト「カクヨム」で著者への還元額が合計3億円を突破した、というプレスリリースが出ていました。著者への分配は2019年10月に開始していますので、こちらは2年弱での実績です。どうしても比べちゃいますよね。
なお、「Kindle Vella」は日本のKDPレポート(新画面)にも、ダッシュボードだけは存在しています。つまり、日本でいつ始まってもおかしくない状態とも言えるでしょう。とはいえ、日本の「Kindleストア」はアメリカの5年遅れで始まってますから、まだ先の話かも? ただ、「Kindleインディーズマンガ」みたいに、日本独自の展開もあるからなあ。
2万件超すフェイク記事・サイトの6割で、Google広告が収益を支える 初の大規模国際調査〈新聞紙学的(2022年11月1日)〉
アメリカの非営利メディア「プロパブリカ」による調査報道。記事内での表記が「Google広告」となっていますが、厳密に言えばそれはアドバタイザー(つまり広告主)向けのサービス名です。広告そのものの問題ではなく、広告が表示されるウェブサイト(つまりメディア)側の問題を指摘しているわけですから、これは「Google AdSense(アドセンス)」の問題だと明記したほうがわかりやすいでしょう。
「アドセンスのアカウントがポリシー違反で停止された」みたいな話は以前からよく目にしていたので、Googleはメディア側にはそれなりに厳しい対応をしている――と思っていたのですが、実はけっこうザル審査だった? どうやら、フェイクニュース対策のリソースが英語圏に偏っているということのようです。これ、いま読んでる『フェイスブックの失墜』(早川書房)でもまったく同じ問題が語られていますね。
2023年のソーシャルメディアマーケティング市場は1兆899億円に拡大の見通し 2022年市場動向調査〈Media Innovation(2022年11月2日)〉
このうち「ソーシャルメディア広告」は9724億円と予想されています。え? そんなに? と驚きました。というか、私の認識が甘かった。別の調査ですが、電通「2021年 日本の広告費 インターネット広告媒体費 詳細分析」によると、2021年の「ソーシャル広告」は7640億円(前年比134.3%)と、すでにインターネット広告媒体費の3分の1を占める状態になっていました。これ、読んだはずなのになあ……ちゃんと読めてなかった。反省。
ただ、ソーシャルメディア広告が今後も順調に伸び続けるか? というと、広告出稿先として疑問符が付くような状況になりつつあるかもしれません。Facebookしかり、後述のTwitterしかり。
ネイバー、米ウェブ小説プラットフォーム「ヨンダー」発売〈韓国経済新聞(2022年11月2日)〉
前述したように、Amazonの「Kindle Vella」はカナダの小説投稿サイト「Wattpad」対抗とされていますが、こちらはその「Wattpad」側からの対抗措置です。今回始まるこの「YONDER」は、「Wattpad」で人気の連載作品などを厳選して提供するプラットフォームという位置づけ。「Kindle Vella」と同じように、冒頭は無料でも一定以上を読むには対価が必要とのこと。
なお、「Wattpad」は昨年1月に韓国NAVERが買収しています(#457)。ウェブトゥーンへの原作供給源として機能させるためには、作家への対価還元も増強しなければならない、ということなのでしょう。
日本でも先日、韓国系の「ノベルピア」が「独占配信なら1PV2円、複数配信でも1PV1円」という破格の条件を提示しているという記事広告をピックアップしました(#544)。恐らく今後、日本でもこのような作家の獲得競争はさらに激化していくのでしょう。
“海賊版サイトの収入源を絶つ” 集英社が広告会社に停止要請 | エンタメ〈NHK(2022年11月4日)〉
タイトルから抜けていますが「スペインの」広告配信事業社に対する停止要請が通った、というニュース。Google AdSenseと同じような、メディア側に設置するタイプのプラットフォームと思われます。海外の広告配信事業社への要請が初めて、というのはちょっと意外でした。「摘発を逃れるため海賊版サイトの運営拠点を海外に移すケースが増えていることが背景にあるとみられます」とあるので、従来は海外の広告配信事業社を使っている海賊版サイトが少なかったのでしょうか。国内事業者向けの対策は、既にやってますもんね。
イーロン・マスクがTwitter買ってからやったことまとめ〈ギズモード・ジャパン(2022年11月2日)〉
イーロン・マスク氏によるTwitter社の買収確定から、毎日のように驚くようなニュースが流れてきます。ネタのような話も含め、一通りまとまっている記事としてピックアップしました。トップの解任や取締役会の解散、従業員の大規模リストラなどは事前に噂が流れていたとおり。
問題は、イーロン・マスク氏の言う「言論の自由(フリースピーチ)」がどれほどのものかと試す輩が大量発生し、その結果ヘイト投稿が急増していたり、その状況を懸念してユーザーが「Mastodon」に逃げ始めていたり、大手企業が広告を引き上げ始めているあたりでしょうか。
客観的には、株式非公開のワンマン企業になったことにより、矢継ぎ早の改革が行われているのは「さすが」の一言。ただ、利用する当事者としての立場(ユーザーも広告主も)では、このプラットフォームに依存し続けるリスクをどうしても考えてしまいます。ちなみに、小学館から「#マンガイチ」というTwitterの利用を前提とした投稿サイトが10月31日にプレオープンしています。タイミング悪……。
ただ、日本はTwitterのユーザー数が飛び抜けて多く、利用者が多いほど価値が増幅される「ネットワーク効果」も働くので、よほど強力な代替手段が出てこない限り簡単にユーザー離れは起きないかもしれません。拡散力を考えると、ちょっと代替が難しいインフラになっちゃってますよね。
技術
グーグル、短編小説を執筆するAIツールでプロ作家と協力–作品を公開〈CNET Japan(2022年11月4日)〉
GoogleからAI関連の発表がいくつか出ていましたが、とくにこれをピックアップ。GoogleのAI研究者でさえ、まだ「(AIを使って)物語全体を書こうとすると行き詰まる」「作業を実際に行うのは作家だ」と発言しているのが印象的。現時点でも短編ならかなりのレベルにまで達しているようですが、恐らく長い物語になると文章として成立はしていてもあちこちで辻褄が合わない、という状態になってしまうのでは。
お知らせ
イベント
11月28日開催の日本出版学会出版デジタル研究部会(HON.jp共催)は『パブリッシング・スタディーズ』第4章「書籍」第3節「デジタル化と今後の展開」の執筆を担当した林智彦会員(有斐閣)にご報告いただきます。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
久しぶりに映画を観に行きました。原作を読んだ11年前「ああ、誰かこの話をアニメ化してください」と感想を書いた『ぼくらのよあけ』です。空間投影ディスプレイに表示された無数の「BLOCKED」はやっぱりゾクッっとした……よき団地映画でした(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。





























