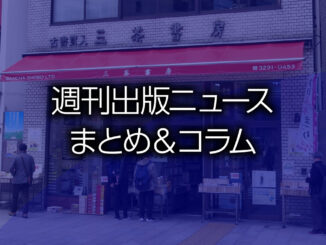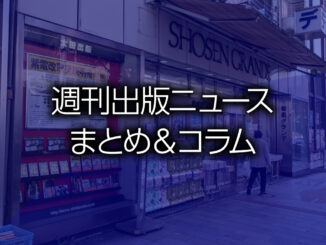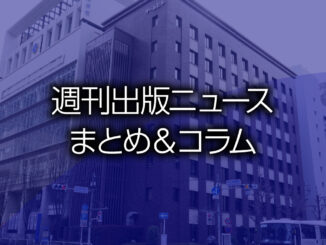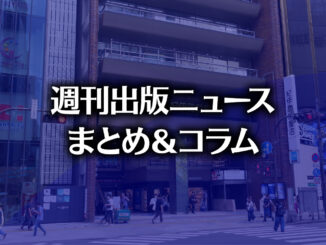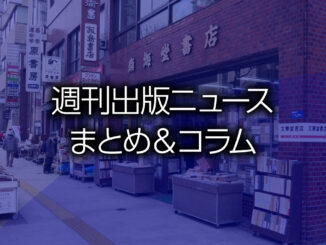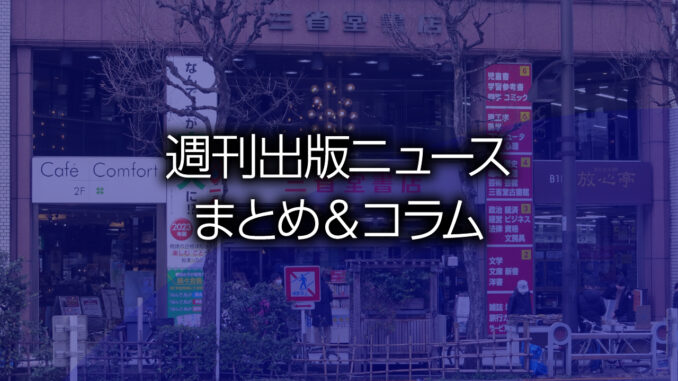
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2022年3月20日~26日は「丸紅、講談社、集英社、小学館の流通新会社設立」「出版業界による読書バリアフリー対応のいま」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
侮辱罪の法定刑引き上げは「表現の自由を脅かす」 日弁連が反対する意見書発表〈弁護士ドットコム(2022年3月23日)〉
侮辱罪の法定刑引き上げ、閣議決定されてから反対するのはさすがにちょっと遅くないですか……私も「表現の萎縮に繫がる可能性」について懸念を表明したのは #511 や #512 の時点なので、あんまり人のこと言えませんが。とはいえ、官公庁から発信される情報をわりと積極的に追いかけているつもりであっても、量が多くてタイトルが分かりづらいため、見落としが結構出てしまうのも事実。どうすればいいんだろうなあ……。
「安倍やめろ」街頭演説ヤジ訴訟、道警は「排除」を正当化できるか? 3月25日に判決〈弁護士ドットコム(2022年3月24日)〉
首相演説やじ、道警の排除は違法 札幌地裁、北海道に賠償命令〈共同通信(2022年3月25日)〉
政治的「表現の自由」を尊重 原告「歴史的判決」と評価、札幌〈共同通信(2022年3月25日)〉
こちらも「表現の自由」に関わる話。ヤジが下品なのは確かですが、声を上げ始めてから「わずか10秒程度」で公権力が排除する行為が正当とは思えません。真っ当な判決でしょう。
杉田水脈議員が中傷ツイートに「いいね」、不法行為認めず 伊藤詩織さんの訴え棄却〈弁護士ドットコム(2022年3月25日)〉
政治信条は横に置いて、これは仕方ないと思える判決。Twitterの「いいね」機能は、「肯定的・好意的な感情を示す以外の目的で用いられることもあるうえ、それ自体からは感情の対象や程度を特定できない」という判決理由は、この問題が起きたのが2018年6月であることを思うと妥当と思います。いまはともかく、まだ当時は以前の仕様を多くの方が引きずっていたと思うのです。行動は急に変わりませんから。
Favorite(☆)=ふぁぼが、Likes(♡)=いいねに変わったのが2015年11月、いいねがタイムラインに流れるようになったのは2017年3月です。それ以降、「RTだけ」「RTといいね」「いいねだけ」という3つの行動分岐を考えると、私の場合、だんだん「いいねだけ」は「好意」寄りに変わっていきました。いまはもう、暴言や中傷ツイートに「いいね」はできない雰囲気になっているように思います。でも、そのいまの空気感を、そのまま当時に当てはめることはできないと思うのです。
社会
リフロー形式のデジタル出版物はページ数がカウントできない〈HON.jp News Blog(2022年3月23日)〉
デジタル出版論の連載再開、第2章は「メディアとビジネスモデル」についてです。第1章より具体的に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオの「4マス」と、本、インターネットについて深掘りしていきます。授業でやっている内容そのままだと薄すぎるけど、足し始めるとキリがないというジレンマ。紙の出版だけでも奥が深いので、それを踏まえたデジタル出版となると、さらに深く、広くならざるを得ないのですよね。さじ加減が難しい。七転八倒しながら書いています。
オンラインセミナー「出版業界による読書バリアフリー対応のいまとこれから」〈公益財団法人 文字・活字文化推進機構 YouTubeチャンネル(2022年3月25日)〉
マラケシュ条約締結から読書バリアフリー法成立までの経緯と現状、今後の対応などについてのセミナー……というか動画が公開されました。オンラインセミナーを開催という事前告知だったので生配信だと思い込んでいたのですが、編集された動画がアップロードされるのは若干意味合いが異なるのでは……?
内容は、非常に面白かったです。とくに後半のトークセッションでは、大手総合出版社(講談社)、中堅専門書出版社(有斐閣)、中小出版社団体(版元ドットコム)それぞれが、全く異なる状況であることが再確認できました。2019年の日本出版学会春季研究発表会「学術書のアクセシビリティ」で聞いた話から、3年経ってもそれほど大きく変わっていない印象です。
つまるところ、制作の業務フローが紙中心から動かせていない、余裕のない中小企業ほど変えられない。障害者対応で個別にテキストデータを提供するより、リフローEPUBを制作・販売するほうが得策なのだけど、文字モノ電子市場がまだ小さく儲かる見込みが立たないから、紙だけ出版の体制を変えられない。だから対応できない、という現状が垣間見えます。
電子書店のビジネスは、電子マンガ市場の拡大によって持続可能なものになったと思います。次は、文字モノ電子市場の拡大に、もっと力を入れて欲しいところです。「電子書籍、儲かるじゃん!」となれば、中小出版社の目の色も変わるはずなので。
経済
【POD特集】福浦社長「POD市場を拡げたい」、マーケットは「個人と出版社のあいだ」 インプレスR&D × メディアドゥ新会社「PUBFUN」〈文化通信デジタル(2022年3月23日)〉
文化通信のPOD特集の1つで、インプレスR&Dとメディアドゥの合弁で設立される新会社の経営陣にインタビューしています。PODは物理メディアですが、電子メディアと同様に品切れを起こさないので、とくに少部数出版にとっての福音となるはず。大いに期待しています。
個人向けにも提供されているインプレスR&D「ネクパブ・オーサーズプレス」は私も利用していますが、法人向けだけだったメディアドゥ「PUBRID」は縁がありませんでした。2つのシステム連携を図っていく中で、どうサービスが変わっていくのか、注目しておきたいところです。
たとえば「ネクパブ・オーサーズプレス」で配信するために Amazon POD の仕様で作ったデータを、「PUBRID」が扱っている Amazon 以外(三省堂・楽天)向けにそのまま流用できるのかどうか、あたりは非常に気になります。ワンソース・マルチユースができないとなると、手間がかかりますからね。
出版3社と丸紅、流通新会社「PubteX」設立 RFIDラボ、今夏に開設へ〈文化通信デジタル(2022年3月24日)〉
昨年5月に日経の“飛ばし”で業界関係者が騒然としていたニュースの続報です。既存の取次を飛ばして書店との直接取引拡大を図る――というわけではなく、発行・配本量の最適化と、RFID(電子タグ)の活用事業が軸となります。今夏にオープンするRFIDショールーム(ラボ)に興味を引かれます。
あとは、出資社に丸紅本体だけでなく、丸紅フォレストリンクスの名前もある辺りも注目点でしょうか。国内で紙・紙製品の販売事業を行っている丸紅100%子会社です。この辺りあまり詳しくないのですが、物流事業の丸紅ロジスティクスや、RFIDと連携した位置情報システムを提供している丸紅情報システムズではないのだな、と。
書籍や雑誌は比較的単価が安い商品なので、RFIDの単価がどこまで下げられるかが普及へのカギと言われています。1枚1円以下の「実現に現実味」という記事が2年ほど前に出ていますが、その当時で「最近のRFIDタグ1枚の価格はおよそ10円前後のもよう」とあります。それがいくらまで下げられるのか。
小説・マンガ投稿サイト「エブリスタ」、メディアドゥが追加出資で完全子会社化〈アニメーションビジネス・ジャーナル(2022年3月25日)〉
DeNAが70%の持ち株すべてをメディアドゥへ売却と発表されたのが昨年9月。NTTドコモが保有していた残りの30%も、メディアドゥが取得し100%子会社になりました。今回プレスリリースはなく適時開示だけだったので、ニュースが出て初めて気付きました……。
「インプリント事業との協働」「投稿された作品の出版やメディアミックスを推進」「各電子書店が手掛けるオリジナル作品や成長著しい縦スクロールコミックへの原作提供」など、掲げられている文言は前回同様です。まあ、既定路線と言っていいでしょう。
適時開示株式会社エブリスタの株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ (PDF : 207KB)〈(2022年3月24日)〉
技術
NFTアートとは呼ばせない、中国のデジタルコレクティブル・プラットフォーム——主要プレーヤーを一挙紹介〈BRIDGE(ブリッジ)(2022年3月22日)〉
中国当局は、仮想通貨取引や採掘も全面的に禁止していますが、NFTの取引はまだ禁止されていません。通貨発行権を犯しているわけではない、という判断なのでしょうか? このことから、中国の大手テック企業もNFTマーケットに参入しています。そういった背景や現状を詳しくレポートした記事です。
まだ禁止されていないけど、規制当局に配慮して二次流通は規約で禁止しているとか、「NFT」という言葉も使わないようにしているといった線引きが、なかなか微妙で面白い。それならNFTは投機対象になり得ないのではと思いきや、将来、政策変更で規約が緩和されたときのキャピタルゲインを期待して購入しているコレクターも多いとのこと。当選発表がいつかわからない宝くじを買うような話です。
しかし、記事中で紹介されている中国のNFTマーケットは「ほとんどが非パブリックブロックチェーン上に構築されている」という辺りが、なんとも言えない感じです。日本でも、楽天やLINEなどのNFTマーケットは同じように非パブリックブロックチェーン(プライベートチェーン)です。事実上、中央集権型と変わらないわけで。それ、ブロックチェーンを使う意味は?
グーグル、「Android」アプリで他社の課金方法も表示するテスト–Spotifyから〈CNET Japan(2022年3月24日)〉
なにやってるんだろう……? と呆れてしまいました。App StoreでApple ID決済の迂回が禁止されていることに対し、Epic Gamesが訴訟を提起したのが2020年8月。その直後に、それまで緩かったGoogle Play決済のルールが厳格化というニュースが流れました。
実際に昨年末あたりから、私が把握しているだけでも「BOOK☆WALKER」「ブックライブ」「Kinoppy」などのAndroidアプリ内決済が、不便な方向への変更を余儀なくされています(それぞれ対応方法は異なる)。デベロッパーはプラットフォームの仕様変更や規約変更に振り回されているわけですが、多くのユーザーはプラットフォームではなく、直接相対するデベロッパーを批判しているのが観測できます。気の毒。
それがここへ来て、他社の課金方法も表示するテストを一部で始めた、と。いや、ほんと、Googleなにやってるんだろう……? 記事内には「手数料にどう影響するかについては発表の中で明らかにしなかった」とありますが、テストを終えて実運用を始める際には、30%より少し安い程度の手数料が要求されるんでしょうか? 要求されるんだろうなあ。
お知らせ
イベント動画
ゲストに落合早苗さんを迎えて「出版DX これでいいのか、電子書籍市場」をテーマに開催された3月27日のHON.jp News Casting、見逃しアーカイブ視聴のチケット販売中です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
この週末、近所の桜が一斉に咲き始めました。まん防が解除されたこともあり、今年は花見宴会もそれなりに行われるのではないかと思われます。日本は平和ですね。戦争反対!(鷹野)