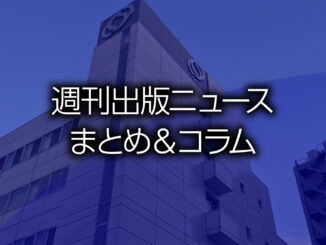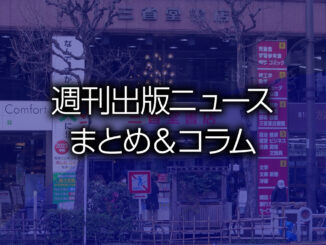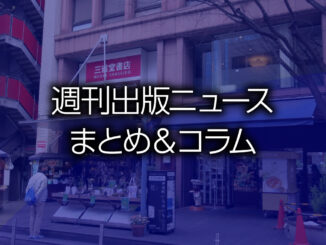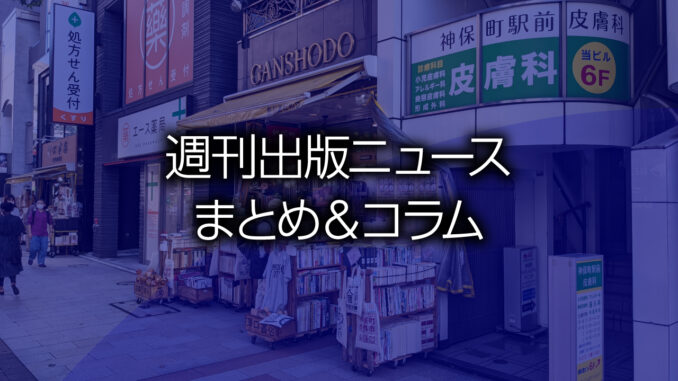
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年2月27日~3月5日は「ロシアで戦時言論規制法可決、各国のマスコミが報道停止へ」「アマゾン実店舗閉鎖」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
侮辱罪の法定刑の引き上げについて考える ~ネット上の誹謗中傷は防げるか~ 北澤尚登 |コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2022年2月28日)〉
先週(#511)の本欄で「表現の萎縮に繫がる可能性」について懸念を記しておきましたが、タイミング良く専門家による解説記事が。やはり、言論活動を萎縮させてしまう恐れについても触れられています。今回が緊急的な措置なら「その効果や弊害について(略)近い将来に検証(必要があれば見直し)が望まれます」と、次のステップへの示唆があるのが良いですね。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第4回)〈文化庁(2022年2月28日)〉
今期最後の法制度小委員会。侵害コンテンツのダウンロード違法化についてのフォローアップと、「DX時代に対応する基盤としての著作権制度・政策に関する論点整理」「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元に係る新しい権利処理方策について」について討議が行われました。後者2つは来期も継続審議。引き続き追いかけます。
ダウンロード違法化についてはユーザー調査を行っているのですが、クイズの全問正答はなんと0.5%、7問中正答4問以下が9割という結果に。まあ、難しいですもんねえ。私も、改めて説明しろと言われたら、正直、ソラで答えられる自信がないです。
興味深いのは、違法ダウンロードを減らした・やめた人が、違法ストリーミング配信には移行していない点。じゃあ、いま増えている海賊版利用者は、新規ユーザーということですか。まあ、もちろん、正直に答えていない可能性もあるわけですが。
英BBCがロシアで取材活動停止 情報統制懸念、CNNも〈日本経済新聞(2022年3月5日)〉
ロシアで戦時統制強化。軍事行動に関し、虚偽の情報を広げたら刑事罰を科す改正法案が可決されました。外国人も対象になっており、「ロシア国内の全ての記者と補助スタッフが仕事を一時停止する以外に手段が残っていない」とのこと。特A級の言論規制があっさり可決・施行されてしまう事態が目の前で起きていることに戦慄します。
社会
【特集 児童書の電子化動向】児童書電子化で出会うチャンスを拡大 電子図書館サービスの増加で児童書にニーズ〈文化通信デジタル(2022年3月2日)〉
考えるべきは「紙VS.デジタル」じゃない 絵本の理想の形とは〈朝日新聞デジタル(2022年2月27日)〉
絵本の読み聞かせ動画「無断公開控えて」著作権侵害ケースも | IT・ネット〈NHKニュース(2022年2月27日)〉
偶然なのか、別々の報道機関でほぼ同時に、別の角度から、児童書・絵本についての話題。NHKは「読み聞かせ動画」問題再び、なので少し毛色が違いますが、文化通信と朝日新聞はどちらも「デジタル化」がテーマです。
絵本ナビの社長・金柿秀幸さんが、考えるべきは「絵本VS.ゲーム、YouTube」とおっしゃっているのが印象的。スマホやタブレットの中に「絵本」という選択肢が無ければ、ゲームやYouTubeなどへ流れてしまうのは必然です。可処分時間やスクリーン時間の奪い合いというのはずいぶん前から言われていることではありますが、それは絵本・児童書という分野でも同じこと、という話なのだと思います。
広義の出版には、講演、音楽、映像、ブログ、Twitterのつぶやきも含まれる〈HON.jp News Blog(2022年3月2日)〉
第1章で、書くのにいちばん時間を要したパート。先行研究を参照しないと……と思い調べ始めたら、芋づる式にあれも読まねば、これも読まねば、になってしまいました。つまり「書くのに」というか「読むのに」時間を要しています。「印税率10%は100年以上前からの慣習」の件は、その流れで発掘しました。イギリスの話ですが、そのまま日本へ制度輸入した可能性が高そう。
先日、サー・スタンリー・アンウィンの『出版概論』という古い本(原書初版1926年10月)を読んでいたら、こんな記述が。ウォルター・H・ページってWikipediaが正しければ1918年に亡くなっているので、印税率10%は100年以上前からの慣習だったようです。https://t.co/RTnxgQ6Fjp https://t.co/UncnbkFiyS pic.twitter.com/XDM1hicGEz
— 鷹野凌@HON.jp📚 (@ryou_takano) February 26, 2022
ちなみに、日本出版学会の学会誌『出版研究』バックナンバーがJ-STAGEで一般公開され始めたのは、2020年3月ごろからだったようです。さりげなくアピールしておきました。ただ、OCRが貧弱なのか、PDFからテキストをコピーすると大変なことに……康煕部首やら異体字やらが、かなりの頻度で紛れ込むので要注意。
絶版本など自宅からウェブ閲覧可能に 国会図書館が5月開始〈朝日新聞デジタル(2022年3月3日)〉
「5月19日から開始予定」という発表があったのが2月1日なので、1カ月遅れの報道。なのに、なぜかバズってました。まあ、知らない方がまだまだ多いということなのでしょう。こうやって話題になるのは良いことだと思います。事前に利用者登録が必要ですからね。
個人的には、「絶版本など」という表記は誤解されるから「入手困難資料」にして欲しいなーとか、入手困難資料として扱われる条件も説明して欲しいなーとか、資料デジタル化の対象が2000年まで拡張されてる件にも触れて欲しいなーとか、いろいろ思うところはありますが。まあ、タイトルに「スマホで閲覧可能に」ってミスリードを入れなくなっただけマシかな?
電子図書館、いいことずくめ? コロナ禍で倍増、陰に休止の動きも [ニュースデータウォッチ]〈朝日新聞デジタル(2022年3月5日)〉
電子図書館(電子書籍貸出サービス)が普及し始めたことについて、「いいことずくめ(ではない)」と課題を指摘する記事。私が昨年10月に書いた「課題」とおおむね符合しています。まあ、ラインアップですよ、まずは。電子図書館サービスの取り扱い点数が、一般消費者向けに売ってる点数の10分の1になっちゃってるわけで。
ベストセラー頼みに「喝」! 急増する電子図書館、専門家の懸念は [ニュースデータウォッチ]〈朝日新聞デジタル(2022年3月5日)〉
専修大学教授・植村八潮さんの「喝」では、「そもそも、図書館にベストセラー本を置く必要はない」「もし(エンタメ分野を)公共のサービスで貸し出すなら、欧州諸国で公共図書館に導入されている公貸権(略)を議論すべき」と、なかなか痛快な提案がなされています。
経済
2021年紙+電子の書籍:雑誌:コミック市場の比率は41.9:17.7:40.4 ~ 出版科学研究所調査より〈HON.jp News Blog(2022年2月28日)〉
先週(#511)の本欄で「出版月報が物理的に手元へ届かないと詳細がわからない」と書きましたが、やはり届いたのは月曜日の昼前でした。準備はしてあったので、数字を入れてグラフの見た目を確認、すぐに公開できました。が、インパクトが小さいのが、あんまり読まれていません。トホホ。
2021年回顧では「さすがにまだ、書籍とコミックは逆転しないと思いますが」と書きましたが、2020年→2021年は、書籍:42.43%→41.9%、雑誌:19.69%→17.7%、コミック:37.89%→40.4%なので、ギリギリ予想通り。このままいけば、2022年には逆転するでしょう。
ただ、これは記事内にも書いたし、恐らく何度でも指摘しておくべきだと思いますが、出版科学研究所の統計は「読者が支払った金額の推計」で、広告収入や電子図書館向けは含まれません。ウェブメディアは広告収入への依存度が極めて高いわけですし、記事のバラ売りやサブスク(定期購読)についてはどこまで捕捉できているか? という問題もあります。
だから、1年後には「書籍をコミックが逆転」、数年後には「書籍+雑誌をコミックが逆転」というニュースがセンセーショナルな形で流れて煽られるような未来が想像できちゃいますが、あくまで「出版科学研究所の観測範囲では」と受け止めておいたほうが良さそうです。実態を把握するのって、ほんとに難しいんですよね……。
米アマゾン、米英の小売り実店舗68店を閉鎖へ〈ロイター(2022年3月3日)〉
2015年に開始したアマゾンの実店舗販売、いわゆるアンテナショップ(和製英語)的な存在だと思っていたのですが、成果が上がらなかったとのこと。傘下のホールフーズによる食料品販売は実績が出ており、残すようです。不採算部門はあっさり切り捨てる、実に“巨大テック企業らしい”判断だなと思います。
Good e-Readerによると、アマゾンの最高経営責任者がジェフ・ベゾス氏からアンディ・ジャシー氏に変わり、事業の見直しを図る中でこのような判断に至ったようです。実店舗担当副社長だったキャメロン・ジェーンズ氏が、昨年11月に退社していたとのこと。株主に対し短期的な成果を見せるには「先代からの負の遺産を清算」するのが手っ取り早いのは確かですが、中長期で見たときどうなるか。

『文藝春秋』創刊100年と文藝春秋の様々な取り組み〈(創) – Yahoo!ニュース(2022年3月3日)〉

新書好調!新潮社が進める組織再編と構造改革 長岡義幸〈(創) – Yahoo!ニュース(2022年3月3日)〉

マガジンハウスが新たに始める新書とコミック〈(創) – Yahoo!ニュース(2022年3月3日)〉

月刊「創」2月号の特集「出版社の徹底研究」と、3月号の特集「新聞社の徹底研究」が、ヤフーニュースへ一斉配信されています。特集の見出しを見る限り、大手ではKADOKAWAだけ取り上げていないのが印象的。一通り読んでみて、個人的に興味深かったのが文藝春秋、新潮社、マガジンハウスの3本でした。
文藝春秋は、書籍の「紙と電子の同時発売」がようやく当たり前のことになった点と、コミック編集局が順調らしい点。新潮社は、デジタル売上の比率が10%以上になったという点と、コミック部門が15%を占めるようになった点。マガジンハウスは、2021年になってようやく基幹雑誌すべてのウェブサイトが出そろった点と、こちらも(#506で既報ですが)コミックへ参入する点。
なんというか――出版DXがマンガを軸としつつ、マンガ以外にも、大手以外にも、徐々に広がりつつあるのだな、と。
技術
紙の本、内容記憶しやすく読解力高まる…スマホと比較 : 科学・IT : ニュース〈読売新聞オンライン(2022年2月27日)〉
なんか既視感があるぞ? と思ったら、2月の初旬にGIGAZINEで報じられていた研究でした。いろいろ調べた結果、ウチでピックアップするのは止めたのですが、読売新聞が4週間遅れで取り上げてしまいました。読書中の呼吸リズムや脳の反応を測定するというアプローチ。「Scientific Reports」に掲載された論文はこちら。
こういう、紙媒体と電子媒体(あるいは反射光と透過光)の特性の違いから読解力や記憶力などの差異を探る研究というのは、過去にもいろいろあります。例えばトッパン・フォームズが2013年に「紙媒体の方が情報を理解させるのに優れている」という研究結果を発表しています。
ところが昨年、同じトッパン・フォームズが、紙媒体と電子媒体の情報伝達効率は、媒体への「慣れ」の影響度が高いという研究結果を発表しています。若年層では電子媒体の方が理解度が高いという結果が出ているのです。面白い。
つまり、前述の研究ももしかしたら、媒体そのものの違いによる影響より、「慣れ」という別因子の影響のほうが大きいかもしれないわけです。個人的には、感覚的に「慣れが大きいじゃないかなあ」と思っていたので、我が意を得たりという感じであります。まあ、もちろん、その感覚が正しいとも限らないわけですが。
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
正気を疑いたくなるような、目を背けたくなるような情報が、怒濤のように押し寄せています。心がぐちゃぐちゃになってしまって、体が思うように動きません。それでもこれだけは言おう。戦争反対!(鷹野)