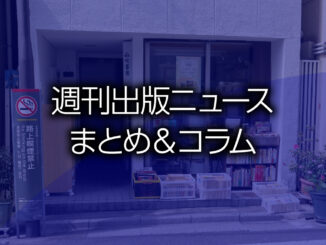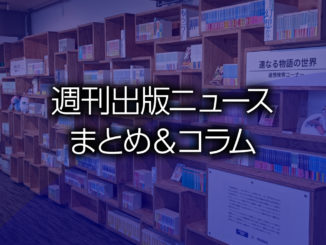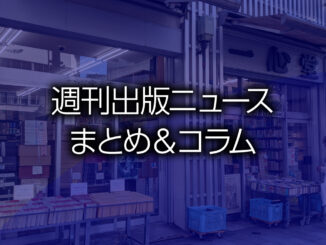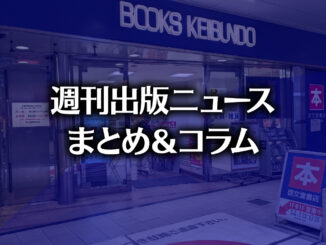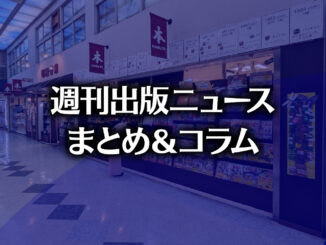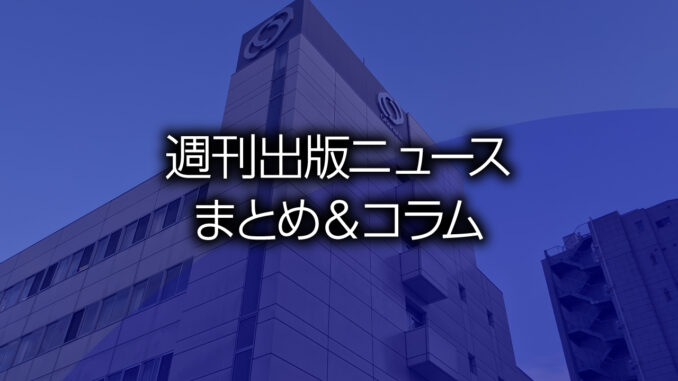
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2022年3月13日~19日は「集英社が宗教2世漫画を打ち切りに」「総務省海賊版対策検討会にCloudFlareが呼ばれるも傍聴できず」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
ネット広告規制 法制度の在り方議論 トラブル対策で検討会 | IT・ネット〈NHKニュース(2022年3月16日)〉
消費者庁「景品表示法検討会」が始まったというニュース。2014年(平成26年)に改正された景表法が、社会環境の変化を踏まえ、見直しが必要かどうかの検討が行われます。
2021年度の「アフィリエイト広告等に関する検討会」では、「広告主が責任をもってアフィリエイト広告を管理」することにより不当表示を防止できる(つまり「アフィリエイターが勝手にやったこと」といった言い訳は通用しない)ため、「景品表示法の改正は現時点では不要」という結論に至っていますが、
#507 でも触れたように、「消費者庁は、ステルスマーケティングの実態を把握するとともに、その実態を踏まえ、消費者の誤認を排除する方策を検討すべきである」とも指摘されており、まさにその検討が今後ここで行われていくことになります。要注目。
インターネット上の海賊版サイトへのアクセス抑止方策に関する検討会(第7回)配付資料〈総務省(2022年3月16日)〉
アクセス抑止方策の効果検証結果についてウイルスバスターから、検索結果表示での海賊版抑止についてはヤフーとGoogleから、そしてCDN事業者のAkamaiとCloudFlareからヒアリングが行われるという、非常に濃い回。傍聴しましたが、CloudFlareからの強い要望により、CloudFlareの発表時には退出を迫られてしまいました……残念。Akamaiは、CDNを利用したい企業は顧客になる前にちゃんと「正規版を扱っているかどうか」を審査していると強調していたので、審査が緩すぎると批判されているCloudFlareが検討会でどう答えたかは非常に気になります。
傍聴できた範囲では、Googleに対し、森委員が「大量の削除依頼が届いているはずの海賊版サイトが、具体的な名称で検索すると1位に表示されてしまうのはなぜか?」という質問を投げかけた辺りがハイライトでした。要するに、著名になってしまった海賊版サイトには、降格シグナルが効きづらくなっているのでは? という指摘なのですが、翻訳の問題なのか、少しズレた回答が返っていました。時間の都合もあり、詳しい質疑応答はテキストでやりましょう、となったので、そのうち(CloudFlareも含め)いろいろ情報が出てくると思われます。こちらも要注目。
国税庁、e-Taxの接続障害に伴う「青色申告特別控除65万円」の取り扱いについて発表〈INTERNET Watch(2022年3月18日)〉
締切前日の3月14日から、e-Taxで断続的に接続障害が起きていました。それが理由で締切に間に合わなかった場合でも、申請すれば、青色申告特別控除65万円の適用が受けられることになりました。e-Taxではなく紙で提出してしまった場合も、申請したうえでe-Taxで出し直せばOK。延長期限は4月15日まで。ちなみに私も認証が通らず少し難儀しましたが、無事3月15日に提出済みです。ギリギリにやるな、という天の声でしょうか……?
社会
国立国会図書館デジタルコレクションに、図書、雑誌等約2万3,500点を追加:パッケージ系電子出版物約300点も含む〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年3月15日)〉
ちょっと「お?」と思ったニュース。パッケージ系電子出版物、つまりCD-ROMやDVD-ROMやUSBメモリなど物理メディアで所蔵されている資料が、国立国会図書館の館内限定ですが、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧できるようになりました。これ、今回が初めてではないでしょうか? チェックしてみたら、「国会図書館限定」と「パッケージ系電子出版物/図書」が並んで表示されました。
紙の資料は、メディア(媒体)とコンテンツ(内容)が一体になっています。メディアがちゃんと保存されてれば、コンテンツが読めなくなることは(あまり)ありません。ところがパッケージ系電子出版物は、メディアの陳腐化、再生装置の入手困難化、プロプライエタリなフォーマットなど、いろんな意味で寿命が短いです。そのため国立国会図書館では「長期保存基本計画」が策定されています。実施された保存対策の成果(の一つ)がこれ、ということでしょう。
ちなみに、物理メディアのない「オンライン資料」――いわゆる電子書籍や電子雑誌は、現時点では「無償かつDRMなし」だけが収集対象になっていますが、2023年1月から「有償DRMあり」も収集対象となる予定です。収集書誌部の方から、これは出版社に限った話ではなく、個人の有償電子出版物も納本を受け付ける予定と伺っています。オンライン申請できるようになるみたいです。代償金はゼロですが、国が、その威信にかけて後世へ残してくれます。楽しみですね。
「パソコンをつかって図書館サービスを体験してみませんか?」を開催〈門真市(2022年3月18日)〉
大阪府門真市の図書館で行われたワークショップのフォトレポート。「かどま電子図書館(LibrariE&TRC-DL)」や国立国会図書館デジタルコレクションなどのレクチャーが行われたそうです。たまたまGoogleアラートに引っかかってきて、恐らくそれほど珍しい取り組みではないとは思うのですが、「こういう取り組みこそが重要だ!」と強く感じたためピックアップしました。デジタルデバイドの解消は、今後の図書館の責務でもあると思うのです。
集英社、宗教2世への取材漫画を打ち切り 「特定の宗教や団体の信者を傷つけるものになっていた」〈ねとらぼ(2022年3月18日)〉
集英社ノンフィクション編集部のウェブメディア「よみタイ」で連載されていた菊池真理子さんの漫画『「神様」のいる家で育ちました~宗教2世な私たち~』が打ち切りに。集英社の弱腰な対応に批判が集まっています。題材として宗教を扱う時点でセンシティブなのは分かっていたはずだし、批判が来るのも覚悟の上ではなかったのか、と。
ただ、もし自分が本件の編集担当だったら、どのような対応が可能だろうか? と考え始めたら、しばらく考え込んでしまいました。体験談を一人称視点で描いているわけですから、「あくまで当事者が感じたことであり、教義を批判しているわけではない」という抗弁ならできるかも? それも「会社が守ってくれる」立場であれば、の話ですが。
関連して、昨年、藤本タツキさんが「少年ジャンプ+」で公開した読み切り作品『ルックバック』が、精神疾患の描写で批判を受け、一部が修正、その後の単行本でも再修正された「事件」を思い出しました。その経緯と是非については、こちらの論考が非常に良いです。こちらも集英社ですが、編集部が違います。外部の声に屈したのは同じでも、「修正」か「削除」かは大違い。
経済
「新聞」はもともとデジタルだった?〈Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)(2022年3月13日)〉
元朝日新聞の服部桂さんによる、「新聞」というビジネスモデルの歴史と今後についてのコラム。マーシャル・マクルーハンの発言に触れ、「その流儀で言うなら、新聞社は新聞ではなくニュースを扱うビジネスだ」と話を繫げているのは、ある意味、期待通りでした。『マクルーハンはメッセージ』という御著書もありますからね。
従来の「新聞」は輪転機で紙に印刷し、地域の販売店が定期購読の契約を獲得して配達する「戸別配達制度」に支えられたビジネスモデルでした。それが、パーソナルデバイスが普及し誰もがいつでも簡単にインターネットへアクセス可能な状態になった現在に至るまで、大きくは転換できていないのが現状です。
――と、批判的な指摘をするのは簡単なのですが、「じゃあ今の状況からどうすれば?」は難しい。服部さんも言われるように、複製のための巨大装置と販売店網という遺産(レガシー)を、簡単には捨てられません。そこでは大変厳しい「撤退戦」を強いられます。私はゼロ年代前半に情報誌の世界で撤退戦を体験しましたが、読者へ届ける情報の質を落とさず(最重要)メディア(媒体)を切り替えていくのは至難の業です。
どこの誰が書いたかわからない真偽不明な怪しい情報に比べたら、まだ、新聞はかなりマシな情報源(高く評価している表現)です。もちろん鵜呑みにはできません。誤報もあるし、偏りもあるし、情報の質が落ちているのも感じますが、相対的にはまだかなりマシ。だから、無くなってしまうのは、私は困る。なんとか、うまく、ビジネスモデルを転換して欲しいものです。
好調アマゾンが対面式書店から撤退へ、リアル店舗事業を絞る理由〈日経クロステック(xTECH)(2022年3月14日)〉
#512 で取り上げた、アマゾンがアメリカとイギリスで本の実店舗販売から撤退する件の続報です。やはり、ジェフ・ベゾス氏がCEOを退いてから株価が低迷している点が理由に挙げられています。主力の直営EC部門で営業費用が膨らみ赤字化しているぶんを、クラウド(AWS)と広告が埋めている状態ですから、「高くつく趣味のようなもの」という指摘があるような事業部門のリストラクチャを図るのは、まあ、当然のことでしょう。
新興ウェブトゥーン制作事業者を苦しめる王者「ピッコマ」の“取引条件”〈DIAMOND SIGNAL(2022年3月17日)〉
取引条件が公開されています。ここ数カ月、独占配信で28%、非独占配信で25%という料率が提示されているそうです。その是非はともかくとして、ピッコマはApp StoreとGoogle Playの決済に強く依存しているので、この低料率の理由はApple税とGoogle税で30%抜かれているからだろう、という事情は推測できます。
ピッコマが「世界1位」と言われていますが、それはApp StoreとGoogle Playに限ればの話。自社決済が強い「Kindle」や「Kobo」などはランキングに入ってません。個人的には、「独占」条件を飲むことはイコール「一強」を育てることだと思うので、悪条件を飲むか否かはよくよく考えていただきたいなと思います。縦スク配信できるプラットフォームは、ピッコマだけじゃありませんからね。
技術
神社の御朱印NFTを無料配布、博報堂らが新たな地方創生施策の実証実験〈日経クロステック(xTECH)(2022年3月16日)〉
この記事、出版とは直接関係しないのですが、#444 でも取り上げた、書店で貰える「御書印プロジェクト」にも応用可能だと思ったためピックアップ。「御朱印をデザインしたNFTを紙の御朱印を授けられた人に無料で配布する実証実験」です。御朱印NFTを手に入れるには、その神社へリアルに足を運ぶ必要があります。つまり、集客に活用できるわけです。
以前、毎日新聞で「御城印NFT」の取り組みが取り上げられたのですが、ただ単に御城印の画像がNFTマーケットで数量限定販売されるだけだったので、正直、拍子抜けでした。Twitterでも「現地へ行かないと買えない、くらいの仕掛けがあってもいい」とつぶやいたのですが、この「御朱印NFT」はまさにそういう仕掛けです。NFTの正しい活用法だと思います。
イベント
【特番】出版DX これでいいのか、電子書籍市場 ―― HON.jp News Casting / ゲスト:落合早苗(O2Obook.biz 代表取締役社長)〈HON.jp(オンライン)/3月27日〉
3月27日は2時間の特番! O2O Book Biz株式会社 代表取締役 落合早苗さんをゲストに迎え、コミックが4割超を占めるようになった出版市場のこの四半期の動向を中心に話を伺います。
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
実は、私の家にはテレビがありません。だから、いまテレビ放送がどんなトーンなのかは、テレビ局系ウェブメディアの文字情報や反響の声から想像するしかありません。でも、私がテレビを見なくなった原因の一つである、専門知識皆無なコメンテーターによる断定的で無責任な放談がいまなお止むことなく続いている――という雰囲気は、なんとなく伝わってきて暗い気分になります。戦争反対!(鷹野)