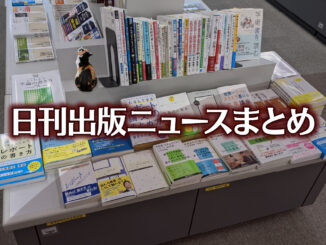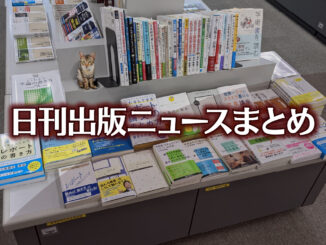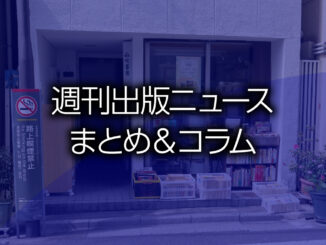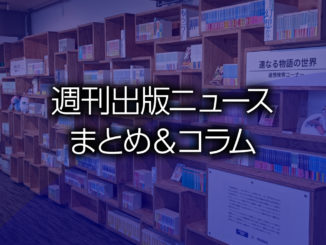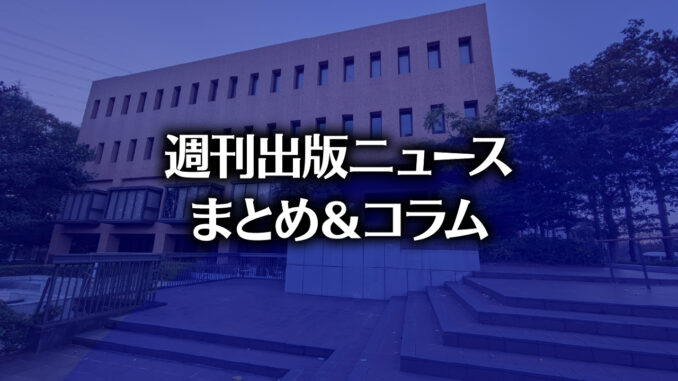
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年4月13日~19日は「オンラインカジノにサイトブロッキングの検討」「三笠書房新刊『困った人』に日本自閉症協会が声明」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
HON.jp Podcasting「#27 自分の作品が勝手に利用される(かもしれない)制度(2025年4月15日版)」を配信しました
未管理著作物裁定制度について取り上げてほしいというお手紙が届きました。さすがに簡単に済むような内容ではなく、台本執筆には2日間かかりました。しかも収録してみたら約50分間と過去最長に。このポッドキャストの方針は「深掘り」だから、私としては良いんですけど、聞いていただいている方々にとってはどうなんだろう? もっと長くてもいい? 短くしてほしい?
制度そのものについては、クリエイター側の「自分の作品をウェブに公開すると、公的なお墨付きで勝手に使われてしまうかもしれない」という懸念は、理解はできます。ただ、利用する側の立場で考えてみると、そんな簡単な話ではないんですよね。従来の制度と異なり、裁定を受けたあとでも権利者の申し出で利用が止められるから。かなりリスクがあります。トラップを仕掛ける人も出てきそう。
この番組ではみなさまからのお便りをお待ちしています。「こんなトピックスを取り上げて欲しい」とか「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。こちらのページでフォームから送付できます。
政治
Google「検索」に排除措置命令、公正取引委員会が違反認定 巨大ITで初〈日本経済新聞(2025年4月15日)〉
かつて「吠えない番犬」と揶揄されたこともあった公取委が、とうとう巨大IT企業に対し「確約手続き」ではなく「排除措置命令」を出しました。伝家の宝刀をついに抜いた! 感があります。しかし、このタイミングかあ……トランプ政権に「非関税障壁だ!」とつけ込まれてしまうかもしれません。
公取委のGoogle排除命令で、割を食うのは結局日本メーカーのワケ ソニーやシャープのスマホ事業に痛手(石川温)〈CNET Japan(2025年4月15日)〉
Googleに排除措置命令、評価や実効性は 専門家の見方〈日本経済新聞(2025年4月16日)〉
その影響についてもさまざまな意見が出ていますので、参考まで。
日本からのオンラインカジノ利用、強制遮断は可能か 総務省が検討会–「通信の秘密」どうなる〈CNET Japan(2025年4月17日)〉
本と直接関わる内容ではないのですが、強制遮断(サイトブロッキング)の是非について政府の検討会でまた議論が始まるということで、ピックアップしておきます。もしここで「ブロッキングしてもよい」という結論が出ると、次は、こんどこそ海賊版サイトという話になるでしょう。
報道資料|「オンラインカジノに係るアクセス抑止の在り方に関する検討会」の開催〈総務省(2025年4月16日)〉
検討会の構成員を見たら、海賊版サイトのブロッキングを検討していた2018年当時、猛反対していた森亮二氏(英知法律事務所弁護士)が入っていることに気がつきました。座長は恐らく曽我部真裕氏かな? あと、山口寿一氏(読売新聞グループ本社 代表取締役社長)が入っていることには、いささか異様なものを感じます。
ちなみに読売新聞は2018年当時「海賊版サイト 接続遮断はやむを得ぬ措置だ」という政権擁護の社説を出し、日本インターネットプロバイダー協会(JAIPA)から厳重に抗議されています(その社説はすでにウェブ上からは消えているので、図書館へ行って縮刷版を改めて確認してきました)。今回のネットカジノも「違法な賭博を野放しにするな」という社説で「(ブロッキングの)導入を検討すべきだ」と主張していますから、読売新聞はブロッキング推進派なのでしょう。検討会、また荒れそうだなあ。
グーグルが広告技術で「独占」、米地裁が認定 売却や分割迫られる恐れ〈ロイター(2025年4月18日)〉
昨年には検索サービスでGoogleの「独占」を認定する判決が出ていました。今度は広告です。Googleはもちろん控訴する方針とのことなので、まだ確定はしていません。しかしこれ、2000年にMicrosoftが司法省に独占禁止法で訴えられたときのことを思い出します。連邦地裁は分割命令を出したんですけど、控訴審でひっくり返されてるんですよね。
社会
(前半無料)私の本のAI要約が販売されていたことと、今後の対策について。〈内藤みか(作家)(2025年4月13日)〉
おお……とうとう身近なところでもこういう事例が出てきましたか。お疲れさまです。やはり売れてる本が狙われやすいようですね。しかし、警告したら瞬時に消えたというのがバカっぽい。AI要約でも制作には地味に手間はかかっているでしょうに、訴えられるリスクを考えていなかったのか。まあ、海賊版DVDとかグッズ販売で逮捕される事例も後を絶たないですし、悪いことだと思っていなかったのかも。
子ども向けサイトに性的な広告 「急激に荒れてきた」ネットの事情〈朝日新聞(2025年4月13日)〉
先週には日経がほぼ同じスタンスの記事を出していましたが、今週はネット広告の業界団体JIAAに対し性的な広告への対応を要求する署名が提出されたこともあり、この問題を取り上げるところが多くなっています。ポッドキャスト「#23 下品な広告(2025年3月18日版)」でも触れましたが、根本的な問題はプラットフォームがザル審査なところです。
後述しますが、Googleは年間51億件の不正広告を停止しているそうです。他に比べたらマシなほうですけど、それでもまだザルなのですよね。Google以外の広告プラットフォームはもっとザル。広告審査のコストをメディア側に丸投げしているようなところもあります。そういう広告システムを導入しちゃったメディアは、目も当てられないような酷いありさまになっています。
性的なネット広告、一筋縄ではいかない規制 業界全体でルール作りを〈朝日新聞(2025年4月18日)〉
こちらは冷静で論理的でまっとうな御意見。刑法には抵触しない“露骨なわいせつ表現ではないものの、性的な場面などを「におわせる」ようなもの”だから、プラットフォームの審査はすり抜けやすい。問題はそのあとで、メディア側が「そういう広告は載せたくない」と思ったとき、容易にブロックできる仕組みだったらここまで問題にはならないはずなんですよね。
というか、メディア側でもブロックできることを、どうやらメディア側でも知らない人が多いみたい。Google AdSenseの場合、管理画面にある[ブランド保護]の[ブロックのコントロール]がけっこう優秀。私が「Googleはマシ」だと言うのは、これが理由のひとつです。だけど「たぶんこれデフォルトのまま使ってるよな」と感じるようなメディアも、残念ながら多いんですよね。
ちなみに、いま話題になってるエロ広告って、ゲームも多いけどマンガアプリも多いと思うんですよ。あえて名前は挙げませんけど。これは広告主や広告代理店の問題。それなのにユーザーからは、主にメディアが責められちゃうわけです。
以前、「もし法規制するとしたら、詐欺対策と絡めてプラットフォーム事業者をターゲットにすべき」と書いたんですが、もう少し補足しておきます。要は、消費者保護を目的として、メディアで広告を表示する際に「広告主」と「プラットフォーム」の明記とフィードバックや通報する仕組みの提供を義務付けるのはどうか? という案です。
現状でもたとえばGoogle AdSenseの場合、バナー広告の右上から「Ads by Google」をクリックすると「この広告主について」とか「ブロック」「レポート」を送れる画面が出てきます。私が「Googleはマシ」だと言うのは、これも理由です。他の広告プラットフォームだと、「プラットフォームの名前しか出ない」とか「プライバシーポリシーしか表示されない」ようなのも多いんですよね。
あくまで目的は消費者保護・詐欺広告対策です。だから義務化できる。その結果、一般ユーザーから見た広告の透明性は高くなります。違法ではないけど変な広告が表示されたとき、怒りの矛先がメディアだけでなく広告主とプラットフォームにも向かうようになるはずです。矛先を向けられるようになれば、多少はマシになるのでは。
流行の「ジブリ風」画像生成 文科省の見解「作風の類似のみなら著作権侵害に当たらない」〈産経ニュース(2025年4月16日)〉
一般論として、著作権法でアイデアは保護されません。アイデアには、文体、作風、絵柄、コンセプト、テーマ、おおまかな設定、ありふれた表現なども含まれます。だから文科省の見解は至極「ごもっとも」な話です。ですが、記事への反響には「なんで文科省がそんなこと勝手に決めるの!」といった強い反発が観測できます。
同じようなことを平易な言い回しで分かりやすく解説している弁護士・福井健策氏のYouTube動画(TBS CROSS DIG with Bloomberg)にも「自称・著作権法に詳しい」などといった批判コメントが付いていて、頭が痛くなりました。なんかもう完全に「敵」扱いなんですよね。
福井氏は、アイデアは保護されないのが前提だけど、生成AIは素早く大量に出力できてしまうから「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当する可能性もあるといった踏み込んだ発言もしています。これはどちらかといえばクリエイターに寄り添っていると思うんですけどねぇ……。
発達障害を「困った人」発売前の新刊に懸念 出版元の三笠書房が見解〈朝日新聞(2025年4月18日)〉
装画に関するご報告と経緯のご説明〈芦野公平(2025年4月16日)〉
表現の内容はさておき、装画担当者が矢面に立つのはおかしくないか? と怒りを覚えました。4月16日の時点で「出版社から装画制作の経緯についての発信の許可を得」た上で、装画担当者からはこのような説明が出ているのに、三笠書房からは情報発信がなかったのですから。出版社のディレクションで描かれた装画なのだから、出版社はクリエイターを守るべき立場でしょう。
結局、三笠書房から公式見解が出たのは翌々日のことでした。そこには「本書籍のような事前予告に対するご意見について、当社が見解を述べるべきかについて躊躇しました」とあります。躊躇しているうちに、日本自閉症協会から声明が出るなど、だいぶ燃え広がってしまった感があります。著者や装画担当者を守る対応を、もう少し早くできなかったのか。
もっとも、三笠書房の見解末尾の追記にあるような、著者や家族に対する誹謗中傷やなりすましによる嘘情報の拡散といった攻撃は、言語道断です。「法的措置をとる」と断定されてますので、いずれ法の裁きが下るでしょう。群衆の暴走も、困ったものです。
「コンテンツを作るのも見るのもAI」時代のメディアはどう変わる?〈あしたメディア研究会 NEWS(2025年4月19日)〉
以前にも書いたように、私は「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側にある状態になる」と、いくらAIの性能が高くても出力はゴミ化していくという考えです。メディア側もバカじゃありませんから、AIが自分たちの害になると思えば、コンテンツをAIには見られない領域に隠すでしょう。まあ、無料公開の広告モデルがそう簡単に崩壊するとも思いませんが、無料の領域が相対的にだんだんゴミ化してくのは間違いないと思うんですよ。
経済
「goo blog」21年の歴史に幕–全ブログが11月18日で閲覧不可に オーナーに引っ越しなど案内〈CNET Japan(2025年4月14日)〉
ブログサービスがまたひとつ逝ってしまいます。同時に「教えて!goo」もサービス終了が発表されました。ニュースメディアに限らず、無料配信で集客し広告で収益を得るビジネスモデルはもう限界に来ている感があります。
同日、FC2の無料ホームページスペース「FC2WEB」も終了の予告が出ていますが、こちらはずいぶん前から後継の「FC2ホームページ」が提供されており、古い技術で構築されたレガシーシステムを葬る意味合いのほうが強そうです。
日販とトーハン、書籍の返品協業を7月に開始〈日本経済新聞(2025年4月17日)〉
あまり詳しくない領域なのですが、書店関係者には大きな影響がある話みたいなのでピックアップしておきます。雑誌ではすでにやってる協業なのですよね。
技術
「実在しない専門家のコメント」メディアに氾濫、指摘受け相次ぎ削除〈新聞紙学的(2025年4月14日)〉
存在しない論文や記事を出典にするハルシネーションにはわりとよく遭遇しますから、実在しない専門家のコメントを創作してしまうハルシネーションも、まあ、当たり前のようにあるでしょうね。問題は、生成AIの出力を鵜呑みにし、ノーチェックで記事に載せてしまうメディアの体制にあります。無能で説明が付きますから、悪意で捏造しているわけではないでしょう。単なる無能。
グーグルが2024年の不正広告対策レポートを発表、AI活用で51億件を停止〈ケータイ Watch(2025年4月16日)〉
前述した、Googleの不正広告対策レポート。年間51億件ですよ。「どしぇー!」と声が出ました。LINEヤフーが2024年度上半期に不承認とした広告は約8900万件ですから、まさに桁違いです。私が「Google AdSenseはそれでもまだマシなほう」と言っていることの片鱗が、ここから読み取れるでしょうか。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
JEPAビジネス研究委員会の企画で、所沢市のKADOKAWAデジタル製造・物流施設を見学してきました。取材ではないので記事にはしませんが、単にインクジェットの印刷機を自社で持って製造するだけの話ではなく、書店からの発注を受けてすぐ直送する仕組みと物流倉庫がセットになっている点がこのプロジェクトのキモであることがよくわかりました。米ライトニングソース社の方が見学させて欲しいと言ってきたそうですよ。すごい仕組みでした。(鷹野)