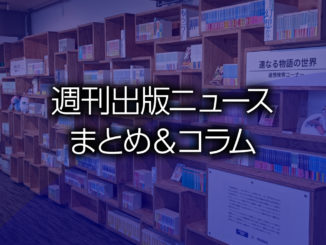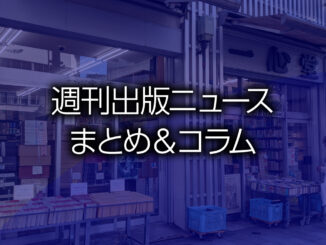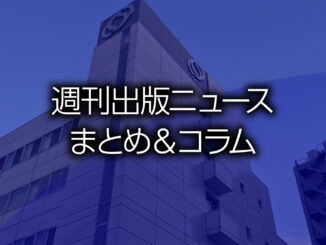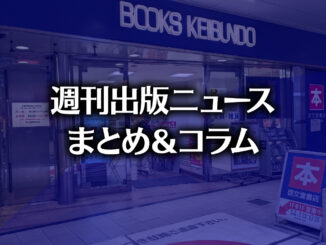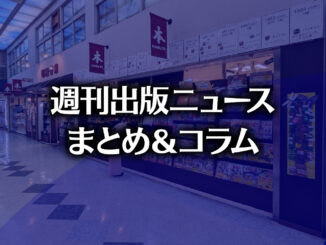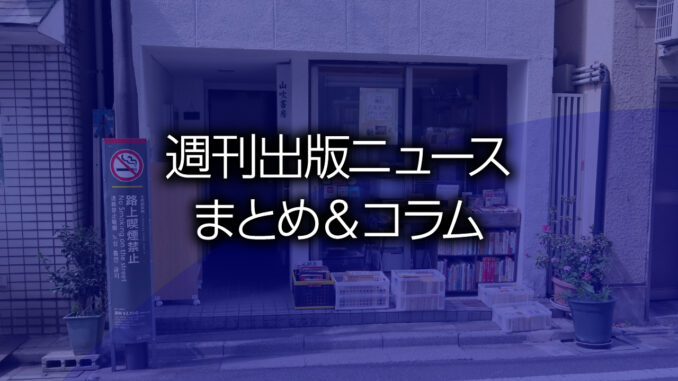
《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
2022年11月13日~19日は「インボイス制度に経過措置検討」「公取委がニュース利用料調査」「pixivでクレカによる表現規制?」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- フリーランスの多くが廃業に追い込まれる…あらゆる団体が「インボイス制度は延期すべき」と訴えるワケ はっきりいって民間にはなにひとつメリットがない〈PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)(2022年11月14日)〉
- ステマを不当表示に 指定告示案の検討進む…消費者庁〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2022年11月14日)〉
- ニュース利用料不当に安い恐れ 公取委、巨大IT調査へ〈産経ニュース(2022年11月16日)〉
- なぜファスト映画による著作権侵害の賠償金額が5億円になってしまうのか(栗原潔)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年11月18日)〉
- 過去の経済産業省委託事業「コンテンツ緊急電子化事業」のURLを用いたサイトに御注意ください!〈METI/経済産業省(2022年11月18日)〉
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
フリーランスの多くが廃業に追い込まれる…あらゆる団体が「インボイス制度は延期すべき」と訴えるワケ はっきりいって民間にはなにひとつメリットがない〈PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)(2022年11月14日)〉
インボイス来秋導入で大混乱!苦闘する税理士 | 特集〈東洋経済オンライン(2022年11月14日)〉
納税免除ルールを無効化、財務省の「インボイス制度」が日本経済を破壊する | DOL特別レポート〈ダイヤモンド・オンライン(2022年11月14日)〉
プレジデント、東洋経済、ダイヤモンドが示し合わせたように同日、インボイス制度の問題を指摘する記事を配信していて驚きました。この後の政府・与党の動きを見るに、反対の声は多少なりとも意味があったように思います。インボイス制度そのものは軽減税率が導入された際に決まっている(※消費税率が10%に上がったのは2019年10月1日以降)ので、このままなら行政機関は粛々と進めるのみ。開始まで1年切ったいまから変えるとしたら、政治の力しかありません。法改正が必要な部分は国会での採決が必要ですが、経過措置に関わる部分は政令なので内閣だけで決められます。これが後述の、政府・与党の対策案に関わってくるのかな、と。
インボイスで漫画家の2割が廃業も? 危機感抱くエンタメ業界 声優・アニメ・演劇団体と共同記者会見〈ITmedia NEWS(2022年11月16日)〉
しかし、こういった「反対の声」が、4大紙+日経のウェブサイトを検索してもまったく出てこないことは改めて指摘しておく必要があるでしょう(唯一、毎日新聞は「ORICON NEWS」配信記事を転載しています)。新聞は軽減税率が適用されてますので、あまりおおっぴらな反対論陣が張りづらい事情があるのでしょう。テレビ系も、クロスオーナーシップの関係か、新聞に追従している?
ちなみに、新聞が軽減税率の対象になっていることで直接恩恵を受けるのは、新聞社ではなく新聞販売所です。新聞販売所は、定期購読の新聞代金を消費税8%で販売していますが、仕入の消費税は10%です。つまり差引2%ぶん、仕入税額控除により納付すべき消費税が少なくなります。新聞社には、新聞販売所が助かる=戸別配達制度の維持、という間接的な恩恵があります。
小規模業者、インボイスなしでも税額控除 政府・与党〈日本経済新聞(2022年11月18日)〉
で、政府・与党から出てきた対策案がこれ。施行令に関わる部分だから、国会を通す必要がない対策です。見出しの「小規模業者」に一瞬期待させられますが、よく読むと、1万円未満の少額取引について「請求書等の保存の有無に関わらず帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める」という時限措置が検討されているに過ぎません。うーん……事業規模あんまり関係ない。むしろこれ、1回の取引額を1万円未満に抑制する圧がかかってしまう可能性がありそう。
いちおう、課税事業者になることを強いられている現・免税事業者にとっても、今後急増が予想される事務処理コストを軽減できるメリットはあるので、無意味ではありません。でもこれってむしろ、事務処理件数が多い大規模事業者のほうが助かる措置では。
[2022年12月4日追記:改めて記事に目を通したら、「事業者は課税売上高で年1億円以下に絞る案がある」と書かれてますね……つまり当初から、中小規模事業者だけを対象とした措置を検討していたことに。こんなの見落とすかなあ……大変失礼しました。]
ちなみにこれ、日本税理士会連合会が要求している経過措置では従来の3万円未満を継続する話ですから、1万円未満ってむしろ後退している……。
そもそもインボイス制度が「税率が分かれた消費税の正確な納税に欠かせない仕組み」というのは、ただのタテマエですよね。対象品目って現状、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読」だけなんですから。対象品目の売上・仕入れがない事業者は、みんな10%ですよ。「ごく一部にだけ適用される軽減税率のために全体を巻き込むな!」って言いたい。
ステマを不当表示に 指定告示案の検討進む…消費者庁〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2022年11月14日)〉
第6回ステルスマーケティングに関する検討会を受けての記事。だいぶ固まってきたようなので、改めて運用基準の方向性(案)を読んでみました。とくに「事業者が第三者をして行わせる表示の例としては、SNSを使った投稿、ECサイトのレビュー投稿、アフィリエイトプログラムを用いた広告表示等が含まれる」については、大きな影響が出そうだと感じました。
要するに、アフィリエイトも【広告】と明記しないとステマになってしまうわけです。で、問題は、今回の指定告示の対象である「事業者」は誰なのか? という点。これに先立つ「アフィリエイト広告等に関する検討会」の報告書では、景品表示法の表示主体は「広告主」であることを周知徹底とあります。つまり、規制の対象はアフィリエイト・サービス・プロバイダ(ASP)や広告代理店、アフィリエイターではないのです。
では、たとえば「Amazonアソシエイト」はどうか? 普通に考えると広告主はAmazonです。つまり、アフィリエイターが「Amazonアソシエイト」のリンク周辺に【広告】と表記しないと、ステマ規制に引っかかるのはAmazonです。わお。現実的に考えると、成約後にAmazonが表示を確認して【広告】と書いてない場合は報酬を発生させない、みたいな運用になりそう。返品・返金があった場合と同様、マイナスの数字が出てくることになるでしょう。そういうケースが爆発的に増えるかも?
ニュース利用料不当に安い恐れ 公取委、巨大IT調査へ〈産経ニュース(2022年11月16日)〉
ついにそこへメスが入りますか。記事には公正取引委員会の発表とありますが、個別の発表ではなく事務総長定例会見の中での言及でした。公正取引委員会のサイト更新はウォッチしてるのですが、これはさすがに見出しだけだと気づかない……とほほ。
最大のターゲットはどう考えても「ヤフーニュース」ですが、事務総長との質疑応答には「Yahoo!ニュース、スマートニュース、LineNews、グノシー、Googleニュース」などをニュースプラットフォームとして認識しているとありました。これ、契約に基づき全文転載しているところと、Googleニュースみたいに見出しとサムネイルだけが自動で載るところとは、切り分けたほうがよさそう。配信先だけで完結するプラットフォームと、自社メディアへの流入促進に繫がるプラットフォームは、別物ですから。
なぜファスト映画による著作権侵害の賠償金額が5億円になってしまうのか(栗原潔)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年11月18日)〉
著作権法114条の規定により、賠償額が1回の再生につき200円と算定された判決。レンタル配信が1作品400円を下らないことなどが踏まえられているそうです。ファスト映画(無断要約)でこれですから、まるごと配信していた「漫画村」の賠償額はもっととんでもない額になりそう。閲覧回数は、検察が押収したデータにあるのかな?
過去の経済産業省委託事業「コンテンツ緊急電子化事業」のURLを用いたサイトに御注意ください!〈METI/経済産業省(2022年11月18日)〉
経産省から注意喚起。というか、あなたたちが「緊デジ」のサイトを消してドメインを手放したのが原因なんですけどね。「緊デジ」事業の終了は2013年3月31日。同6月3日にタイトル一覧が公開されて批判に火がつき、その1年後にサイトを閉じると発表。さっさと幕引きを図った結果がこれですから。ちなみに「Wayback Machine」にもあまり記録が残っていませんが、2015年8月にはもう「BUY THIS DOMAIN」表示になっています。
なお、内閣官房のドメイン管理ガイドができたのは2015年6月ですから、「緊デジ」サイトが閉鎖されたのはその前のできごとです。いまはgoドメインの使用が遵守事項になっていますので、今後はこういうことはあまり起きないはず……起きないでね?
社会
※デジタル出版論の連載はお休みしました。しばらく不定期連載になります。ご了承ください。
新聞定期購読、6割以下に : メディア信頼度トップはNHK〈nippon.com(2022年11月15日)〉
新聞通信調査会が毎年やっている「メディアに関する世論調査」の結果。前から思ってるんですが、メディアの分類が「NHKテレビ」「新聞」「民放テレビ」「ラジオ」「雑誌」「インターネット」って、あまりに雑じゃありませんか? 実際に自分がこのアンケートに答えてくれと依頼されたら、正直、困っちゃうと思うんですよね。
たとえば「新聞」は、大手紙の中でも差がありますし、スポーツ紙の信頼度は格段に下がります。「雑誌」だって、編集部によって違うでしょう。「テレビ」は見ないので知りません。「インターネット」なんか、既存の四大マスメディアが配信している記事もあれば、匿名掲示板みたいなのまであり、信頼度にはものすごーく幅があります。包摂して考えるとしたら、信頼度が低い部分に足を引っ張られるから、そりゃ自ずと低くなりますよね。
E2554 – 電子書籍のアクセシビリティに関する日本産業規格〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年11月17日)〉
ご自身も視覚障害者である植村要さんによる、JIS規格制定についての論考です。JISやISOが参照している関連文書がいろいろあって煩雑なのと、関連文書は規格制定後もアップデートされている(規格が参照している文書が最新ではない)というのは、重要な指摘だと思いました。他にもさまざまな課題が指摘されています。
私は以前も書いたように(#535)、紙との差異を小さくする意味で「ページナビゲーション(静的な改ページ位置へのナビゲーションを提供)」が最も留意すべき点だと考えます。制作ツールやビューア側の対応が必要です。
経済
Gakken、無料のまんがサイト「ガッコミ」を公開、毎週金曜に更新 日本の歴史、科学ふしぎクエストシリーズなど16作品を公開、順次拡大〈こどもとIT(2022年11月14日)〉
新たな出版社直営の無料マンガサイトがオープン。「NEW日本の歴史」などが公開されています。ちょっと試しに読んでみましたが、最後のページから次のアクションへ誘導する工夫が欲しいと感じました。1話2話と公開されているのに、1話の最後から2話への誘導がないので、一覧ページへ戻ってから2話を開くという2ステップが必要になっています。ステップが1つでも余計にあると、それだけ離脱者が増えますよ。もったいない。
なお、株式会社Gakkenは10月1日付けにてスタートした総合出版社で、学研教育みらいを存続会社とし、学研プラス、学研メディカル秀潤社、学研出版サービスと合併、さらに、学研エデュケーショナルの一部部門を移管しています。存在は認識していましたが、本欄でピックアップしていなかったので、この機会に紹介します。
米アマゾン、1万人削減へ 米報道、週内にも開始〈共同通信(2022年11月15日)〉
赤字のスマートスピーカー「アレクサ」を中心としたデバイス部門や、人事、小売部門での人員削減とのこと。書籍販売やレビューチームも含まれるという続報もありました。日本国内はどうなるかまだわかりませんが、グローバルでは出版物に関連する部署で大きな動きがある、ということは頭に入れておいたほうがよいでしょう。

米ハイテク企業で始まった「大量解雇」真の理由 | The New York Times〈東洋経済オンライン(2022年11月16日)〉
Twitter、Metaに続いてAmazonも……といったところで、このような「巨大IT企業」とか「GAFA」などと雑にまとめて語る報道を散見します。いまのところMicrosoft、Appleは、採用ストップという話はあれど、削減まではいかず。Googleも現段階では削減のうわさのみ。それぞれ得意分野や業態もぜんぜん違いますから、少し注意が必要でしょう。
「児ポ」「獣姦」──pixivの一部サービスで規制強化、対応なければアカ停止も ユーザーからは批判相次ぐ〈ITmedia NEWS(2022年11月15日)〉
pixivから「決済を伴う取引に関するサービス共通利用規約改定の事前のお知らせとお願い」というお知らせが出ています。本稿執筆時点で新しい規約はまだ公開されていませんが、現時点でも「国際カードブランド等の規約でも、下記を含むコンテンツや商品の取引が禁止されております」という記述があり、カード会社からの圧力があったのではないかと推測されています。
7月にはDMMとFANZAがMastercardの取り扱い終了という動きがあったばかりなので、pixivは弱腰ではないかといった批判が散見されています。私は当時も書いたように、これは民間による表現規制なので、具体的にどうやって対抗すればいいかが思いつかないのが正直なところ。
ただ、今回のpixivに関しては、日本でも違法である実在児童の性虐待記録物(私は被害者のいない創作との混同を避ける意味で「児童ポルノ」とは呼びません)などが、大量のAI生成コンテンツなどに紛れて販売されていたようです(私は未確認)。どうやらその対処が必要になっている、ということのよう。詳しくは、山本一郎さんによる経緯まとめ記事をご参照ください。クレジットカード会社は「Pornhub」に対する訴訟の巻き添えを食らった、などの背景にも触れられています。
技術
Googleやメタ、ネット広告をプライバシー配慮型に転換〈日本経済新聞(2022年11月14日)〉
サードパーティクッキー廃止に向け、新たな方式に転換が進められています。そういえば先日、「Google Ad Manager」から「広告のパーソナライズに対応できるようファーストパーティ Cookie が更新されました」というお知らせが届いていました。ヘルプページもできてますね。
インテル、96%の精度でディープフェイクを検出する新技術「FakeCatcher」〈CNET Japan(2022年11月18日)〉
フェイクニュースを潰すためには、こういったディープフェイクの検出も重要です。もう一歩進めて、AI生成コンテンツの検出が可能になれば、いろんな意味でさらにニーズが高くなりそう。べつにAI生成コンテンツが「ダメ」というわけではないのですが、区別はできるようになって欲しいなと。
お知らせ
イベント
11月28日開催の日本出版学会出版デジタル研究部会(HON.jp共催)は『パブリッシング・スタディーズ』第4章「書籍」第3節「デジタル化と今後の展開」の執筆を担当した林智彦会員(有斐閣)にご報告いただきます。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
すっかり忘れていたんですが、「週刊出版ニュースまとめ&コラム」はこの8月に10周年を迎えてました(過去形)。2012年8月に個人ブログで始めた当初は単に「気になるニュースまとめ」という名称で、著作権、電子書籍、IT技術のニュースをまとめてコメントするコーナーでした。長年のご愛顧に感謝いたします(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。