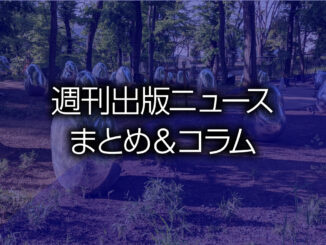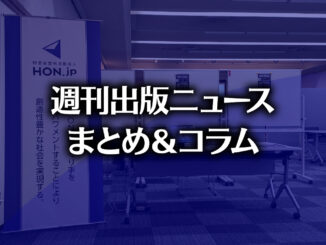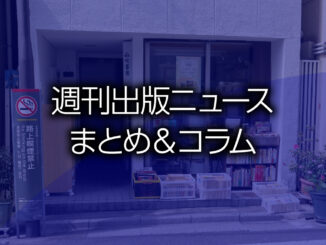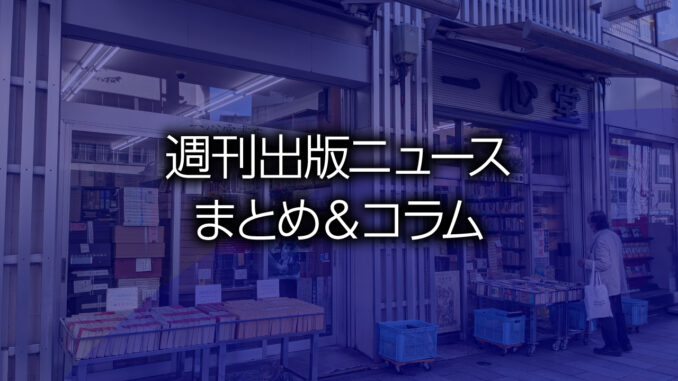
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2022年2月13日~19日は「TechCrunch Japan、Engadget日本版が閉鎖へ」「鬼滅の刃アニメ関連で分断煽りのマッチポンプ報道」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- ブックライブ、創作者向け基盤 発信・販売機能を一元化〈日本経済新聞(2022年2月16日)〉
- エンガジェット、TechCrunch日本版の終了を惜しむ 海外メディアの運営って結構大変という話:ヤマーとマツの、ねえこれ知ってる?〈ITmedia NEWS(2022年2月16日)〉
- 創業以来最大の赤字:朝日新聞社で今、何が起きているのか〈nippon.com(2022年2月16日)〉
- ブックライブ for Androidアプリの提供方法の変更について〈株式会社BookLive(2022年2月17日)〉
- 鬼滅の刃「物議」報道で考える、炎上や対立をあおるメディアとポータルサイトの構造問題(徳力基彦)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年2月19日)〉
- 技術
- お知らせ
- メルマガについて
- 雑記
政治
NHK改革の「進展を」 有識者会議に新聞協会が意見〈共同通信(2022年2月16日)〉
総務省の公式サイトに「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」の配付資料が公開されたという新着情報があり、「あまり関係なさそうだな……」と思いつつ念のためページを開いてみたら、ヒアリング対象に「一般社団法人日本新聞協会」の名前が。放送制度の話になぜ日本新聞協会が? と驚きました。
デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(第5回)配付資料〈総務省(2022年2月16日)〉
日本新聞協会の資料(5-1)を見ると、“NHKのネット業務は受信料を原資にした「放送の補完」であり、その拡大は民間メディアの事業に影響を与えかねません。” などの主張が。いわゆる「民業圧迫」という批判です。なるほど。NHKが過去記事をすぐ消してしまう理由の一つに、こういう圧力があるからだろうなあ、と思いました。
そういえば放送法の「マスメディア集中排除原則」ってありましたねぇ……新聞社とテレビ局はグループ企業ではなく「系列」とか「提携会社」「協力会社」という扱いになっています。2004年に読売新聞が日本テレビを実効支配していることが発覚した問題とか、2005年のライブドアによるニッポン放送へのTOBとか、いろいろあったのを思い出しました。
社会
トレースはもはや「つみ」状態なのか 引用とオマージュと再構築の果てに浮かび上がった問題とは?:小寺信良のIT大作戦〈ITmedia NEWS(2022年2月14日)〉
いわゆる「トレパク」問題について。イラストレーター・古塔つみ氏から「引用・オマージュ・再構築として制作した一部の作品を、権利者の許諾を得ずに投稿・販売してしまったことは事実」という謝罪文が出ています。その「引用・オマージュ・再構築」という表現も、ちょっと引っかかるよね、といった話。
出典を明示してないからそもそも「引用」ではないとか、「オマージュ」なら原作への敬意が必要だとか、逆に、トレースという技法そのものがアウトみたいな誤った批判も散見される、などなど、「トレパク」疑惑が話題になるたび、繰り返されてきた議論でもあります。
この騒動を見ていて思い出したのが、福井健策さんの「ファストコンテンツって、悪いのか?」というコラム。「合法」か「違法」かという法的な評価軸とは別に、「燃えにくい」か「燃えやすい」かという社会的な評価軸で整理できそう、という話です。手書きのマトリックス図が分かりやすい。ファストコンテンツ(要約)だけでなく、今回のトレパク騒動にも応用できそうです。
あくまで一般論ですが、イラストなら「絵柄」「モチーフ」「構図」「ポーズ」などはアイデアの範疇とされ、合法である可能性が高いです。今回の騒動で言えば、小寺さんも挙げている『AKIRA』のバイクは、さすがにその範疇を踏み越えているように思えます。しかし、糾弾の対象になっている作品の中には、もし法廷で争われたら合法だと判断されそうなものまで混在しているように思えます。擁護するわけではなく、法的な判断と、社会的に許されるか否かのラインは異なるということです。
インターネット白書ARCHIVESで2021年版が無料公開に ~ 最新版『インターネット白書2022』発行に合わせ〈HON.jp News Blog(2022年2月14日)〉
毎年恒例、1年前のインターネット白書が無料公開されました。過去25年分のバックナンバーが、誰でも検索・閲覧できます。TIMEMAPの年表表示は、検索したキーワードがいつごろから話題になったかが把握できて便利です。
たとえば「マンガ」と検索すると、インターネット白書では1999年版、イースト下川和男さんによる「インターネットと共に変わる電子出版」で、電子書籍コンソーシアムについて説明している中で触れられたのが初出、ということがすぐに分かります。興味深い。調べ物が捗ります。
経済
ブックライブ、創作者向け基盤 発信・販売機能を一元化〈日本経済新聞(2022年2月16日)〉
凸版印刷のグループ会社で電子書店「ブックライブ」を運営するBookLiveが、マンガやイラストのアップロード、販売、ポートフォリオ、コミュニティといった機能を統合したプラットフォーム「Xfolio(クロスフォリオ)」を開始した、というニュース。クリエイターエコノミーへの本格参入、と言って良いでしょう。サイトを見てみたら「クローズドβ参加クリエイター」という欄があるので、いきなり始めたわけではなく、前から準備を進めていたようです。知らなかった。
プレスリリースには「ポートフォリオ+ダウンロード販売+自家通販+ファンコミュニティ機能が1つのプラットフォームとして揃ったクリエイター向けサービスとして業界初」と謳われています。ほんとうに初かどうかはともかく、先行他社の「各機能において最適化された」サービス(pixiv「BOOTH」や集英社「MangaFolio」など)とどう差別化するか、どうやってクリエイターを集めるか。今後、マンガ・イラスト以外のカテゴリ追加や、投げ銭機能、NFTマーケットなども予定されているようです。大手企業グループのやることですし、今後の動向にも要注目です。
エンガジェット、TechCrunch日本版の終了を惜しむ 海外メディアの運営って結構大変という話:ヤマーとマツの、ねえこれ知ってる?〈ITmedia NEWS(2022年2月16日)〉
TechCrunch Japanおよびエンガジェット日本版 終了のお知らせ〈Boundless株式会社(バウンドレス)(2022年2月15日)〉
ライター、編集者、翻訳者など周囲の方々が騒然としていたニュース。親会社が転々とした挙げ句、投資会社によるリストラ。記事アーカイブさえ残さず消えるという、なんとも言えない、切ない終わり方です。運営元のVerizon Media JapanがBoundlessと名前を変えていたこと、気づかなかったなあ……。
ちなみにこういう、法人がサイトを消すという判断をした場合に、従業員として書いた記事なら「職務著作」なので、書いた本人には著作権がありません。つまり、どうしようもない。外部の寄稿者なら、その法人との契約次第です。著作権譲渡という条件が明示されていたなら、やはり、どうしようもありませんが、とくになにも交わしてないなら「初出をそのメディアに委ねただけ」なので、著作権は寄稿者に保持されます。
なお、HON.jp News Blogへの寄稿は、著作権譲渡ではなく寄稿者が保持したまま(All rights reserved by the Author)なので、寄稿者自身が他で利用したいと思った際にとくに断りなど要りません、という説明をさせてもらっています。これは日本独立作家同盟「月刊群雛」のころからのポリシーです。
創業以来最大の赤字:朝日新聞社で今、何が起きているのか〈nippon.com(2022年2月16日)〉
昨年退社したばかりのOBによる内情分析――なのですが、正直、そもそも「志半ばで社を去る人たち」とか「経営が傾かなければ、みんな定年まで勤め上げて円満退職したのでは」などという考え方そのものが、世の中と25年くらいのギャップがあるように思えました。整理解雇を「リストラ」と言い替えるようになったのって、1990年代のバブル崩壊以降のことですよね。
ブックライブ for Androidアプリの提供方法の変更について〈株式会社BookLive(2022年2月17日)〉
Google Playのポリシー変更により、アプリ内「ストア」の機能を提供するのが困難になったため、Google Playでの配信を3月29日で終了、APKファイルを端末にダウンロードしてインストールする方式に変更することになった、というお知らせが。2020年9月に「Google Play」ストアがアプリ内課金のルールを厳格化というニュースがありましたが、どうやらそれが直撃したようです。当時、「ヘタをするとiOS版と同様、Android版からもストア機能を削る電子書店が出てくるかもしれません」と書いた予想が的中してしまいました。
Apple決済強要が問題視されている渦中に、それまで許容していたGoogleが引き締めにかかるという。なかなかえげつない真似をします。公正取引委員会の出番では。ちなみに他社では、昨年末に「BOOK☆WALKER」がAndroidアプリ内ストアでは「全額コイン支払い」だけが利用できるように変わったことには気づいていましたが、他はどうなのかしら?
鬼滅の刃「物議」報道で考える、炎上や対立をあおるメディアとポータルサイトの構造問題(徳力基彦)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年2月19日)〉
昨年末の振り返りコラムで、伝統的メディアが釣り見出しを使うようになってきた点について「気になる釣り見出し化」という指摘をさせてもらったばかり。本件も、「週刊実話」を刊行している日本ジャーナル出版が運営するニュースサイトによる問題です。
ほとんど捏造に近いやり方で分断を煽る記事によりPVを稼ぐ手法は、5年ほど前にまとめブログやキュレーションメディアが問題視されたことを思い出します。そういうやり方を、いまは雑誌やスポーツ紙のような伝統的メディアのウェブ版が取り込んでいる感があります。あの辺りにいた人たちが、そちらへ移籍していったということなんでしょうか。
あるいはこれは、以前から紙媒体で行われていた行為だったかもしれません。「マッチポンプ」って言葉、ずいぶん前からありますもんね。紙媒体だとえげつない表紙で見分けが付くため中身を読まずに済んでいたのが、ウェブだと記事単位に断片化して流通して目に触れる場所へ出てきてしまう、という。
技術
フランス書院の電子書籍サイト「オパールCOMICS」にてセルシスの電子書籍ビューア「CLIP STUDIO READER」が採用〈株式会社セルシスのプレスリリース(2022年2月15日)〉
あれ? と思ったプレスリリース。フランス書院はこれまでシャープの「book in the box」や「EBLIEVA」を採用していました。セルシスのリリースには、まずコミックレーベル「オパールCOMICS」で利用開始、そして「今後もフランス書院の各レーベルで順次利用開始の予定」とあるので、全面リプレイスのようです。
NFTに対する技術的な誤解〈Zenn|エンジニアのための情報共有コミュニティ(2022年2月17日)〉
NFTの技術解説。そんなに難しい話ではなく、オンチェーン・オフチェーンの違いや、非中央集権的か否かなど、できること、できないことが明示されていてわかりやすいと思います。だから結局、プライベートチェーンを使ったり、NFT化できる利用者を事前審査で絞ったりと、中央集権型と事実上変わらない仕組みで運用されているところが多いのが現状なのかな、と。過度な期待が萎んだあとこそが、本番でしょう。
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
1日1時間ほど散歩をしているのですが、最近はだんだん暖かくなってきたので、歩き終わるころには汗が垂れてくるほどになっています。もうすぐ春ですね(鷹野)