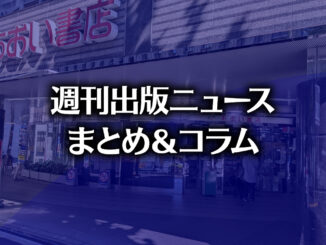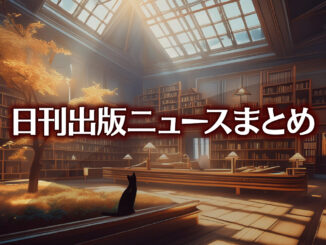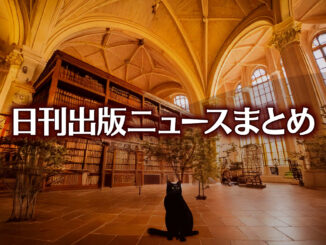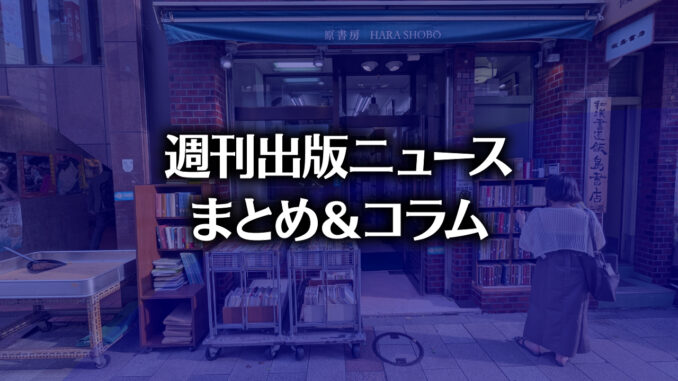
《この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です(1分600字計算)》
2025年10月26日~11月1日は「CODA、出版社らがOpenAIに無断学習中止を要請」「Adobe MAX 2025開催」「gooポータル終了へ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
子どもの半数以上が読書「しない」に松本文科大臣「衝撃」 幼少期振り返り「小さい頃から本を読むのが大好きだった」〈TBS NEWS DIG(2025年10月28日)〉
政治家の発言なので「政治」ジャンルにしておきます。飯田一史氏の『「若者の読書離れ」というウソ』がヒットしたおかげで、こういう言説にカウンターを当てやすくなりました。感謝。松本洋平氏は私と同い年なんですが、我々が子供のころはいまの子供よりもっと読書してなかったという事実を認識すべきです。
そういうデータは、毎年実施されてきた「学校読書調査」にしっかり残されています。中高生で不読者(0冊回答)が最も多かったのは1997年で、不読率は中学生55.3%、高校生69.8%でした。小学生は1998年の16.6%が最高です。
いまの全国SLA公式サイトには直近31年のデータしか載っていないため「我々が子供のころ」である1993年以前と比較できないのですが、昔のデータをWayback Machineから掘り出してみたところ、やはり「我々が子供のころはいまの子供よりもっと読書してなかった」ことが再確認できました。
出版市場のピークは1996年ですから、小中高生が最も本を読んでいなかった時期とほぼ重なっているという、なんとも皮肉な状態だったのです(市場の大きさは人口でおおむね説明できてしまう)。で、この状況は、21世紀に入ってからはむしろ「朝読」活動などにより改善しているんですよね。
あと先日も書いたように、ベネッセの調査はパネルが偏っていることに留意する必要もあります。たとえば、進研ゼミの受講者が多かったりするんです。
「無書店自治体が3割近く」という現状で、作家と読者を結ぶ「リアル体験」に取り組む“街の書店”の挑戦 『独立系書店』と呼ばれる個人経営の書店も増加中〈女性セブンプラス(2025年10月31日)〉
関連する話題なのでついでにピックアップ。何度も言うようですが、こういうウソから書き始める文章を垂れ流すのは、もういいかげんやめましょうよ。
「最近の若者は本を読まない」「子供の活字離れが進んでいる」という現実が社会問題化して久しいが、
ここでもう読むのを止めて閉じようと思いました。でも、諦めずにちゃんとツッコミ入れ続けることも大事ですよね。「現実」は違う。ウソはいけない。こんな欺瞞はすぐバレます。読者からますます信頼されなくなりますよ。
米政府がスマホ新法について言及、「知的財産権の正当な行使を尊重する」〈ケータイ Watch(2025年10月29日)〉
こちらのニュースを読んだとき、私は「あれ? トランプ政権はこういう規制を非関税障壁と呼ばなくなったのか」と思ったのですが、続報を見てポイントがズレていたことに気づきました。勘違い。
Apple、日本のスマホ新法けん制 米政権通じて異例の文言〈日本経済新聞(2025年10月31日)〉
そういうことだったのか! 原文の該当箇所はこちら。
Japan will implement its Mobile Software Competition Act in a way that does not discriminate against U.S. companies, balances the need for fair and free competition with user safety and convenience, and respects the legitimate exercise of intellectual property rights.(日本は、米国企業を差別せず、公正かつ自由な競争の必要性とユーザーの安全・利便性のバランスを保ち、知的財産権の正当な行使を尊重する形で、モバイルソフトウェア競争法を施行する。)
この「米国企業を差別せず」などの文言が、アップルによるロビー活動によってねじこまれた可能性が高いそうです。なるほど……身の処し方が上手いというか、政商化と蔑むべきか。
決算:「トラ」の威をかるApple 関税影響かわし増収、日本の規制にも圧力〈日本経済新聞(2025年10月31日)〉
だれうま(誰が上手いこと言えといった)。
フリーランス法1年、指導・勧告445件 取引条件を示さず違反続く〈朝日新聞(2025年11月1日)〉
とくにコンテンツ制作でのリテイクが問題になることが多いようです。小学館が勧告を受けたのは記憶に新しい。とはいえ私も記事にある「七つの禁止行為」がパッとわからなかったので、公取委の特設サイトで確認してみました。
発注側の禁止行為として定められているのは、①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更・やり直し、の7つです。このうち①②③⑦には受注側の過失がないにも関わらず、という条件が付いています。
つまり、リテイクそのものがダメというわけではなく、理不尽なリテイクがダメ、ということになるでしょう。しかし、たとえばドラマ版「セクシー田中さん」みたいに原作者が脚本に納得しないケースは、どう対応すればいいのか。うーん……リテイクの発生が予想できる場合は、条件をあらかじめ定めておくしかなさそう。
ちなみに、ウチはいろいろ考えたうえで、記事広告の場合は発注書に「先方校正で重度な修正が発生した場合は、協議のうえ原稿料を上乗せいたします」という一文を入れることにしました。先方校正って、往々にして大幅なリテイクが発生しがちなんですよね。
情報誌で働いていた若いころ、先輩・上司から「先方校正は絶対にやるな」と厳命されたのを思い出します。取材後に売れた物件を「差し替えたい」と言われ、大変なことになる可能性が高いんですよね。まあ、印刷所への入稿締切を死守しなければならないから、というのも大きかったわけですが。
社会
社説:読書推進月間 本と触れ合う時間を意識的に〈読売新聞(2025年10月26日)〉
ついついスマートフォンを見てしまうことも多いだろう。
スマホで読書している人もお忘れなく。確か『重版出来!』にそういうエピソードがあったよなーと思い調べてみたら、第11刷「タイムマシンにお願い! 山」でした。「バイブス」の編集長が電車の中で、みんなスマホかタブレットを見ているのを嘆いている。しかし、同じ光景を見た電子書籍の部署の人は「みんな、電子で漫画読んでくれてるなーーッッ!!」と喜んでいる。2巻138ページです。なんとこれ、2013年に描かれた回なんですよね。
動画AIのSora、無断学習中止を 国内業界団体のCODAがOpenAIに要請〈日本経済新聞(2025年10月28日)〉
生成AI関連でCODAがリリースを出すのは恐らく初めてです。公式サイトを調べましたが、少なくとも私には、今回のこの要望書を提出というお知らせしか見つけられませんでした。反響では、とくにクリエイターの方々による歓迎する声や、「やっと!」「遅い!」という方向で批判する声が観測できました。
OpenAI社に「Sora 2」の運用に関する要望書を提出〈一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(2025年10月28日)〉
Sora 2のように特定の著作物が出力として再現・類似生成されている状況においては、学習過程での複製行為そのものが、著作権侵害に該当し得ると考えます。
これ、私も同感なんですよね。ディズニーの件が報道された際にも書いたんですが、さすがにこれはもう「非享受目的」要件を満たさないケースに該当するのでは、と。専用SNSの運用を始めちゃったり、インタラクティブファンフィクションなんて言い出したりと、極めて類似した出力結果の二次利用を前提としたサービス設計を行っているわけですから。
アメリカの著作権法ならフェアユースで通るかもしれませんが、日本の著作権法第30条の4は微妙に違います。「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」という要件なので、「なにを」「どのように」ではなく「なんのために」が問われます。
OpenAIが「Sora 2」を、極めて類似した出力結果の二次利用を前提としてサービス設計しているということは、AI開発の目的が「他人に享受させること」になっているわけです。うん、ダメじゃん。生成・利用段階でフィルタリングすればいいって声もありますが、学習・開発段階でアウトでしょ。
「クリエーターの著作権守る」小野田紀美氏 動画生成AIの著作権問題 体制整備検討〈産経ニュース(2025年10月28日)〉
政治も動きそう。
講談社やKADOKAWAなど19団体が生成AI巡り共同声明 「Sora 2」問題受け〈ITmedia AI+(2025年10月31日)〉
CODAの声明とは少し違っていて、著作権法第30条の4(つまり学習過程)には触れない形になっています。なぜ。あと、共同発出者の一覧に集英社がない。なぜ。
「作家の尊厳を踏みにじった」――集英社、動画生成AI「Sora 2」に抗議 権利侵害には「厳正な対応」〈ITmedia AI+(2025年10月31日)〉
と思ったら、集英社は単独でさらに少し違う文面のリリースを出していました。CODAや出版社系の共同声明より短いのですが「心血を注いで作品を作り上げた作家の尊厳を踏みにじり」など、より怒りがにじみ出る文面になっていると感じました。
経済
「gooポータル」11月25日にサービス終了–28年間の歴史に幕〈CNET Japan(2025年10月26日)〉
おお……最近、goo辞書やgooブログなど、付随サービスを次々と終了させていると思ったら、ついにまるごとシャットダウンですか。おつかれさまでした。gooメールだけは、2026年2月25日にサービス終了予定とのことです。以前の勤め先でgooポータルとの提携が始まったとき、こちらは大文字グーだったので「小文字グー」と呼んで区別していたのを思い出しました。
【最新米メディア報告】図書館御用達取次ベイカー&テイラー倒産が伝える「学び方の変化」(大原ケイ)〈The Bunka News デジタル(2025年10月27日)〉
AIに質問を投げれば答えっぽいものが返ってくる時代になってしまったいま、教材に関わる者がこの変化をどう受け止めるか? という最後の問いが重い。eラーニングとか教育ICTなど、前から言われてきて少しずつ変わりつつあるとも思うのですが。
技術
ステーブルコインJPYC初日、3時間で1500万円発行 社長「通貨史の分岐点」〈日本経済新聞(2025年10月27日)〉
これで「日本のステーブルコイン元年」が始まりました。出版関連では、漫画家支援プラットフォーム「comilio(コミリオ)」が実装準備を進めているそうです。「決済加盟店への加入」みたいなプロセスが不要なので、いわゆる「金融検閲」問題の解消に繋がることが期待されています。どうやって実装すればいいんだろう? と公式サイトを確認したら、ERC-20準拠と記されていました。イーサリアム・ブロックチェーンなのですね。
“イーロン・マスク版Wikipedia”初期版公開 特徴はAIファクトチェック 「すでにWikipediaより優秀」〈ITmedia NEWS(2025年10月28日)〉
その「優秀」というのは、誰にとって優秀なのか? が問題でしょう。Wikipediaと一語一句同じページの存在も複数確認されているという報道もありました。つまり、イーロン・マスクにとって都合の悪いページだけ書き換えているのでしょう。オルタナ・ファクトが捗りそう。私は絶対に使わない。
商用可能な画像生成AI「Adobe Firefly Image Model 5」が発表、テキストプロンプトで画像編集が可能に〈窓の杜(2025年10月28日)〉
ウェブ版「Adobe Firefly」を確認してみたら、デフォルトはプレビュー版の「Image Model 5」ではなく、Google「Nano Banana」に設定されていました。どちらのインパクトが強いか判断した結果でしょうけど、なんか負けを認めてる感もあります。「Photoshop」アプリの新バージョンをインストールするかどうか迷いましたが、初期不良が怖いので少しだけ保留しておきます。
Googleだけの特権は不公平 クラウドフレアCEOが語る AI クローラー問題〈DIGIDAY[日本版](2025年10月30日)〉
こちらは、少し前からCloudflareが繰り返し主張していることです。本欄でも以前に取り上げた話題ですが、周囲で「知らなかった」という方を複数観測したため、改めて。身近な人にも読まれてないんだなあと苦笑いしつつ。
GoogleのAI学習用クローラーは「Google-Extended」です。つまり「Google-Extended」をブロックすれば、GoogleのAI学習には使われません。しかし、検索用クローラーの「Googlebot」で収集したデータは、「AIによる概要(AI Overviews)」や「AI Mode」といった検索拡張生成(RAG)に用いられています。このことをCloudflareは問題視しています。
しかしこれは検索拡張生成だから「学習済みモデル」によってデータを加工しているだけであって、新たな学習には用いていないはずなのです。このため、Cloudflareが推進しようとしている「Pay per crawl」の対象から、Googlebotは外れてしまっています。つまり、Cloudflareの発言は若干ポジショントーク気味なんですよね。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
日曜日の朝、目が覚めて「HON.jp News Blog」を開こうと思ったら「500 Internal Server Error」でサイトが開けません。WordPressの管理画面にも入れない状態。エラーログを確認しようとレンタルサーバーの管理画面を開いたら、なぜか容量が一杯だという警告が。いろいろ調べてみたら「WP Fastest Cache」プラグインの一時キャッシュファイルが原因でした。管理画面から削除操作をしても、なぜか削除されない症状が積もった結果だったようです。バグっぽい。ところがブラウザのファイルマネージャーやFTPソフトでも削除操作が効きません。そこで「Tera Term」をインストールしてSSH接続という慣れない手段を使い、不要なキャッシュをフォルダごと削除(rm -r)して無事復旧に至りました。そして、この作業で日曜日が半日潰れました。とほほ。(鷹野)