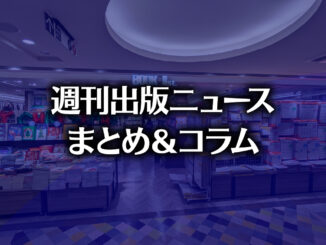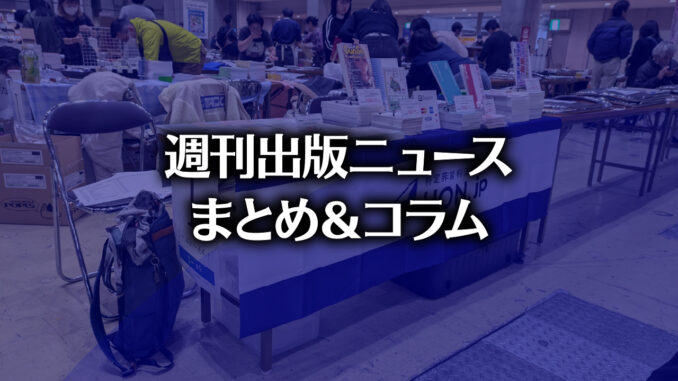
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2025年5月18日~24日は「アニメ@wikiが有料会員制に移行」「Google検索に“AI Mode”が無料で追加」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
お知らせ
HON.jp Podcasting「#32 価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側に(2025年5月20日版)」を配信しました
「goo辞書」サービス終了というニュースに触れ、前から何度も書いていることではありますが、これを機にいろいろ掘り下げてみることにしました。無料で公開し広告で稼ぐモデルが終わったという話に留まらず、同じ情報でも人と場合によって価値が異なる場合もあるというところまで掘ってます。
この番組ではみなさまからのお便りをお待ちしています。「こんなトピックスを取り上げて欲しい」とか「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。こちらのページから送付できます。
政治
経済産業省、「令和6年度アクセシブルな電子書籍市場等の拡大等に関する調査」の報告書等を公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2025年5月21日)〉
昨年までの報告書と明らかに異なるのは、世界標準仕様の最新動向がものすごーく詳細になっていること。つまり、めっちゃ技術寄りです。これは、議論参加メンバーにKADOKAWAの高見真也氏が入ったからでしょうか。p14~p29(右下に書かれたページ番号だと15~28)が高見氏による報告で、これはJEPAセミナーなどで拝見した、私はもう見慣れた感じの内容です。
で、その高見氏によるスライドデザインをそのまま継承する形で、さらに詳細な標準動向が96ページにわたって報告されています。ガイドブック骨子と合わせ、アライド・ブレインズ株式会社による作成です。代表の大野勝利氏は、電流協とは絡みがあるみたいだけど、JEPAとは接点がないっぽい?
図書館・学校図書館の運営の充実に関する有識者会議(第4回)配付資料〈文部科学省(2025年5月21日)〉
経済産業省の動きとパラレルで、こちらでもアクセシビリティ・読書バリアフリー関連で電子図書館に関する話題が結構多いです。
改正著作権法、26年4月施行に 著作権者が不明な作品も利用可能に〈朝日新聞(2025年5月23日)〉
こちらはこれから始まる「未管理著作物裁定制度」の話なんですが、なんかどうも世間一般(はてなブックマークが世間一般と言えるか? という問題もありますが)にはまだ、50年以上前からある「著作権者不明等の場合の裁定制度」と混同されてるっぽいです。よく似た別の制度なんですよね。この記事のタイトルも紛らわしい。
以前、ポッドキャストでも解説しましたが、従来の制度は裁定を受けたら、もし裁定期間内に権利者が現れても、期間満了まではそのまま合法的に利用が継続できます。ところが新制度は、裁定期間内でも権利者が申し出れば、利用を停止できます。利用する側からすると、わりとリスクが大きい制度なのですよね。
「著作権法施行令の一部を改正する政令(仮称)案」に関する意見募集の実施について〈e-Govパブリック・コメント(2025年5月20日)〉
で、その新制度の手数料などについて、パブコメが実施されてます。手数料は1件1万3800円とのことです。従来の裁定制度の倍。そして補償金は別途かかります。ちなみに従来の裁定制度は、以前は1件1万3000円だったのが、あまりに利用されないため2018年から6900円に改定されたという経緯があります。それを踏まえたうえで新制度の手数料を1件1万3800円に設定するということは……なんか、あんまり使って欲しくないのかな? という印象を受けますね。
社会
第39回納本制度審議会議事録〈国立国会図書館―National Diet Library(2025年5月19日)〉
2月27日に開催された納本制度審議会の議事録が公開されました。有償オンライン資料の登録状況が気になっていたのですが、以下のように報告されていました。
最初に、有償のオンライン資料の登録状況についてです。この表の左から三つ目の「登録点数」という列を御覧ください。全面的な制度収集を開始した令和5年1月からの累積で、令和7年1月20日時点で有償のオンライン資料数は1,716点登録されております。発行主体別の内訳を見ますと、上から順に出版社23社から1,272点、私立大学や学協会52団体から187点、その他20の法人・団体から57点、個人37名から200点となっております。また、右側に移りまして資料のフォーマットを見てみますと、PDFが1,183点、EPUBが533点となっております。
わっはっは、もう笑えるくらい惨憺たる有様です。HON.jpの本は電子版も納本していますが、その他法人・団体扱いの57点に含まれていることになるでしょうか。なお、電子納本を除外されている電書連・機関リポジトリの収録点数は10万2312点(1月20日時点)とのこと。電子書店での配信数と比べると、かなり少ない(2023年5月に「BOOK☆WALKER」のラインアップを調査した時点でISBN有だけで50万点を超えています)。まあこれは、電書連に加盟しているのは大手だけだからかもしれませんが。そして、JPROは電子書籍を登録してないところも多いから、その登録点数約12万点と比べて「その差、2万点」なんて言ってちゃダメだと思いますよ。
人がAIのサポートで記事を読む時代になにを届けるか〈モリジュンヤ(2025年5月20日)〉
ちょうど、けんすうさんがメディアのバイアスがかかった発信ではなく、素の取材データをローデータ(raw data)として出していく、それを元に人がAIを使って知っていくのでは、ということについて言及していました。
けんすう氏は「メディアが編集をする時代が終わった」と主張。取材データはまるごとYouTubeなどで公開し、要約したい人や背景を知りたい人はAIを使うようになる、としています。長年にわたる「マスコミの切り取り」とか「恣意的な編集」などへの反発もあるとは思いますが、これに私は不同意です。
なぜなら、一次情報(ローデータ)の内容は玉石混交で、AIにはその正しさを検証できない場合が多いから。LLMグルーミングみたいな情報操作に対抗できない可能性も高いです。学習用データセットの偏りによるAIバイアスにも懸念があります。あまりに牧歌的すぎるのでは。
Google検索は、世界最高峰の頭脳が長年改善し続けているアルゴリズムで結果を表示しています。それでも「上位にいつも正しい情報がある」とは限らないわけです。いくらAIが高性能になっても、ゴミの山からはゴミしか生成できませんよ。
映画の文字抜き出しサイトの運営者ら5名等を検察庁に送致〈一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)(2025年5月21日)〉
いわゆる「ネタバレサイト」の摘発事例です。推測ですが、CODAはあえてタイトルには「ネタバレ」と書かなかったのかな、と。「ネタバレ」という言葉の与える印象って、どちらかというと「合法」寄りだと思うんですよ。弁護士・福井健策氏が「ファスト映画」が問題になったころに書かれたコラムの四象限で言うと、「アイデア借用・非侵害」かつ「燃えやすい・燃えた」に該当しそう。
しかし本件の場合、「セリフ・動作、情景、場⾯展開などのストーリー全体の克明な内容を権利者に無断で文字起こし」しているそうです。つまりこれは「表現借用・法的侵害」にあたるパターンでしょう。しかも摘発されたのは法人ですよ。怖いもの知らずだなあ。法人の著作権侵害は、刑事罰の罰金が最高3億円まで跳ね上がります(個人は1000万円)。怖い、怖い。
note化するニッポンのWEB記事〈シュッパン前夜 編集部(2025年5月23日)〉
「note化」ってなんだろう? と思ったら、要するに「エモい記事」のことですって。なんというか、そもそも「たくさん読まれなきゃいけない」みたいに思ってしまうところから、なにかがおかしい気がします。noteってページビューが収益化されるわけではないはずなのに。ページビューが収益化されるウェブ広告の世界に、考え方が狂わされてるんじゃないでしょうか。つまり、Google AdSenseが悪い。
私は、1500字のエモくて薄い記事を量産してたくさんの人に読まれ数日後には忘れられるのではなく、魂を込めた1万5000字の濃い記事が読んで欲しい対象に届いて記憶に残るようにしたいです。そういう意味で、10年以上前から「読者を減らす」ことを提言していた堀正岳氏は、慧眼だと思います。
経済
ローソン「マチの本屋さん」は何を変えたか 書店空白地に本棚をつくった〈ITmedia ビジネスオンライン(2025年5月19日)〉
少しややこしいが、ローソンでは「マチの本屋さん」とは別に、スリーエフとの協業店舗「ローソン・スリーエフ」などでも、地域の書店と連携した「書店併設型店舗(2014年~)」を展開している。この店舗はスリーエフ発のビジネスモデルで、30年ほど前から続いている。
ローソン「マチの本屋さん」はもともと、スリーエフのやっていたモデルを踏襲しているはずなんですよね。スリーエフは、2016年にローソンと資本業務提携しています。そういう協業の歴史に触れてる記事は、最近だと珍しい気がします。
ただ、私が書店併設スリーエフによくお世話になっていたのは、2008年ごろだったはずなのですよね。だから「書店併設型店舗(2014年~)」という記述にはちょっと「アレ?」となりました。スリーエフ書店併設型店舗の歴史は、20世紀末まで遡るはず。
あと、タイトルにある「書店空白地」には、やっぱり引っかかりますねぇ……地元だからよく覚えているのですが、2022年にできた2号店のローソン碧南相生町三丁目店は、歩いていけるくらい近くに文化堂新川本店という書店があったはずです。また、同じ市内には三洋堂書店 碧南店があります。ここは、一般的な意味での「書店空白地」とは言い難いと思うのです。
ちなみに文化堂新川本店は、Googleマップのストリートビューを見る限り、2023年1月の時点ではまだ店に灯りがついていることが確認できました。しかし、いまはもうGoogleマップでは検索できなくなっています。ローソン碧南相生町三丁目店ができたこととの関係を考えずにはいられません。
アニメ情報サイト「アニメ@wiki」が有料会員制に移行 Wikipediaへの“まるまる転載”に対策〈ITmedia NEWS(2025年5月19日)〉
これも「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側に」の典型事例。理由として言及されているのはWikipedia転載への対処ですが、結果としてAIボットのクロールを防ぐことにもなります。つまり今後、AI検索の出力結果に「アニメ@wiki」で公開された新作アニメの情報は反映されなくなります。しれっと捏造されたりすることになるのでしょう。
技術
生成AIの答え信じて大丈夫?Grokファクトチェックに誤りも? ChatGPTは? “ハルシネーション”はなぜ起こる|フェイク対策〈NHK(2025年5月17日)〉
生成AI関連の話は、PESTのどこへカテゴリーするか迷います。これは前述の「人がAIのサポートで記事を読む時代になにを届けるか」と似た話なので「社会」でも良い気がしますが、ハルシネーションとかAI技術への過信ってあたりを考慮すると、やはり「技術」かなあ、と。
grokにファクトチェックさせている人は何も知らない〈Books&Apps(2025年5月22日)〉
こちらもそういう話ですね。おおむねおっしゃるとおりだと思うのですが、ちょっと別の観点も必要だと感じました。つまり「ファクトチェック」と言われる側にも問題があるのでは? と。てきとうなことを言い散らかしてる人に対し「それおかしくね?」「嘘乙」「Citation needed(要出典)」みたいなツッコミを入れるかわりに「@grok ファクトチェック」とやってる人も、それなりにいる気がします。
つまり「@grok ファクトチェック」というリプライは、ファクトチェックそのものが目的ではなく、発言者を批判する目的になっている場合も多いのでは、と。揶揄する手段と言ってもいいでしょう。文責もGrokにまるなげです。こうなると、Grokの出力内容が正しいかどうかも、もはやあまり関係なくなっていて、Grokによる出力をまったく読んでいない可能性すらあるかも。
まあ、もちろん、Grokの「ファクトチェック」を鵜呑みにしている残念な方も、やはり、それなりにいるとは思いますが。どちらにせよ、文責まるなげだから、間違いを指摘されても「AIが間違えたのだから私は悪くない」って開き直れちゃうんですよね。
コアな技術を現実に Google I/O基調講演にみる「グーグルらしさ」〈Impress Watch(2025年5月21日)〉
Google I/O 2025関連の速報記事をざっと読んで思ったのが、いちばんインパクトが大きいのはGoogle検索へ追加する「AI Mode」を無料で提供するってやつかな……でした。その後に読んだこの記事で、がっつり取材している西田宗千佳氏が、今年最大のトピックは検索への「AI Mode」導入とおっしゃっていて、意見が同じで安心しました。
ちょうどこのタイミングで、Good e-ReaderがAI Overviewsにニュースメディアが殺されるという趣旨の記事を出していますが、たぶん「AI Overviews」より「AI Mode」のほうがメディアにとってヤバイ、と思います。「メディアにトラフィックを送る」ことで共存共栄してきた関係が、これで本格的に壊れてしまいそう。
Google検索とAI検索のコンバージョン率を比べると、現時点ではGoogle検索のほうが高い(一部業種を除く)という調査結果もあります。それによってメディア側の思考は「AI企業には記事を使わせない」方向へさらに傾き、ますます「価値ある情報の多くがペイウォールの向こう側に」なっていきそうです。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」で新たに誕生した16点の作品を合本にしました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
な、なんとか2024年度の会計処理が終了……あとは総会に向けて資料を準備しなければ。重たいタスクをひとつ片付けると、次の重たいタスクが降ってきます。いやーん。(鷹野)