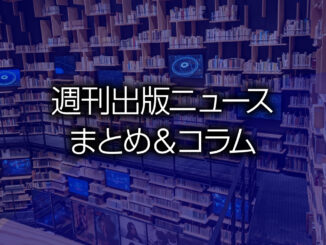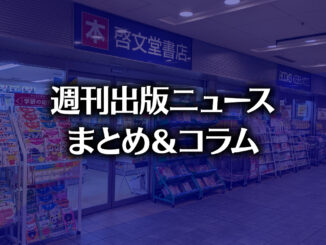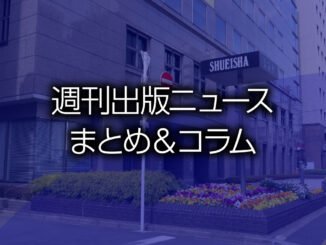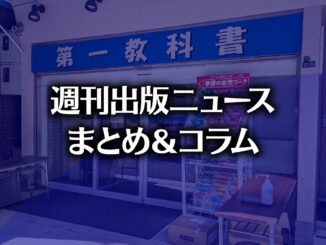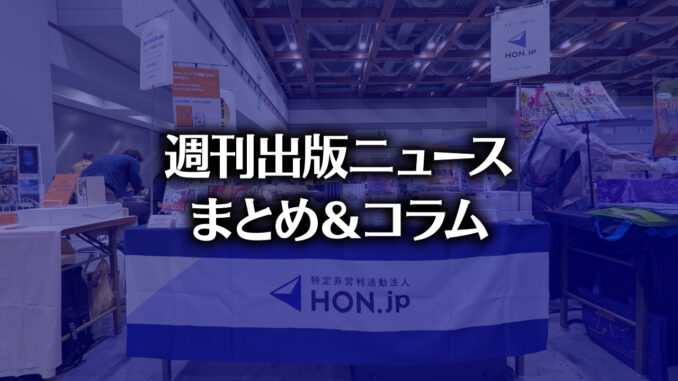
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2025年10月19日~25日は「NHK ONEのウェブ記事は1週間から1年程度で削除」「EPUB 3.3対応の電書連制作ガイド10年ぶり改訂」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 3日間で小説を書き上げる文芸ハッカソン“NovelJam”、今年も開催〈Dig-it [ディグ・イット](2025年10月20日)〉
- 小4~高3の子どもが読書を「しない」割合は半数超、15年調査より1.5倍に増加【ベネッセ教育総合研究所ほか調査】〈EdTechZine(2025年10月20日)〉
- AIで書き、AIで隠す——中国の大学で広がる「卒論チェック戦争」〈36Kr Japan(2025年10月22日)〉
- Amazon is asking authors to verify their identity on KDP(Amazonは著者に対し、KDP上で本人確認を行うよう求めている)〈Good e-Reader(2025年10月24日)〉
- 集英社・文芸編集部、『青の純度』めぐる“書評”に言及 風評に「断固抗議いたします」〈ORICON NEWS(2025年10月25日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
〈ふざけるなNHK〉「NHK ONE」不具合連発で現場は大混乱 エースアナが続々謝罪の“異常事態”に〈デイリー新潮(2025年10月20日)〉
「『NHK ONE』は、妥協の産物」 なぜ時代に逆行するサービスが生まれたのか 「現場の記者のモチベーションは低下している」〈デイリー新潮(2025年10月20日)〉
その「ふざけるな」はNHKに言っても仕方ない気がします。先週のまとめで、東京新聞が「一体なぜ?」などと白々しいことを言っていたことについて触れましたが、この記事でも後編2ページ目にこう書かれています。要するに、新聞社や民放による政治的な圧力の結果なのですよね、これは。
読売新聞の山口寿一社長を筆頭とする日本新聞協会からの“民業圧迫論”などによって、新サービスはなくなり(後略)
あと、困ったことにNHK職員(匿名)の声として、こんなことも記されています。
ウェブ上での公開は1週間のみ。長期で読まれてほしい記事に選ばれても、1年後には削除されてしまいます
ああ……以前から私が危惧していたとおりになってしまいました。「NHK ONE」になっても結局、過去記事はどんどん消しちゃうようです。というかこの様子だと、前より酷くなるようですね。まあ、だったら契約はしません。そんなメディアは使わない。ソースに使えないから、ピックアップもしない。極力避けて通るようにします。あれ? これって新聞社や民放の思うつぼ?
社会
3日間で小説を書き上げる文芸ハッカソン“NovelJam”、今年も開催〈Dig-it [ディグ・イット](2025年10月20日)〉
運営側で取材を受けた立場ですが、客観的に見て「なんか楽しそう!」と感じました。素晴らしいレポート、ありがとうございます!
小4~高3の子どもが読書を「しない」割合は半数超、15年調査より1.5倍に増加【ベネッセ教育総合研究所ほか調査】〈EdTechZine(2025年10月20日)〉
こちらの調査、以前から「ベネッセが関わっているならパネルが偏ってるんじゃないの?」と疑っていたのですが、2024年2月に出版された『パネル調査にみる子どもの成長』(勁草書房)にはやはり、進研ゼミの受講者が多いとか、そもそもベネッセの保有する個人情報が偏ってる(私立が多い)とか、保護者の学歴が10ポイントくらい高いとか、無作為抽出でもないなどなど、プレスリリースには載っていない情報が記載されていました。いちおうあれこれ補正はしているようですけど「偏ってるデータの経年変化である」ことは念頭に置いたほうがよいです。
あと、プレスリリースには見出しに「スマホ時間と読書時間は逆相関関係があり」なんて書いてあるんですが、因果関係が証明されたわけではありません。そもそも「スマホ時間」ってなんですか? スマホ時間にはスマホで本を読んでる時間も含まれますよね? 他のメディアで言えば、テレビでバカ番組をダラダラ観ているのと、Eテレの教育番組を真剣に観ているのとでは、ぜんぜん意味が違います。それと同じことだと思うんですけどね。問題はデバイスそのものではなく、なんの用途に使っているか? でしょう。
「どうしてもスマホに…」 進む”読書離れ” 各地で活字文化を守る取り組み 公立図書館ではスポンサー募集で書籍購入費工面 私設図書館では個性的な一冊との出会いも〈TBS NEWS DIG(2025年10月20日)〉
こちらもそうですが、スマホで本を読んでる人もいっぱいいますよね。「マンガは本じゃない」「マンガは読書に含まれない」などと前時代的な反論をされそうな気もしますが。
AIで書き、AIで隠す——中国の大学で広がる「卒論チェック戦争」〈36Kr Japan(2025年10月22日)〉
AI検出ツールに引っかからないように改変するAIツールを使ったら、かえってAI検出ツールに引っかかる率が高くなった、みたいな笑えない話もあるようです。それって、ただの詐欺なのでは?
全員が対象ではなく、多数の本を出版していると連絡が来るようです。いまのところまだ私には届いていません。マイケル・コズロウスキー氏が言うように「大量生成されるAI本への対策」という理由もあるとは思いますが、著作者名の詐称が行われトラブルが起きたときの対応も視野に入ってそうな気がします。
集英社・文芸編集部、『青の純度』めぐる“書評”に言及 風評に「断固抗議いたします」〈ORICON NEWS(2025年10月25日)〉
【追記あり】アーティスト原田裕規が篠田節子の小説『青の純度』の書評で、自著の「ラッセン本」との類似を指摘。「願わくば適切な手続きのもとで記されてほしい」〈Tokyo Art Beat(2025年10月23日)〉
原田裕規氏のサイトに掲載された文書が10月17日の時点でバズっていたのは把握していたのですが、片方の言い分だけではちょっと判断できないと思い保留していました。これに対し、集英社・文芸編集部からの声明は、原田氏の書評に対しては遺憾の意(篠田節子氏は原田氏の本を読んでおらず独自に取材して執筆していると主張)、SNSでの「剽窃」うんぬんといった風評に対しては断固抗議、という内容でした。
この集英社の声明を受け、原田氏はX(旧Twitter)で「到底受け入れられず、誠意の感じられない内容に感じました」と表明し、コメントを公表しています。ただ、当事者である原田氏自身が「本件は著作権侵害にあたる事案ではない」と書いているのですよね。「原田氏の著書に依拠しなければ絶対に書けない小説」と断定できるわけではなさそう。うーん、それはちょっと分が悪い。
末尾に「このコメントをもって、私から本件に対する発信の締めくくりとさせていただきたいと思います」とあるので、恐らく直接的な話はこれで終わるでしょう。第三者による「剽窃」うんぬんの風評については、もしかしたら発信者情報開示請求や名誉毀損での訴えなどの続きがあるかもしれませんが。
経済
生成AIの進展:ビッグテック、そしてメディアに何をもたらすか|講師 藤村厚夫氏〈日本電子出版協会(2025年10月20日)〉
録画を拝見しました。紹介されているベンチャーキャピタルBONDによる“Trends - Artificial Intelligence”を読んでみようと思ったら、なんとスライド340ページの大長編。これは骨が折れそうだ……と思いNotebookLMの力を借りてみました。
私が最近気になり始めた「AIバブル」については、直接的に「バブル」という言葉は使われていないようですが、「過熱した期待」「巨額の資金投入」「高い評価額」「歴史的な混乱のパターンとの類似性」など、その可能性は強く示唆されているようです。
別のベンチャーキャピタルAir Street Capitalによるレポートでは「AI関連企業の年間収益は約200億ドル」とされており、巨額なインフラ投資に比べると売上規模はまだあまりに小さいと言わざるを得ないように思います。耳目を集めるための話題づくりリリースが断続的に行われている感もあります。そろそろ危ないんじゃないだろうか。
2025年9月期 紙書籍雑誌推定販売金額は前年同月比1.8%減、雑誌再検証で3~6月の数字は改善 ~ 出版指標マンスリーレポートより〈HON.jp News Blog(2025年10月24日)〉
6月号・7月号で3月以降の雑誌データについて「算出データに一部不明瞭な箇所が残る」ため8月以降に再検証を行う予定とされていましたが、修正が入りました。修正前の数字と比較してみましたが、5月以外は改善しています。4カ月間で25億7200万円増えました。4月号では「ローソンとファミリーマートの配送が日販からトーハンに変わり、雑誌販売を終了した店舗の返品による影響」とされていましたが、修正後はその影響がやや小さくなったと言えそうです。
技術
Googleが「プライバシーサンドボックス技術」の大部分を廃止へ〈ケータイ Watch(2025年10月20日)〉
とうとうトドメを刺されました。R.I.P. あれ? まだ「Killed by Google」には載ってない?
EPUB 3.3対応へのバージョンアップ「電書連 EPUB 3 制作ガイド ver.1.1.4」を公開します〈デジタル出版者連盟(旧・日本電子書籍出版社協会)(2025年10月24日)〉
10年ぶりの改訂! ガイドの名称も「電書協」から「電書連」に変わりました。まずは関係者のみなさま、お疲れさまでした。とにかく「改訂された」という事実が喜ばしい。昨年のHON-CF2024で「現在準備中のアップデート内容は小規模な更新」と伺っていたのですが、更新履歴を確認したら、今回の1.1.4へのバージョンアップ分だけで7ページありました。履歴には変更前後が両方記載されているからそのぶん量も多くなるとはいえ、わりとしっかり改訂されている印象を受けました。「今後のRSに期待する項目」もけっこう多いですね。
まあ、EPUB 3.3対応とはいえ「EPUB Accessibility 仕様への対応は含まれていません」と注記されているのですが、アクセシビリティ対応は次の課題でしょう。高見氏が登壇時におっしゃっていたとおり、制作側だけでなく、流通側、ビューア側の「全てでやらないと意味がない」わけですから。制作側からの問題提起は成されました。次は流通側、ビューア側が、これを受けてどう対応するか? でしょう。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
神保町ブックフェスティバルは2日とも雨天中止となりました。残念。そういえば今年の10月は雨が異様に多いなーと思い日本気象協会のページを調べてみたら、東京の天気で1日から26日までのあいだに「晴」が含まれる日はたったの6回でした。終日晴れたのは17日のみ。「曇」が12回、「雨」が11回。いやあ、洗濯が捗らないわけだ。(鷹野)