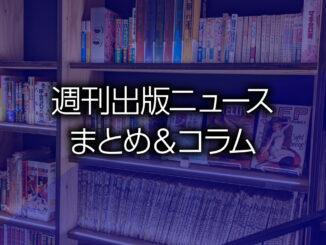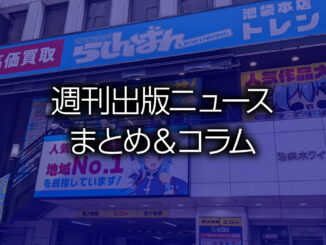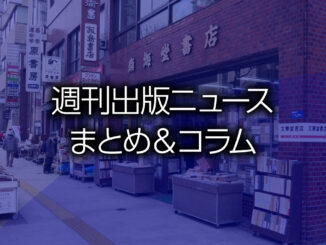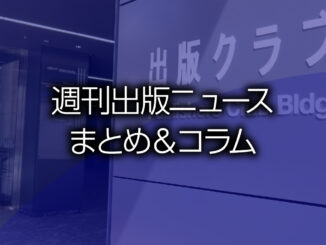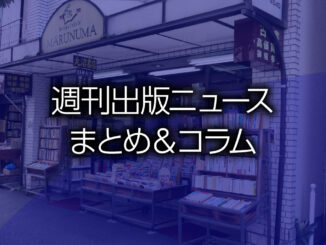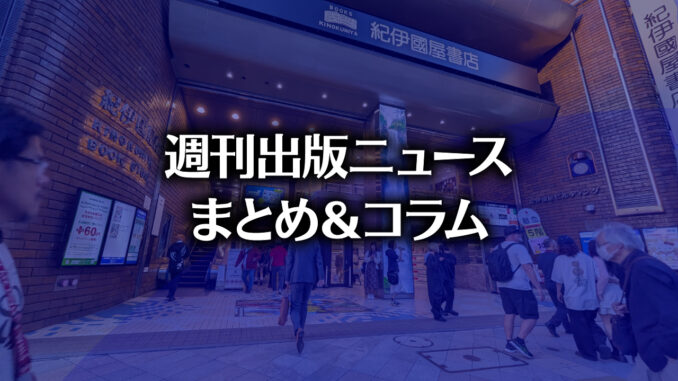
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2025年10月12日~18日は「図書館等公衆送信補償金制度を活用したサービスが訴えられる」「Googlebotのクロールページ数換算で送客効果は10年前の7分の1に?」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります。メルマガでもほぼ同じ内容を配信していますので、最新情報をプッシュ型で入手したい場合はぜひ登録してください。無料です。クリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)でライセンスしています(ISSN 2436-8237)。
先週も多忙につき、やや縮小版でお届けします。
【目次】
政治
NHKの優良ネットコンテンツが9月で公開終了…受信料を払っていても「閲覧の方法はありません」 一体なぜ?〈東京新聞デジタル(2025年10月12日)〉
白々しい……と思ってしまいました。「一体なぜ?」って、それは日本新聞協会や日本民間放送連盟(クロスオーナーシップで新聞社が放送業に資本参加している)がNHKのインターネット活用業務「必須業務化」に対し「民業圧迫」だと猛反発して総務省の研究会などでも圧力をかけてきた結果でしょう。なにをすっとぼけてらっしゃるのか。つまりこれは、新聞社・放送事業者による政治的な働きかけの結果です(だから、あえて政治ジャンルとしました)。もしかしたらペイウォールの向こう側で「我々が消したのだ」と自省しているのかもしれませんが……それはないだろうなあ。
法律書デジタル図書館を提訴 出版社や著者が「著作権侵害」主張〈日本経済新聞(2025年10月15日)〉
法律書デジタル図書館による図書館等公衆送信補償金制度を活用したサービス展開が、違法であると出版社等に訴えられました。本件を受けた法律書デジタル図書館のプレスリリース(PDF)はこちらです。
2月にこのサービスが報道されたとき私は「株式会社で営利目的の事業をやりつつ、同じ仕組みを一般社団法人に転用して『営利を目的としない事業』としてやる、ということなのでしょう。法律的にギリギリセーフのところをうまく攻めてる感があります」と書いたのですが、出版社側はアウトと判定したことになります。
法律には「特定図書館等においては、その営利を目的としない事業として」と定められているので、主な争点は「営利目的ではないかどうか」になるでしょう。非営利型の一般社団法人なら少なくとも定款に「剰余金の分配を行わない」ことと「解散したときは、残余財産を国・地方公共団体などへ贈与する」ことを定めている必要があります。
そこで定款を確認しようとウェブを調べたのですが、どうやら公開されていない(少なくとも私には見つけられない)ようです。知らなかったのですが、一般社団法人には定款を誰でも閲覧できるようにする義務はないのですね。縛りが緩いなあ。
他の観点として、サービス内容的に非営利型ではなく会員相互の共通利益を図ることを主たる目的とする「共益的活動を目的とする法人」とみなされる可能性もある気がします。会費が月9800円で、PDF送信1回ごとに手数料250円と補償金も別途必要という事業形態が「非営利」とみなされるのかどうか。
あとは、出版社が同様のサービスを提供していることが「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に該当するかどうか。まあ、こういう境界事例は裁判でないと白黒決着が付きませんから、徹底的に争って判例を作って欲しいところです。
法律書のページをPDF送信「やめて」 出版社が私設図書館を提訴〈朝日新聞(2025年10月15日)〉
文化審議会委員として公衆送信導入の議論に携わった大渕哲也・東大名誉教授は、自治体や大学の図書館以外が参入することは「全く想定していなかった」といい、「登録審査を厳しくするなどの抜本的対策が必要ではないか」と提案する。
驚愕。さすがに「想定外」はないでしょ。少なくとも、大渕氏が参加していた文化審議会著作権分科会の「図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム」の「論点について(PDF)」の「著作権法第31条の対象となる施設について」には、「① 公共図書館(図書館法第2条第1項の図書館)/(※)公立・私立の別を問わない」と明示されてます。そして、図書館法第2条第1項には「一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの」とばっちり書いてあります。それを法律の専門家が軽々しく「想定外」とか言ってはいけないのでは?
このワーキングチームの議論、当時私はリアルタイムでオンライン視聴していますが、議事録もしっかり残っているので再確認してみました。「主体となる図書館等の範囲」についての議論が行われた際、具体的に「一般社団法人」という話が出ていないのは確かです。ただ、茶園委員が「図書館であることは必然ではないとも言えます」と問題提起をするなど、「自治体や大学の図書館以外が参入すること」は「まったくの想定外」とは言えなさそうです。
社会
第0回「カタカナでサンブックス、横浜の浜に田んぼの田に山で、サンブックス浜田山と言います」(前編)〈出版フィールドワークプロジェクト(2025年10月10日)〉
第0回「カタカナでサンブックス、横浜の浜に田んぼの田に山で、サンブックス浜田山と言います」(後編)〈出版フィールドワークプロジェクト(2025年10月13日)〉
出版フィールドワークプロジェクトは、榎本周平氏(青土社 営業部)を発起人として日本出版学会内に設立された、出版業界人のナラティブをアーカイブ化していく試みです。学会員としてエールを送る意味でピックアップしておきます。
経済
「小説家になろう」が創作活動支援のための収益還元サービス「なろうチアーズプログラム」を開始〈株式会社ヒナプロジェクトのプレスリリース(2025年10月14日)〉
2024年2月末日で創業メンバーの梅崎祐輔氏と平井幸氏が退任し、現社長・青山侑矢氏が就任したタイミングで示唆されていた「ユーザー(著者)への収益還元」機能がついに実装されます。昨年9月の「HON-CF2024」にご登壇いただいた際にはまだ「開発中」とおっしゃっていました。
サービスの開始予定は10月28日で、いまは事前登録を受け付けています。収益還元を受けられるのはこのプログラムに登録したユーザー(著者)で、収益化したい作品を選んで設定すると、作品ページ内にこのプログラム用の広告が設置される形になるそうです。
これ、昨今のウェブ広告事情を念頭に置くと、作品ページのどこにどういう形で広告が設置されるのか? が少し気になりますね。まあ、作品を読む体験を著しく阻害されるようなことは恐らくないとは思いますが。
動画配信サービス「Hulu」が電子コミックサービスを 本日10月15日(水)からスタート〈Hulu News & Information(2025年10月15日)〉
ビーグリー、HJHDへ電子コミックを提供〈新文化オンライン(2025年10月17日)〉
Huluがビーグリーの支援で電子コミックサービスに参入。最後発組になるわけですが、勝算はいかに。「dアニメ」もだいぶ後発(しかも「dブック」があるのに)で、ブックウォーカーがバックエンドに入ってますが、実績はどうなっているのか気になります。
ちなみに私は「dアニメ」をアニメ視聴のために契約していますが、関連するコミックやラノベは「dアニメ」ではなく普段使っている場所で買っています。まあ、まだ利用していないユーザーも多い(利用率は有料無料合わせて40%程度)ので、他社から奪うというより、新規開拓という観点のほうが強いのでしょうけど。
サイト訪問激減、「コンテンツに対価を」 米クラウドフレアCEO〈日本経済新聞(2025年10月18日)〉
サイトを巡回しデータを自動収集するプログラム「クローラー」で10年前はグーグルが2ページ読み取るごとに1人をサイトに送客していたのに、今年6月時点では1人の訪問を得るのに14ページを読み取らせる必要があるとのことでした。
つまり、送客効果が7分の1になっていると。Cloudflareを利用しているサイトのデータを集計しているのでしょうから、データは正しいとして、問題はそれがすべてAI検索のせいなのか? というところでしょう。というのは、仮に10年前の総ページ数がいまの7分の1なら、訪問減とAI検索とは関係ないって話になりますから。つまり、ライバルが増えた結果、検索結果からの流入が「薄まった」という可能性なども考慮する必要がある、ということです。
まあ実際には、新着ページの増加率が加速しているのは確かですが、古いページはサービス終了等でガンガン消滅しているのと、古い情報は検索結果上位に出づらくなる、などなど、いろいろ複雑な要素が絡むはずではありますが。要は、そういう他の要素抜きで考えちゃダメだと思うのですよね。
AI検索でメディアの広告収入が激減 「人間の代わりにAIが記事を読む時代」と闘うTollBit〈TECHBLITZ(2025年10月15日)〉
デジタルガレージ、メディア向けAI検索対策〈日本経済新聞(2025年10月16日)〉
Cloudflareに負けじと、あちこちから似たような新サービスが提供され始めました。メディア企業側による「アクセスが減っている」という主張は、正直私は「あまり信用できない」と思っています。ちょうどこのタイミングで西田宗千佳氏が「ウェブのトラフィックに大きな影響がでたという決定的な証拠はない」とおっしゃっていて、その通りだよなあと。AI検索のせいでアクセスが減っていると主張しているメディアが、サイト評判の悪用でペナルティを受けているところだったりしますし。
逆に、AI検索企業側のPerplexityはメディア企業と直接取引するプログラムを始めました。日本語でプレスリリースを出しているあたりに、日本のメディア企業に対するエール(というか秋波)を感じなくもないのですが、訴えられてから慌てて対応を始めた感は否めません。
技術
AIモードのリンククリックは3%未満!? 見えてきた「AIモードの適切な位置づけ」【SEO情報まとめ】 | 海外&国内SEO情報ウォッチ〈Web担当者Forum(2025年10月17日)〉
AIモード経由だと滞在時間が短くなるのは意外でした。事前に概要が出力されているから、出力の正しさを確認だけするような行動になるんでしょうか。コンバージョンレートが高くなるのは想定通り。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』は各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
NovelJam 2025の本戦3日間が無事(?)終了しました。まだ審査や販売競争などが残っているので、完全には終わっていませんが。せっかく用意したモバイルWi-Fiルーターが遅い・重い・切れるで散々だったことや、そのせいでZoomが本番直前に落ちるなど配信関連でトラブルだらけだったことや、会場のスピーカーアンプにうまく接続できなかったことなど、反省点の多い回でした。配信はできれば有線LANがあるところでやりたい……。(鷹野)