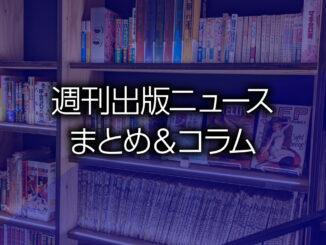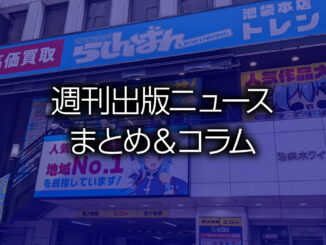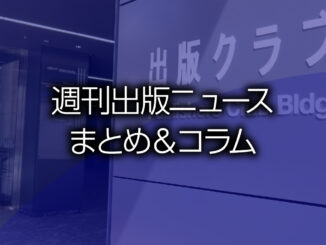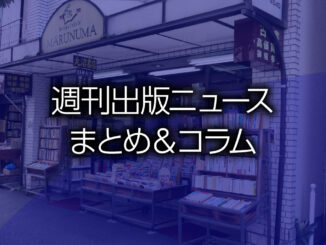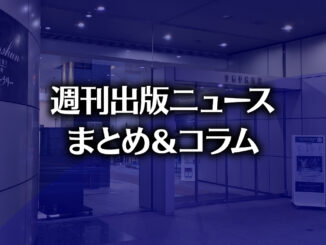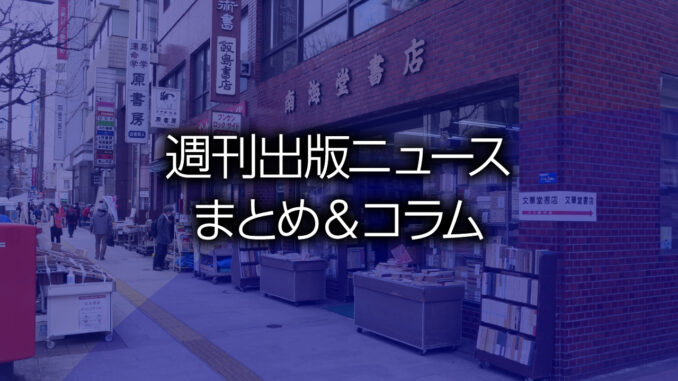
《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
2022年6月12日~18日は「侮辱罪厳罰化の改正法成立」「大規模事業者取得利用者情報適正取扱いの義務化」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
政治
侮辱罪厳罰化、改正法が成立 ネット中傷対策で懲役導入〈共同通信(2022年6月13日)〉
何度かお伝えしてきた(#511、#512、#515、#521、#522)侮辱罪の厳罰化、表現の自由が制約されていないかどうかを3年後に検証することを付則に明記する形の改正法が成立しました。法務省部会の見解では、公正な論評なら刑法35条(正当行為)により侮辱行為の違法性は阻却されるとのことですが、それを承知で仕掛けてくるSLAPP訴訟がどの程度発生するかが今後の焦点となるでしょう。
“ターゲティング広告”規制など 改正電気通信事業法が成立〈NHK(2022年6月13日)〉
NHKの見出しがまた「ターゲティング広告」に絞った書き方になっていますが、LINEの個人情報問題を発端とし、総務省・電気通信事業ガバナンス検討会で規制の強化が検討されてきたものです。報告書案がパブコメでネット業界から反発を受け、当初案より後退する形となった(#505、#506を参照)改正案が成立しました。利用者数1000万人以上など、大規模な事業者が取得する利用者情報の適正な取扱いが義務化されます。なお、規律の詳細については、特定利用者情報の適正な取扱いに関するワーキンググループで検討することになっており、すでに第1回目の会議が6月17日に行われています。
出版社に「合理的な条件」下で図書館への電子書籍ライセンス提供を求める米・メリーランド州の法律に関し、連邦地方裁判所が違憲と判断〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年6月16日)〉
アメリカ・メリーランド州で、出版社が電子書籍のライセンスを「合理的な条件」で公共図書館に提供することを求めたり、ライセンスを図書館に販売しない期間の設定を禁じたりする州法が成立したのですが、米国出版協会(AAP)が無効であると訴え、結局「違憲かつ法的効力なし」と判断されました。
本件、#489で紹介した「ライセンスは誰のために:電子書籍をめぐる米国州法の動向」が、過去の経緯を丁寧にまとめていてわかりやすいです。これで、法案に知事が拒否権を発動させたニューヨーク州や、他の6州で検討されていたという法制化への動きも、止まってしまうことになるのでしょうか。「お前には売ってやらない」問題は、そのまま固定化されそうです。
社会
連載「デジタル出版論」は、筆者多忙につきお休みとさせていただきました。1週だけで済むかな……?
経済
Amazon’s withdrawal from China questioned by the Jiangsu Consumers Council(アマゾン(Kindle)中国撤退を江蘇省消費者委員会が疑問視)〈Good e-Reader(2022年6月14日)〉
Kindleの中国撤退、ユーザー側がどういう反応をしているかが気になっていました。「クラウド内の電子データは信頼できない」といった嘆きの声が上がるなど、やはり問題になっているようです。江蘇省消費者委員会は、消費者の正当な権利と利益の保護など、アマゾンに対処を求めているとのこと。ソースは微信公众平台の記事です。
事業者側のネガティブを取り除くだけでなくユーザーにポジティブな広告を再検討する #宣伝会議〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年6月17日)〉
月刊『宣伝会議』2022年7月号の特集「デジタル広告品質とコンテキストターゲティング」から、広告事業者に対するQ&Aなど一部の記事が公開されています。とくにJICDAQ認証が顕著なのですが、広告主(アドバタイザー)・代理店・メディアなど「事業者側」のネガティブを取り除くことばかり熱心に取り組んで、実際に広告を見る「ユーザー側」が置き去りになっている感があったのですよね。そういう風潮に釘を刺していて、我が意を得たりと思いました。こういう声が広告事業者側から出てくるのは良い傾向。
Japan Book Bank、1年2カ月で版権取引42件成約〈新文化(2022年6月17日)〉
書協とVIPOが2021年3月に開設した、海外向け出版コンテンツカタログ「Japan Book Bank」(#459や#466を参照)の実績が出てきました。登録コンテンツが2870点、問合せ数371件、うち成約が42件。記事内に記されている率と数から計算すると、成約率が一番高いのは恐らく画集(登録数上位に入ってないのに成約数が多い)で、マンガや文芸書などフィクション系の成約率もそこそこ高いようです。国内出版社と利用者は無料で登録でき、マージンも発生しないとのことなので、リスクゼロで試すことができるのがよいですね。
技術
Next Commons、小説『僕らのネクロマンシー』のNFT版を発売 独自のコントラクトにより電子書籍の貸し借りも実現〈gamebiz(2022年6月14日)〉
単に「OpenSea」でNFTを売るだけでなく、トークンを持っていないとダウンロードサイトにアクセスできない仕組み(MintGateというSaaSを活用)と、トークンを持ってると宿代やイベント参加費が安くなるなどの「会員証」的役割もあるのが面白い試みだと思いました。「NFTを持っていると特典が得られる」といった付加価値を提供する方向性は、私はアリだと思います。
ちなみに記事のタイトルにある「電子書籍の貸し借り」は、正確に言えば「オーナーシップの貸し借り」です。トークンの所持によりファイルをダウンロードするための入り口は制御されていますが、オーナーシップを借りてダウンロードしたファイルには影響が及びません。つまり、コンテンツそのものはいくらでも複製可能です。NFTの購入で手に入る価値の本質はオーナーシップであり、コンテンツそのものではないと考えたほうがよさそうです。
ソーシャルDRMはファイルに購入者情報を埋め込むことで所有者を明らかにしていますが、本件では購入者情報がブロックチェーンでパブリックになっています(※個人情報が開示されるわけではありません)。DRMフリーで販売されてる書籍を所有していても、それを正規に購入したものだと第三者に「証明」するのはちょっと難しい(※支払履歴などを開示できるなら不可能ではありませんが)。だけど、本件のようにパブリックなブロックチェーンに購入履歴が刻まれてる形なら、第三者でも容易に検証可能、と。
講談社など出版3社と丸紅、4億冊データで本の需要読む 返品削減へ〈日本経済新聞(2022年6月15日)〉
3月に設立された新会社「パブテックス」についての詳報。書店への配本数をAIで算出、年2000億円にも及ぶという返品関連コストの削減を図ります。また、ICタグを普及させ検品負担を軽減し、万引き被害の抑制を図ることなども狙いです。データを活用すればするほど、「類書の実績」や「同じ著者の過去実績」がますますものをいうようになってしまいそうな予感があります。まあ、マス向けの本ならそれでもよさそうですけど。
『キャプテン翼』のNFTを海外事業者が無断で発行? 作者・高橋陽一さんら「絶対に買わないで」呼びかけ〈弁護士ドットコム(2022年6月17日)〉
こういう事件も起きてしまうのもNFT界隈。関係者によると、この海外事業者には事前に「違法(詐欺)なもの」だと伝えていたにも関わらず、強行突破されてしまったそうです。凄まじい。やはり「誰でも販売できるNFTプラットフォーム」だと、こういう事件を防ぐのは難しそう。正規に権利許諾されているかどうかなんて、第三者からは分からないですからねぇ……。
集英社「non-no」講談社「ViVi」…編集システム共通化〈日本経済新聞(2022年6月18日)〉
総合誌面制作プラットフォーム「MDAM」について。集英社が中心となって開発し、大日本印刷が導入促進・運用支援パートナーになっている仕組みです。あまり新しい情報はありませんが、ちょうど周囲でこの「MDAM」が話題になっていたので、ピックアップしました。もっと詳しい話を伺ってみたいところ。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
週の後半から急に暑くなり、エアコンの助けを借りています。しかし今からこれでは、電力不足で全国規模の節電協力要請が行われるという夏本番が思いやられます。ロシアのウクライナ侵略に伴う燃料供給不安も要因の一つとのこと。戦争反対!(鷹野)