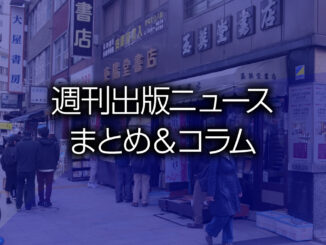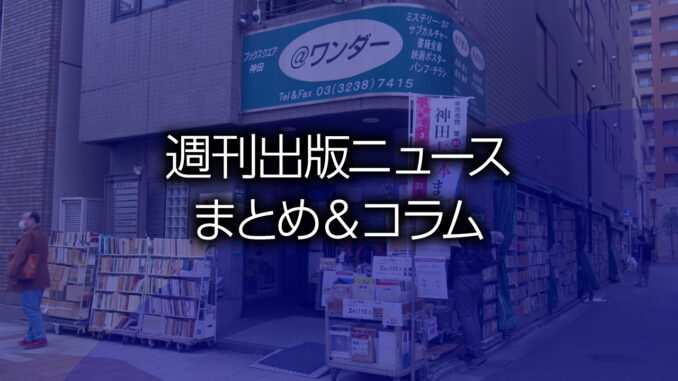
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年5月15日~21日は「国立国会図書館、入手困難資料の個人送信開始」「侮辱罪厳罰化可決へ」「ゆっくり商標問題」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年5月16日)〉
- 科学技術振興機構(JST)と剽窃判別ソフトTurnitin、パートナーシップを締結〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年5月17日)〉
- 元司書が語る! 国立国会図書館の絶版本「読み放題解禁」がスゴい | 独学大全〈ダイヤモンド・オンライン(2022年5月19日)〉
- 枕詞のように「出版不況」と言われるが、実態は「雑誌不況」である ―― デジタル出版論 第3章 第1節〈HON.jp News Blog(2022年5月18日)〉
- デジタル教科書、授業準備「負担軽減」5割以上が実感〈日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB(2022年5月20日)〉
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
侮辱罪厳罰化、「3年後の検証」明記 衆院法務委で可決〈朝日新聞デジタル(2022年5月18日)〉
国会審議で賛否が割れていた本件、結局、表現の自由が制約されていないかどうかを3年後に検証することを付則に明記する形で着地しました。スラップ訴訟が濫発されるような事態が起きたら、「公共の利害に関する場合の特例の創設も検討すること」とされています。まあ、無難な落としどころではないかと。
[社説]記事表示の対価は欧州参考に〈日本経済新聞(2022年5月20日)〉
先週、「グーグル、欧州300超のパブリッシャーにニュース使用料支払いへ」というニュースがありました。本欄では日本との関連の薄さを考慮しピックアップしなかったのですが、日経から「IT(情報技術)大手は、このことを重く受けとめるべきだ」という我田引水な社説が出ていたので改めてピックアップしておきます。まあ、言いたい気持ちはわかる。
そこで、日本の著作権法で同様の制度を導入するにはどうすれば? という思考実験をしてみました。平成30年改正の「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定」に補償金を導入する形ならあり得るかも? とくに第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)。実際には、この権利制限をすでに利用しているケースが非常に多いと思うので、影響が大きすぎて難しいかなとは思いますが。
社会
「ゆっくり茶番劇」事件の炎上要素抜き解説(栗原潔)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年5月16日)〉
UGCで誰かが始めてトレンドになり共有財産化したような概念を勝手に商標登録する事件は以前からたびたび起きていましたが(エイベックス「のまネコ」問題が有名)、今回は「元ネタと無関係な個人」が登録したうえ「年間で10万円(税別)の使用料が必要」と主張したことで大炎上となりました。その炎上要素を抜きにした商標登録部分のみを、おなじみ弁理士・栗原潔さんが解説してくれました。
この「ゆっくり」動画の産地である「ニコニコ動画」のドワンゴからも見解が出ているので、合わせてピックアップしておきます。後半の「非類似にあたる文字列」は圧巻です。この対応は素晴らしい。
文字商標「ゆっくり茶番劇」に関するドワンゴの見解と対応について〈ニコニコインフォ(2022年5月20日)〉
科学技術振興機構(JST)と剽窃判別ソフトTurnitin、パートナーシップを締結〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年5月17日)〉
最近、論文投稿の仕組みや剽窃チェックなどについて調べていたのですが、タイミング良くこんな記事が。科学技術振興機構は電子ジャーナルプラットフォーム「J-STAGE」を運営しています。つまり「J-STAGE」に今後登録されるコンテンツすべてと、過去に登録されたコンテンツ約260万件が、剽窃チェックの対象になります。これはすごい。過去の所業がバレてしまう人も出てきそう。震えて眠れ。
この「Turnitin(ターンイットイン)」がどれくらいの精度で剽窃を検出できるかはわかりませんが、リリースによると「教育機関や出版社、企業などの1万6,000以上の団体に導入」されている実績があるとのことです。
元司書が語る! 国立国会図書館の絶版本「読み放題解禁」がスゴい | 独学大全〈ダイヤモンド・オンライン(2022年5月19日)〉
楽しみにしていた「個人送信」が、ついに始まりました。各社から報道されていましたが、このタイミングで読書猿さんと書物蔵さんの対談という形のガッツリ記事を出したダイヤモンド・オンラインをピックアップしておきます。書物蔵さんの「自宅の隣に国会図書館がたつようなもの」という例えがわかりやすい。
利用者登録の申請がオンラインからできるようになって、申請が殺到しているようです。「手続に相当の日数を要する見込み」という案内がツイッターに出ていました。2月の時点(#508)で「いまのうちに登録しておくことを強くオススメします」と書いたとおり、まあ、予想通りではあります。
個人向けデジタル化資料送信サービスの開始に伴い、現在オンラインで、大変多くの利用者登録(本登録)の新規登録及び移行手続の申請をいただいており、手続に相当の日数を要する見込みです。
ご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
— 国立国会図書館 NDL (@NDLJP) May 21, 2022
現状だとトップページや検索結果一覧がモバイル非対応(個別ページは対応済み)なのが残念ポイント。「スマホで読める」のは確かなんですが、その手前の検索して調べる段階がまだ不便なのですよね。いま「次世代デジタルライブラリー」で公開されている全文検索機能が「2023年1月頃公開予定の次期・国立国会図書館デジタルコレクションで提供する見通し」なので、その際いっしょにモバイル対応されることを期待しています。
あとは、補正予算でデジタル化された1969年以降2000年までの入手困難資料の追加も大いに期待。事前除外手続きでは「毎年7月に、翌年に送信を開始する送信候補資料のリストを公開し、事前除外申出を7月から11月まで受け付け」て、12月に送信資料が決定されるというスケジュールになっています。つまり、これから毎年12月に資料がドカッと追加されるお祭り騒ぎが起きることになりそうです。うひょー!
枕詞のように「出版不況」と言われるが、実態は「雑誌不況」である ―― デジタル出版論 第3章 第1節〈HON.jp News Blog(2022年5月18日)〉
デジタル出版論の連載、第3章「出版ビジネスの現状と課題」へ突入しました。ここからしばらくは「狭義の出版」の話になります。紙と電子の違いを中心に掘り下げていく中で、今回の「雑誌不況」のような客観的事実の指摘も行っていきます。次は「再販制度」の予定です。
デジタル教科書、授業準備「負担軽減」5割以上が実感〈日本教育新聞電子版 NIKKYOWEB(2022年5月20日)〉
文科省の調査。「教員の負荷軽減に繫がる」という認識が広がると、急速にDXが進みそうです。実際、授業のために紙に印刷して配る工程って、なにげに負荷が大きいのですよね。大量印刷でプリンターの順番待ちが発生しますし。2015年に実践女子短期大学で非常勤講師を始めたとき、印刷物を用意するのがすぐに嫌になって、ペーパーレスに切り替えたのを思い出しました。
経済
信じてますか No.1〈NHK | WEB特集(2022年5月17日)〉
景品表示法により「No.1」をうたうには根拠が必要なのですが、ここ数年、その「No.1」を意図的に作り出す調査会社が跋扈している問題が起きています。これを指摘する報道がNHKから出ました。以前、日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)が抗議状を公表した際にもピックアップしましたが(#506)、NHKが報じたというのはインパクトが大きい。
これ、「嘘ではない」からタチが悪いのですよね。日々いろんな調査結果が発表されリリースも届きますが、昔からリサーチをやっている企業(粗悪な調査結果を出したら評価が下がってしまうことを恐れるはず)以外で、調査方法が「インターネットリサーチ」としか書いてなかったら、私は無視するようにしています。粗悪な調査は結果がねじ曲がる。総務省統計局に、有名な「アメリカ大統領選挙の番狂わせ」の記事があったので紹介しておきます。
E-Book sales in the UK drop to the lowest since 2012〈Good e-Reader(2022年5月20日)〉
イギリスでE-Bookの売上が2012年以来最低水準まで落ち込んだ、とのこと。おや? と思うところですが、実はこれ鵜呑みにできません。参照されているニールセンのデータは「非ISBN書籍をカウントしないことで恣意的操作されている」と指摘されていたことがあります。
https://hon.jp/news/1.0/0/8650
いまも恐らくそれは変わっていないと思うのですが、Good e-Reader がソースとしている the Bookseller の記事も、the Bookseller がソースとしている Nielsen BookData も、有料会員向け。検証が難しい。イギリスはとくにKindleが強い(2018年のJPOと文化通信社のレポートにはシェア90%という記述があった)はずで、アマゾンの秘密主義により非ISBN書籍のデータはなかなか表に出てこないのが現状だと思われます。
ちなみに恣意的操作云々とニールセンを批判していた Data Guy「Author Earnings」は、その数年後に閉鎖されています。どうも2018年1月のレポートを巡ってインディー作家とトラブルがあったようなのですが、詳細は不明です。
技術
国立国会図書館、OCR処理プログラムと学習用データセットを公開〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年5月16日)〉
OCR処理プログラムはCC BY 4.0ライセンスで公開。NDLラボのリリースには「既存のライブラリ等を利用している部分については寛容型オープンライセンスのものを採用しているため、商用非商用を問わず自由な改変、利用が可能です」という記述も。すげぇ!
開発はモルフォAIソリューションズ。プレスリリースによると、複雑なレイアウトにも対応しているとか、旧字旧仮名にも対応しているとか、精度もなかなかのもののようです。
また、学習用データセットは、LINEに委託して作成したもののうち、パブリックドメインのものが公開されています。LINEは1年前に「247万点・2億2300万枚超の全文テキストデータ化に「CLOVA OCR」が採用」というリリースを出していましたが、今回はとくになし。
NDLラボの資料に、それぞれ「どんな年代の資料でも精度面で競合サービスに勝てる最強の日本語OCRを仕上げて、当館の活字のデジタル化資料を全部処理してください」「どんな年代の資料でも精度面で他サービスといい勝負のできるAI OCRを開発して、当館で自由にカスタマイズやソースコード公開ができるようにしてください」というミッションが出ていたことが記されていました。過去分のOCRがLINE、今後のOCRがモルフォAIソリューションズという棲み分けだったんですね。なるほど。
JASRACがデジタルサービス続々、ブロックチェーン使う楽曲存在証明は6月開始〈日経クロステック(xTECH)(2022年5月18日)〉
作品情報データベースを持っているJASRACならでは……と思ったのですが、むしろJASRAC非会員の作品情報データベースを強化するためのサービス展開のようです。なりすまし防止の「KENDRIX」は、JASRACの非会員を含め誰でも無料で利用できるとのこと。
オリジナルの作者が「KENDRIX」を利用していない場合に、なりすまし防止のためのサービスになりすまし登録ができてしまう可能性をどう防ぐかが気になります。一歩間違うと「OpenSea」のような偽NFTが跋扈する場になってしまいます。誰でも利用可能とはいえ、それなりにしっかりした身元証明が必要であれば、逆に「消えない犯行証明」にもなりそうですが。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
ブッシュ元米大統領が「イラク侵攻は不当」と言い間違え、直後に「ウクライナのことだ」と訂正したニュースがありました。いや、実際にイラク侵攻も不当だったことは明らかになっていますが。笑って誤魔化そうとするな。戦争反対!(鷹野)