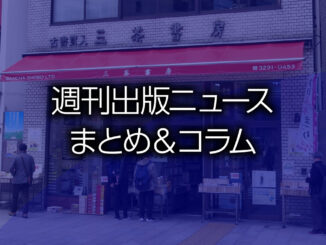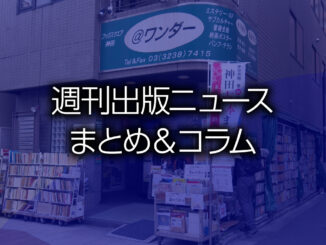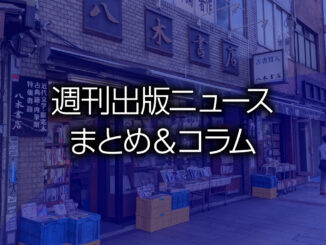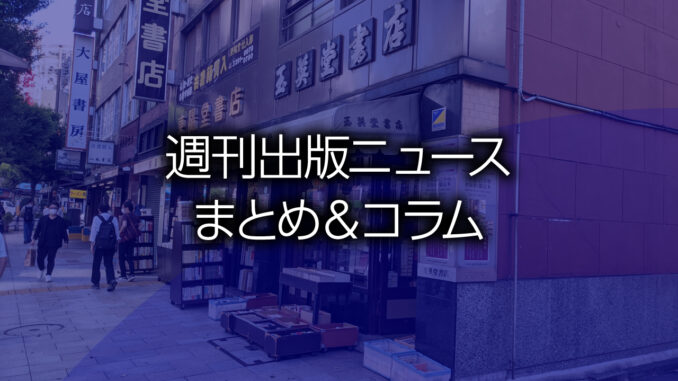
《この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です(1分600字計算)》
2022年1月30日~2月5日は「リーチサイトとネタバレサイトの摘発相次ぐ」「コロコロ電子版閲覧権+付録だけ販売」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
政治
集英社、講談社、小学館、KADOKAWAがクラウドフレア社を提訴〈コミックナタリー(2022年2月1日)〉
#507 で「方針を固めた」報道をピックアップしましたが、その2日後には、実際の提訴に踏み切りました。対象は各社1作品のみ、賠償請求が総額4億6000万円。はっきり言って「安い」ので、譲歩を引き出したい戦術なのかな? という気がします。
著作権侵害、深刻に受け止める 米クラウド社、提訴にコメント〈共同通信(2022年2月2日)〉
こちらの共同通信報道は、Cloudflare社からのコメントが中心。「深刻に受け止める」が見出しになっていますが、むしろ「同社のサービスが著作権侵害に寄与するものではないと米国の連邦裁判所から判断されている」が、彼らの一番アピールしたいことのように思えます。
「連邦裁判所から判断」とはどういうことか? と調べてみたら、Cloudflare社が勝訴を誇示する「In a win for the Internet, federal court rejects copyright infringement claim against Cloudflare」というエントリーが昨年10月に公開されているのを見つけました。よく読むと「District Court」だから地裁判決だったりします。相手が控訴したかどうかまでは不明です。
もっとも、アメリカの著作権法では合法でも、他国では非合法という場合も意外と多いわけで。法律が違いますからね。著作権法は属地主義です。日本の司法判断がどうなるか、注視しておきたいところ。
リーチサイト運営者 書類送検へ〈日本経済新聞(2022年2月3日)〉
すでに閉鎖されているようなので名前を出しますが、リーチサイト「漫画天国」運営者を警視庁が書類送検する方針とのこと。ただ、本件の容疑はリーチサイトが違法となった改正著作権法が施行される前の事例で、表紙画像の掲載が著作権法違反に当たると判断されたそうです。2020年10月施行以降の侵害については、別容疑扱いになるのかな……?
「ネタバレサイト」運営会社など書類送検へ 著作権法違反疑い | IT・ネット〈NHKニュース(2022年2月3日)〉
海賊版サイト関連の報道が連発。こちらはセリフなどをまるごと転載する、いわゆる「ネタバレサイト」の運営者を福岡県警が書類送検する方針とのこと。任意の調べに対し「悪いことだと知っていた」などと、容疑を認めていることも明らかになっています。これは以前、逮捕者が出た「ファスト映画」の事例に近いと言えるでしょう。
異なる事例の情報が同時多発的に出ていますが、以前も書いたように「海賊版を一撃で退治できるような特効薬は存在しない」ので、広告掲載を潰すなど他の手法も含め継続した取り組みが行われています。それがたまたま同時期に重なって報道されている、ということなのでしょう。
インボイス制度の中止要求 日本出版者協議会〈共同通信(2022年2月3日)〉
中小出版社の団体である出版協から、インボイス制度中止要求の声明。フリーランスへ発注する立場からの声明である点がポイントでしょう。フリーランスは、免税事業者が多いですからね。仕入れ額として税控除できなくなると、中小出版社の収益に直撃してしまいます。ウチも他人事ではありません。
ちなみに、いつものように意見もなにも付けず、ただ単にTwitterへ流しただけなのですが、なぜかプチバズってしまいました。そして、なぜか HON.jp News Blog のアカウントに「遅い」だのなんだの、好き勝手な意見が飛んでくるという状態に。
ただ、インボイス制度反対の声に対する意見をウォッチしていると、益税に対するヘイトが想像以上に強いことを感じています。制度上認められているとはいえ「俺の払った消費税を自分の財布に入れやがって」的な。本来、消費税そのものへ向けるべきヘイトが、こっちへ向かっちゃってる感があります。なんというか、財務省の思うつぼ。
文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第3回)〈文化庁(2022年2月4日)〉
あまり本気で追いかけていなかった「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度」などを検討していた法制度小委員会。傍聴申込みを忘れていて、大量に公開されている資料だけ目を通したのですが、報告書(案)を見て「もっとちゃんと追っていればよかった……」と後悔しました。
出版権のような差止請求可能な制度を、他の著作物の独占的ライセンサーにも拡大するための検討を行っている、という雑な認識をしていたのですが、海賊版の削除請求を容易にするためのものでもあったのですね。認識不足でした。トホホ。資料の量があまりに多いので、気になる方は、まずは参考資料2の概要から見ることをオススメします。
結論としては、独占的ライセンスの対抗制度と、独占的ライセンシーに差止請求権を付与する制度の導入が適当である、と。ただ、出版権のような専用利用権構成と独占的利用許諾構成のどちらを採用するかは、具体的な制度設計をする文化庁の判断に委ねられました。また、著作権登録対抗制度の見直しも、継続検討していくことが望ましいとしています。今後は注視します。
アプリ自社決済の強制禁止、米上院司法委が法案可決〈日本経済新聞(2022年2月4日)〉
昨年、韓国で成立したのと同様の、アプリストアでの自社決済システム強要を禁じる「開かれたアプリ市場法案」が、上院委員会で可決しました。賛成20に対し反対2という大差で、超党派による承認だったそうです。まだ法案成立ではなく、上下院本会議での審議可決と、法案一本化などの手続きが残っています。が、巨大IT企業が本国お膝元で規制されると、グローバルに影響が出ることになるでしょうから、今後も動向から目が離せません。
社会
国立国会図書館、「個人向けデジタル化資料送信サービス」を5月19日から開始予定〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年2月1日)〉
5月19日から開始予定と、日付が明確になりました。楽しみ! 国立国会図書館の利用者登録は無料・郵送でできます(返送用の切手代も不要)ので、いまのうちに登録しておくことを強くオススメします。条件は、満18歳以上で、国内在住であること。必要なのは、申請書と本人確認書類です。
国立国会図書館、「次世代デジタルライブラリー」の全文検索対象拡大と画像検索機能改善を実施〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年2月1日)〉
国立国会図書館が実施しているデジタル化資料のOCRテキスト化事業の成果物の一部が全文検索の対象に追加されました。保護期間が満了している図書資料約7万点です。今後、随時追加されていく予定とのこと。また、保護期間が満了していない資料の全文検索機能は「2023年1月頃公開予定の次期・国立国会図書館デジタルコレクションで提供する見通し」ともあります。1年後に大幅なバージョンアップが来る!
国立国会図書館ウェブサイト利用規約〈国立国会図書館―National Diet Library(2022年2月1日)〉
といった大きな情報がドンドンと連続で出ている影に隠れていますが、なにげにこれも大きな変化です。関連してピックアップ。国立国会図書館ウェブサイトで公開されている情報の利用について、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠 = CC BY 相当の利用条件に変わりました。
以前は、パブリック・ドメインの作品でさえ転載依頼フォームからの申し込みが必要とされていた(リンク先は、それが不要となった2014年にマガジン航へ寄稿した記事)のですが、今後は「基本的に無断で利用できる」に変わったのです。
国立国会図書館の関係者がTwitterに投稿しているのを見かけましたが、この規約改定は10年がかりだったとのこと。お疲れさまでした。なお、「第三者に権利があることを表示・示唆している場合」など、対象外のケースもありますのでご注意ください。
2021年はデジタル出版50周年だった〈HON.jp News Blog(2022年2月2日)〉
ここ数年、大学の非常勤講師として講義している内容を、テキスト化して連載してみることにしました。構成は決まっているのに、書き出しをどうするかを結構悩みました。まあ、タイミング的にも、先人に敬意を表する意味でも、ここはやはり「Project Gutenberg」50周年かな、と。今後は週1回くらいのペースで更新していく予定です。終着まで1年がかりかな……?
https://hon.jp/news/1.0/0/category/feature-articles/column/digital-publishing-theory
経済
週刊誌がいま“デジタル配信記事”に力を入れる理由 FRIDAYデジタル芸能デスクが明かす〈ニッポン放送 NEWS ONLINE(2022年1月31日)〉
辛坊治郎さんのラジオ番組書き起こし。基本、生放送なので、口が滑ってしまった、あるいは、誤解を招く言い回しをしてしまった部分もあるかと思いますが、以下の発言はちょっと気になりました。
「FRIDAY」から記事を、簡単に言うと流用しているので、そこに関しては原価がかかっていないわけです。
これ、逆の立場で考えると、「ウチが汗水流した成果をタダで持っていきやがって」という話になりますよね。言い回しの問題ではなく本当に「原価がかかっていない」状態だとしたら、組織間対立を生みかねない発言だと思います。こういうのは、売上比率での原価按分か、公平に収益分配すべきでしょう。
ちなみに以前、文春オンラインは各編集部に収益分配している、というインタビュー記事がありました。#501 でピックアップしてます。より公平にするため、按分比率はPVではなくUUをベースにしているそうです。そういう気を遣っているからこそ、ここまで成長できているのだと思います。
「ステマ」と宣伝の境界線とは? TikTok問題から考える〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年2月1日)〉
「そのSNS投稿、大丈夫?」ステマに関する10の疑問に答えるQ&A〈AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議(2022年2月2日)〉
観念的な話ではなく、実務的な話。WOMマーケティング協議会(WOMJ)の「口コミマーケティング」に関するガイドラインに基づく“境界線”について、策定・改訂に関わった当事者による解説です。TikTokのステマ騒動は、れっきとした「企業の宣伝活動」だと断じています。これはガイドラインが禁止している「偽装行為」である、と。Q&Aに記載されている「消費者が正しく情報を知る権利が保護されているか」という観点が重要だと思います。
サブスク1,000万件,NYタイムズが3年で倍増のわけとは〈新聞紙学的(2022年2月3日)〉
ついに1000万件! 日本のトップランナーである日経電子版の有料会員がまだ100万に届いていないことを思うと、ずいぶん水をあけられた感があります。とはいえ、主軸のデジタルニュースは6割強で、ゲームや料理情報などジャンル別のサブスクもそれぞれ100万件以上あるそうです。紙の新聞も含まれていますが、「80万件足らず」とのこと。紙と電子の比率も、凄まじいものがあります。
技術
ここにきて「コロコロコミック」の勢いが凄いことになっていた…! 久々の“100万部突破”を達成したワケ(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2022年2月1日)〉
プレスリリースのタイトルが付録の内容と「2月号発売!」だけなので、本文を読まずに見逃していました……不覚。コロコロコミックという看板商品で紙版無し・電子版閲覧権+付録だけ販売というモデルが試行されていました。
実はこれ、過去にも2回試行されていて、今回で3回目だったそう。「過去2回の経験を踏まえ、部数的にもかなりの勝負をかけて」いるそうで、紙版の有無でどれくらい販売数に違いがあるか、わたし気になります!
なお、電子版はコロコロ公式のサブドメインで配信されており、ここで16桁のシリアルコードを入力する方式。FAQの対応環境を見るに、ブラウザビューアでストリーミング配信のようです。ただ、他の雑誌でよく見かけるような「閲覧期限」は設定されておらず、「無制限でお楽しみいただけます」と明記されています。
となると問題は、こういう事業モデルの継続性でしょう。過去の経験上、出版社の公式配信でも安心はできません。例えば、講談社デジタル本棚「codigi」は、3年でサービス終了しています。
コロコロの場合、紙版のオマケで電子版が付いてくるわけではないぶん余計に、継続性が問われるのではないかと思うのです。電子版閲覧権+付録販売で充分に収益性が上がるくらい売れているならそんな心配は無用でしょうし、リアル書店にとっても朗報と思いますが。果たしてどうなのか。
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
集中していると時間があっというまに過ぎていきます。子供のころから過集中傾向があり、呼ばれているのにまったく気づかないことも。「無視するな」と怒られたりするんですが、本人、ほんとに気づいていないのです(鷹野)