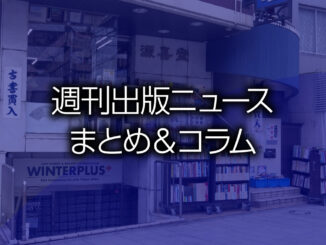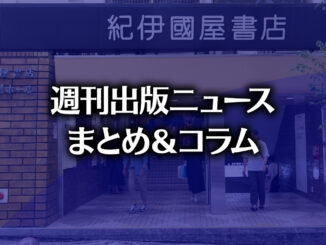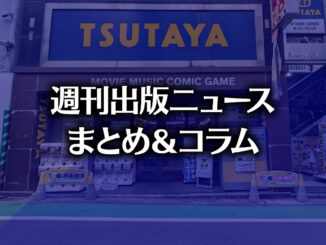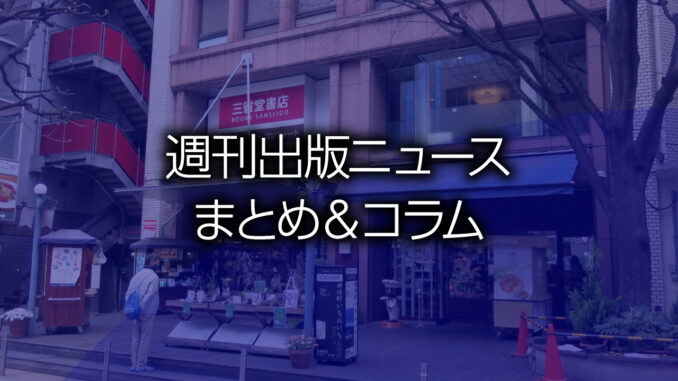
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2022年5月8日~14日は「侮辱罪厳罰化への国会審議で賛否」「ウェブトゥーン参入企業が増えたわけ」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
政治
米グーグルを独禁法違反で提訴、「ティンダー」運営会社〈ロイター(2022年5月10日)〉
Google Playの決済手段拘束が独占禁止法違反であるという訴え。#520 で「Appleと同様の措置をとれば、Appleと同様に目を付けられるだけ」と指摘しましたが、今後恐らく、Epic Games対Appleの訴訟と同じ道を辿ることになるのでしょう。なにやってるんだか。
ネットの誹謗中傷は減るのか?木村花さん死去で加速した侮辱罪厳罰化への動き、母・響子さんと共に戦う弁護士の懸念〈ORICON NEWS(2022年5月13日)〉
侮辱罪厳罰化へ向けた国会審議が大詰めに。発端となったのはフジテレビ「テラスハウス」問題で、亡くなられた木村花さんの母・響子さんと弁護士による政治家への働きかけにより改正へ動き出したという経緯があります。つまりこちらの記事は、推進する側の意見です。
新聞各紙をざっと調べたところ、産経新聞は明確に賛成。朝日新聞は「慎重な検討が必要」。東京/中日新聞は「異を唱えたい」。読売新聞と毎日新聞は、社説的なものは見つけられなかったのですが、記事の傾向的には賛成っぽい感じでした。
【多面鏡】ネットの誹謗中傷 はびこる「凶器」、厳罰化やむなし 東京社会部長・酒井孝太郎〈産経ニュース(2022年2月28日)〉
(社説)侮辱罪厳罰化 慎重な審議を求める〈朝日新聞デジタル(2022年5月8日)〉
<社説>侮辱罪の厳罰化 言論封殺の危惧を持つ〈東京新聞 TOKYO Web(2022年5月14日)〉
政治家によるスラップ訴訟や公権力による濫用(ヤジで逮捕とか)が怖いのは確かですし、私も #511 や #512 や #515 で表現の萎縮に繫がる可能性について懸念を表明していますが、なにがなんでも反対というわけではありません。
法務省部会での審議(第2回の議事録より)では、刑法231条(侮辱罪)には除外規定が無いが、刑法35条(正当行為)により侮辱行為の違法性は阻却されるという見解が示されています。また、民事でも「社会通念上許される限度を超える侮辱行為でないといけないとされて」いるので、刑事ならもっと限定される、と。
つまり、朝日新聞が報じている立憲民主党議員の質問「大臣の資質があるか疑問」程度なら、「公正な論評」の範疇(=侮辱罪にはならない)とみなされそうです。少なくともいきなり逮捕なんてことはなさそう。
関連して、イギリスでスラップ訴訟を防ぐための法改正が検討されているというレポートを正会員の小林恭子さんが書かれていたので、合わせてピックアップしておきます。名誉毀損が免責される「公益に資する内容の公表」適用枠の拡大や、原告が受け取る損害賠償金額への限度付与などが検討されているそうです。
富豪や大企業が起こす「スラップ訴訟」 言論の自由萎縮を懸念し、英政府が撲滅を模索(小林恭子)〈個人 – Yahoo!ニュース(2022年5月10日)〉
プラットフォームサービスに関する研究会(第36回)配布資料〈総務省(2022年5月12日)〉
プラットフォームサービスにおける違法・有害情報対策の検討会。偽情報に関する意識調査や、諸外国におけるファクトチェック支援団体の状況などの資料が公開されています。とくに事務局からの資料7「コンテンツモデレーションにおける透明性と説明責任に関するサンタクララ原則」が気になりました。というか、この原則の存在を知りませんでした。2018年に策定、2021年に改訂されバージョン2.0になっています。
「人権およびデュープロセス(適正な手続き)」や「理解しやすいルール及びポリシー」など5つの基本原則や、運用原則、政府などのための原則が定められています。Facebook、Google、Twitterなど12のプラットフォーム企業が支持しているそうです。えっと……これらのサービスから問答無用でBANされ説明も無いような状況をよく見聞きするんですが、実行が伴っていないような気が。まあ、あくまでこれはガイドであって、規制のためのひな型を意図したものではないそうですが。
社会
若者の間で“図書館人気”が沸騰! 利用率が過去最高に〈Pen Online(2022年5月9日)〉
アメリカの話。来館者数は2009年から2019年で21%減少しているそうです。つまり、遠隔サービスによる利用が非常に伸びているというわけ。デジタル化にともない、書籍の約58%はオンラインで貸し出されているそうです。ニューヨーク公共図書館の電子書籍貸出アプリ「SimplyE」が例示されています。
日本も早くそういう状態になって欲しいものです。関連して、国立国会図書館から以下のような検討会の報告書が出ていたので、合わせてピックアップしておきます。
図書館におけるアクセシブルな電子書籍サービスに関する検討会 令和3年度報告書〈国立国会図書館―National Diet Library(2022年5月12日)〉
プラットフォームでマスコミ4媒体とウェブ発メディアは同じ土俵で競う〈HON.jp News Blog(2022年5月11日)〉
デジタル出版論の連載、第2章はここでひと区切り。次の第3章「出版ビジネスの現状と課題」で、著者や書店のビジネスモデルや、再販制や委託販売などについても深掘りする予定です。プラットフォーム支配については第4章「情報流通と巨大IT企業」、検索サイトについては第5章で取り上げます。このままのペースだと、全体で25万字くらいになりそう。
経済
【マンガ業界Newsまとめ:番外編】なぜこんなにWebtoon進出企業が多いのか?〈菊池健|note(2022年5月7日)〉
正会員の菊池健さんによる考察。日本におけるウェブトゥーンの源流「comico」から現在に至るまでの経緯まとめと、近年また急に参入が増えた理由についてです。詳しくは読んでいただきたいのですが、端的に言えば「ウェブトゥーン発のヒット作が出た」ことと、「世界市場で有望視されている」「メディアミックス展開のリソースがある」といったところ。
つまり、ウェブトゥーン事業はいまなら投資家から資金が調達しやすい(だから新規参入しやすい)ということなのだと思います。各社から新しい作品の投入が始まっていますので、あとは「次のヒットがいつ生まれるか」でしょう。鬼滅クラスのメガヒットは「千三つ」で、世相など運にも左右されますから、いまはとにかく「数」を打って多様性を確保することだと思います。
アメリカで新聞・雑誌業界団体統合へ 名称は「News/Media Alliance」〈文化通信デジタル(2022年5月12日)〉
Merger of News Media Alliance (NMA) and The Association of Magazine Media (MPA) is a go!〈Editor and Publisher(2022年5月6日)〉
News Media Alliance and MPA – The Association of Magazine Media announce merger | What’s New in Publishing 〈Digital Publishing News(2022年5月10日)〉
日本で言えば「日本新聞協会と日本雑誌協会が統合」みたいな話です。「デジタル出版論」の第1章で述べた、紙では「メディアを異にする」区別に意味があったのが、デジタル化に伴い融合していく、という流れを象徴するような出来事と言えるでしょう。
KADOKAWA 2022年3月期 通期連結業績発表 過去最高(*)の売上高、営業利益、営業利益率を達成〈株式会社KADOKAWAのプレスリリース(2022年5月12日)〉
大手出版社の好決算が続きます。公式サイトで「通期決算説明資料」を確認しました。電子書籍事業の詳細(p30)ではけっこう詳しい数字が明かされていて、興味津々です。

売上高縦軸の単位は前期同様なら「Million JPY」で、ストア事業(BOOK☆WALKER)とプラットフォーム事業(dマガジン)と外販の合算です。4Qが135億5200万円なので、通期では500億円くらい。国内ストア事業は+15%、外販が+23%、グローバルが+53%で15億円くらいでしょうか。恐らくラノベ比率が高いとは思いますが、文字モノ比率が3割近いのも良いです。いやあ、すごい。
グーグル、検索結果やYouTubeの広告を設定する「My Ad Center」〈ケータイ Watch(2022年5月13日)〉
今年の Google I/O でもさまざまな発表がありましたが、なかでもこちらをピックアップしておきましょう。#520 で「デリケートな広告」をユーザーの任意で除外できるようになる予定という報道を紹介しましたが、同じ方向性の内容のようです。先の報道では「YouTubeとGoogleディスプレイネットワーク(GDN)のみ」、今回は「YouTube、検索、Discover」と、対象範囲が少し異なるのが気になります。GDNは、提携メディアにも関わってくる話ですからね。
技術
AIで文章書き換え盗作 中国で「洗稿」横行 広告収入目当てか〈西日本新聞me(2022年5月7日)〉
DeNAの医療メディア「Welq」が編集部の指示で剽窃記事を量産していたことが明らかになり炎上・閉鎖されるなどの問題が、2016年から2017年に大きくクローズアップされたのを思い出しました。当時、私は「出版ニュース」に「ネットで氾濫する捏造・剽窃記事を出版業界は笑えるか?」という論考を寄稿しています。
このとき「真偽のほどは不明だが、剽窃記事を自動生成するボットの存在まで噂されている」と書いたのですが、この「洗稿」はまさにそのようなツールということになるのでしょう。人の手で剽窃するのは少なからず手間がかかる(コストを要する)わけですが、AI任せで自動生成ならコストを限りなくゼロに近づけたうえで量産できてしまいます。
逆に、AIによる類似性や剽窃のチェックツールも登場していますが、見抜ける/見抜けないのイタチごっこになる予感があります。当時の私は「テクノロジーの進歩によって世の中は健全な方向へ進んでいるに違いない。そう私は信じている。」と結びました。いまでもそう信じたい。信じたいのだけど、昨今の情勢を見るに……いや、希望を捨ててはならない。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/1.0/0/category/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
この週末、日本出版学会の総会・理事会が開催され、理事を拝命しました。東京電機大学 矢口博之さんの後任で、出版デジタル研究部会の部会長、ということになりそうです。HON.jpとの共催で事例発表などができたら、などと考えています。「こんなのどう?」と気軽にご提案ください。
懸念されていたロシアによる宣戦布告は行われませんでしたが、引き続き戦争反対!(鷹野)