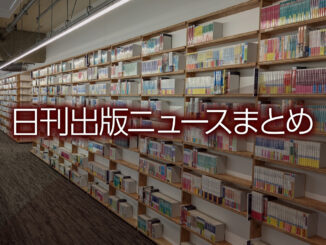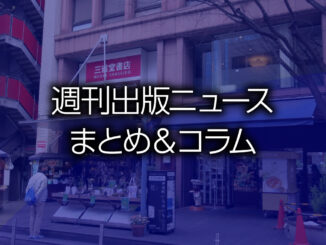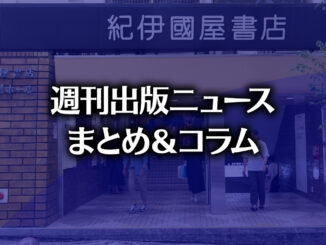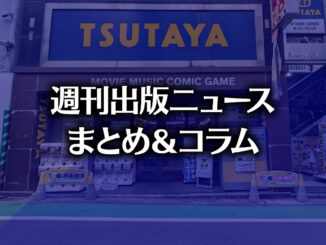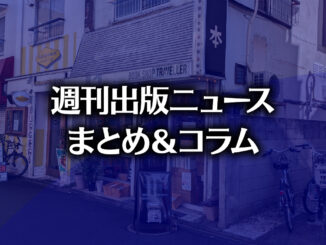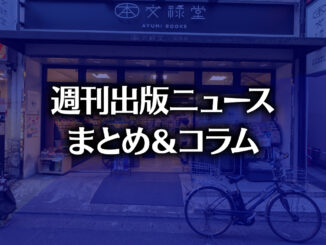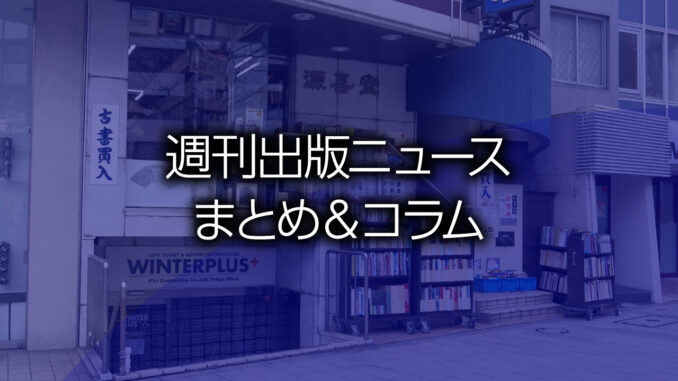
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2023年1月8日~14日は「2023年予想」「人はまちがえる生き物」「リテールメディア伸長の意味」「物流2024年問題」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 総合
- 政治
- 社会
- 経済
- 戦国時代に突入した米デジタル広告市場〈日経ビジネス電子版(2023年1月10日)〉
- デジタルコミックで北米市場を攻めるNTT西日本の勝算〈ニュースイッチ by 日刊工業新聞社(2023年1月10日)〉
- 迫る物流2024年問題 その荷物、来春から届きますか?〈日本経済新聞(2023年1月11日)〉
- 2022年のEC業界振り返り&2023年に起きそうなこと【ネッ担まとめ】 | ネットショップ担当者が 知っておくべきニュースのまとめ〈ネットショップ担当者フォーラム(2023年1月11日)〉
- 【CES2023】Amazonが広告を席巻する日(玉井博久)〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2023年1月13日)〉
- 技術
- お知らせ
- 雑記
総合
2023年出版関連の動向予想〈HON.jp News Blog(2023年1月11日)〉
いやあ、苦戦した。結局10日間費やしてしまいました。前半のマクロ環境分析(PEST)に時間がかかってます。とくに、インボイス制度があっちにもこっちにも影響しそうで。1年後は前倒しできるよう、もう少し工夫します。今年の5つの予想は以下のとおり。まあ、予想というか、私がこういうことを重視して情報を追っている、とお考えいただければ。
- メディアビジネスの転換が進む
- 書籍でもワークフローの見直しが進む
- コンテンツの輸出が拡大する
- エディターシップの必要性が高まる
- 技能継承の必要性が高まる
ロイター研究所「ジャーナリズム、メディア、テクノロジーのトレンドと予測 2023年」を読む〈Media Innovation(2023年1月13日)〉
ロイター・ジャーナリズム研究所(英国)の2023年トレンド予測。今年起こり得る業界の動きとして「印刷コストの上昇と販売網の弱体化」が避けられない、というのは日本も同じ。広告よりサブスクリプション・メンバーシップを重要視というのも同じ。若年層に人気のあるTikTok、Instagram、YouTubeに力を入れる、というのは……日本だとどうなんだろう?
……と思い、ひとまずTikTokの国内企業系アカウントランキングを確認してみました。報道機関系ではやはりテレ朝や日テレなど、テレビが強い。さすが映像のプロ。また、新聞系だと朝日・毎日・日経はそれなりにフォロワーがいます。ただ、公式サイト側からのリンクが見つからない。なぜ。読売・産経はそもそもアカウントが見つからない。うーむ、これは党派性の問題か。Instagram、YouTubeにはあるんですが。
出版社系だと、メガヒットIPの公式アカウントが目に付きます。去年の検証5番目、こういう調査をやればよかったなあ。いまさらですが。報道目的でのSNS分析ツールの導入、検討したほうがいいかもしれない。
政治
“海賊版問題”教材を初作成 来年度から高校授業で活用 文化庁 | 教育〈NHK(2023年1月12日)〉
これは良い動き……というか、教材は「初作成」なのですね。2019年に政府がまとめた「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー」では、第1段階の1番目に「著作権教育・意識啓発」が挙げられています。まあ、どういう動画かにも依ると思いますが、テキストやポスターよりリーチしやすいかな?
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
人はまちがえる生き物です――言葉を届ける前にしておきたい12のケア〈第2回〉〈HON.jp News Blog(2023年1月10日)〉
校正者・大西寿男さんによる連載2回目です。人間のやることだからミスは必ず起きる、というのが前提なのですよね。「目を変える」は、書体や大きさを変えるだけでも、けっこう効果的だと思います。なお、大西さんは1月13日放送のNHK「プロフェッショナル」に出演されました。見逃し配信はこちら(閲覧にはNHKの受信契約が必要です)。
「有害表現」リストが炎上 スタンフォード大がサイト閉鎖〈Forbes JAPAN(2023年1月10日)〉
masterが「奴隷主を想起させる」とか、white paperが「白=良いという価値観を示すことで、無意識の人種的偏見を助長する」といった指針リストが炎上、結局、サイトを閉鎖することになったとのこと。過剰なポリティカル・コレクトネスが「言葉狩り」のようになっている問題の、揺り戻しでしょうか。「キャンセルに使用されることへの懸念」というのは、以前、大原ケイさんに寄稿いただいた「キャンセル・カルチャー」問題のことだと思われます。
経済
戦国時代に突入した米デジタル広告市場〈日経ビジネス電子版(2023年1月10日)〉
Alphabet(Google)とMeta(Facebook)の2強だったアメリカ広告市場で、Amazon、TikTok、Microsoft、Appleなどが勢力を伸ばし、AlphabetとMetaの合計シェアが50%を割り込んだとのこと。「メタとグーグルの圧倒的シェアが打撃を受けた要因の一つは、アマゾンがデジタル広告の世界に手を広げてきたことにある」と巧妙な言い回しをしていますが、少なくともGoogleの広告売上は落ちてないはず。成長が鈍化しているのは確かですが。「リテールメディア」のような違う領域が急激に伸びたことで、全体のパイが増え、結果としてシェアが下がったことを「シェアが打撃」と表現するのは、ちょっと違うんじゃないかという気が。
というか、これは2023年予測にも書いたんですが、リテールメディアって広告費もらう代わりに「店のいい場所」を明け渡す形だから、そのうち本業の小売に影響が出てくると思うのですよね。ユーザーにとって有益な広告ならまだしも、邪魔な場合も多いわけですし。バーンズ&ノーブルが宣伝費(コアップ)をもらうのやめて復活したのと、真逆のことをやっているわけです。短期的には広告売上が伸びるとか、広告を出した商品が売れやすくなるという効果が出るでしょうけど、長期的には「ロングテール部分の売上が落ちる」という傾向になってしまうんじゃないかなあ、と。
デジタルコミックで北米市場を攻めるNTT西日本の勝算〈ニュースイッチ by 日刊工業新聞社(2023年1月10日)〉
今年の予想「輸出拡大」への動きがさっそく。NTT西日本というか、子会社NTTソルマーレの展開する「MangaPlaza」の話です。コンテンツ数を増やしたことで、「結果どうなった?」という続報に期待したいところです。
迫る物流2024年問題 その荷物、来春から届きますか?〈日本経済新聞(2023年1月11日)〉
トラックドライバーの時間外労働の上限が、2024年4月から罰則付きで年960時間に短縮されることが決まっています。多くの運送事業者がこの規制に対応できず、「最大4割が倒産・廃業」するという予測も出ているほど。それがいわゆる「物流2024年問題」です。
本件、2023年予想で具体的に触れるかどうか迷った(結局削った)んですが、いちおう念頭には入れたうえで「先に流通インフラが維持できなくなる」と書いています。要因を深掘りするより「じゃあどうすれば?」を重視した結果……って後から書いてもなあ。一言だけでも触れておけばよかった。反省。
ちなみに、この記事では触れられていませんが、物流問題のブレイクスルーは「自動運転トラック」の実用化と普及かな? と。調べてみたら、高速道路での後続車無人隊列走行は2021年時点で実証に成功していて、2022年度以降に商業化実現を目指す、という段階まで来ているんですよね。少なくとも長距離輸送は、そろそろ自動化できそう。
2022年のEC業界振り返り&2023年に起きそうなこと【ネッ担まとめ】 | ネットショップ担当者が 知っておくべきニュースのまとめ〈ネットショップ担当者フォーラム(2023年1月11日)〉
国内を中心としたEC業界の2022年回顧と2023年予想まとめ。キーワードは規制強化、原材料・物価高など。変化の激しい1年になりそう、とのこと。「出版物販売額の実態2022」によると、販売ルート別でインターネットは2割弱まで拡大(電子媒体除く)していますから、ECの動きも継続的にウォッチしておく必要があるでしょう。
【CES2023】Amazonが広告を席巻する日(玉井博久)〈AdverTimes.(アドタイ) by 宣伝会議(2023年1月13日)〉
アメリカで開催された「CES2023」のレポート。2023年予想で、Amazonについて「成長分野=広告に力が注がれるだろう」と書いたとおりの方向へ動いているようです。繰り返しますが、この動きはじわじわと本業に良くない影響を与えると思います。急な変化ではないから、気づきづらいとも思いますが。
技術
Kobo Web Reader has officially launched〈Good e-Reader(2023年1月14日)〉
Rakuten Koboでブラウザビューアが提供開始。ただ、ヘルプを確認したら“Note: Kobo Web Reader is not available to customers in Japan.”とのこと。日本向けには提供されないそうです。「おまくに(お前の国には売ってやらない)」か。記事を読む限りAmazon「Kindle Cloud Reader」より使い勝手が悪いと不評みたいですが。
Rakuten Koboはアプリも日本向けだけ別になっているみたいですし、専用端末内の機能も日本向けには提供されていないものがあるので、正直「またか」感があります。単純な開発リソースの問題ではない気も。まあ、Amazon「Kindle Cloud Reader」も日本向けは文字モノ非対応ですから、縦書き対応が難しいということかもしれませんが。
お知らせ
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
年を取ると時間が早く経つように感じると言いますが、私は昔から過集中なところがあり、熱中していて時間が経つのを忘れて、気づくと日がどっぷり暮れているなんて経験を繰り返しています。もっとも、昔は呼ばれても気づかないレベルで集中していて「無視された」なんて怒られることもあったくらいですが、最近はそうでもなくなった(と自分では思っている)のですが(鷹野)