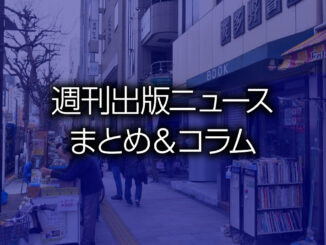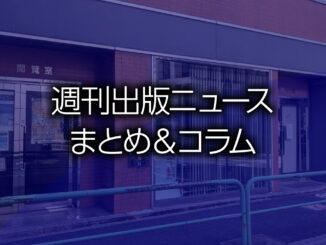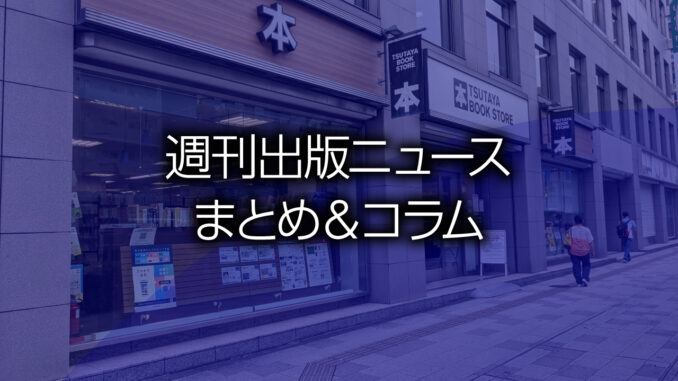
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2021年12月26日~2022年1月8日は「国際海賊版対策機構(IAPO)創設へ」「2年ぶりのコミケ開催」「書籍販売額15年ぶりプラスの見通し」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- ファストコンテンツって、悪いのか? ~「良い要約」と「悪い要約」を考えてみる~ 福井健策|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2021年12月27日)〉
- 国際海賊版対策機構(IAPO)4月創設へ 日米中韓ASEANなどが協力〈アニメーションビジネス・ジャーナル(2022年1月5日)〉
- 漫画村が消え、漫画BANKは閉鎖。海賊版対策は進んだ。だが、状況は悪化している | 海賊版サイトの現在地 前編〈コミックナタリー(2021年12月28日)〉
- 海賊版サイトを利用するのは、マンガ文化を破壊するテロリストに資金提供しているようなもの | 海賊版サイトの現在地 後編〈コミックナタリー(2021年12月29日)〉
- 一般社団法人ABJによる「NO MORE 漫画泥棒」告知活動のお知らせ〈株式会社メディアドゥ(2021年12月28日)〉
- 漫画海賊サイト、歯止め利かず 巣ごもり背景、アクセス26倍―「将来の傑作消える」作家怒り〈時事ドットコム(2021年12月30日)〉
- 海賊版、民間連携で抑止〈日本経済新聞(2022年1月1日)〉
- 「個人クリエーターも相談を」続く漫画の海賊版被害、文化庁がサポートへ〈SankeiBiz(サンケイビズ)(2022年1月2日)〉
- コロナ禍で膨張「違法漫画サイト」駆逐できぬ元凶 | ゲーム・エンタメ〈東洋経済オンライン(2022年1月7日)〉
- 「海賊版で読みました」無邪気なファン 「ネギま!」赤松健さんの怒りポイント〈時事ドットコム(2022年1月6日)〉
- 米・ニューヨーク州知事、出版社に「合理的な条件」下で図書館への電子書籍ライセンス提供を求める法案に拒否権を行使〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年1月4日)〉
- 社会
- 経済
- 技術
- イベント
- メルマガについて
- 雑記
政治
ファストコンテンツって、悪いのか? ~「良い要約」と「悪い要約」を考えてみる~ 福井健策|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2021年12月27日)〉
逮捕者も出た「ファスト映画」ではなく「本の図解要約」について。おなじみ福井健策さんが、軽妙な語り口で「良い要約」と「悪い要約」の境目について解説しています。「アイデア」は法律的に保護されないけど、法的に問題が無かったとしても「燃えやすい(批判されやすい)」のはどの辺りか? という観点がさすがです。「不快だ」「言い方が気に入らない」といった気持ちの問題は、一筋縄ではいきません。自分でも「倫理的にどうなの?」といった考え方はしますし。
国際海賊版対策機構(IAPO)4月創設へ 日米中韓ASEANなどが協力〈アニメーションビジネス・ジャーナル(2022年1月5日)〉
年末年始、特集的に海賊版サイトの問題を取り上げる記事や動きがたくさんありました。そんな中、いちばん私の目を惹いたのがこちらの国際海賊版対策機構(IAPO:International Anti-Piracy Organization)。日本政府やコンテンツ海外流通促進機構(CODA:Content Overseas Distribution Association)が進めてきた構想で、昨年9月に開催された東南アジア諸国連合知的財産権執行専門者ネットワーク(ANIEE:ASEAN’s Network of IPR Enforcement Experts)の会議で提唱、各国から賛同を得て発足することが決まったそうです。
改めて調べてみたところ、昨年4月の知的財産戦略本部構想委員会コンテンツ小委員会に「CODAの活動とご提案(支援要請)」という資料がありました。提案①が「国際海賊版対策機構(仮称)」の創設です。「インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表」しか目を通してなかった(載ってない)から、気づかなかったなあ……不覚。
IAPOの参加予定国は日本、アメリカ、韓国、中国、ASEAN各国など。著作権団体が中心のようですね。代表世話人はCODAが担当する予定とのこと。「国際連携・国際執行の強化」という方針に沿った、良い方向性の良い動きと思います。
その他の海賊版サイト問題関連記事は、私が把握しているだけで以下の通り。長期休暇でキッズや暇な人の目に触れる機会も多いでしょうから、効果的ではあるでしょう。文化庁が「個人クリエーターも相談を」とサポートへ乗り出し始めているというニュースも興味深い。
漫画村が消え、漫画BANKは閉鎖。海賊版対策は進んだ。だが、状況は悪化している | 海賊版サイトの現在地 前編〈コミックナタリー(2021年12月28日)〉
海賊版サイトを利用するのは、マンガ文化を破壊するテロリストに資金提供しているようなもの | 海賊版サイトの現在地 後編〈コミックナタリー(2021年12月29日)〉
一般社団法人ABJによる「NO MORE 漫画泥棒」告知活動のお知らせ〈株式会社メディアドゥ(2021年12月28日)〉
漫画海賊サイト、歯止め利かず 巣ごもり背景、アクセス26倍―「将来の傑作消える」作家怒り〈時事ドットコム(2021年12月30日)〉
海賊版、民間連携で抑止〈日本経済新聞(2022年1月1日)〉
「個人クリエーターも相談を」続く漫画の海賊版被害、文化庁がサポートへ〈SankeiBiz(サンケイビズ)(2022年1月2日)〉
コロナ禍で膨張「違法漫画サイト」駆逐できぬ元凶 | ゲーム・エンタメ〈東洋経済オンライン(2022年1月7日)〉
「海賊版で読みました」無邪気なファン 「ネギま!」赤松健さんの怒りポイント〈時事ドットコム(2022年1月6日)〉
若干ベクトルの違う観点のある記事が、この時事ドットコムの「赤松健さんの怒りポイント」。赤松さんのコメントには以下のように、ブロッキング導入への動きを改めて牽制する部分がありました。
いつか「政治家を批判するブログもブロッキングしよう」となってしまうことにもつながりかねず、ブロッキングを「漫画家の権利を守るため」と言って安易に導入することには強い違和感があります。
そう、そこなんですよ。熊本大の大日方信春教授が「海賊版サイト運営者と閲覧者の表現の自由を侵害するものとは考えられない」「サイト・ブロッキングのための法律に『合理的な期待』を守るための仕組みが規定されていれば、閲覧者の通信の秘密を侵害するとは言えない」という主張をしていますが、著作者側の懸念はそこじゃありません。
大日方教授の主張が間違っているとは思わないのですが、当時、ちばてつやさんや里中満智子さんや赤松健さんといった「海賊版ブロッキングによって権利が守られるはずの立場」の側から挙がった憂慮や懸念は、それでは解消できないのです。
児童性虐待記録物を刑法の緊急避難でブロッキングしたロジックが、海賊版対策へ転用されそうになった経緯を私は忘れていません(当時、反対声明を出しています)。それがさらに転用され、たとえば為政者にとって都合が悪い――でも真っ当な表現が、理不尽な言いがかりで規制されてしまうような未来まで一直線に繫がっているように思えて、怖いんです。
米・ニューヨーク州知事、出版社に「合理的な条件」下で図書館への電子書籍ライセンス提供を求める法案に拒否権を行使〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年1月4日)〉
Internet Archive、出版社に「合理的な条件」下で図書館への電子書籍ライセンス提供を求める米・メリーランド州の法律を支持すると発表〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年1月4日)〉
図書館への電子書籍ライセンス提供を「合理的な条件」で出版社に求める法案を巡る動向。支持を表明しているInternet Archiveは、「National Emergency Library」問題で出版社側と対峙する裁判の当事者でもあります。ポジションが明確でわかりやすい。
これまでの経緯は、カレントアウェアネス-Eに掲載された辻慎太郎さんの「ライセンスは誰のために:電子書籍をめぐる米国州法の動向」に詳しいです。図書館の電子資料費負担が重荷になってきている状況の是正や、図書館にライセンスを販売しない期間の設定を禁止する法案ですが、出版社側からは「合理的な条件」が定義されていないといった反発があるようです。うーむ、政治闘争。これぞ民主主義。
社会
「コミケ99」来場者数は11万人 コロナ禍で感染対策を徹底、100回目への試金石に〈KAI-YOU.net(2021年12月31日)〉
有料チケット制を導入して1日5万5000人に制限、ワクチン接種証明確認を必須とし、サークルスペースの間隔も広げるなど、感染対策を徹底して2年ぶりの開催となりました。Twitterでは不満の声も観測されましたが、さまざまな制約がある中「よくぞ開催までこぎつけた」と、まずは賛辞を送りたいです。
コミケ代表が語る、コロナ禍開催の経緯と決断「今回はこれが精一杯」〈KAI-YOU.net(2022年1月7日〉〉
代表の「今回はこれが精一杯」という言葉は、やるだけのことをやりきったという思いの裏返しではないでしょうか。
コミックマーケット99における新型コロナウイルス感染者の発生について(2022年1月6日)〈コミックマーケット公式サイト(2022年1月6日)〉
残念ながら、スタッフ2名に感染者が発生したという報告も出ていますが、すぐにこれだけの報告ができる体制ができているのは、むしろ「しっかりしているなあ」と感じさせられました。
LF23 図書館とデジタルメディア、融合の可能性 ~ データ戦略とデジタルアーカイブ~ 21.12.28〈図書館総合展 YouTubeチャンネル(2022年1月5日)〉
昨年11月に行われた図書館総合展のオンラインフォーラム映像が公開されました。登壇者は吉見俊哉さん(東京大学)、福井健策さん(弁護士)、山田太郎さん(参議院議員)、鮫島浩さん(ジャーナリスト)。司会は内田朋子さん。私はライブで視聴しましたが、図書館に限らず、デジタル政策、著作権、アーカイブ、メディアのゆくえなど、なかなか刺激的なフォーラムでした。
冒頭、福井さんが「私にとって図書館はメディアだったから」と、テーマそのものへの疑義でジャブを打ったのが印象的でした。山田議員も「いつまで経っても書庫を管理する館でいいのか」と爆弾投下。吉見さんは「デジタル化は都市と地方の教育格差を埋める」という話を展開したとき、公共図書館と大学図書館までしか話を広げなかったのが若干残念でした。大学進学率は半分程度なんですから、むしろ小中高の学校図書館のほうが地域格差是正には影響大きいと思うんですけどね。
図書館流通センター(TRC)、「図書館ピクトグラム」を公開:欧文印刷と共同開発〈カレントアウェアネス・ポータル(2022年1月6日)〉
公開されたピクトグラムにはCC0、パブリックドメインのマークが表記してあります。「個人、法人、商用、非商用問わず無料でご利用頂けます。申し込みも必要ありません。素材の加工、編集、改変等を自由に行えます。」とあります。太っ腹! 素晴らしい!
経済
Kウェブトゥーンが人気、年売上高が1兆ウォン突破で作家平均収入は5668万ウォン=韓国報道〈ワウコリア(2021年12月26日)〉
ちょっと「あれ?」と思った記事。平均5668万ウォンは約546万円です。少し前に、韓国「NAVER WEBTOON」で連載を持っている作家の全体平均年収は約3000万円(日本円換算)という記事がありました。範囲が異なるとはいえ、ずいぶん乖離があるような?
年収という言葉は一般的に、勤め人なら税金などが引かれる前の「総支給額」で、個人事業主なら「売上」です。ウェブトゥーンの制作はスタジオ型とのことですが、平均546万円や3000万円というのはスタッフに分配する前の額なのか、後の額なのか。分配前で546万円だと、かなり厳しいような気がするのですが。
「DLsite」のエイシスが漫画を対象とした提携電子書籍ストアでの販売支援サービスを開始〈MdN Design Interactive-(2021年12月27日)〉
同人誌電子版のディストリビューションサービスを開始。メイン提携が「コミックシーモア」「BookLive!」「DLsite comipo」で、その他提携ストアがAmazon「Kindleストア」「Renta!」「まんが王国」「Reader Store」「honto」「楽天Kobo」など。「メイン」と「その他」の違いはなんだろう……? 直接取引か否か?
書籍ことしの販売額 15年ぶりプラス見通し “巣ごもり”一因か | 新型コロナ 経済影響〈NHKニュース(2021年12月28日)〉
出版科学研究所「出版月報」12月号の記載。雑誌は3%強のマイナスですが、書籍は2%増に落ち着きそう、とのこと。年始に発表された日販の店頭売上前年比調査では、12月は全体で84.0%だったそうです。ただしこれは、2020年に『鬼滅の刃』最終巻の発売フィーバーでコミックが大幅に伸長した反動で、今年は62.6%と大幅減になっている影響が大きいです。書籍は95.9%なので、大きくズレることはなさそう? 詳細は1月25日の発表を待ちましょう。
浦沢直樹、電子版解禁!「YAWARA!」「20世紀少年」配信、「あさドラ!」新刊も(コメントあり)〈コミックナタリー(2021年12月28日)〉
ようやく解禁。コメントの1行目が「とはいえ、私はやはり紙の本が好きです。」というのが、これまで電子化を拒んできた浦沢さんの心情を率直に表しているように思います。YouTubeで浦沢さん本人が説明していますが、「見開き推奨!」というマークが表紙の次に表示されるようになっています。「この作品は、左右2ページを見開いた状態で読むことを想定し演出されています」と。なお、このマークは漫画家なら誰でも使えるフリー素材として考えているそうです。なるほど。
技術
デジタルの商品認証技術「NFT」 経産省が初の実証実験へ | IT・ネット〈NHKニュース(2021年12月27日)〉
記事2枚目の額縁裏面写真にロゴがあることから、経済産業省が委託しているのは「Startbahn Cert.」であることがわかります。「集英社マンガアートヘリテージ」で、ブロックチェーン連携販売証明書部分を提供しているスタートバーンです。
集英社との事業は物理メディアのみですが、「Startbahn Cert.」はもちろんデジタルにも対応しています。洋服の3Dデータということで、メタバース関連です。今回はファッション分野なので「出版」とは少し縁の遠い話ではありますが、無縁ではないし無関係でもいられないのでいちおうピックアップしておきました。
イベント
【年末特番】2021年の出版ニュースを振り返る ―― HON.jp News Casting / ゲスト:西田宗千佳(ITジャーナリスト)〈HON.jp(オンライン)/12月26日〉
12月26日の HON.jp News Casting は2時間の特番、ゲストはITジャーナリストの西田宗千佳さんでした。前半はこちらのアーカイブでどなたでもご覧いただけます。
後半の部を視聴したい方は、Peatixでチケットをお求めください。1月15日AM6時まで購入可能です。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
新年明けましておめでとうございます。2022年もHON.jpをよろしくお願いいたします。毎年恒例の振り返りは、毎年恒例と化した年内ギリギリ更新。そして年始の予想記事は、本稿執筆時点でもまだ終わっていません。まだ年が明けた気がしない!(鷹野)