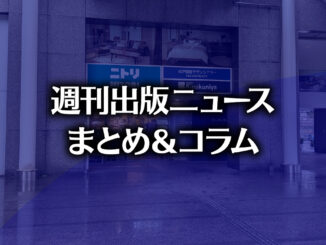《この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年4月15日に配信した第27回では、未管理著作物裁定制度について語っています。
【目次】
#27 自分の作品が勝手に利用される(かもしれない)制度
こんにちは、鷹野です。今回は「自分の作品が勝手に利用される(かもしれない)制度」をテーマにお話したいと思います。ちょっと刺激が強い言い回しですけど、そういう危惧をしている人もけっこういるようですし、実際そういうことも起こり得る制度だったりします。
その制度の名前は「未管理著作物裁定制度」と言います。これ、今週のメルマガ1週刊出版ニュースまとめ&コラム #661(2025年4月6日~12日)〈HON.jp News Blog(2025年4月14日)〉
https://hon.jp/news/1.0/0/55308#2025410を配信したら「番組で取り上げて欲しい」っていうお便りが届いたんですね。恐らく、文化庁が制度周知の広報資料2未管理著作物裁定制度〈文化庁(2025年4月10日公開)〉
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.htmlを公開したってのをメルマガで取り上げたからだと思います。文化庁告示案のパブコメ結果もほぼ同時に公開3「著作権法の一部を改正する法律に基づく文化庁告示案の概要」に関する パブリックコメント(意見公募手続)の結果について(PDF)〈文化庁著作権課(2025年4月8日)〉
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000291272されて、けっこう反発しているクリエイターの方が目につくんですね42026年度から始まる「未管理著作物裁定制度」、文化庁に批判が多数寄せられているが、どうも誤解されている気がする「著作権の理念に適う制度」〈Togetter [トゥギャッター](2025年4月11日)〉
https://togetter.com/li/2537221。
で、この「未管理著作物裁定制度」なんですけど……けっこう難しいんですよ。他のテーマをやったうえでお便りを紹介して、5分10分くらいで簡単にお話できるっていうような内容じゃないです。だから今回は、まるごとこの話題を扱うことにしました。
というわけで、まずそのいただいたお便りから紹介しましょう。モリアキさん、読み上げてください。
未管理著作物裁定制度ですが、「著作財産権」のことばかり問題にされますが、もっとも重要な観点は「著作者人格権」ではないでしょうか。書き手に所有権が所属する自然権ですが、これを文化庁が一時的なものであれ吸い上げてしまうということになります。「著作者人格権」の尊重が揺らぐ今、この制度は非常に危ういのではと感じます。
はい、モリアキさんありがとうございます。遠山さん、お便りありがとうございます。著作者人格権、大事ですね。著作権(財産権)と同じように著作者が作品を生み出した瞬間に自然発生する権利です。だけど、著作権のように売ったり譲ったりできないっていう権利なんですよね。著作者人格権。売ったり譲ったりできない権利のことを一身専属と言います。
この著作者人格権を「文化庁が一時的に吸い上げる」というのは、制度的にはちょっと正確じゃないですね。むしろ否定されます。否定されるんですけど「尊重されてないんじゃないか?」というニュアンスはわかります。反発してるクリエイターの方が、けっこう反発しているっていうのも、この「尊重されていない」感があるからだと思うんですね。
実は今回このポッドキャストを収録するのにあたって、いろいろ確認したいことがあったんで、文化庁に直接電話で取材しています。で、確認したうえで「ちょっとそれは不信感を増幅させちゃうんじゃないの?」と思ったんで、それは伝えておきました。そのへんはまたあとで説明しますね。
ポッドキャストをお聞きの方には、まずこの「未管理著作物裁定制度」がどんなものかの説明が必要でしょう。こちらは2023年、令和5年通常国会で成立した改正著作権法に基づく制度です。公布から3年以内の施行とされています。つまり、法律はもう成立しているんです。
成立しているけど、まだ施行されていない。そういう段階ですね。法律で決まってますから、行政機関がいまから勝手に「中止します」とかできないわけですよ。で、補償金を伴う制度なんですけど、その管理とか登録確認を行う機関というのがまだ決まってません5【追記】2025年10月21日付で指定補償金管理機関として公益社団法人著作権情報センターが指定された
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/94284502.html。昨年末に説明会とかやってますけど、まだ決まってません。
だからもちろん、運用ガイドラインみたいなのも、まだ公開されてません6【追記】2025年12月24日付で「裁定の手引き 概要版」が公開された
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94304601.html。ま、要するに、細かなことはまだわからない段階なんですよ。それが前提です。わからんことが多いと、そりゃまあ、いろいろ想像して不安になりますよね。無理はないと思います。
従来の裁定はなんのための制度なのか?
じゃあ、そもそもこの裁定制度って、なんのためにある制度なのか? これは、作品の権利者を探しても見つからないという孤児著作物、オーファン・ワークス(Orphan Works)の問題というのがまずあります。
作品の権利者、あるいは、ご遺族、相続人ですね。その権利を継承した人が見つからない作品がどうなってしまうか? というと、物理メディアがある場合は、中古での流通だけになりますよね。あるいは、違法な海賊版でしか流通しなくなってしまう、みたいな状態になるわけですよ。
具体例を言うと、漫画家の柴山薫さんという方がいらっしゃいます。代表作には、集英社「月刊少年ジャンプ」などで連載していた『爆骨少女ギリギリぷりん』などがあります。柴山薫さんはですね、2007年に急性心不全でお亡くなりになられてるんですね。
ご両親もすでに亡くなられていて、弟がどうやらいるらしいっていう噂はあるんですけど、その弟さんを見つけ出すことができない。権利継承者ですね。権利継承者が見つからないんで、柴山さんの作品は、古本か海賊版でしか読めない、そんな状態になってしまってました。
で、私自身がこの「孤児著作物」っていう問題を初めて知ったのが2013年、弁護士の福井健策さんが「そろそろ本気で『孤児作品』問題を考えよう」7【ネット著作権】 そろそろ本気で「孤児作品」問題を考えよう〈INTERNET Watch(2013年3月12日)〉
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/591351.htmlという記事をINTERNET Watchの連載で書かれたことがきっかけだったと記憶しています。
その2013年の時点で、世の中のあらゆる作品の50%以上が孤児著作物という試算がなされていたそうです。作品の権利者が見つからない孤児著作物、オーファン・ワークス。これ世界的に問題になってるんですね。
著作物の利用には許諾を得るというのが大原則です。利用といっても商品として売ることだけじゃないです。勝手にデジタル化できないとか、もちろんネット公開もできないとか、美術品だったら展示公開もできないとか。もういろんな形での利用というのができなくなっちゃうわけですね。これ、映像作品なんかだともっと深刻で、出演者全員の許諾が要るんですよ。だから、めちゃくちゃ大変なんです。
許諾を取りたくても、権利者が見つからない。物理メディアに記録された作品なら、そのメディアが経年劣化でもう読めなくなってしまう。すると、作品も一緒に世の中から消滅しちゃうんですよ。映画は、昔のフイルムの時代の映画は、そのフイルムの保存ってのがかなり問題になってます。経年劣化でフイルムがもうぐちゃぐちゃになっちゃう。
で、そういう作品を、権利者を探しても見つからない場合は、文化庁長官の裁定によって合法的に利用できるようにするというのが「著作権者不明等の場合の裁定制度」です8著作権者不明等の場合の裁定制度〈文化庁〉
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/1414110.html。
この裁定制度って、1970年、現行の著作権法が制定されたときから存在してます。すごい歴史ある制度なんですよ。著作権法第67条。便宜上、ここでは「従来の制度」と言いますね。この従来の制度、実はぜんっぜん使われてなかったんですよ。
権利者を一生懸命探して、一生懸命探したけど見つからなかったということを証明して、それを文化庁に認めてもらったうえで、補償金を払えば利用できる、そういう制度なんですけど、まあ、めちゃくちゃハードルが高かったんですよね。以前は、その裁定の申請がもう年に数回あるかないかレベルだったそうです。0回の年もある。
めちゃくちゃハードルが高いって評判が悪かったんで、だんだんハードルは下げられていきました。一生懸命探したという、その「相当な努力」というのの見直しとか、申請手数料が以前は1件1万3000円だったのが、いまは6900円に値下げされた、とか。それでようやくこの従来の裁定制度というのは、以前に比べたら、利用件数が増えてきたんですね。
[記事化時追記:柴山薫さんの事例を挙げたのは、裁定制度をより利用しやすい仕組みに改善するための実証事業が2016年に始まり、そこで柴山薫さんの作品が用いられることになったから9孤児著作物をより利活用しやすくするための大きな前進!権利者団体が実行委員会を結成し実証事業を開始〈見て歩く者 by 鷹野凌(2016年11月9日)〉
https://wildhawkfield.com/2016/11/demonstration-experiment-for-orphan-works-utilization.html。ただ、ポッドキャストの収録時に、そこまで入れると長すぎてしまうと思い省いてしまった。いま思うと触れておくべきだったので、追記しておく。]
まあ、それでもやっぱりまだ使い勝手が悪いって声はあります。これは6年くらい前に聞いた話10本当に使えるアーカイブに必要なことは? 権利者・実務者による活発な議論〈INTERNET Watch(2016年6月24日)〉
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/event/1006931.htmlですけど、たとえば「青空文庫」という非営利団体があります。基本は、著作権が切れてパブリックドメインになった作品をボランティアの方がテキスト化して、だれでも利用できるように公開するっていう活動をしている団体です。
2018年末に環太平洋パートナーシップ協定、CPTPPが発効しました。これによって、日本の著作権保護期間というのが著作者の死後50年間だったのが70年間に延長されました。そのため、2019年から2038年までは、新たなパブリックドメイン作品が発生しないという期間になったんですね。
もちろんそれでも、2018年までにパブリックドメインになった作品はパブリックドメインのままですし、青空文庫がテキスト化してない作品っていうのもたくさん残ってますから、それによって青空文庫の活動が止まっちゃう、ってことはないんですね11著作権保護期間が延長された世界でも、できることはたくさんある #著作権延長後〈HON.jp News Blog(2019年1月11日)〉
https://hon.jp/news/1.0/0/14964。
ないんですけど、せっかくの機会だから青空文庫でも裁定制度を試してみようという話になったそうなんですよ。明治時代に発表されたある短い作品、作者は恐らくもう亡くなってます。でも権利を相続した人がどこにいるのか、もうさっぱりわからない。
で、裁定制度を利用しようと。申請してみたら、補償金額が3万2400円と。これたぶん消費税8%のころですね。税別だと3万円だと思います。青空文庫は非営利のボランティア活動なんですよね。この作品1つのために、3万円が持ち出しになってしまう。これは、さすがに厳しいと。
そのうえ「裁定されたサイト内での閲覧に限られる」という制限があるそうなんですよ。つまり、裁定制度を使って、青空文庫のウェブサイトで作品を公開したとしても、青空文庫のサイトで閲覧はできるけど、もしその作品を二次利用したいと思ったら、利用したい人が改めて裁定制度に申請する必要があるんですよ。利用したい人が。
まあ、だから「いつでもどこでも誰でも自由に本が読める」ようにするっていう青空文庫のコンセプトからすると、ちょっと外れちゃうんですよね。なかなか難しいところです。
従来の裁定はどんな感じで使われているのか?
じゃあこの裁定制度、どんな感じで使われているか。従来の制度のほうですよ。従来の裁定制度のほうは、文化庁のサイトにある「裁定実績データベース」というページで公開されています。全部公開されてます。
直近、令和6年、2024年のデータを見ると、裁定された著作物の数は1127点ありました。点数はそこそこ多いですね。著作物の種類だと、言語が682点、地図が268点、美術が98点と続いてます。利用者・申請者は39件。けっこう少ないですね。著作物の数は1127点あるのに比べると、けっこう少ない。
これは、申請手数料6900円が申請1回あたりで必要なんですよね。1点ずつバラバラと申請するとえらいお金かかっちゃうんで、まとめて申請したほうが楽なんですよ。楽というか得ですね。だから、利用者・申請者は少ないけど、点数は多いという形になるのかなと。
利用者・申請者は、申請した著作物の点数が多い順に言ってくと、岐阜県図書館が1番でした。続いて、世界思想社教学社。その次が、エデュケーショナルネットワーク、増進会ホールディングス・Z会グループの企業ですね。その次がベネッセコーポレーション。次が長野県。サントリーホールディングス、光文社などなど。
(申請内容は)岐阜県図書館は古い地図を大量に申請してますね。世界思想社教学社とエデュケーショナルネットワークとベネッセコーポレーションは、いずれも入試の過去問題です。参考書を作るためでしょうね。サントリーホールディングスは、昔の広告で使っていたイラストが大半です。長野県は、長野県飯田創造館というところが所蔵してる作品集にある美術作品が申請されてる感じです。
光文社の事例が面白い。これは洋書ですね。アシェットが発行してるモーリス・ルブラン「アルセーヌ・ルパンシリーズ」の、日本語名で言うと「三十棺桶島」だと思います。挿絵を一通り裁定申請してる感じです。
モーリス・ルブランのほうは、もうパブリックドメインです。けど、挿絵のモーリス・トゥーサンという方が、調べてみたら1974年に92歳で亡くなっているんですね。長生きされたので、現時点でもまだ著作権が存続してるんです。死後70年ですから。だから、当時の挿絵で復刊しようとしてるのかなと。当時の挿絵で復刊しようと思うと、権利相続者の許諾が当然必要なんですよね。まだ著作権存続してますから。
子孫、どれくらいいるんでしょうね。孫、曾孫、玄孫くらいまでいる可能性ありますね。全員に許諾とらなきゃいけないんですよ。全員ですよ。何十人いるんだろう。ヘタすると数百人レベルになるんじゃないですか。孫とか、曾孫、玄孫まで入れたら。まあ、普通に考えると、それ全部許諾取るの難しいですよ。だから裁定制度を使ったということだと思います。
従来の裁定ではどんなトラブルが起きたか?
じゃあ、この裁定制度、従来の制度のほうですね。裁定制度を使ったうえでのトラブルはあるのか。これ実はですね、一昨年、KADOKAWAから「電子書籍版・小説『ダークエルフ物語』シリーズ全作品の一時配信停止のご報告とお詫び」というプレスリリースが出てるんですね12電子書籍版・小説『ダークエルフ物語』シリーズの全作品の一時配信停止のご報告とお詫び〈KADOKAWA(2023年4月24日)
https://www.kadokawa.co.jp/topics/9731/。
『ダークエルフ物語』は翻訳小説なんですけど、翻訳者の権利者が見つからなかった。で、裁定制度を使ったと。復刊、販売、配信してたんですけど、裁定を受けるときに「販売数の上限」というのがあるんですね。気づいたらそれを超えちゃってたそうなんですよ。
まあ、それだけじゃなくて、裁定申請中の著作物の利用に係る複製物であることとか裁定を申請した年月日っていうのを(販売・配信する作品内に)記載しなきゃいけないんですけど、その記載が抜けてたと。ちょっと規定に外れたことをやらかしちゃってたみたいなんですけど。
まあ、記載が抜けてたのはアカンですね。アカンって話なんですけど、「販売数の上限」のほうはね、これ、電子書籍は難しいですよ。紙の本みたいに何部刷ったみたいな話ならわかりやすいんですけど、電子書籍って在庫数って概念ないですからね。
電子書籍は一カ所で売ってるわけではなくて、いろんな電子書店に配信するわけですよ。すると、合計どれだけ売れたって数字って、集計しないとわからないんですよね。だからって、販売部数をコントロールするとかって、あんまり現実的じゃない。
まあ、デジタルでもNFTを使って販売数限定みたいな手法もあるにはあるんですけど、まだぜんぜんメジャーじゃないんですよね。メジャーじゃないから、販売機会を損ねちゃう可能性があります。難しいですよ、これは。
それで、さっきお話した文化庁に確認した件ってなんだったのか? というと、この従来の裁定制度のほうです。裁定を受ける利用者側向けのガイドはあるんですね。実際に裁定を受けた事例を紹介する「裁定実績データベース」もあります。
でも、たとえば、いままで集めた補償金はいくらプールされてるの? わからないんですよ。裁定を受けたあとに権利者が見つかった場合にどういうフローになるの? わからないんですよ。裁定を受けたあとに権利者が見つかった件数は? わからないんですよ。(文化庁の人は)たぶん数件とか言ってましたけど、たぶんってなんですか? っていう話ですよね。
あと、実際にその(あと)出てきた権利者に支払った補償金っていくらなんですか? わからないんですよ。もちろん記録は残ってると思いますよ。記録は残ってるんでしょうけど、それがちゃんと統計的に分かる形で公表されてない。公表されてないんですよ。これ文化庁に確認しました。公開してないそうです。
それって制度的に透明性が低いって思われてもしかたないですよねって。新制度ができるっていうタイミングなのに、それじゃあ不信感を増幅させちゃうんじゃないですか? っていう。ちょっと説教になってしまいました。文化庁の方にそれはしっかり伝えております。
新制度「未管理著作物裁定制度」はどうやって成立した?
で、ここまでお話してきたのは従来の裁定制度ですね。今回のポッドキャストの始めに紹介した「未管理著作物裁定制度」は、2023年、令和5年通常国会で成立した改正著作権法に基づく制度だと、最初に言いました。新制度です。
従来の裁定制度はそのまま残ります。「未管理著作物裁定制度」と何回も言うの面倒なんで、ここからは「新制度」と言いますね。この新制度は、新たに設けられた著作権法第67条の3に基づく制度なんです。
だから、新制度が施行されたら、裁定制度は2つになるんですよ。ここがややこしくて、(いま)ChatGPTとかGeminiとかPerplexityみたいな生成AIで調べるとですね、従来の制度と新制度が混ざって回答してくるんですね。
「違いを説明して」って出てきた答えのソースを確認したらですね、従来制度のところで新制度の解説記事が参照されてたりするんですよ。「は? ほんとかよ?」っていちいちソース確認しないと、怖くて使えないですね。だから今回のポッドキャスト、下準備にえらい手間どりました。生成AI、まだうまく使えてないですね、私。ま、それはどうでもいいんですけど。
この新制度は、文部科学大臣および文化庁長官の諮問に応じて設置された、文化審議会著作権分科会の基本政策小委員会というところで審議されてきました。諮問というのは、有識者なんかに意見を求めるって意味です。で、有識者で組織された委員会なんかで議論した結果、その報告書が答申っていうやつです。
今回の新制度の場合、「デジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度・政策の在り方について」というのが文部科学大臣から諮問されました。諮問されたのが2021年の7月。中間まとめがその年の12月には出て、でも答申、最終報告書は2023年2月までかかってます。で、そのときの通常国会で審議されて、改正法案がそのとき可決した、という流れですね。
つまり、2年がかりなんですよ。2年がかりで、大勢の有識者、委員の方が討議して、大勢のいろんな関係者に何度もヒアリングして、パブコメもやって、というプロセスをちゃんと経たうえで成立してるんですよね。この新制度。特定の誰かひとりが勝手に作った制度じゃないんですよ。なんかね、SNSを見てると特定の誰かを、誰か1人を悪者にしようとするような声も見かけるんですけど、そんな簡単な話じゃないですよ。
ただね、これね、私もこういう政治的な動きって興味あるんで、文化審議会著作権分科会のなんちゃら委員会ってそれなりにチェックしてます。それなりにチェックしてるつもりなんですけど、すごーく興味ある場合は傍聴までしてます。傍聴までしてるんですけど、ぜんぶの動きを追いかけるのは正直難しいです。めちゃくちゃいろんなところでいろんなことが話し合われてるんですよ。
著作権法は文化庁管轄ですけど、その方向性(を決めているの)って内閣府なんですよね。内閣府の知的財産戦略本部ってところが決めてます。知的財産戦略本部が「知的財産推進計画」ってのを毎年まとめてるんですね。それに基づいて文化庁が、著作権法どういうふうな感じにしていきましょうかというのを、委員会なんかを設置するわけです。
その「知的財産推進計画」が経済振興なんかに絡んでくると、それは経済産業省の管轄になるわけです。そっちでも別の討議が行われる。情報通信系に関わってくると、総務省の管轄になります。教育とか図書館関係だと文部科学省です。条約が絡んでくる、海外が絡む話だと外務省、みたいな。めちゃめちゃいろんなところでいろんなこと話し合われてるんですよ。
で、個々の、個別の審議会とか委員会レベルでも、毎回毎回めちゃくちゃたくさんの資料が出てくるんですよ。それぜんぶ読んで理解して是非を判断してって、興味を持って追いかけてる私みたいな人間でも難しいです。はっきり言って、難しいです。
ましてや、ふだんはそういうところと直接関わりのない方、あるいは、ニュースをいつも追いかけてるわけではない方が、ちょっと理解不足になってしまうってのは、むしろ当然のことだと思うんですね。
文部科学大臣はなぜ新制度を諮問をした?
で、新制度に話を戻します。文部科学大臣がなぜ「デジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度・政策の在り方」というのを諮問したかというと、デジタル化が進む以前の著作物というのは、まあ、おおむね「産業」だったわけです。
出版社とかテレビ局とかレコード会社みたいな。そういうところが世に送り出す「産業」だったわけなんですね。そういう出版社とかテレビ局とかレコード会社みたいに著作物を産業で扱っているところというのは、まあ、もちろん分野にもよるんですけど、著作物を集中管理する仕組みというのがあるんですね。
わりと整ってる分野もあります。有名なところだとJASRACですね。JASRACは悪名もとどろいてますけど、著作物を集中管理して権利者に収益を分配するという意味においては、すっごい重要な役割を果たしている組織なんですよ。
ところが、インターネットが普及しました。だれもが自分の作品を、不特定多数に向けて発表できるようになりました。そういうふうになったここ20年くらいのあいだに、集中管理されてない、要は個人クリエイターの作品、それも膨大な作品がインターネット上で公開されてきたわけです。
なかには消えてしまった作品もたくさんあります。サイトがサービス終了しちゃったとかね。ま、クリエイター自身が消したっていうのももちろんあるでしょうけど。いろんなサービスが終わっちゃって、もう二度と見ることができない作品もいっぱいあります。
そういう集中管理されていない著作物の利用というのが円滑に行われるようになると、クリエイターへの対価還元もスムーズになる。対価還元によって、また新たな創作機会を生み出す。そういう良い循環というのを生み出したい。そうやって文化の振興を図りたい。ということが、審議会のまとめなんかを読むと、そういうことが書いてあります。
要は、従来の裁定制度は、著作権なんかを集中管理してる事業者で対応できるけど、そこからこぼれちゃうところを新しい制度で補おうと。というのが今回話題になってるこの「未管理著作物裁定制度」なんです。
従来の制度と新制度の共通点は?
もう30分ぐらい話してますけど、もうちょっと続きます。ここからは、従来の制度と新制度の共通点。まず共通点。次に違い。このへんの深掘りをしましょう。でもまあ、まだ細かな運用が決まってないところも多いんで、あくまで現時点でわかる共通点、現時点でわかる違いです。
まず共通点。従来の制度も新制度もどっちも、著作物を利用しようと思ったら補償金が要ります。お金かかります。つまり、どっちの制度も有償でもちゃんと手続きをして合法的に利用したいというニーズに応える制度なんですね。これが今回の最大のポイントです。重要なところです。
だって、そもそも無断で勝手に利用しようとするような輩なんて、わざわざ裁定制度なんか使わないですよ。裁定制度を使うにはお金かかるわけですから。わざわざそんな手続きしないですよ。しなくても無断で転載されてる海賊版とかゴロゴロしてるわけじゃないですか。
新制度に反対してる方が「ウォーターマークを消されてしまう」とか「無断転載されてフリー素材化される」みたいな心配をしてらしゃってるんですけど、それはね、もう裁定制度以前の問題です。裁定制度と関係なく、問題です。
サインを消したら氏名表示権の侵害ですよ。ウォーターマークを消したりトリミングしたりしたら、同一性保持権の侵害ですよ。どっちも著作者人格権の侵害になるわけです。でもそういう違法行為って、裁定制度の有無とかぜんぜん関係なく行われてますよね。
だから裁定制度はむしろ、ちゃんとクリエイターに収益還元をしたい、でも連絡がつかない、そういう場合に、ちゃんと手続きをして補償金を払えば合法的に利用できる、そういう制度なんです。
ちなみにこれは従来の裁定制度のQ&Aにも書いてあるんですけど、「裁定を受けたとしても、著作者人格権等を侵害する行為が認められるわけではないので御注意ください」って書いてあるんですよ。Q&Aに。
最初に紹介したお便りの、著作者人格権を「文化庁が一時的に吸い上げる」っていうのは、制度的には正確じゃありませんと言ったのは、これが理由なんですね。著作者人格権を侵害する行為が認められるわけではない。
で、これ法的な原則って従来の制度も新制度も同じですから、(新制度で)裁定を受けたとしても著作者人格権を侵害する行為は認められるわけではありません。それをまず、利用する側がしっかり認識しておく必要はあるでしょうね。
まあ、裁定制度はちゃんと手続きをして合法的な利用をする、そのための制度ですから、著作者人格権もしっかり尊重されるとは思います。少なくともね、非合法な海賊版みたいなのよりは、尊重されると思いますよ。
で、有償です。有償だから、裁定制度の対象になる、対象にしたい作品は、利用することによってなんらかの利益を生み出しそうな作品に、限定されちゃいますよね。さっき非営利団体の青空文庫が裁定制度を試した話をしましたけど、利益を生まない利用は補償金が重たいんですね。だから、非営利だと使いたくても使えない、という感じになってしまいます。
だから、さっきチラッと紹介した従来の裁定制度を利用してるところも、恐らく文化振興で予算化されてる県とか市町村みたいな自治体とか、映像アーカイブを後世に残すために頑張ってるNHKとか、あとは、出版社による復刊とか、過去問題集みたいなのとか、そういうのが中心なんですよね。
じゃあ、新裁定制度だとどのくらいのレベルまで利用されるんだろう。これね、補償金がどれくらいになるか次第ですね。従来の裁定制度は、文化庁が補償金額シミュレーターってのを公開してます13著作権者不明等の場合の裁定補償金額シミュレーションシステム〈文化庁〉
https://www.bunka.go.jp/saiteisimulation/。試しにやってみました。
イラストをグッズ化するという想定で、美術(絵画)で、グッズ作成、売価を1個500円として、1万個作成するというシミュレーションをしてみました。補償金は55万円になりました。売価合計額の1割といったところですね。
つまり、少なくとも1100個売れないと、補償金だけでも元がとれない――まあこれは1万個が多すぎるって話かもしれませんけど。そういう収支の計算をしたうえで「あ、これならいけそうだな」って作品じゃないと、わざわざ裁定制度で利用するってことには、なりづらいわけですよ。
まあ、いまの話は従来の裁定制度のシミュレーションですけど、新制度だとどうなるでしょうね。同じくらいの補償金額なのか、もっと下がるのか。そのへんは正直、制度の詳細が決まらないとわからないです。とはいえ、従来の制度も新制度も、著作物を利用しようと思ったら補償金が要る。これはもう共通点ですね。
従来の制度と新制度の違いは?
次に、従来の制度と新制度の違いについて。従来の制度は、裁定で利用する期間ってのを、申請する側が決めるんですよ。決めるんですけど、上限ないんですね。期間の上限はない。だから5年でも10年でも申請できるんです。
ところが新制度は、最大で3年間という上限があります。だから、無限に使われるってことは絶対ないわけですね。そのうえ、新制度は、裁定を受けて利用を始めたあとに、権利者が裁定取り消しや利用停止を申請できるんですよ。
これ、従来の制度は、裁定を受けたら、もしそのあと裁定期間内に権利者が現れたとしても、裁定期間が終わるまではそのまま合法的に利用を継続できるんですね。公開されてる資料でそのへんのことが明示されていないんですけど。
明示されていないんで、わからなかったんで、文化庁に確認したんですけど。(従来の制度は)権利者が名乗り出ても期間満了までは利用できる。従来の裁定制度はそういうものだ、ということが確認できました。
ただ、裁定を受けても著作者人格権は残ってますから、もし権利者の意に沿わないような利用をされてたら、裁定取り消しってなる可能性はありますね。だから、ウォーターマークを消したりトリミングしたりなんて、著作者人格権を侵害するような真似をしたら、従来の制度でも危ないんですよ。
で、これが新制度だと、3年以内の裁定を受けた期間の中でも、権利者が申し出たら、取り消し・利用停止できちゃうんですよ。これね、利用する側からすると、ちゃぶ台ひっくり返されたみたいな話ですよ。地雷踏んじゃったみたいな。制度上はもうそうなってるからしょうがないんですけどね。
だから、ウォーターマークを消したりトリミングしたりなんてことがなくても、著作者人格権関係なくても、権利者が「利用するな」って言えば終わるんですよ、新制度については。終わっちゃうんですよ。
新制度の対象となる著作物は?
あと、新制度の対象になる著作物、これは「集中管理されていない」ことが前提です。集中管理ってなにかっていうと、さっき例にあげたJASRACとかです。文化庁に「著作権等管理事業者」として登録する制度というのがあるんです。その登録されてる団体がいま28事業者あります14著作権等管理事業者の登録状況〈文化庁〉
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kanrijigyoho/toroku_jokyo/。
出版、本に絡むところですと、日本文藝家協会、日本漫画家協会、日本複製権センター、学術著作権協会、教科書著作権協会、日本出版著作権協会、出版物貸与権管理センター、出版者著作権管理機構あたりと、あと写真とか美術の著作物に関係する団体も絡んでくるでしょうね。まあ、いろんな団体が登録されてますけど、そこで集中管理されてる著作物は、新制度の対象外です。新制度の対象にはならないです。
そのうえで新制度だと、その著作物の周辺に「利用ルールが明示されていない」かつ「問い合わせ先がない」かつ「連絡先もない」そういう場合は対象です。あるいは「利用ルールが明示されていない」かつ「問い合わせ先がない」かつ「連絡先はあるんだけど、問い合わせても14日間返事がない」そういうのは新制度の対象です。
この「連絡先に問い合わせて14日間返事がない」これがわりとポイントで、権利者の意思が確認できなかった場合でも利用可能になるんですね。もちろんすぐ利用可能になるわけじゃなくて、裁定の申請をして通ったら、補償金を払って、それから利用できるというわけですけど。
でもここが、嫌がってる方々の「嫌ポイント」のひとつになってるみたいですね。だから「問い合わせを無視していると勝手に利用されちゃう」みたいな。「無視してるのは返事をしたくない、嫌がってるわけだから、そういう場合は使えない制度にしくださいよ」みたいな。
ええ、まあ、気持ちはわかります。でもね、無視しちゃダメですよ。嫌なら「嫌です」って返事を、意思表示をすればいいんですよ。(返事は)「検討中」でもいいみたいですね。14日間以内に「検討中」みたいな意思表示になる。
どういう形でも利用されたくないなら、もう事前に利用ルールを明示しておけばいいんです。利用ルールが明示されてないから使われちゃう可能性があるわけで。利用ルール、たとえば「無断利用禁止」とか書いておけば、裁定制度をちゃんと使おうってところはそれで引き下がりますよ。「無断利用禁止」って書いててもウォーターマークを消すみたいなやんちゃなことする輩は、わざわざ金のかかる裁定制度なんか使わないですよ。
で、もしその連絡が来てることに気づかなくて、裁定制度で使われちゃったってことにあとから気づいた。それが嫌だったとしたら、すぐ裁定取り消しとか利用停止を申請すればいいんですよ。裁定制度を使うようなところは真面目ですから、ほとんどの場合、それで解決すると思うんですね。取り消せる制度ですから。
だからこれ正直言うと、利用する側の立場で考えたら、新制度を使うのは怖いですよ。さっき言ったように、従来の裁定制度なら少なくとも裁定を受けた期間内は利用が保証されるんです。でも、新制度だと、嫌だと言われたらすぐ利用するのやめなきゃいけないんですよ。
そうやって裁定受けたあとに利用が止められるってどういうことかっていうと、まだ細かな運用ルールが決まってないから細かいところはもちろんわからないですけど、恐らく補償金ですから、返ってこないと思うんですよ。すぐ止められちゃったとしても。
物理メディアだと、在庫は破棄しなきゃいけないですよ。大損ですよ。もし新制度を利用するとしても、そういうリスクがあることを考慮しなきゃいけないわけですね。そりゃ慎重になりますよ。下手なことできないですよ。
まとめ
そろそろまとめに入ります。まとめると、そもそも著作権法の目的って「文化の発展に寄与」することなんですよね。「文化の発展に寄与」するためにある法律です。だからそのためには、「権利の保護」と「公正な利用」のバランスが必要なんです。あまりに権利が強いと利用が阻害されちゃいます。逆に、あまりに自由な利用ができてしまうと、こんどは権利が阻害されちゃう。
だから、こういう新しい制度を用意するときって、そのバランスをどう取るか? というのを、有識者の方々が長い時間かけて討議したりとか、影響を受けそうな関係者にヒアリングしたりして、それで初めて新しい制度ができるわけなんですね。
誰かが強引に新しい制度を作ろうとしても、そういう討議の段階で反対する人がいれば、バランスをとろうと調整が入りますよ。討議で意見が真っ二つに割れちゃって「報告書がまとめられませんでした」っていう答申が出たこともありますよ。海賊版対策で、違法ダウンロードの範囲を拡大するときがそれでした。いっかいそれで白紙に戻ってますからね。
今回の場合、制度を準備するプロセスの段階では、そこまで反対する人はいなかったわけです。ちなみに、4月8日に公開されたパブコメの結果というのは、法律がもう成立した段階の話なんですよね。成立した前提で、それに基づく「文化庁告示案の概要」に対するパブコメなんですよ。
だから、やることが決まっていて、利用の可否についての権利者の意思をどうやって確認するかみたいな、細かな運用の話の段階に入ってるんです。細かな運用を決めていく段階の話になってるので「パブコメが無視された」みたいな声も若干見かけたんですけど、この段階で「新制度をやめろ」みたいな、そういうちゃぶ台返しは、まあ、そりゃ無理ですよ。無理です。法律はもう決まっちゃってますから。
あとは、細かな運用の中で、法律の範囲内で、どれだけ、ちょっとでも自分に有利な形にできるか、とか。あるいは、ちょっとでも骨抜きにできるか、とか。そういう細かなところで攻防をする段階ですね。いまは。施行前ですから。
仏像を作るとき最後に目を入れる開眼の儀式ってのを行うんですけど、それをしないと「仏作って眼を入れず」とか「仏作って魂入れず」とか言われるわけです。制度はほとんどできてるけど、まだ完成はしていないわけです。
交渉は最後の最後まで諦めるなといいます。もしこれを聞いてる方が新制度に反対だったら、「どうやったら骨抜きにできるか?」みたいな方向で考えて行動するのが建設的じゃないかな、と私は思います。もし反対ならね。反対なら「どうやったら骨抜きにできるか?」そう考えた方がいいでしょう。
というわけで「自分の作品が勝手に利用される(かもしれない)制度」って今回タイトルに入れましたけど、むしろ「自分の作品が勝手に利用されるかもしれないけど利用停止もできちゃう制度」と言ったほうがいいかもしれません。そういう「未管理著作物裁定制度」について取り上げました。