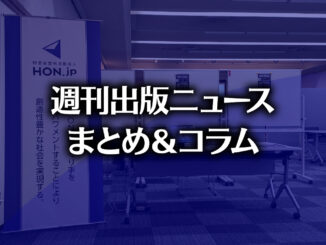《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年2月18日に配信した第19回では、「週刊ダイヤモンド」2月17日発売号の書店販売中止と、トムソン・ロイターがAIスタートアップ企業に勝訴したニュースについて語っています。
#19 雑誌の発売中止/AIと著作権
こんにちは、鷹野です。今回は「雑誌の発売中止」と「AIと著作権」、この2つのトピックスについてお話したいと思います。まず「雑誌の発売中止」から。雑誌の休刊、ではなく、発売中止という怖い話です。モリアキさん、どんな事件があったか簡単に説明してください。
はい、モリアキさんありがとうございます。いやー、怖いっ! 背筋が寒くなりました。
私も昔、週刊情報誌を制作していた
私も、ずいぶん昔の話になりますが、週刊誌を制作していた経験があります。私が20代の後半くらいのことなので、いまから20年から25年くらい前の話です。週刊誌といっても毎回ゼロから制作するようなものではなくて、情報誌なので、新規在庫が入荷したら情報を入れ替えるみたいな。そういう感じなんで、前の号からの流用も多かったんですよね。だから、そんなめちゃくちゃハードな感じではなかったんですけど。
私が入社したころは月2回刊だったんです。まだ。あいだが2週間とか3週間あくと、在庫の入れ替えってけっこう多くなるんですよ。だから、月2回刊のころのがキツかった記憶があります。で、途中から週刊化してたんですけど、週刊化してからのがラクになったんですよね。
だから、毎回ゼロから制作している週刊誌のスケジュールの厳しさっていうのは、私自身、体感したことがありません。まあ、そうとうキツイだろうなという想像はできますけどね。思い返すと私自身、価格を間違えるとか、電話番号を間違えるとか、写真がテレコ、つまり、入れ違いをしちゃったとか……そういうミスはちょくちょくありました。
まあ、人間のやることですからね。必ずミスはあります。そうやってミスが出たら、お客さんのところへ菓子折持ってすっ飛んでいって平謝りとか、ありました。なかなか許してもらえなくて、「こいつを担当から外せ」みたいなことを言われたりとか、「いま書店で売ってるやつぜんぶ回収してこい!」とかね、そういう無理難題言われたりとか……まあ、いまだから笑って話せますけど、いろいろありました。
ただ、さすがにね、発売中止は経験ないです。台風が直撃してスケジュールがヤバイみたいなことはありましたけど。週刊でも、ある程度はバッファがあるんですよ。私がやってたころで、半日くらいは余裕がありました。
(私が関わっていた)最後のころは、発売日が水曜日で、その前の週の金曜日の正午がデータ入稿の締切で、その日のウチに色校まで終わらせる、みたいなスケジュールでした。確か。でも台風が直撃したとき、色校を土曜日の午前中までズラしたことがあったんですよ。それでも火曜日には事務所に見本誌が届いてましたから、印刷会社さんすげーって感心してた記憶があります。
私が制作してたころはまだFAXが全盛期で、原稿がFAXで届く。原稿チェックして現地取材したら、FAXを借りて原稿入稿して、事務所に戻ったらもうゲラが出ていて、ゲラをチェックしたらFAXで校正バックして、パソコンで写真をセットして、校正バックと写真セットが終わったページはもう翌日くらいに色校が出て、みたいな流れ作業になってました。
最初のころ、私の最初のころ、月2回刊のころというのは、色校はみんなで集まって一斉に見るっていう感じだったんですけど、週刊化するときページ単位で随時チェックするってやり方に変わったんです。正確には色校というか、最終版面に近い状態がレーザープリンターで出力されるという、色校モドキに変わったんですけどね。
完成誌面と刷り上がりイメージがちょっと違うんで、「こんなの色校じゃねえよ」って文句言ってた人がいたのを覚えてます。写真がとくに荒いんですよね。なんで、心配なところは色校を見つつ、パソコンの画面で自分がセットした写真を確認するみたいな、そんなこともやっていたことを思い出します。
まあ、随時チェックって要するに工程が一部前倒しされるわけなんで、作業負荷が分散されるんですよね。ずいぶんラクになった記憶があります。月2回刊のころって、日付が変わる前に帰れるほうが珍しかったんですよ。それが週刊化以降は、日付が変わる前に帰れるようになった、というね。それくらいの変化ですけど。まあ、ブラック職場だったのは間違いないです。そんな思い出です。
発売中止でどれくらい損害が出たか?
で、今回の「週刊ダイヤモンド」の話に戻ると、定期購読はもう発送しちゃったあとだったみたいなんですね。なので、発売中止になるのは書店売りだけという。そういうタイミングだったそうです。月曜日発売だと、いまはいつが校了日になるんでしょうね? 水曜日の夜くらい?
定期購読って、宛名ラベル貼りとか袋詰めとか、そういう工程があるはずですから、機械で自動化されてたとしても、ダンボール詰めそのままより、そのまま発送するより時間がかかるはずですからね。定期購読だと書店発売日より1日早く着くみたいなのもありますから、校了はもうちょっと早いかもしれないですね。まあ、週刊制作の現場を離れてもう長いので、最近の状況は正直よくわかりません。
で、気になるのは、発売中止でどれくらい損害が出るか? というところですね。SNSで「ダイヤモンドヤバいんじゃ?」みたいな声も見かけましたけど、実際のところはどうなのか。まあ、ちょっと簡単に試算してみましょう。
実は「週刊ダイヤモンド」は昨年10月に、「サブスク雑誌」として大幅リニューアルしますというリリースを出しています。サブスク雑誌ってなんぞや? と思ったら、要は書店売りをやめる。それで、定期購読とデジタル版だけになる、という話だったんですね。それが2025年4月からと予告されてたので、実はもう直前に迫ってたっていう、そういうタイミングで起きた事故です。
で、書店売りはどれくらいあったか? というと、年明け早々に下山進さんがAERAに連載している記事に数字が出てたんですが、有料デジタル購読者が約4万3000、紙の定期購読が約3万2000、紙の書店売りは約1万7000部とのことでした。
発売中止なのは書店売りだけなので、1万7000ですね。それ掛ける定価が税込780円で、だいたい約1320万円くらい。その売上が、ダイヤモンド社と、取次と書店から失われるということです。週刊誌の正味ってどれくらいなんだろ? 委託なら普通は77%とか78%でしょうか? だとすると、ダイヤモンド社の売上としては約1000万円くらい。
それとは別に、破棄コストもかかりますし、広告主に損害賠償って話になるかもしれません。とはいえ、ダイヤモンド社の年間売上って、ホームページに載ってましたけど、2024年3月期で148億円あります。148億円。なんで、1000万円失ったところで、さすがにこれ一発で会社が傾くってことはないと思います。雑誌だけじゃないですからね。書籍もあります。
書籍売りがあるんで、書店から「週刊ダイヤモンド」が撤退しても、大きな問題にはならないみたいな、そんな声もありました。あと、デジタルの購読料もありますし。もちろん1000万円プラスアルファの売上は消えちゃう。痛いはずです。ちょっとしたチェック漏れでこういう事態になってしまう。怖いなあ、って思います。
―― この続きは ――
《残り約4000文字》