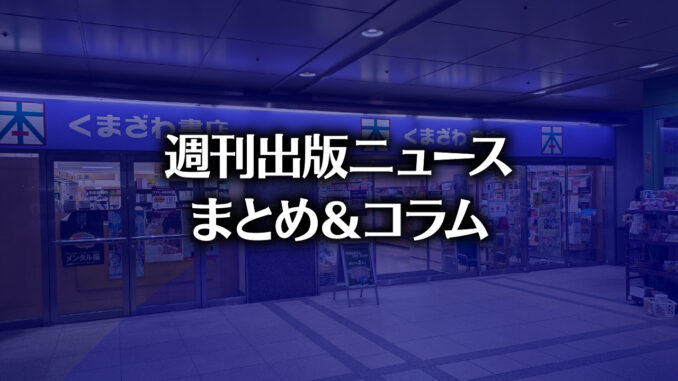
《この記事を読むのに必要な時間は約 12 分です(1分600字計算)》
2025年4月6日~12日は「再販契約書ヒナ型変更に物議」「人は本を読まなくなってきたのか?」「トランプ政権が関税で朝令暮改」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
お知らせ
HON.jp Podcasting「#26 パブリッシャーとプラットフォーマー(2025年4月8日版)」を配信しました
なぜ「出版社」と言わず「パブリッシャー」と呼んでいるのか? という話から。要するに、自前でコンテンツを制作・配信しているところが「パブリッシャー」だから、出版社だけではなく、新聞・テレビ局・ウェブメディアなども含まれる、という意図で使い分けをしています。
じゃあ、Yahoo!ニュース エキスパートはどうなんだろう? けっこう表現に口を出してくると聞くけど……とか考え出すとややこしい。Yahoo!ニュースとしては、ほんとうは「プラットフォーマー」として振る舞いたいはず。つまり、記事の内容には責任を負わないことにしたいのだけど、苦情は自社へ飛んでくるから、対応せざるを得ない、みたいな感じなのかな、と。
この番組ではみなさまからのお便りをお待ちしています。「こんなトピックスを取り上げて欲しい」とか「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。こちらのページでフォームから送付できます。
政治
Books Escape New Tariffs, At Least for Now(少なくとも今のところ、書籍は新たな関税を免れる)〈Publishers Weekly(2025年4月7日)〉
米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)がそのまま維持されているので、「準拠」と見なされる商品(書籍や紙など)に新たな関税は課されないということのようです。先週の時点では「もし書籍の輸入が免税だったとしても、原材料のチップや紙は関税の対象でしょうから、むしろアメリカ国内では製造していられない状況になるかもしれません」と危惧していたのですが、カナダ産の紙はUSMCAで対象外になるそうです。なるほど。
しかし、トランプ政権が朝令暮改で関税適用を90日間延期したり、スマートフォンなど電子機器を除外すると言い出したりと、わけがわからない状態になっています。だからこの記事も「少なくとも今のところ」と留保しておかなければならないのでしょう。ふつうに考えたら、部品など材料には高関税を課したまま完成品だけ適用除外したら、国内で組み立てるのは不利になりますよね。だけど、それに気づいたら、またすぐ変わりそう。振り回される方々が気の毒だ。
未管理著作物裁定制度について〈文化庁(2025年4月10日)〉
新裁定制度の広報資料が公開されました。「勝手に使われちゃうの?」などと気にしていた方が多かった点について、FAQも載っています。ちゃんと目を通すべし。
石破首相 映画やアニメなどの海外展開に向け支援策強化へ|映画〈NHK(2025年4月10日)〉
「石破総理大臣からは『サポートはするがコンテンツの内容には口を出さない』という話があり
そんなの本来は「当たり前」の話なんですけど、なんか妙に関心してしまいました。どうも以前はこれが「当たり前」じゃなかったような気がしていて。
社会
「人が本を読まなくなってきた現状」を前に、足すくむ編集者〈GotandaYoshiko(2025年4月6日)〉
ちょっといろいろ反論したくなってしまうエッセイ。まずその「人が本を読まなくなってきた現状」に疑いがあります。文化庁の令和5年度「国語に関する世論調査」では、不読率60%超という過去最悪の数値が公表されたのは確かです。しかし、文化庁は「調査方法の変更のため、令和元(2019)年度以前の調査結果は参考値となり、比較には注意が必要。」とも書いているのですよね。ほとんどのメディアがそれを無視して比較し、危機感を煽っています。もし以前と同じ調査方法だったら、変化はなかったかもしれませんよ。ちなみにこの調査の読書率に、電子書籍は含まれるけど、雑誌や漫画は含まれません。
でも、出版市場推計は縮小しているではないか、と言われるかもしれません。でもそれは「取次ルート経由で“売れてない”」ことは意味しても、“読まれていない”とは限りません。古書市場や図書館利用を無視してませんか? また、出版社の会議で出てくる意見だけで「活字離れは年配者にも広がっている」と判断していいのですか? それは、団塊世代が後期高齢者になり老眼で本が読めなくなったことを意味しているだけなのでは? などなど。
いま、物理的な本を売る価値〈WirelessWire News(2025年4月9日)〉
これまで“生成AIすごい”と煽りまくり続けてきた清水亮氏が、急にシェア本棚とか同人誌の話題を始めています。ここへ来てアナログ回帰ですか。まあ、それはべつに良いのですが、以下の箇所にはさすがにちょっとびっくりしました。
いま、紙の本を正規ルートで出版すると、それは全てAIの学習材料にされてしまう。Kindleで出すなんてもってのほかだ。
えっと、それはつまり「Amazonはすでに書籍データをAI学習用に使っている」という前提に立ってらっしゃる? まあ、「そう思っておいたほうが安全」とは言えるかもしれませんが、いまのところまだ明確にはなっていないはず。いつでも使える状態にあるのは確かですけど、もし使っていたとしら、購入済み書籍の一部シリーズだけ要約が生成できるなんていうまどろっこしい真似をしますかね?
第6回:本屋と「表現の自由」(岩下結)〈マガジン9(2025年4月9日)〉
「書店はメディアである」から、書店自身にも「表現する自由」はあるはず、という話。これはおっしゃるとおり。福嶋聡氏の「言論のアリーナ」論は、ジュンク堂書店のような超大型店じゃないと成立するのは難しいと思います。ふつうの中小規模店は、どんな本を並べるか? を自らの意志においてしっかり考え選択すべきでしょう。なにを仕入れるか、なにを仕入れないかは、わざわざ「表現の」と付けるまでもなく、自由であるはずです。
経済
Apple Pages Can No Longer Publish E-books to Apple Books(アップル・ページズはアップル・ブックスに電子書籍を公開できなくなりました)〈Good e-Reader(2025年4月6日)〉
PagesからApple Booksにブックを直接公開できなくなったとのこと。ただし、Apple Books対応フォーマットで書き出したのちパブリッシングポータルを使えば公開できるそうです。私の元にもiTunes Connectから「変更しました」というお知らせが事後的に届いていました。予告はなかったと思いますが、たぶんそれが問題になることもない程度しか利用されていなかったんでしょうね。
AI学習に対価、noteが文章投稿者に最高40万円を還元〈日本経済新聞(2025年4月8日)〉
投稿記事をAIの学習用として用いる場合に、クリエイターへ対価還元する道筋を用意する動きです。素晴らしい。記事末尾に「noteには日本経済新聞社が出資している」と情報開示されているのも素晴らしい。ただ、この動きと直接絡むのは恐らく、今年1月にnoteがGoogleと資本業務提携したことにあるでしょう。もっとも、Googleだけが対象というわけではないことを示すためか、プレスリリースにGoogleの名前はありませんが。
再販契約書ひな型、第六条2項「官公庁等の入札に応じて〜」を削除へ〈新文化オンライン(2025年4月10日)〉
こちらのニュース、周囲の業界人がかなりザワザワしていて、今後どうなるかが気になっています。再販売価格維持契約書(取次-小売)ヒナ型の第6条2項とは、「官公庁等の入札に応じて納入する場合」は適用除外になるという条項です。昨年末、本件が話題になったときには「そもそもこの条項が設けられた理由が知りたい」と思ったのですが、それはすぐ「WTOの政府調達協定の規定を批准しているから」だと知ることができました。
次に思ったのが「なぜこの条項を削りたいのか?」です。それは昨年の記事に「官公庁等の入札に応じた本の納品は価格維持の適用外であり、多くの書店が値引きを求められている」からだとありました。しかし、この条項を削ることで、ほんとうに値引き要求は回避できるのでしょうか?
あえて名前は挙げませんが、周囲でこの動きに反対している方によると、独占禁止法第23条4項の「著作物再販売価格維持行為」は、5項で組合・農協・生協などが対象事業者から除外されているので、その抜け道を残したまま契約書ヒナ型のこの条項を削っても意味がない、ということのようです。
独占禁止法は強行法規なので、契約より法律が優先されます。仮に官公庁等の入札に応じて組合・農協・生協などが納入(再販売)する場合、メーカーは価格拘束できません。値引き販売できてしまいます。なるほど確かに、これは大きな抜け道だ。
つまり、もし再販契約書ヒナ型の「官公庁等の入札に応じて納入する場合」が削除されたら、その契約に同意した書店は値引きできなくなるので、組合・農協・生協などが官公庁等の入札に応じたら勝てなくなるわけです。
これはすなわち、新再販契約書に同意した書店は「もう官公庁等の入札は応じません」と意思表明をするのも同然、自縄自縛です。もしそれが目的なら、単に入札に応じなければいいだけの話なので、わざわざヒナ型の条項を削る必要はないでしょう。なにか別の狙いがあるはず。
どうもこれは、図書館流通センター(TRC)を入札から排除するのが狙いではないか? という声も目にしました。しかし、契約締結には双方の合意が必要です。排除されるのがわかっていて、新再販契約書をまき直すことはしないでしょう。
また、仮に書店に対し不利になるような契約を取次が強制したら、こんどは優越的地位の濫用で独占禁止法違反になりそうです。あとそもそも、この条項を削ってしまうと、今後は「WTOの政府調達協定の規定」を守らないことになるわけですが、それは大丈夫なんでしょうか?
技術
AI製のジブリ風画像、「作風」保護の議論再燃 世界で流行〈日本経済新聞(2025年4月11日)〉
著作権法でなぜ「作風」が保護されないか? というと、端的に言えば、権利が強くなりすぎて利用を阻害し、文化の発展に寄与しなくなるから。だからもし規制するとしたら、人間による作風の模倣には影響が出ないようにする必要があるでしょう。それはもはや著作権法の領域ではなく、テクノロジーそのものを規制するような話になるのかもしれません。
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』12月1日より各ネット書店にて好評販売中です。1月からKindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時に開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」から16点の本が新たに誕生しました。全体のお題は「3」、地域テーマは東京が「デラシネ」、新潟が「阿賀北の歴史」、沖縄が「AI」です。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
今年もまた、大学の非常勤講師を続けています。春学期は演習が2つ。デジタル出版の演習授業で昨年は40人履修というハードモードを食らいましたが、今年は30人程度に落ち着きそうです。とはいえ、以前は10人前後でしたから、飛躍的に負荷が増えているのは間違いありません。負荷軽減のため、少し内容に変更を加える予定です。定員は教室の座席数によって決まり、それ以下の人数制限はできないと教務に断られてしまったので、致し方ありません。(鷹野)



















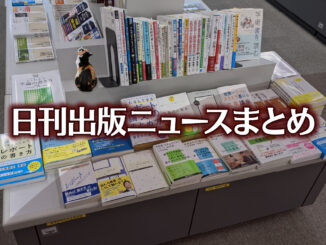

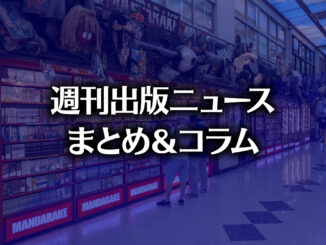
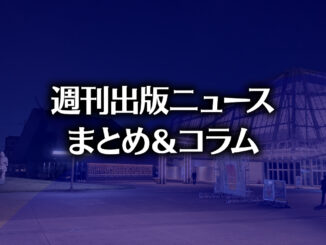
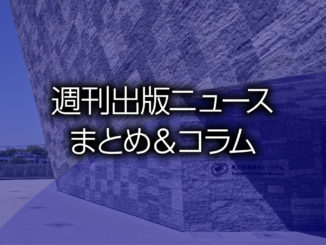
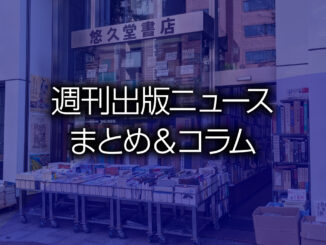
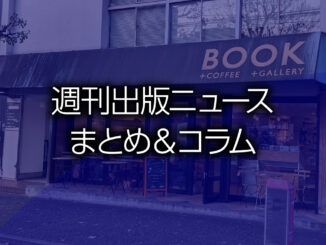
再販契約書の変更の件で、抜け穴として組合・農協・生協などが対象事業者から除外されているとのご指摘ですが、公立図書館では、バーコードや請求ラベルなどの装備を含めて契約している自治体が大半ですので、農協・生協などは入札に応じない(応じられない)のが現状です。(この装備を切り離してほしいという書店からの別の要望もあるのですが)組合は、地域の書店が組合を作れば可能だと思いますが、書店はそもそも値引きをしないことを要望していますので、組合をつくって入札には応じないのでは。
コメントありがとうございます。ご指摘通り、図書館への納入には「装備」という要素もありますよね。触れるかどうか迷ったのですが、省いてしまいました。経産省の書店ヒアリングの中で、むしろ装備で値引きが行われているみたいな声もあったように記憶しています。
現状では農協・生協などが入札に応じられないとしても、もし新規契約獲得のチャンスがあるなら装備対応できるような体制を新たに整える可能性もあるように思いますが、いかがでしょう?