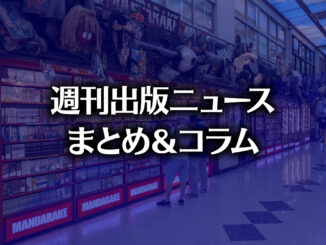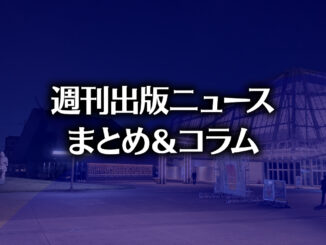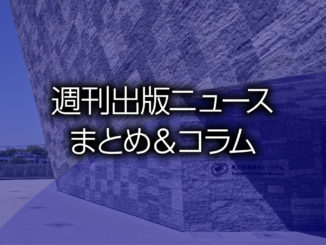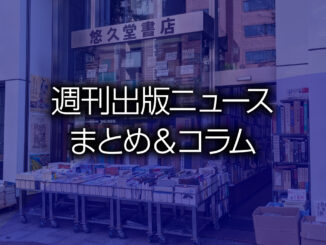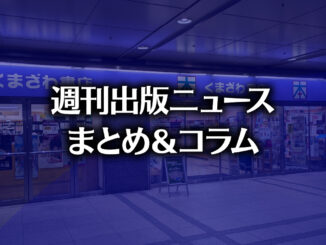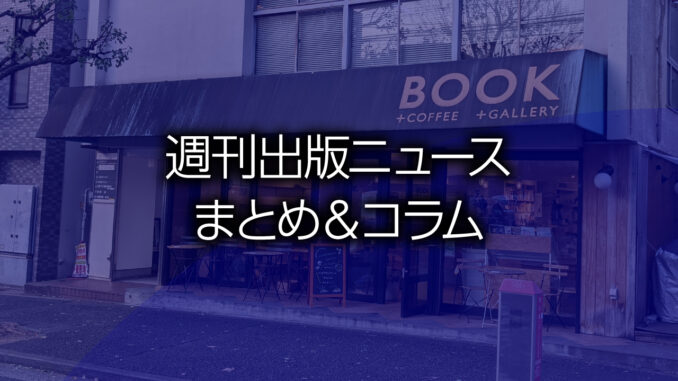
《この記事を読むのに必要な時間は約 11 分です(1分600字計算)》
2022年3月6日~12日は「町長発言で図書館資料が閲覧不可に」「まんが図書館で“有害図書”を除外」「アマゾンで書籍の値引販促計画」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- なぜいま「韓国のマンガ」が日本で人気なのか…日韓マンガ業界の第一人者が語るウェブトゥーンへの誤解と最新事情(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2022年3月7日)〉
- 限界を迎える広告代理店ビジネス──業界タブーに切り込み「デジタルシフト事業」に挑むデジタルHDの狙い〈MarkeZine(マーケジン)(2022年3月8日)〉
- 減り続けるまちの本屋さんに新風 各地に広がるシェア型書店とは〈毎日新聞(2022年3月10日)〉
- アマゾン 紙書籍で最大50%値引き販促を計画 出版社がポイント還元率設定〈文化通信デジタル(2022年3月11日)〉
- 丸善CHI、電子書籍伸び純利益4%増 22年1月期〈日本経済新聞(2022年3月11日)〉
- 持続可能な書店のビジネスモデルとは?那須ブックセンターの挑戦で見えたもの〈ほんのひきだし(2022年3月12日)〉
- 技術
- イベント
- お知らせ
- メルマガについて
- 雑記
政治
海賊版対策、相談窓口設置へ 文化庁、中小・個人を支援〈共同通信(2022年3月6日)〉
文化審議会著作権分科会の国際小委員会で話し合われていた、来年度設置予定の海賊版相談窓口について。「ベトナム系」など海外に拠点があるとみられる海賊版サイトに対し、中小企業や個人クリエイターが削除要請や法的措置を行うのはハードルが高いということで、弁護士など専門家から無料で助言をもらえる窓口となります。今夏ごろ設置予定とのことです。
「反論満載のうそ本」町長の発言きっかけ、町図書館で閲覧不可に〈朝日新聞デジタル(2022年3月9日)〉
岐阜県御嵩町の行政について扱った本が著者から寄贈され、図書館では蔵書として扱う予定だったのに、首長の町議会での発言をきっかけに閲覧不能対応となった事件。図書館の資料収集・提供の自由に対する侵害です。町議会で「検閲にあたるのでは」と質問され、ここの記述が誤っていると答弁したとのこと。閲覧不能にされていたら、それが正しいか誤っているか、検証すらできませんよね。検閲はダメ。読売新聞でも報じられており、隠そうとしたらかえって目立ってしまった「ストライサンド効果」が起きています。図書館関連なので[社会]と迷いましたが、首長が関わる表現規制ということで、[政治]でピックアップ。
「暴力」除外もゴルゴOK 宝達志水のまんが図書館 「有害図書」明確基準なく|文化|石川のニュース〈北國新聞(2022年3月11日)〉
こちらは逆に、町議会の一般質問で「差別的な本や過度な描写がある本を制限すべき」という指摘があり、「有害図書」を選別することにしたとのこと。青少年健全育成条例に基づく有害指定ですらなく、あいまいな独自判断による選別を行っているようです。この記事からは「陳列しないが閉架で蔵書はする」のか「蔵書もせず破棄」なのかは不明です。ただ単に記事を投稿しただけのウチのアカウントに対し、引用RT含め反発の声がたくさん届いています。こちらも議会が関わる表現規制ということで、[政治]でピックアップ。
「暴力」除外もゴルゴOK 宝達志水のまんが図書館 「有害図書」明確基準なく|文化|石川のニュース|北國新聞https://t.co/W2NeiIMrqd
— HON.jp News Blog (@HONjpNewsBlog) March 10, 2022
社会
表現と伝達のプロセスは、デジタル化とネットワーク化によって激変した〈HON.jp News Blog(2022年3月9日)〉
第1章完、これが1回目の講義内容にあたります。実際の授業でここまで細かく話はできませんが、「デジタル」や「出版」といった言葉の定義や、「パブリック」の意味について改めて考えるきっかけになったらいいなあ、と思っています。次から第2章へ突入しますが、原稿のストックが乏しいため1回お休みする予定です。ご了承ください。
経済
なぜいま「韓国のマンガ」が日本で人気なのか…日韓マンガ業界の第一人者が語るウェブトゥーンへの誤解と最新事情(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2022年3月7日)〉
「マンガ王国」日本に迫る「韓国産マンガ表現」の熱風…『俺レベ』制作会社日本支社長が語る日韓マンガ最新事情(飯田 一史)〈マネー現代 | 講談社(2022年3月7日)〉
知人の名前が出てきてびっくり。イ・ヒョンソクさん、『俺レベ』に関わっていたんですね。飯田一史さんによるインタビューです。韓国でスタジオ制作が増えたのは、市場が広がった結果そういう投資もできるようになったからであり、「ウェブトゥーンの基盤になっているのはNAVERwebtoonのような誰でも自由に投稿できる場所」などの発言は、結構重要な指摘という気がします。
ただ、日本はいまマンガ市場が非常に儲かっていますし、裾野も広いですから、いきなりスタジオ制作の段階からチャレンジすることが可能な環境でもある、とも言えるでしょう。三木一馬さんがおっしゃっていた、レッドオーシャン化によって作品の多様性が生まれるというのは、たくさんのトライアンドエラーが行われるということでもあり。環境や文化の違いもありますから、やってみないと分からないことも多いと思います。
限界を迎える広告代理店ビジネス──業界タブーに切り込み「デジタルシフト事業」に挑むデジタルHDの狙い〈MarkeZine(マーケジン)(2022年3月8日)〉
ネット広告専業代理店として業界2位のオプトホールディングが、デジタルホールディングスと名前を変え、主事業を「デジタルシフト事業」に変えていっている経緯についてのインタビュー。広告代理店のビジネスモデルはもう限界なので、広告主のビジネスそのものをデジタルシフトするお手伝いをしたい、と。
コンテンツのデジタル化、業務プロセスのデジタル化、ビジネスモデルのデジタル化、という3段階はわかりやすい。でも、DXの先にあるIX(産業変革)を目指そうというビジョンに対し「まだ1合目にも行っていない」という言葉が出るのは、いろいろ苦労しているんだろうなあ、という感じがします。
減り続けるまちの本屋さんに新風 各地に広がるシェア型書店とは〈毎日新聞(2022年3月10日)〉
本棚から溢れた愛蔵書、神保町の“棚主”になって新たな命を吹き込もう 誰でも本屋になれる共同書店〈PASSAGE〉の企て〈JBpress (ジェイビープレス)(2022年3月11日)〉
異なるメディアでほぼ同時に「シェア型書店」の記事。JBpressは神保町の「PASSAGE」のみで、毎日新聞は逆に「PASSAGE」がなく、福岡、吉祥寺、山口などの事例を紹介しているので、偶然タイミングが重なったものと思われます。本棚の一角を販売用に貸し出すという、コンパクトな場貸しのビジネスモデルです。先駆けである吉祥寺「ブックマンション」を、2019年7月にオープンした当時に取材した記事を見つけましたので合わせて紹介しておきます。
アマゾン 紙書籍で最大50%値引き販促を計画 出版社がポイント還元率設定〈文化通信デジタル(2022年3月11日)〉
アマゾンが絡む話なのに意外と話題になっていませんが、業界関係者以外には背景含め意味がわかりづらいかも。メーカーが小売店に対し定価販売を強制する行為は独占禁止法で禁止されていますが、書籍や雑誌は例外的に定価販売が認められています。それが通称「再販制度」です。そのため、書店は勝手な値引き販売ができません。しかしこのプログラムは、アマゾンが勝手に値引きするわけではなく、あくまで出版社側の任意で行う販促値引きであり、アマゾンが負担するのは1%だけという点がポイントです。
例外的に定価販売が認められているとはいえ、公正取引委員会は競争政策の観点から廃止したい意向があります。しかし、いきなり廃止というのは影響が大きいため、業界団体に対し「弾力的な運用」で非再版商品の発行・流通を拡大したり、各種割引制度を導入することなどを求めています。詳細は2001年の公正取引委員会「著作物再販制度の取扱いについて(PDF)」をご参照ください。つまり本件は、20年以上前から続いている、ある意味「撤退戦」的な問題が背景にあるのです。
その「再販制度の弾力運用」という姿勢を見せる目的もあって、2003年から年2回、多くの出版社が参加する期間限定の「謝恩価格本フェア」が行われています(45%割引での販売)。これがいまは「楽天ブックス」だけを通した販売なのです(以前は「ブックサービス」で行われていましたが、楽天が買収、吸収合併されました)。アマゾンの今回の動きは、これに対抗したものではないかと思われます。
公正取引委員会から求められている「弾力的な運用」を思うと断りづらいし、アマゾンとの直接取引も増えてますから、これを期に「いつでも販促策として大幅なポイント還元を行えるツール」を手にしておきたいと考える出版社も少なくないかも? という気もします。ただ、もちろんリアル書店側が黙っちゃいないとは思いますが。
丸善CHI、電子書籍伸び純利益4%増 22年1月期〈日本経済新聞(2022年3月11日)〉
丸善CHIホールディングスの「文教市場販売事業」セグメント「利益」が急伸。決算短信を参照してみたら、同セグメントの主要な会社名には丸善雄松堂と図書館流通センターが挙げられていました。つまり、機関向け電子書籍貸出サービス「Maruzen eBook Library」と、公共図書館向け電子書籍貸出サービス「TRC-DL」が、この好業績に寄与しています。素晴らしい。ただ、新型コロナ対策の地方創生臨時交付金による特需もあったと思うので、次期以降が正念場となるでしょう。
持続可能な書店のビジネスモデルとは?那須ブックセンターの挑戦で見えたもの〈ほんのひきだし(2022年3月12日)〉
書店空白地域が増えている中、その空白を埋めるにはどういうビジネスモデルが可能かを模索し、うまくいかなかった事例をインタビューの形で記録に残してくれました。畑村洋太郎さんの提唱する「失敗学」や、日経ビジネスの「敗軍の将、兵を語る」シリーズを想起させられます。失敗から学べることは多いです。よい記事と思います。
技術
【NeosVR】7万冊以上の蔵書が収められた図書館ワールドが登場 ページをめくって読書できる〈Mogura VR(2022年3月10日)〉
パブリックドメインの作品を利用したヴァーチャル図書館の試み。面白いチャレンジと思いますが、スクリーンショットを見る限り行間が狭すぎるのと、禁則処理を行っていない点が気になりました……。
イベント
【特番】出版DX これでいいのか、電子書籍市場 ―― HON.jp News Casting / ゲスト:落合早苗(O2Obook.biz 代表取締役社長)〈HON.jp(オンライン)/3月27日〉
3月27日は2時間の特番! O2O Book Biz株式会社 代表取締役 落合早苗さんをゲストに迎え、コミックが4割超を占めるようになった出版市場のこの四半期の動向を中心に話を伺います。
お知らせ
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
日課の早朝散歩をしていると汗だくになるほど、穏やかで暖かい気温になってきました。梅や桜があちこちで咲いていて、日本は平和だなと感じます。戦争反対!(鷹野)