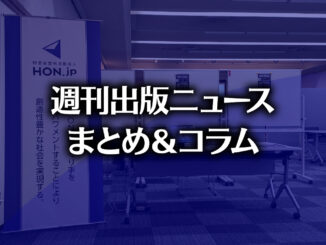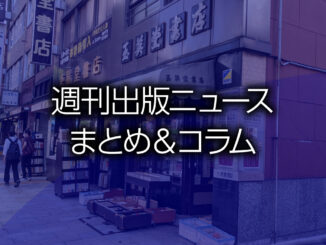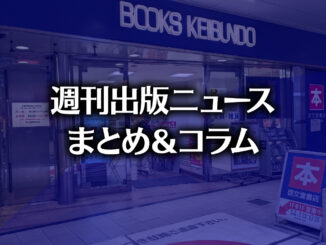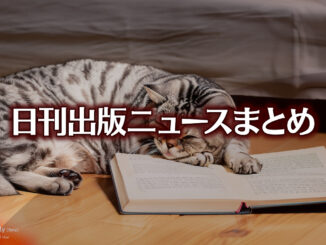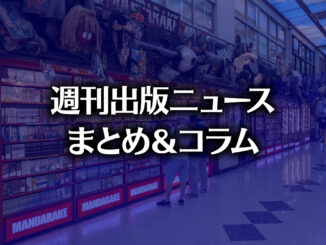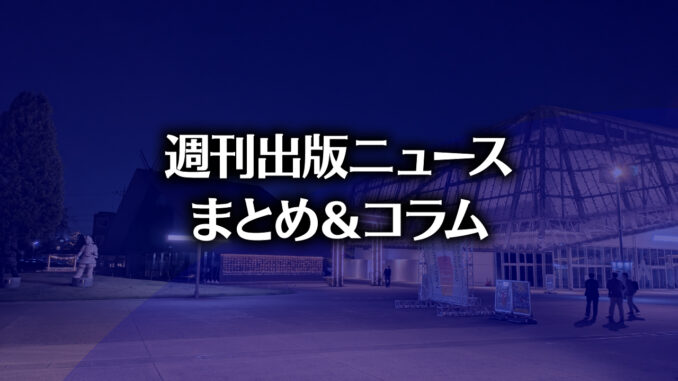
《この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です(1分600字計算)》
2025年7月6日~12日は「秀和システム承継企業確定」「米国AI著作権法論議の記録帳」「Cloudflare、AIボットのクロール状況を可視化」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- お知らせ
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- お知らせ
- 雑記
お知らせ
HON.jp Podcasting「#38 AIと米地裁判決/CDNがAIボットをブロック(2025年7月8日版)」を配信しました
前半は Anthropic と Meta への判決と、日本との違いなどについて。後半は Cloudflare によるAIクローラーのブロックについて。前後半繋がっている話です。
この番組ではみなさまからのお便りをお待ちしています。番組の感想や「こんなトピックスを取り上げて欲しい」「最近こんなことが気になっているが、どう思うか?」「こんな本が面白かった」など、本に関わることならなんでも構いません。こちらのページから気軽にお送りください。
東京・札幌・沖縄で作家・編集者・デザイナーが3日間集まり“本”を創り上げていくパブリッシングイベント「NovelJam 2025」開催!
今年もやります! 10月11日から13日の開催です。ただいま参加者募集中! 詳細は上記リンク先の開催概要をご確認ください。クラウドファンディング、法人協賛も募集しています。
政治
村上春樹の小説が「禁書」に? もし日本が「国連サイバー犯罪条約」参加したら…慎重な検討が必要なワケ〈東京新聞デジタル(2025年7月8日)〉
先週、うぐいすリボン主催の「国連サイバー犯罪条約と『表現の自由』問題 勉強会(出版関係者向け)」を取り上げましたが、大手メディアも反応し始めました。残念ながら東京新聞は契約していないため、ペイウォールの向こう側は読めていませんが。
動きはじめた米国AI著作権判決と、 控えめにいって大騒動な米国AI著作権法論議の記録帳 福井健策|コラム〈骨董通り法律事務所 For the Arts(2025年7月11日)〉
現時点での米国AI著作権法論議が、控えめにいってめちゃくちゃわかりやすくまとまっています。流石すぎる。ちなみにこの「市場希釈化」理論は日本でもすでに問題提起されていて、昨年3月に文化庁が公開した「AIと著作権に関する考え方について(PDF)」にも盛り込まれていますました(p23 イの3丸)。
実は、ここにそれが盛り込まれることになった立役者は、なにを隠そうこのコラムを書いている福井健策氏であります。そしてその件については、ポッドキャスト「#38 AIと米地裁判決/CDNがAIボットをブロック (2025年7月8日版)」で触れたばかりでした。実にタイムリー。
その詳細は、文化審議会著作権分科会法制度小委員会(第6回)の議事録を参照してみてください。見え消し版のp20 イの3丸「アイデアが類似する作品が大量に生成されることでクリエーターの市場圧迫が考えられるが、」以降の議論です。
福井氏に続く上野達弘氏の意見と、さらに応答する福井氏の「上野委員とこういう議論ができること自体が非常にぜいたくな話だなあと思うわけですけれども」あたりの話が、傍聴している立場としても「こんなすごい議論をタダで聞けるなんて!」と興奮させられたのを思い出しました。
当時、この議論を踏まえて脚注で補うのかと思ったら、本文にどかっと追記されていて大いに驚いた記憶もあります。「アイデアは保護されない」という著作権法の原則に、法制度小委員会が一石を投じた形になっているんですよね。いやー、すごい(語彙力不足)。
社会
雑誌や新聞記事の“コピペ”は「著作権侵害」!? 5月には“書類送検”も…「犯罪者」にならず情報をシェアするには【弁護士解説】〈弁護士JPニュース(2025年7月8日)〉
えーっと、こういう解説記事ですら日本複製権センター(JRRC)の名前が挙がらないのは、どうかしてると思うのですよ、正直。企業内での共有は私的複製にならないのはその通り。合法的に企業内でシェアするには「JRRCと利用許諾契約を結びましょう」という選択肢もあるわけです。要するに対価を払えばいいわけですよ。
信頼関係だけでは成り立たない?|【出版時評】2025年7月8日付〈The Bunka News デジタル(2025年7月8日)〉
うーん……少なくともその「?」はもう要らないでしょう。信頼関係だけで成り立つというのは、時代遅れな考え方ですよ。ちなみにフリーランス法で初の勧告を食らった小学館も光文社も、資本金1000万円超ですから、フリーランス法以前に下請法を遵守してなかったことになります。とほほ。
なお、文化通信社は資本金1000万円だから下請法はギリギリ対象外でしたけど、フリーランス法は対象です。フリーランス法施行は2024年11⽉1⽇ですから、注意喚起するならその前にしておかないと。いまごろこんなこと言ってて大丈夫なのかな? と心配になってしまいました。
日本の個人の生成AI利用率は27% 中国81%、米国69%と大きな差 情報通信白書〈ITmedia AI+(2025年7月9日)〉
情報通信白書の最新版が出ました。まだ読めていません。というか、データ集のみ先行公開の段階で、まだ概要(PDF)しか出てないようですね。ちなみに記事には「利用しない理由は『生活や業務に必要ない』が4割を超えて最多」とありますが、これは「テキスト生成AIサービスを利用しない理由」です。
恐らく画像生成は理由が違うだろう……と思ったら、テキスト生成より画像生成のほうが利用率は低いんですね。意外。どうも調査のタイミング的に「ジブリ風」が流行る前だったっぽい。2025年の「国内外における最新の情報通信技術の研究開発及びデジタル活用の動向に関する調査研究」が見つけられないのですが、2024年調査の実施期間が2023年10月12日から2024年3月29日までなので。
経済
広告か有料購読か、答えのないニュースの在り方 ペイウォールの課題は“マンガ配信”に解決のヒント?:小寺信良のIT大作戦〈ITmedia NEWS(2025年7月4日)〉
マンガ配信みたいな話売りモデル、つまり記事単位のバラ売りはどうか? という提案です。新聞系ウェブサイトに定期購読以外の選択肢がないのはおっしゃる通り。「この記事だけ読みたい」と思ったとき、近所のスーパーまで行ってバラ売りしてるのを1部買ってくる手間をかけるくらいなら、1記事100円くらいなら喜んで払いますよ。そう新聞社の中の人にも伝えてるんですけどねぇ……。
ただ、マンガ以外のバラ売りって、国内ではあまりうまくいっている印象がありません。小説で話売りモデルを展開しようとした「LINEノベル」が1年足らずで撤退した大失敗事例とか。雑誌記事のバラ売りモデルも過去にいくつか試行事例がありますが、うまくいっているという話は聞きません。むしろ、記事単位のバラ売りをちゃんと定着させた「note」が例外的な成功事例なのでは。
生成AI「翻訳」が引き起こす「コンテンツ大航海時代」 日本の漫画が世界で戦う際の“勝ち筋”は?:グロービス経営大学院 TechMaRI 解説〈ITmedia ビジネスオンライン(2025年7月11日)〉
こちらは「ずいぶん簡単におっしゃるなあ……」という印象を受けました。とくにここ。
韓国Webtoonの最大市場は日本(2022年の輸出額の45.6%)である。このため、日本が海外に進出するために、縦読みをまねすればいいというほど単純ではないが、Webtoonのように全く新しいフォーマットの発明も一つの方法だ。
全く新しいフォーマットを発明しろですと? いやはや。具体的にどういうフォーマットが考えられるだろう? 私はもう頭が固いのか、立体視みたいなのしか思い浮かびませんでした。それにはまずVR機器の普及が必要ですね。ヘッドマウントより眼鏡型が有望かな?
とりあえず縦スクに限った話でも、横読みを縦スクにするには結構な手間がかかることを理解しているのだろうか? という疑問も。なお、KADOKAWAはすでに「BOOK☆WALKER Global」で英語版「TATESC COMICS」を2022年から配信していることは指摘しておきましょう。
【続報】秀和システムの出版事業 トゥーヴァージンズが承継へ 負債・未払金承継せず〈The Bunka News デジタル(2025年7月10日)〉
破産した秀和システムの出版事業を引き継いだ会社からの連絡を読んで、思わず笑ってしまった(CloseBox)〈テクノエッジ TechnoEdge(2025年7月9日)〉
株式会社秀和システムの出版事業譲受について〈株式会社トゥーヴァージンズ(2025年7月11日)〉
【お知らせ】株式会社秀和システムの出版事業譲受について〈秀和システム(2025年7月11日)〉
続報。秀和システムの出版事業はトゥーヴァージンズが承継し、株式会社秀和システム新社として再出発することに決まったそうです。ただし、負債・未払金は承継しないそうです。これ、金融機関からの借入以外の「未払金」に限って考えると、対象は従業員の給与、著者への原稿料や印税、編集費やデザイン料(外注してたら)、印刷製本、倉庫、運搬費あたりでしょうか。
とくに、著者への未払原稿料や未払印税を「承継しません」と宣言したうえで、既刊の著者が新会社での出版契約を継続したいと思うかどうか、疑問です。身近なところでは、山口哲一氏が「未払印税払うくらいの姿勢は見せないと承継させない」と宣言していました。
逆に売掛は、基本的には取次だけでしょうか? 書店との直接取引や直販があれば話は別ですが。取次は、出版社の倒産リスクをヘッジするため、小規模なところほど入金を遅らせる傾向があるはずですよね。秀和システムはどうだったんでしょうね?
あと「委託販売」との関係がどうなるのか。これ正直、私にはわかりません。委託といいつつ基本は「返品条件付き売買契約」ですから、所有権は移転しているはず。その場合でも、取次や書店にある商品は債権回収の対象になるのでしょうか? それとも、ならない? 「返品条件付き」をどう解釈するか次第?
スマートニュース、広告主自ら出稿・運用できる新機能「セルフサーブ型広告」を7月10日から提供開始〈スマートニュース株式会社のプレスリリース(2025年7月10日)〉
Google広告やYahoo!広告は前からセルフで出稿できる形になってますから、ようやく仕組みが追いついた形でしょうか。広告主の立場で考えると「気軽に出稿できて良い」のですが、受け手の立場で考えるとクソみたいな広告が大量に来ることが予想できてしまいます。それにスマニューの審査体制が耐えられるかどうか。恐らく、ある程度はAIで自動的にさばくんでしょうけど。
技術
Newsbrands most hit by increased zero-click searches from Google(グーグルのゼロクリック検索増加で最も打撃を受けるのはニュースブランド)〈Press Gazette(2025年7月7日)〉
ゼロクリック率が最も高かったのは、日本の「livedoor.com」(79.5%)だったそうです。1年前は43.6%だから、激増しています。ただ、他のサイトのデータを見るとあまり増えてないところもあるし、中にはゼロクリックが減ってるところもあるので、AI Overviewsだけを要因とするのは早計かも。
ところで、livedoorニュースっていまはもう独自記事は配信していないですよね? 基本、他メディアから提供されたニュースを転載しているだけのニュースアグリゲーターだから、ニュースメディアとして分析したらダメかも。Similarwebの分類そのままなのかしら?
「AIはどれだけ巡回し、どれだけ人を連れてくるのか」 Cloudflareが可視化:数字で見るAIクローラーの影響〈@IT(2025年7月8日)〉
GooglebotからGPTBotへ:2025年にあなたのサイトをクロールしているのは誰か〈Cloudflareブログ(2025年7月1日)〉
AIボットのクロール状況が可視化されています。こんなにいろいろなボットが、知らないうちにサイトを徘徊してるんですね。これ、Cloudflare の「Pay per crawl」で学習用ボットによるスクレイピングはブロックできたとしても、検索結果へ表示するためのインデックス作成用ボットが検索拡張生成(RAG)用も兼ねてるあたりが次の問題になりそう。
要するに、Google検索からの流入を捨てないと、AI Overviews(AIによる概要)やAI Modeなどで要約利用されることは防げないわけです。これらのサービスは、学習済みのAIモデルにより素材を要約して出力しているだけで、素材を学習しているわけではない(はず)ですから。文化庁が「AIと著作権(2023年6月19日の著作権セミナー)」で早々に整理していたように、学習段階と出力段階に分けて考える必要があります。
OpenAI製ブラウザ、まもなく登場か–Googleが支配するウェブに風穴を開ける可能性〈CNET Japan(2025年7月10日)〉
どうせ Chromium なんでしょ? と思い、ロイターの原文を参照したら大正解でした。それ、開けた風穴の向こう側にも Google がいるって話になりますよねぇ……Googleの手のひらの上。まあ、Google はブラウザのレンダリングエンジンを Apple の WebKit からフォークして Blink を作って Chrome に搭載してますから(2013年)、OpenAIが同じようにフォークする未来もあり得る?
お知らせ
ポッドキャストについて
5年ぶりに再開しました。番組の詳細やおたより投稿はこちらから。
新刊について
新刊『ライトノベル市場はほんとうに衰退しているのか? 電子の市場を推計してみた』各ネット書店にて好評販売中です。Kindle Unlimited、BOOK☆WALKER読み放題、ブックパス読み放題、シーモア読み放題にも対応しました!
「NovelJam 2024」について
11月2~4日に東京・新潟・沖縄の3会場で同時開催した出版創作イベント「NovelJam 2024」で新たに誕生した16点の作品を合本にしました!
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届くHONꓸjpメールマガジンのほか、HONꓸjp News Blogの記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。FacebookページやX(旧Twitter)などでは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
https://hon.jp/news/daily-news-summary
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算号数、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行号数です。
雑記
今年の夏は、まだ本気出してない感じがします。大学へ行くとき、昨年までこの時期は九段下の駅を降りて坂道を(by 爆風スランプ)登っていくのが地獄だったんですが、今年はまだなんとかなっています。……なんてことを書いていると、本気の夏が来たりして。やめてー。(鷹野)