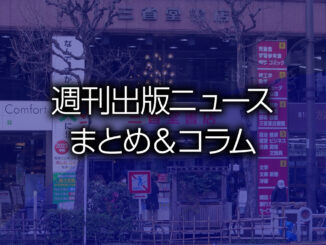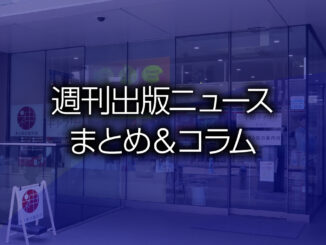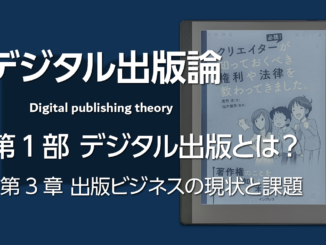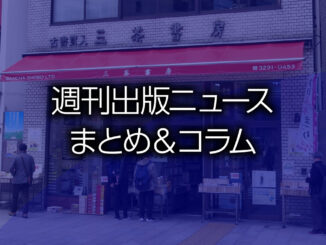《この記事を読むのに必要な時間は約 9 分です(1分600字計算)》
第2章 メディアとビジネスモデル
第1章では「デジタル」や「出版」といった言葉の定義とともに、さまざまなメディアの歴史を簡単に振り返りました。第2章ではもう少し踏み込んで、主要なメディアの定義やビジネスモデルについて考えていきましょう。
「情報伝達の媒体」を具体的に挙げると?
私は大学の講義で毎年、受講生に「情報伝達の媒体」(=メディア)の名前を「思いつく限り具体的に列記」してもらう課題を出しています。過去5年分、約2200件を単語単位で集計してみたところ、上位は以下のような結果となりました。集計には、テキストマイニング(text mining:文章採掘)のツールを使っています1ユーザーローカル「AIテキストマイニング」の集計結果ページ
https://textmining.userlocal.jp/results/Tv6dRrQAJ6JGZT8GaqqwWGqGzFinLCcu
(※無料だと1万字の上限があるため、今回の過去5年分が限界だった)。
- テレビ
- 新聞
- ラジオ
- 本
- 雑誌
- インターネット
- 手紙
- SNS
- スマートフォン
- チラシ
新聞、雑誌、テレビ、ラジオの「4マス」と、本、インターネットが上位を占めています。なんだかんだ言って、やはり身近なものが強い印象です。意外なことに「スマートフォン」が下位ですが、充分な前処理をせずに集計しているせいでしょう。たとえば「スマートフォン」を略した「スマホ」は別扱いになっています。
課題で提出された元データには、略語以外にも、ひらがな・カタカナ・漢字の表記揺れ、誤変換、括弧書き補足の有無、列記ではなく文章で提出されたケースなどもあります。集計結果を基になにか考察しようと思うなら、丁寧な前処理(データクレンジング)が必要です。ツールで自動処理というのは、ラクですが、落とし穴もあることを頭に入れておく必要があるでしょう。
なお、個人的には、挙げる人が少ない回答が好きです。たとえば「表情」は非言語(ノンバーバル)の情報伝達手段として非常に身近で有効的な媒体ですが、挙げた人は5年間で2人だけでした。「表情もメディアである」ことは、なかなか思いつかないようです。
というわけでここからは、ここで上位に挙がっているメディアを中心に、その定義やビジネスモデルについて、確認してみることにしましょう。本、雑誌、新聞、ラジオ、テレビ、インターネットの順です。
本(book / 書物 / 書籍 / 図書)とは?
改めてまず、言葉の定義から。精選版日本国語大辞典(小学館)によると、本は、漢語では「草木の根、または根に近い部分」でしたが、日本では「物事のもとになるもの、根本、基本の意から、規範となるもの、主たるもの、本来的なものなど」を指す言葉となりました。書物、書籍、図書などとも呼ばれます2基本的には、同じものを指す言葉。本稿ではなるべく「本」と表記するようにしているが、出版業界では「書籍」、図書館業界では「図書」と呼称される場合が多いため、それぞれの業界に関連する話題ではどうしてもその表記になってしまいがち。。最も歴史の長い情報伝達の媒体の1つです。
49ページ以上の非定期刊行物
1964年にユネスコで採択された出版物統計の国際標準31964年UNESCO採択勧告の原文「Recommendation concerning the International Standardization of Statistics Relating to Book Production and Periodicals」
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13068&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Definitions “A book is a non-periodical printed publication of at least 49 pages, exclusive of the cover pages, published in the country and made available to the public;”では、本は「国内で出版され、かつ、公衆の利用に供される少なくとも49ページ(表紙を除く。)以上の印刷された非定期刊行物」41964年文部省(当時)による「図書及び定期刊行物の出版についての統計の国際化な標準化に関する勧告」の仮訳より
https://www.mext.go.jp/unesco/009/1387084.htmと定義されています。5ページから48ページの短いものは「小冊子(pamphlet)」、雑誌や新聞は「定期刊行物(periodicals)」と、別途分類されています。
この定義には「印刷された(printed)」という言葉が入っていますが、前提となる一般定義(General definitions)で「印刷という用語は、方法のいかんを問わず、各種の機械印刷による複写を含む(The term printed includes reproduction by any method of mechanical impression, whatever it may be.)」とされています。複製の手段を問わないのであれば、デジタル出版物を含めても良さそうです。

では文字数カウントで代替できるか? というと、若干無理があります。というのは、紙の本でも、紙の大きさ(判型)、文字の大きさ、余白の広さ、1行あたりの文字数や行数などは、1点ごとに異なります。また、段落や改ページ、空行、見出し、挿絵や図の有無などによっても、1ページあたりの文字数は変化します。
だからもし「49ページ以上」を文字数に換算しようと思うと、「2万~3万字程度」などといった幅のある表現になってしまいます。では、たとえば2万5000字の文章は「本」なのか「小冊子」なのか。文字数は少ないが図表が多い場合はどう考えるのか。さまざまな例外が出てきそうで、明確にするのは難しそうです。
―― この続きは ――
《残り約1000文字》
〈前へ〉