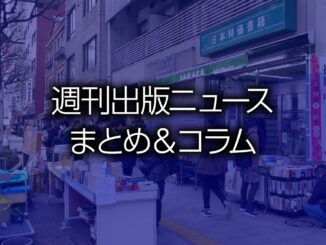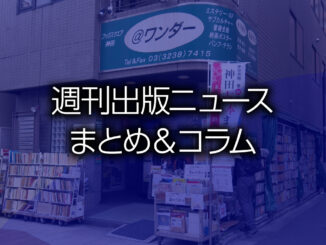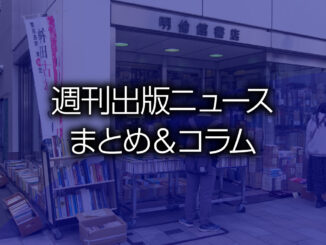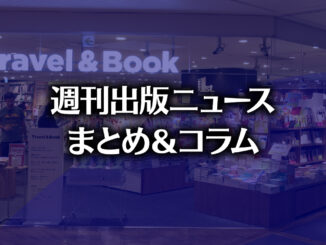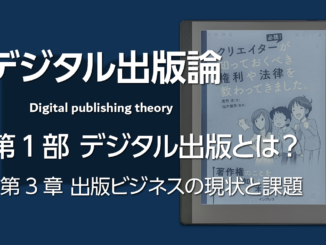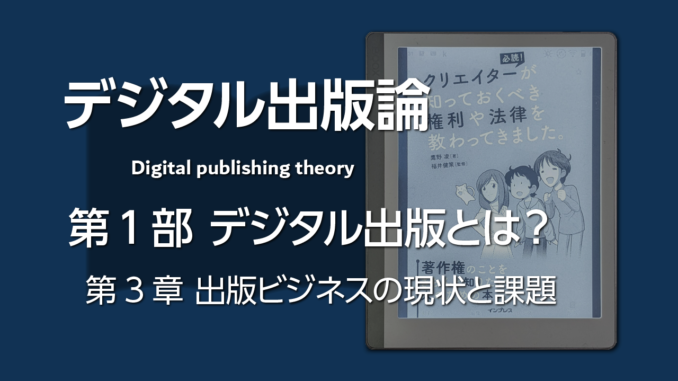
《この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です(1分600字計算)》
紙と電子の販売/配信モデルの違い
同じ内容の出版物でも、紙と電子とでは販売/配信モデルや適用される法制度などに、若干の違いがあります。少し深掘りしてみましょう。
著作物再販適用除外制度(再販制度)
取次ルートの販売モデルでは、紙の本は小売店において「定価」で販売される場合がほとんどです。これは本来、一般的なメーカーと小売店の関係においては独占禁止法で「再販売価格維持行為」として禁止されている行為です1私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第2条⑨不公正な取引方法四
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/lawdk.html。
ただし、書籍、雑誌、新聞、音楽用CD、音楽テープ、レコード盤の6品目は例外的に、この独占禁止法の適用が除外されています2公正取引委員会「よくある質問コーナー(独占禁止法)」の「Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。」より。
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12。これを、著作物再販適用除外制度、通称「再販制度」と言います3独占禁止法第23条。
この適用除外に基づき、パブリッシャーと取次・小売店とのあいだで「再販売価格維持契約(再販契約)」が結ばれ、値引き販売が禁止されます4一般社団法人日本書籍出版協会の契約書ヒナ型を参照。なお、パブリッシャーが認めた場合は、定期刊行物や継続出版物などの長期購読前金払いや大量一括購入、謝恩価格本などの割引が行える契約になっている。
https://www.jbpa.or.jp/publication/contract.html。なお、再販契約で定価販売が義務付けられるのは小売店と取次であり、パブリッシャー自身が値引き販売を行うことは禁止されていません5たとえば、出版社のスタッフが期間限定イベントで手売りするようなケースは、値引き販売されている場合が多い。ただ、書店とのあいだで利益相反になってしまう恐れもあるため、あまり大規模な形では行わないのが通例だ。。
また、パブリッシャーが発行するすべての著作物について、再販契約を結ばなければならないわけでもありません。国が制定し遵守が義務付けられているという意味での「制度」ではないのです6出版流通改善協議会「再販契約の手引き【第7版】」より。
https://www.jbpa.or.jp/pdf/resale/tebiki7.pdf。
紙は再販、電子は非再販

https://www.tohan.jp/business/pdf/BOOKSTORE_OPEN.pdf。
公正取引委員会は長年、この再販制度を「競争政策の観点からは廃止すべき」と考え続けています。しかし出版業界はこれに抵抗し続けています。以前、見直しが議論された際は、協議の結果、2001年に「廃止には国民的合意が形成されるに至っていない状況にあり、当面制度を存置することが相当」と結論づけ、それが現在も続いています8清田義昭「日本における再販制度問題の経過と結論」(2001年)
https://doi.org/10.24756/jshuppan.32.0_161。
ホールセールモデルとエージェンシーモデル
なお、電子出版物は「有体物」ではなく情報として流通することから、適用除外の対象外(つまり定価販売を強制できない)とされています9公正取引委員会「よくある質問コーナー(独占禁止法)」の「Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。」より。
https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ13。物理書店での値引き販売はあまり見かけませんが、電子書店では頻繁にセールが行われているのは、そういう違いがあるからです。
ただし、電子出版物の販売価格すべてが、完全に電子書店の自由になっているわけではありません。出版社が電子版を電子書店に卸売りする「ホールセール(卸売)モデル」では、小売価格の決定権は電子書店にあります。しかし、電子書店が出版社から販売業務を請け負う「エージェンシー(委託販売)モデル」では、小売価格の決定権は出版社にあります10詳しくは公正取引委員会の共同研究報告書 平成25年度 CR 01-13「電子書籍市場の動向について」(2013年6月26日)を参照。
https://www.jftc.go.jp/cprc/reports/jointresearch/index_2.html。
アマゾン「Kindleストア」ではこの違いが判別しやすく、ホールセールモデルの場合は「販売者:Amazon Services International, Inc.」と表記されていますが、エージェンシーモデルの場合は「販売者:株式会社 講談社」「販売者:株式会社集英社」「販売者:小学館」など出版社名が表記されています11筆者の調べによると、講談社、小学館、集英社のほか、白泉社、光文社、文藝春秋、スクウェア・エニックス、岩波書店がエージェンシーモデル。。電子取次を経由する場合は、ホールセールモデルになっているようです。
―― この続きは ――
《残り約1700文字》
〈前へ〉