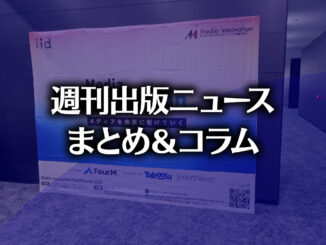《この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です(1分600字計算)》
「ぽっとら」は、HON.jp News Blog 編集長 鷹野凌がお届けするポッドキャスト「HON.jp Podcasting」の文字起こし(Podcast Transcription)です。2025年3月4日に配信した第21回では、詐欺広告の話題と、作家自身による出版の話題について語っています。
#21 詐欺広告/作家自身による出版
こんにちは、鷹野です。今回は「詐欺広告」と「作家自身による出版」をテーマにお話したいと思います。まず「詐欺広告」について。先月末に、ちょっと「おや?」と思う政府の動きが報道されたので、掘り下げておきたいと思います。モリアキさん、簡単に説明してもらえますか?
はい、モリアキさんありがとうございます。なんか法改正って話が急に出てきたなと思ったんですけど、よくよく調べてみたら単に私のスコープ外でした。今回のこの原稿(台本)を用意するのにあたってですね、改めて調べてみたんですけど、ちょっと「やられた!」って気分になりました。いや、まあ、たいした話じゃないんですけど。
私ね、総務省の検討会はそれなりに追いかけてたつもりなんですね。総務省では、偽・誤情報対策。ニセ、誤りの情報ですね。その対策ということで、去年の9月まで「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」というのがありました。もうまとめも出ています。
で、(2024年)10月からは名前が変わって「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」、そこでもいろいろな議論がいまなお行われています。そこには「デジタル広告ワーキンググループ」というのもあって、そこではずばり、SNSでのなりすまし型「偽広告」への対応に関する事業者ヒアリング、なんてのも行われていたんですよ。
ただ、現時点だとまだ「法制化」みたいなところまでは進んでない段階だったんで、いずれそういう話も出てくるかな? とは思ってたんですね。まだ先だと思ってたのに、急に報道に出てきたんで、「おや?」ってなったんです。
これね、どうやら警察の捜査とか公判なんかの「刑事手続きをIT化する」という流れがあって、刑事訴訟法とか刑法の改正というのが、法務省で議論されてきたみたいなんですね。法務省。総務省じゃなくて法務省。法務省はね、さすがにスコープ外でした。
スコープをどこまで広げるか? 問題(余談)
ちょっと(話が)脱線しますけど、国の機関すべてに目を配るのはね、正直難しいです。だからこういうのって、どうやってアンテナ立てておけばいいのかな? って、ちょっと困っちゃってるんですけど。今回みたいに報道で具体的に「私電磁的記録文書等偽造・行使罪」みたいな、具体的なキーワードが出てくれば、そこから深掘りするのはぜんぜん可能なんですよ。
それでも、今回は日曜日にメルマガの原稿を書いたときには、法務省との関係って調べ切れてなかったんですけどね。Googleで調べてもうまく引っかかってこなかったし、いまPerplexityで調べてみたら、やっぱり法務省は出てこなかったんです。どうすればいいんだろうね。
私はたとえば、Googleアラートっていう便利なサービスを長年愛用しています。キーワードを登録しておくと、関連する新着情報をメールで送ってくれるんですね。メールが随時か、1日1回かは選べるんですけど、随時だとメールの数が多すぎてだるいんで、1日1回に設定してあります。
で、いまそのGoogleアラートに登録しているキーワードは、さっき見たら111個あってですね。まあ、なかには新着情報がめったに出てこないマイナーなキーワードもあるんで、毎日チェックしてますけど、Googleアラートからのメールは1日60通とか70通くらいです。1キーワード1通なんで、1通に入ってる新着記事の数はいろいろです。1件だけのもあれば、20件くらいあるものもある、みたいな感じです。
Googleアラート以外にも、企業から届くプレスリリースが1日200から300件くらい。あとは、RSSリーダーに登録しているウェブサイトの更新情報が、これまた1日300件くらい。それらをぜんぶひと通り、毎日チェックしてるわけです。これは取り上げておこうとか、そうじゃないみたいなのを判断して。
HON.jp News BlogのSNSアカウントでキュレーションってのをやってるわけなんですね。それが1日にだいたい20件くらいです。だからね、ほとんどは捨ててるんですよ。チェックしてる情報の、数百件ある記事の見出しだけ見て捨てるみたいなのを、もうずっとやってるんです。
そういう状態なんで、スコープを広げるのは正直きついんですよ。ちょっとでも広げると、またドバッと情報増えるんで。しかも法務省とか、おそらく出版とほとんど、ほとんど関係ない動きがほとんどだと思うんですね。スコープに入れると、チェックする時間の大半が無駄になるってのが目に見えてるわけです。正直、法務省までスコープには入れたくないんです。
だから、政府の動き、とくに規制に関わる動きって影響が大きいんで、やっぱり事前にチェックしておかなきゃいけないなって思うんですけど、思うんですけど! あまりに多すぎる。多すぎるんですよ、情報。
国家機関って、公務員試験を突破した日本の頭脳と言っていい頭の良い方々が数十万人いるわけですね。もっと言えば、審議会とか検討会って、外部の専門家を集めて議論してるわけですよ。専門家。その道の専門の人。
その動きをプロセスまで含めて追いかけるのは、まあ至難の業ですよね。専門性が高すぎちゃって、私の理解が追いつかないって場合も、ほんと結構あります。まあ、そういうわけで、総務省だと思っていたら、法務省でした、という愚痴で脱線しました。
Metaの「法令上義務はない」発言が法制化へのトリガーを引いた?
話を本題に戻します。今回のテーマ「詐欺広告」ですね。今回の報道は、法改正の案が閣議決定されたという話で、これから国会で審議されたのち成立して、公布されて施行ってというプロセスを辿るわけですけど、その法改正しなきゃダメだねってなる前の、原因となる話があるわけです。それをちょっと振り返っておきましょう。
さきほどモリアキさんの説明の中で「社会問題化しているSNS型投資詐欺」っていう話がありました。これが大きな話題になったきっかけっていうのが、ファッション通販の「ZOZOTOWN」ってありますね。「ZOZOTOWN」創業者の前澤友作さんが、Facebook Japanとその親会社のMeta社に対し、公開で抗議した。それが大きな話題になってきっかけだったと思います。2024年3月ごろですね。
その前澤さんをはじめ、堀江貴文さんとか、村上世彰さんとか、森永卓郎さんとか、そういう著名人の名前とか写真を無断で使った投資広告が、Facebookにバンバン出てたんですよ。で、その広告からLINEグループなんかに誘導されて、そこでお金をだまし取られる、みたいな。
おもいっきり詐欺。詐欺広告ってやつです。名前とか写真は無断で使われてるだけなので、当然、前澤さんはまったく関係してないし、知りもしないわけです。むしろ被害者。だから「なりすまし広告」なんて言われ方もしています。
そりゃもちろん「Facebookはなにしてんの?」って話になりますよね。端的に言って、広告審査が甘いんです。ザル。これはべつにFacebookに限った話じゃなくて、巨大IT企業のプラットフォームって、わりとどれもザルです。
人間が1件1件丁寧に見たりしないわけですよ。機械的なチェックだけです。彼ら自慢のAIが、広告で使っちゃまずい言葉とか図柄なんかをアルゴリズムで自動判定するわけですよ。その自動判定でOKとなったら、もうほいっと出しちゃう。ほぼ自動です。
で、出してからなにか問題が起きたら、そこから人間が出てきて対処する、という流れになるんですよ。インターネット広告って一般的に、ユーザーからそういう違反なんかを報告できるようになっている場合が多いんですね。
なかには、報告する手段すら提供されてない、論外と言っていい広告プラットフォームもありますけど。少なくとも、FacebookとかGoogleの広告には、右上のメニューのところから「広告を報告する」っていう窓口がいちおう設けられてます。GoogleとかFacebookにはね。
ただ、報告しても、あんまり対処された気がしないんですよね。それが私の正直な実感です。私もね、もうさんざん「こりゃダメだろ!」って広告を報告してきましたよ。それで、そういう広告が出なくなった! 効果が出た! と思ったことって、ほぼないんですよ。ない。皆無と言っていい。
で、こういうプラットフォームには、もう世界中から膨大な件数の報告が飛んでるはずなんですよ。ただ、たぶんそういう報告の件数が多い、クレームの多い広告から順に、人間が処理するみたいなフローになってるんじゃないかな、と。まあ、これは想像ですけどね。巨大プラットフォームの中で審査できる人も限られてるでしょうから、クレームの多いものからってなってても不思議じゃないかなとか思うんですけどね。
これは、こういうプラットフォームには思想の根幹に、だれでも自由に情報発信できるとか、だれでも自由に執筆できるとか、だれでも自由にアプリ配信できるとか、そういうのがあるわけです。根幹にね。広告も同じです。だれでも自由に広告が出稿できる、広告の民主化だ! みたいなね。そういう仕組みが、巨大IT企業のプラットフォームなわけです。
じゃあ、それを政府、監督官庁がプラットフォーム事業者に「改善しろ!」って命令出したりすりゃいいじゃん、って思いますよね。現状だと、できないんですよ。命令する根拠となる法律がないんですよ。去年、この詐欺広告が大きな話題になったとき、政府は要請を出してます。要請ね。要するに単なるお願いです。
これね、日本の企業だと、この要請レベルでわりと対処してくれたりするんですよ。お願いでね。お願いで動いてくれる。日本の企業は。でも外資はそんなお願いなんて聞きやしないんですよ。聞いちゃいない。で、被害者が損害賠償請求の訴訟を起こしても、Meta社はこんなこと言ってたんですよ。
ってね。義務がないから責任もない。責任もないから損害賠償する必要もない。そういうロジックなわけです。私ね。このMeta社の「法令上義務はない」って発言が報道されたときに、「ああ、これはトリガー引いちゃったな」って思ったんですよ。法制化へのトリガーね。義務がないから言うこときかないって言ってるわけですよ。なら義務にするしかないですよね。もう強制的に言うこと聞かせるしかないわけですよ。
―― この続きは ――
《残り約6000文字》