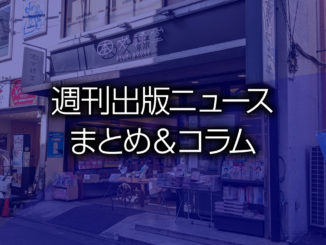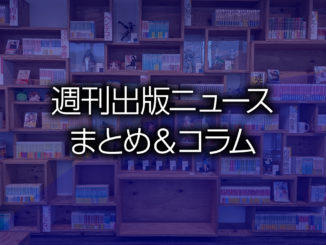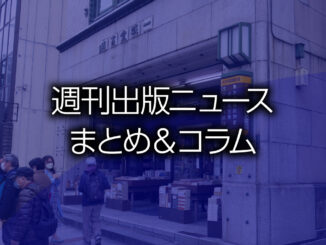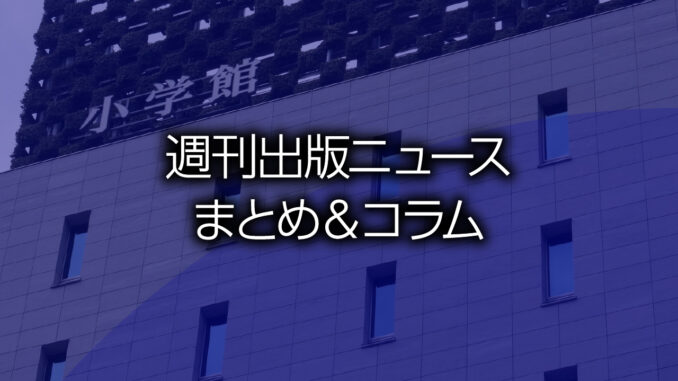
《この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です(1分600字計算)》
2022年12月4日~10日は「書店議連、軽減税率等を求める」「セルシス子会社、ブロックチェーンによるコンテンツ流通基盤を発表」などが話題に。広い意味での出版に関連する最新ニュースから編集長 鷹野が気になるものをピックアップし、独自の視点でコメントしてあります(ISSN 2436-8237)。
【目次】
- 政治
- 社会
- 経済
- 技術
- ChatGPTによる回答をStack Overflowが一時的に禁止 大量のもっともらしいが不正確な回答に対処しきれず〈ITmedia NEWS(2022年12月6日)〉
- “ヤフコメ”削除率は3.22%、7割超がAIによる自動削除。ヤフー「2021年度メディア透明性レポート」公開〈INTERNET Watch(2022年12月7日)〉
- マンガ・アニメ制作アプリ最大手のセルシス、デジタルデータに「所有権」を付与する流通支援ソリューション「DC3」発表〈INTERNET Watch(2022年12月9日)〉
- Google検索、デスクトップPC版に連続スクロール導入。6ページ分をイッキ見可能に〈テクノエッジ TechnoEdge(2022年12月9日)〉
- お知らせ
- 雑記
政治
権利不明の著作物、二次利用促進 一元窓口新設へ法改正〈日本経済新聞(2022年12月5日)〉
著作権侵害の賠償上乗せ、 海賊版の被害深刻 法改正へ〈日本経済新聞(2022年12月5日)〉
2つとも、文化審議会著作権分科会法制度小委員会から報告書(素案)が出たことを受けての記事です。検討事項はこの「簡素で一元的な権利処理方策と対価還元の制度化について」と「海賊版被害等の実効的救済を図るための損害賠償額の算定方法の見直しについて」以外に、「立法・行政・司法のデジタル化に対応した著作物の公衆送信等」「研究目的に係る権利制限規定の創設について」もあります。ただ、後者2つはどちらも「必要に応じて検討」と報告書(素案)にあり、しばらく動きは無さそう。来年以降で法改正など動きがあるのは、記事になった前者2つに絞られたと言って良さそうです。
私は、関係者ヒアリングを何回か傍聴したんですが、とくに「簡素で一元的な権利処理と対価還元の制度化」について、窓口組織の設立や運営に要する費用が民間に丸投げになることを危惧する声が多かった印象があります。そのためか、報告書(素案)概要には「手数料収入、公的な支援、共通目的事業等の活用を検討する」(p10)とあり、いちおう考慮されたのかな? という印象です。
なお、賠償上乗せは、字面からは「懲罰的賠償制度」のような印象を受けてしまいますが、そうではありません。実際、議論の中では「懲罰的な効果」をもたらす制度に見直すべきという意見もあったようですが、民法等が「実損の填補を原則」としていることから、あくまでその範囲内での上乗せという案になっているようです。
書店議連「中間まとめ」発表 送料無料の制限やICタグ・軽減税率など盛り込む〈文化通信デジタル(2022年12月9日)〉
また「軽減税率」の適用を求める方向に。以前は、当時の菅官房長官が「例えばポルノ雑誌とかそういうものが全部入ってしまう。線引きというものをぜひ、業界の皆さんのなかで決めて頂く」などと言い出したことが、業界関係者にあらぬ期待を抱かせてしまい、振り回された経緯があります。租税法律主義があるから、自主規制で税率は決められないのが大前提なのですよね。
それなのになぜか「有害図書」を業界で自主的に区別するなんて話が浮上してきて、さすがにそれはヤバイだろと大慌てしたことを思い出します。第三者委員会を設立して「著しく性的・暴力的な表現で青少年に影響を与える」かどうかを諮問する――などという案が真面目に検討されてたんですから。今度はうかつに誘いに乗っちゃ駄目ですよ。もし適用を求めるとしても、清濁関係なく全ての書籍・雑誌(電子含む)を対象としないと。

あと、対象になった「新聞」が、消費税関係の問題に切り込めず腰砕けな状態になっている現状も、よく見ておいたほうがいいと思います。権力に尻尾を振りながら批判できますか? ユーザーの負担が軽減されるのは書店にとって良い話かもしれませんが、著者・出版者にとっては「表現が死ぬ」危険と隣り合わせです。私は、これで「新聞は死んだ」と思っています。
もう一つ。「インボイス制度は軽減税率があるから必要」という建付けで動いているので、軽減税率を求めることイコール「インボイス制度が始まるのを許容する」ことになります。仕入税額控除できない免税事業者との取引になっても、「そのぶんは出版者側で負担します」と誓えますか? 出版者が軽減税率適用を求めるのであれば、「零細フリーランスを守ります」という宣言が必要でしょう。
社会
※デジタル出版論はしばらく不定期連載になります。ご了承ください。
WEBTOON(ウェブトゥーン)利用者に関する調査〈MMD研究所(2022年12月5日)〉
コミックアプリ・サービス利用者の4割以上が、ウェブトゥーンの閲覧経験があるとのこと。男女年齢層で好まれるジャンルの傾向がかなり異なる点なども面白い。ただ、こういった本題のウェブトゥーンについてより、同時に尋ねているコミックアプリ・サービス全般についてのほうが、もっと興味を惹かれました。
サービス別の利用経験と「直近1カ月」についても尋ねているのですが、差分をとってみたら面白いことに。当然、どのサービスも「直近1カ月」では利用率が減少しますが、プラットフォーム系が10ポイント前後減少しているのに対し、出版社系を中心に5ポイント前後の減少に留まっているグループもあるのです。詳しくは、MMD研究所のレポートを参照してみてください。
なお、これは前回の調査をピックアップした際にも書きましたが(#532)、これはコミックアプリ・サービス限定の調査である点には注意が必要です。Kindleストアや楽天Koboといった総合型は、選択肢から外されています。繰り返しますが、それが「ダメ」という話ではなく、除外されている部分があることを念頭に入れておくべきです。
書店8343億円、インターネット2808億円…出版物の売り場毎の販売額推移(最新)〈ガベージニュース(2022年12月7日)〉
日販 「出版物販売額の実態 2022」発行を受けての、ガベージニュースによる毎年恒例の推移グラフ化。こちらは物理の販売ルートのみで、電子出版物は含まれていません。コロナ禍による巣ごもり需要が高まった影響か、インターネットルートが2020年から急増している点がトピックスでしょう。
1973年以降の長期推移を見ると、1980年代初頭からコンビニが勢力を伸ばし、書店やその他取次(キオスクなど)を侵食していった様子が見えます。ところが、出版社直販やインターネット通販の数字を算出するようになった2007年あたりから、コンビニも減少傾向に転じます。書店はここ3年ほど微減で踏みとどまっていますが、まだ数字が出ていない2022年は……。
経済
Adobe、画像生成AIでつくった素材の販売認める 許諾なしの生成はNG〈KAI-YOU.net(2022年12月7日)〉
Adobe Stockで、AI生成コンテンツの販売を認める新たなガイドラインが制定されました。とはいえよくよく読むと、AI生成以外にも適用されている「特定できる人物」や「知的財産の情報」を含めるには許諾が必要というポリシーと、適切な許諾なしでの「第三者のコンテンツを元に作成したコンテンツ(例:人、場所、知的財産、アーティストのスタイルなどに言及したプロンプトで生成されたもの)」の投稿が禁止されているという、わりと納得しやすい感じの内容です。
また、英語のポリシーまで確認してみましたが、AIが機械学習する際のデータをどこから持ってきたのか? については、とくに問うような文言は見つけられませんでした。無断転載の横行している掲示板「Danbooru」を学習元にしていることを公言している「NovelAI」は、自分でイラストを描く方々から蛇蝎のごとく嫌われていますが、Adobeのガイドラインはそこを問題とはしてないようです。
アップル、「App Store」の価格設定を大幅改定–50円から160万円まで可能に〈CNET Japan(2022年12月7日)〉
来年春から。従来は160円、320円、480円、650円、800円、1000円……みたいに、Appleが指定した価格帯以外では設定できなかったのですが、50円~2000円は10円刻み、2000円~1万5000円までは100円刻みで設定できるようになるとのこと。あまり話題になっていませんが、大きな変更です。詳細はApple公式のお知らせを参照してみてください。
まあ正直、いままでが自由効かなすぎだったのですよね。これまでは「550円で売りたい」と思っても、値下げして480円にするか、650円に値上げするしかなかったわけですから。あと、為替変動でいきなりAppleから「Tier変更」が通知され、価格変更を余儀なくされこともたびたびありました。Apple IDの決済を使う限り、従来はその呪縛からは逃れられなかったのです。この変更によりやっと、同じ本なのに「Apple Books」での販売価格だけ常に他店と異なる状況から解放されることに。
技術
ChatGPTによる回答をStack Overflowが一時的に禁止 大量のもっともらしいが不正確な回答に対処しきれず〈ITmedia NEWS(2022年12月6日)〉
プログラミング関連のQ&Aサイトで、AIチャットボット「ChatGPT」により生成された回答の投稿が禁止に。同じように「Yahoo!知恵袋」などでも、AI生成の「もっともらしいが不正確な回答」で埋め尽くされる状況に陥ることが予想できます。ナレッジコミュニティは、これで機能しなくなる可能性が高そう。まあ、そもそもちゃんと人間が答えてるケースでも「もっともらしいが不正確な回答」は多いわけですが。「ChatGPT」は「しれっと嘘をつく」という評判(#549)なので、まずは創作に活用するのが良いのでは、と思いました。
“ヤフコメ”削除率は3.22%、7割超がAIによる自動削除。ヤフー「2021年度メディア透明性レポート」公開〈INTERNET Watch(2022年12月7日)〉
見出しを読んだ最初の印象は「たったの3.22%か……」なのですが、月平均でなんと約42.8万件を削除しているとのこと。そりゃ、自動処理じゃないととても追いつかないでしょうね。数の暴力です。ヤフコメは11月15日から携帯電話番号の設定が必須になったので、次回の報告ではそれによる抑止効果がどの程度あったか? という情報が出てくるでしょう。
マンガ・アニメ制作アプリ最大手のセルシス、デジタルデータに「所有権」を付与する流通支援ソリューション「DC3」発表〈INTERNET Watch(2022年12月9日)〉
ついに本棚連携が実現されるか? と、少しワクワクしています。正直、見出しに「所有権」と書かれた時点で身構えてました(法的にはデジタルコンテンツの所有権は認められていない)。ただ、「DC3」の公式サイトを確認してみたところ、Q&Aに「当面は、所有という文言は使わず、公式には、保有という表記にいたします」とあります。記事を書いた側の、表現の問題でしょうか?
実際のところ、NFT系のサービスで「所有権」「唯一無二」「民主化」といったワードが出てきたら、私は強い疑いの眼でチェックするようにしています。しかし、公式サイトのQ&Aを一通り読んだ印象は「かなりまとも」でした。とくに「従来のサービス、サーバーなどの仕組みをそのまま利用したまま導入できる」というのが、かなり良いのではないでしょうか。
中立的な立場という姿勢を明確化しているのも良いと感じました。自身もコンテンツ販売を行ってるLINEや楽天のブロックチェーンに、競合他社が参加するのは「敵に塩を送る」ようなもの。だけどこの「DC3」はセルシスの子会社であり、自社でコンテンツ販売をやらない中立的な立場で「基盤」を提供すると明言しています。これなら乗りやすいのでは。
あとは、小規模事業者でも気軽に参加できるような料金設定ならなお良い……と思ったら、なんと初期導入費ゼロ。システム利用料は固定額なしで、コンテンツ販売額の0.5%というリーズナブルな設定です。これは、往々にしてユーザーから信頼されづらい小規模事業者(直販含む)ほど、真面目に導入を検討したほうが良さそうな気がします。というか、検討します。
Google検索、デスクトップPC版に連続スクロール導入。6ページ分をイッキ見可能に〈テクノエッジ TechnoEdge(2022年12月9日)〉
モバイルには1年前から先行して連続スクロールが導入されていましたが、今後はデスクトップ版にも導入されることに。まだ現時点ではアメリカだけのようですが、日本にも近いうちに適用されることでしょう。
検索結果表示は設定で100件に変えているので、個人的には影響ないんですが、世の中的には順位とCTRの関係に大きな変動がありそうです。恐らく下位のCTRが上がるはず。とはいえ「下位でも多少は流入がある」程度でしょうけど。
ちなみに2021年のデータでは12位あたりを底に、さらに下位のほうがCTRが高いという逆転現象が起きています。モバイルで連続スクロールが導入されたのは2021年10月なので、タイミング的にそれ以前のデータです(国別は2020年7月から2021年6月までの12カ月間)。
当時は「次へ」でのページ切り替えではなく、「もっと見る」ボタンでスムーズに11位以下を確認できる状態だったはずです。いまはボタンタップさえも必要なくなり、スクロールするだけでシームレスに40件まで読み込まれます。つまり、半端な下位より40位に近いほうがCTRが高い状態になっているかも?
お知らせ
イベント
12月25日の HON.jp News Casting は年末恒例の2時間特番! フリージャーナリストの西田宗千佳さんをゲストに迎え、2022年の出版関連ニュースをITの観点で振り返り&掘り下げます。
HON.jp「Readers」について
HONꓸjp News Blog をもっと楽しく便利に活用するための登録ユーザー制度「Readers」を開始しました。ユーザー登録すると、週に1回届く HONꓸjp メールマガジンのほか、HONꓸjp News Blog の記事にコメントできるようになったり、更新通知が届いたり、広告が非表示になったりします。詳しくは、こちらの案内ページをご確認ください。
日刊出版ニュースまとめ
伝統的な取次&書店流通の商業出版からインターネットを活用したデジタルパブリッシングまで、広い意味での出版に関連する最新ニュースをメディアを問わずキュレーション。TwitterやFacebookページは随時配信、このコーナーでは1日1回ヘッドラインをお届けします。
メルマガについて
本稿は、HON.jpメールマガジン(ISSN 2436-8245)に掲載されている内容を同時に配信しています。最新情報をプッシュ型で入手したい場合は、ぜひメルマガを購読してください。無料です。なお、本稿タイトルのナンバーは鷹野凌個人ブログ時代からの通算、メルマガのナンバーはHON.jpでの発行数です。
雑記
最近、地味な編集作業をコツコツやっていて、連載の執筆に手が回らないという情けない状況が続いています。まあ、数年間のあいだ貯めてたことをまとめてやってるから大変なのですが。この大きな峠を越えれば来年からはルーチンの延長上でできるはず。もうしばらく頑張ります(鷹野)

※本稿はクリエイティブ・コモンズ 表示 – 非営利 – 継承 4.0 国際(CC BY-NC-SA 4.0)ライセンスのもとに提供されています。営利目的で利用される場合はご一報ください。